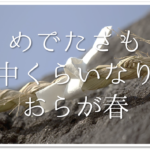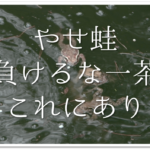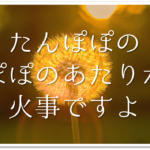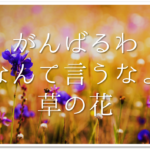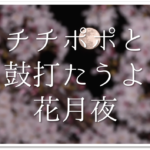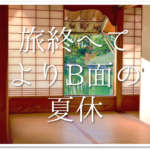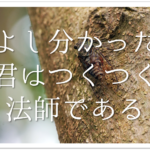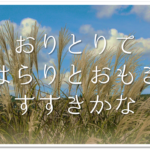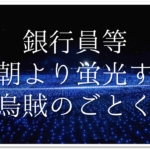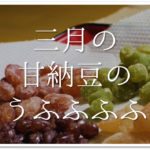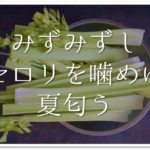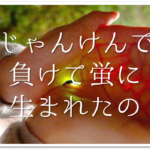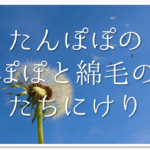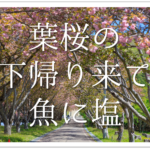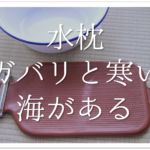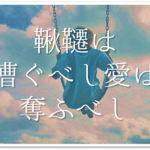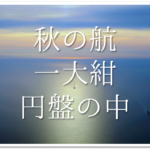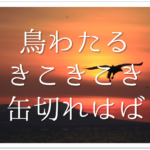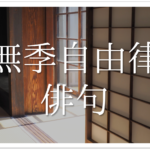俳句は五七五の十七音で構成される詩で、季語を詠み込むことによって豊かな四季を表せます。
江戸時代から現代まで多くの俳人が俳句を詠んでいて、その作風はさまざまです。
今回はそんな俳句の中でも、クスッとくる面白い有名俳句を40句紹介していきます。
たんぽぽのぽぽのあたりが火事ですよ#たんぽぽ #ぽぽのあたり #火事 pic.twitter.com/CEwrFhJNII
— ユキカ (@fjord335) February 21, 2015

面白い有名俳句【前編10句】

【NO.1】松尾芭蕉
『 於春々(ああはるはる) 大哉(おおいなるかな) 春と云々 』
季語:春(春)
意味:ああ、新春だ、春が来た。おめでたいことだ、春は良いなあ。

【NO.2】松尾芭蕉
『 納豆切る 音しばし待て 鉢叩き 』
季語:鉢叩き(冬)
意味:納豆汁を作るために納豆を切っているご家庭よ、少し待ってくれ。空也念仏の鉢叩きが聞こえてきたのに。

【NO.3】松尾芭蕉
『 あら何ともなや 昨日は過ぎて 河豚汁(ふぐとじる) 』
季語:河豚汁(冬)
意味:ああ何ともなかったなぁ。河豚汁にあたらないか不安だった昨日は過ぎ去ったのだ。

【NO.4】与謝蕪村
『 河豚汁(ふぐじる)の われ生きている 寝ざめ哉 』
季語:河豚汁(冬)
意味:河豚汁を食べたが、私はまだ生きている朝の寝覚めであることだ。

前項の俳句とほぼ同じ感想を与謝蕪村も詠んでいます。作者の好物も同じく河豚であったため松尾芭蕉の句を意識したか、河豚汁を食べた当時の人たちはみな同じことを思っていたのか、想像すると楽しい句です。
【NO.5】与謝蕪村
『 ところてん 逆しまに銀河 三千尺 』
季語:ところてん(夏)
意味:白く霞むところてんが黒いお椀の中に落ちていく。まるで天地を逆さまにした三千尺の銀河のようだ。

【NO.6】与謝蕪村
『 閻王(えんおう)の 口や牡丹を 吐かんとす 』
季語:牡丹(夏)
意味:閻魔大王の口が真っ赤で、真っ赤な牡丹の花を吐き出そうとしているように見える。

【NO.7】小林一茶
『 そば時や 月の信濃の 善光寺 』
季語:そば時(秋)
意味:蕎麦の食べ頃だなぁ。信濃国といえば更科の月に善光寺だ。

【NO.8】小林一茶
『 めでたさも 中くらいなり おらが春 』
季語:おらが春/初春(新年)
意味:新年になってめでたいが、めでたさはあいまいなものであるこの新春だ。

【NO.9】小林一茶
『 やせ蛙 負けるな一茶 これにあり 』
季語:やせ蛙(夏)
意味:やせ蛙よ、負けるな。一茶はここで応援しているぞ。

【NO.10】河合曽良
『 畳めは 我が手のあとぞ 紙衾(かみぶすま) 』
季語:紙衾(冬)
意味:その畳んである畳目は、私が畳んだものだぞ。師が使った紙衾の。

面白い有名俳句【中編10句】

【NO.11】坪内稔典
『 たんぽぽの ぽぽのあたりが 火事ですよ 』
季語:たんぽぽ(春)
意味:たんぽぽの「ぽぽ」というあたりが火事になっていますよ。

【NO.12】坪内稔典
『 がんばるわ なんて言うなよ 草の花 』
季語:草の花(秋)
意味:がんばるわ、なんて言わないでくれよ。野に咲いている花はがんばらずとも自然に咲いているのだから。

【NO.13】松本たかし
『 チチポポと 鼓打たうよ 花月夜 』
季語:花月夜(春)
意味:チチポポと音を立てて鼓を打とうよ。この心地よい花月夜に。

「チチポポ」という擬音が面白い一句です。作者は能役者の家に生まれましたが、病気で役者の道はあきらめています。しかし趣味で舞を舞うことはあったようで、この句もそのときに詠まれたものでしょう。
【NO.14】黛まどか
『 旅終へて よりB面の 夏休 』
季語:夏休(夏)
意味:A面にあたる旅を終えて、これからB面である普通の生活をする夏休みだ。

A面、B面という言葉は最近では聞かなくなりましたが、レコードやカセットテープなどでよく使われました。メインである旅行は終わってしまったけれど、まだ夏休みは残っているという元気な一句です。
【NO.15】池田澄子
『 よし分かった 君はつくつく法師である 』
季語:つくつく法師(秋)
意味:よしわかった。君はツクツクホウシのようである。

【NO.16】飯田蛇笏
『 おりとりて はらりとおもき すすきかな 』
季語:すすき(秋)
意味:折り取るとはらりと重いススキであることだ。

【NO.17】金子兜太
『 銀行員等 朝より蛍光す 烏賊のごとく 』
季語:無季
意味:銀行員たちは朝から蛍光灯を付けている。まるでホタルイカのようだ。

【NO.18】坪内稔典
『 三月の 甘納豆の うふふふふ 』
季語:三月(春)
意味:三月に食べる甘納豆は思わず笑いが出るほど美味しい。

「甘納豆」を題材とした12ヶ月の俳句の中の3月の句です。「うふふふふ」と笑い声で終わっているのが特徴的な句で、笑いが出るほど美味しい様子が伺えます。暖かくなってきた外の陽気と合わせて、作者が楽しげにしている一句です。
【NO.19】日野草城
『 みずみずし セロリを噛めば 夏匂う 』
季語:セロリ(冬)
意味:みずみずしいセロリを噛めば夏のような青い匂いがする。

一見「夏」が季語のように思える句ですが、「セロリ」という冬の季語が主題です。正反対の季節を詠んだ面白い句で、寒い冬でもセロリを噛めばみずみずしい香りがして、夏のような印象を受けると詠んでいます。
【NO.20】池田澄子
『 じゃんけんで 負けて蛍に 生まれたの 』
季語:蛍(夏)
意味:じゃんけんで負けて蛍に生まれたの。

面白い有名俳句【後編10句】

【NO.21】高浜虚子
『 川を見る バナナの皮は 手より落ち 』
季語:バナナ(夏)
意味:川を見ていると、バナナの皮が手から滑り落ちた。

【NO.22】高浜虚子
『 又例の 寄せ鍋にても いたすべし 』
季語:寄せ鍋(冬)
意味:客が来るので、今日の夕飯はまた例の寄せ鍋にでもしてください。

【NO.23】夏目漱石
『 東西(ひがしにし) 南北(みなみきた)より 吹雪哉 』
季語:吹雪(冬)
意味:東西南北あらゆる方向から吹雪が吹き付けていることだ。

【NO.24】芥川龍之介
『 凧三角、四角、六角、空、硝子 』
季語:凧(春)
意味:三角や四角、六角形の凧が上がっている。色とりどりの凧が上がる空はまるでガラス細工のように美しい。

【NO.25】山口誓子
『 長時間 ゐる山中に かなかなかな 』
季語:かなかな(秋)
意味:登山で長時間山の中にいると、かなかなかなとヒグラシの声が聞こえてくるなぁ。

【NO.26】草間時彦
『 秋鯖や 上司罵る ために酔ふ 』
季語:秋鯖(秋)
意味:秋鯖を食べよう。今日は酔いにまかせて上司を罵るために酔うのだ。

【NO.27】高野素十
『 餅板の 上に包丁の柄を とんとん 』
季語:餅(冬)
意味:餅を置いた板の上に包丁の柄をとんとんと叩きつけて調節する。

【NO.28】稲畑汀子
『 三椏(みつまた)の 花三三が九 三三が九 』
季語:三椏の花(春)
意味:ミツマタの花が3本の枝ごとに3つ咲いている。三三が九、あちらも三三が九だ。

【NO.29】永田耕衣
『 恋猫の 恋する猫で 押し通す 』
季語:恋猫(春)
意味:恋をしている猫が、恋しい猫に対して押し通すように思いを告げている。

【NO.30】加藤楸邨
『 たんぽぽの ぽぽと綿毛の たちにけり 』
季語:たんぽぽ(春)
意味:たんぽぽの「ぽぽ」という部分に綿毛が立っているよ。

「たんぽぽのぽぽ」という表現は江戸時代にはすでに存在していました。この句は「たんぽぽの ぽぽともえ出る 焼野かな」という句を元にしています。
面白い有名俳句【おまけ編10句】

【NO.31】上島鬼貫
『 そよりとも せいで秋たつ ことかいの 』
季語:秋たつ(秋)
意味:そよりとも風と吹かないくせに立秋になったとはどういうことだろうか。

【NO.32】向井去来
『 たけの子や 畠隣に 悪太郎 』
季語:たけの子(夏)
意味:タケノコが生えてきたなぁ。畑の隣に住んでいる悪童が悪さをしないか心配だ。

【NO.33】正岡子規
『 おそろしや 石垣崩す 猫の恋 』
季語:猫の恋(春)
意味:なんとおそろしいことだ。石垣も崩すほどの春先の猫たちの恋模様よ。

【NO.34】正岡子規
『 毎年よ 彼岸の入に 寒いのは 』
季語:彼岸(春)
意味:毎年のことだよ。春の彼岸の入りに寒いのは。

【NO.35】正岡子規
『 漱石が 来て虚子が来て 大三十日 』
季語:大三十日(冬/暮)
意味:夏目漱石があいさつに来て、高浜虚子もあいさつに来る大晦日だ。

【NO.36】細見綾子
『 葉桜の 下帰り来て 魚に塩 』
季語:葉桜(夏)
意味:葉桜の下を帰ってきて、下ごしらえに魚に塩を振る。

【NO.37】西東三鬼
『 水枕 ガバリと寒い 海がある 』
季語:無季
意味:水枕をしている。ガバリと寒い海がそこにはある。

【NO.38】三橋鷹女
『 鞦韆(しゅうせん)は 漕ぐべし愛は 奪ふべし 』
季語:鞦韆(春)
意味:ブランコは漕ぐべし。愛は奪うべし。

【NO.39】中村草田男
『 秋の航 一大紺 円盤の中 』
季語:秋(秋)
意味:秋の航海中だ。見渡す限り紺色で、円盤の中にいるようだ。

【NO.40】秋元不死男
『 鳥わたる こきこきこきと 缶切れば 』
季語:鳥わたる(秋)
意味:こきこきこきと缶切りを動かしていると、鳥が空を渡っていった。

以上、面白い有名俳句40選でした!

今回は、有名な俳人のどこか笑える句や面白い表現の句を40句紹介してきました。
その作者の作風とは思えないとぼけた句や、どこか危なっかしい笑いを含んだ句など多くの面白い俳句があります。