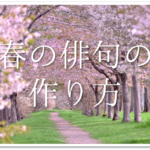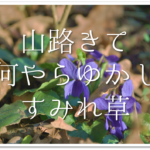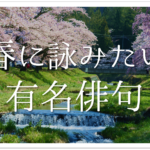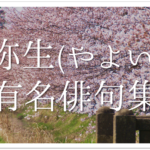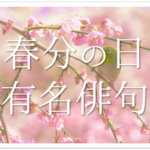江戸時代に成立し現在まで多くの人に楽しまれている「俳句」。
日本人にずっと愛されてきた国民的文芸ですが、ここ最近はいっそう俳句に親しむ方が増えている様子も見られます。
子どもからお年寄まで、誰にでも簡単に楽しみながら作ることができる点が俳句の大きな魅力と言えます。
今回は、「3月」に詠みたいおすすめ有名俳句&一般俳句作品を30句紹介していきます。
おはようございます♪
今朝は「うれしいひな祭り」の曲で目覚めました。
3月3日は雛祭ですね。桜餅でもお供えしましょう。
今日は近所の友達数人と逢うことに‥。のぞきゆく雛を見る眼や皆やさし #haiku pic.twitter.com/6GaNgj2xzq
— ゆう (@povpj5QvyZyfcWR) March 2, 2017

目次
俳句に3月らしさを出す!3月の季語を知ろう

俳句には「季語(きご)」というその時の情景や状況、作者の気持ちをより具体的に読み手へ伝えるため、用いられる言葉があります。
例えば、今回のテーマである3月には「桜」「ひなまつり」「ウグイス」「春休み」といった季語があります。
季語は一見難しい言葉ばかりかと思われがちですが、馴染み深いものも多く、その季節の特徴…つまり、その季節らしい言葉であれば季語となるのです。

3月の季語【一覧】
三月 弥生 春一番 春の月 雪解け 雛の日 雛祭り ひな人形 桃の節句 桃の酒 白酒 雛あられ 風花 忘れ雪 春の闇 春寒し 春の雪 水温む 春めく 忘れ雪 寒戻る 啓蟄 青麦野遊び 磯遊び 雛菊 紅梅 入学試験 卒業 桜便り 桜 彼岸桜 糸桜 しだれ桜 山桜 夜桜 夕桜 なずな たんぽぽ すみれ 椿 花 霞 黄砂 三月十一日 地震 春の夕 春雨 春時雨 あたたか 春うらら 春光 東風 青菜 青海苔 鰆(さわら)草餅 春の菜 韮 ぜんまい わらび 土筆 伊予柑 レガッタ ボートレース 朧月夜 入り彼岸 彼岸入り 木の芽 木の芽時 山笑う 春景色 春分 春分の日 春休み 鴬(うぐいす) おたまじゃくし つばめ 蜂 蝶

3月の季語を使った有名俳句集【前編10句】

それでは早速、3月の季語を使った有名俳句を紹介していきます。
【NO.1】夏目漱石
『 鴬や 障子あくれば 東山 』
季語:鴬(春)
意味:うぐいすの声が聞えたので何気なく障子を開けてみると、思いがけなく東山の風景があり、趣を感じました。

【NO.2】正岡子規
『 薄赤き 顔並びけり 桃の酒 』
季語:桃の酒(春)
意味:3月3日、桃の酒を酌み交わし、皆うっすら赤い顔になっています。

【NO.3】富安風生
『 三月の 声のかかりし あかるさよ 』
季語:三月(春)
意味:三月の声を聞くと、昨日とはさして変らぬ今日であるのに、なんだか周囲が明るくなったような気がします。

【NO.4】小林一茶
『 夕ざくら けふも昔に 成にけり 』
季語:夕桜(春)
意味:桜の咲く春のうららかな日々だけれど、一日が終わる夕暮れどきは侘しく、ながめていたあの夕ざくらも、もう過去のものとなりました。

【NO.5】芥川龍之介
『 三月や 茜さしたる 萱の山 』
季語:三月(春)
意味:三月になった。萱を積んであるところに日が映えて、なんともあたたかく美しいのだろう。
(*茜さす…照映えて美しい様。美しく照り輝くこと *萱…かや ススキ・スゲなど屋根をふくイネ科などの植物の総称)

【NO.6】山口青邨
『 春雨の 音がしてくる 楽しさよ 』
季語:春雨(春)
意味:春雨がふり出して雨音が聞えてきた。寒い冬の雨音とは違い、これから芽吹くものたちの命を育む、乾いた土をたたく雨音は、春の訪れも感じ、聞いていて楽しくなります。

【NO.7】与謝蕪村
『 雛祭る 都はづれや 桃の月 』
季語:雛祭り(春)
意味:都のはずれのこんな田舎にお雛様を飾ってあるんだなあ。三月なのですね。

【NO.8】高井几董(たかいきとう)
『 雪どけの 音聞いて居る 朝寝哉 』
季語:朝寝(春)
意味:朝寝坊をした。まだ床の中にいて、静かに雪どけの音を聴いています。

【NO.9】水原秋桜子
『 碧天や 雪煙たつ 弥生富士 』
季語:弥生(春)
意味:深く青い空に雪煙がたっている。その中に三月の富士山が見えます。

【NO.10】松尾芭蕉
『 山路来て なにやらゆかし すみれ草 』
季語:すみれ草(春)
意味:山道を歩いていたら、路傍にすみれの花が咲いています。ひっそりと春をつげるその姿をなんだか慕わしく思いました。

3月の季語を使った有名俳句集【後編10句】

【NO.11】松尾芭蕉
『 草の戸も 住み替はる代ぞ 雛の家 』
季語:雛(春)
意味:この草でできた家も、住み替わる時が来た。雛人形が良く似合う娘のいる家族だそうだ。

【NO.12】与謝蕪村
『 菜の花や 月は東に 日は西に 』
季語:菜の花(春)
意味:菜の花が咲いているなぁ。月は東から昇り、日は西に沈んでいく。

【NO.13】小林一茶
『 おらが世や そこらの草も 餅になる 』
季語:草も餅/草餅(春)
意味:何ともありがたい世だ。そこらの草も草餅にできる。

【NO.14】正岡子規
『 毎年よ 彼岸の入りに 寒いのは 』
季語:彼岸(春)
意味:毎年のことだよ。彼岸の入りに寒いのは。

【NO.15】夏目漱石
『 菫ほどな 小さき人に 生まれたし 』
季語:菫(春)
意味:スミレの花ほどの、目立たずひっそりと生きる人に生まれたかったなぁ。

【NO.16】高野素十
『 野に出れば 人みなやさし 桃の花 』
季語:桃(春)
意味:野に出れば、会う人たちはみな優しかった。桃の花が咲いている。

【NO.17】水原秋桜子
『 雛壇や 襖はらひて はるかより 』
季語:雛(春)
意味:雛壇が見えるなぁ。襖をはらっているのか遠くからも見える。

【NO.18】水原秋桜子
『 来しかたや 馬酔木咲く野の 日のひかり 』
季語:馬酔木咲く(春)
意味:歩いてきた方を振り返ると、白い馬酔木の花が咲く野に日の光が差し込んでいる。

【NO.19】細見綾子
『 菜の花が しあはせさうに 黄色して 』
季語:菜の花(春)
意味:菜の花が幸せそうな黄色い花を咲かせている。

【NO.20】坪内稔典
『 三月の 甘納豆の うふふふふ 』
季語:三月(春)
意味:三月に食べる甘納豆が美味しくて、うふふふふと笑いがこぼれる。

3月の季語を使った一般俳句作品集【おまけ10句】

ここからは一般の方が作った3月の俳句作品を紹介していきます。

俳句作りの際はぜひ参考にしてみてください。
【No.1】
『 春寒や 死にきれぬほど 散らかりぬ 』
季語:春寒(春)
意味:立春を過ぎてもまだ寒くて、このまま死んでしまったらどうなるかしらと思うほど、散らかったままです。

【No.2】
『 おひなさま ゆっくりしまう 母の顔 』
季語:おひなさま(春)
意味:雛祭りがおわって、おひな人形をお母さんがゆっくりとしまっています。

【No.3】
『 三月の ハンカチ乾く 暇もなく 』
季語:三月(春)
意味:三月はお別れ事が多くて、涙でハンカチが乾く暇がありませんでした。

【No.4】
『 春寒し 薪割る音の 山を割り 』
季語:春寒し(春)
意味:まだ寒い初春、山へ来てみると誰かが薪を割る音が響いている。その音はまるで山を割っているように聞えます。

【No.5】
『 焼却炉に アルバム放り 卒業す 』
季語:卒業(春)
意味:焼却炉にアルバムを放り込みました。本当の意味で卒業です。

【No.6】
『 日帰りの 山はなだらか つくしんぼ 』
季語:つくし(春)
意味:日帰り登山をしました。なだらかな山道、帰り道はなおさらで、つくしをみつけながら下山しました。

【No.7】
『 あたたかや 縄文人の子の 手形 』
季語:あたたか(春)
意味:縄文人の子どもの手形をみました。なんてあたたかい気持ちにさせることでしょう。

【No.8】
『 木の芽和(あえ) ひとり前とは これつぽち 』
季語:木の芽和(春)
意味:ひとり分の木の芽和えとはたったこれだけの量なのですね。

【No.9】
『 朝ざくら 家族の数の 卵割り 』
季語:朝ざくら(春)
意味:朝のきれいな桜を見ながら、家族の人数分、卵を割っています。

【No.10】
『 春うらら 私の時計 眠たがる 』
季語:春うらら(春)
意味:春のうららかな日々、私の時計は眠りたがるのです。

以上、3月の季語を含んだおすすめ俳句集でした!