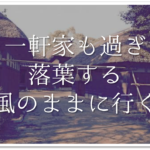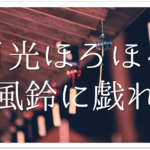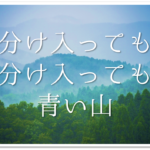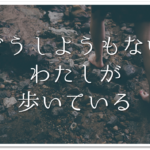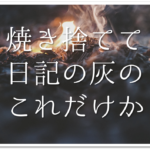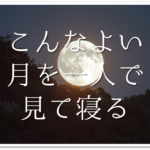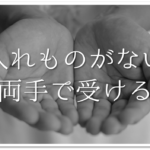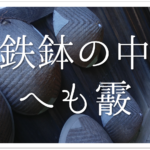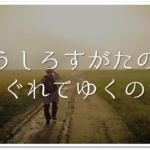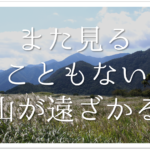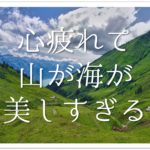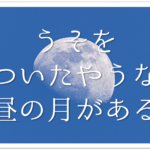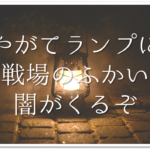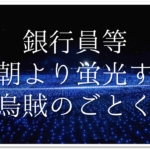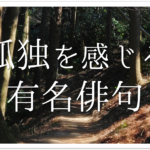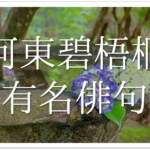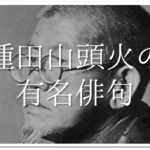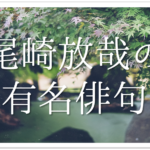無季自由律俳句とは、その瞬間の心を規則にとらわれず、自由に表現する俳句のことです。
季語もなく、韻律の規則もなく、素直に表現されるその句はより直接的に作者の心情を語ります。
ゴミ箱に 勉強の証 頑張ろう
俳句 無季自由律 pic.twitter.com/kR43OZzYSp
— me🦋 (@snowmpeace) May 23, 2015
今回は、過去に有名俳人が詠んだ「無季自由律俳句」を30句紹介していきます。

目次
無季自由律俳句とは?

無季自由律俳句とは、自由律俳句に加えて季語や季題を必要としない俳句のことを言います。
(※自由律俳句・・・五七五の定型俳句に対し、定型に縛られずに作られる俳句のこと)
つまり、無季自由律俳句は俳句の基本とも言える俳句の基礎「季語を入れる」「十七音で句を作る」を無視した俳句のことです。
五七五にとらわれない俳句を提唱した最初の人物は、明治後期の俳人である「河東碧梧桐(かわひがしへきごとう)」です。ただし、河東碧梧桐の段階ではまだ季語を含む自由律俳句もありました。
その後に続いた荻原井泉水(おぎわらせいせんすい)、種田山頭火(たねださんとうか)、尾崎放哉(おざきほうさい)は季語を廃し十七音を無視して、口語で瞬間的な印象を読む無季自由律俳句を打ち出しました。
無季自由律俳句は昭和初期には衰退しますが、戦後になると口語俳句の一ジャンルとして再び注目され、現在に至ります。

次に、無季自由律俳句おすすめ集を紹介していきます。
おすすめの無季自由律俳句【30選】


ここからは、無季自由律俳句を時代別【出現期5句・成立後20句・戦後5句】に紹介していきます。
出現期の無季俳句/自由律俳句【5選】

【NO.1】荻原井泉水
『 水あれば 田に青空が 深く鋤かれある 』
意味:田んぼに水があると、青空が田んぼの水に映って深く鋤かれていく。

無季俳句ですが、読むと田んぼに水が入っているため夏の風景だとわかります。韻律自体は五七八という字余りの破調ですが、無季自由律俳句のはしりの句と言ってもいいでしょう。
【NO.2】荻原井泉水
『 空をあゆむ 朗朗と月ひとり 』
季語:月(秋)
意味:月がひとり、明るく空を歩いていく。

擬人化を使った情景の句です。「朗々と」という言葉から月の明るい夜空だと連想できますが、季節を断定できる情報が省略された自由律俳句が出てきました。
【NO.3】荻原井泉水
『 棹さして 月のただ中 』
季語:月(秋)
意味:船の上から棹をさして、水面に映る月の真ん中を漕いでいく。

まるで一枚の絵画のような情景句です。水面に月が映るほど天気のいい夜、凪いで水面の月が崩れないほど風のない日ということがわかります。こちらも季語の秋と断定できるだけの情報が省略されている自由律俳句です。
【NO.4】荻原井泉水
『 一軒家も過ぎ 落葉する 風のままに行く 』
季語:落葉(冬)
意味:最後の一軒家も通り過ぎ、落ち葉がハラハラと風に乗って落ちていくままに歩く。

集落最後の一軒家を通り過ぎて1人で歩いていく様子を表した句です。落葉が冬の季語ですが、ここでは落ちていく葉を作者のどこか寂しい心情に託しているため無季俳句とも考えられます。
【NO.5】荻原井泉水
『 月光ほろほろ 風鈴に戯れ 』
季語:風鈴(夏)
意味:月光がほろほろと降り注ぎ、風鈴と戯れているようだ。

月の光が風鈴に当たっていて、風鈴と光が戯れているという幻想的な風景を詠んだ句です。風については言及されていませんが、「戯れ」とあるように風鈴が風で揺れていたのかもしれません。
成立後の無季自由律俳句【20選】

【NO.1】種田山頭火
『 分け入っても分け入っても 青い山 』
意味:分け入っても踏み越えても、どこまでも青い山が続いていく。

【NO.2】種田山頭火
『 雨ふるふるさとは はだしであるく 』
意味:故郷に雨が降っている。裸足で歩いていく。

【NO.3】種田山頭火
『 父によう似た声が出てくる旅はかなしい 』
意味:行方不明の父によく似た声を聞く旅は悲しい。

【NO.4】種田山頭火
『 どうしようもない私が歩いている 』
意味:歩く以外に生きる術のない、どうしようもない私が歩いている。

【NO.5】種田山頭火
『 焼き捨てて 日記の灰の これだけか 』
意味:何年分の日記だろうと、焼き捨ててしまえば日記の灰はこれだけしか残らない。

【NO.6】種田山頭火
『 捨てきれない荷物のおもさ まへうしろ 』
意味:捨てきったと思っても捨てきれない荷物の重さよ、まだ肩の前や後ろに振り分けないといけないほどある。

【NO.7】尾崎放哉
『 こんなよい月を 一人で見て寝る 』
意味:こんなにいい月夜を一人で見ながら寝る。

【NO.8】尾崎放哉
『 わが顔ぶらさげて あやまりにゆく 』
意味:私の顔をぶら下げて謝りに行こう。

「ぶらさげて」という言い回しから、どこかバツの悪さを感じる微笑ましい句です。気安い間柄の相手が目に浮かびます。
【NO.9】尾崎放哉
『 入れ物がない 両手で受ける 』
意味:鉢がないので施しを両手で受け取る。

【NO.10】尾崎放哉
『 月夜の葦が 折れとる 』
意味:月夜に照らされた葦が折れている。

折れている葦に焦点を当てることで、月夜の水辺の陰影がはっきりと見えるようです。「折れとる」は鳥取県の方言で、方言をそのまま使用している珍しい俳句になっています。


【NO.12】橋本夢道
『 無礼なる妻よ 毎日馬鹿げたものを食わしむ 』
意味:無礼な妻よ。毎日よくもこんなものを食べさせるものだ。

【NO.13】栗林一石路
『 シャツ 雑草にぶっかけておく 』
意味:シャツを雑草の上に放り投げておく。


【NO.15】種田山頭火
『 うしろすがたの しぐれてゆくか 』
意味:後ろ姿が時雨の中に消えていく。

【NO.16】種田山頭火
『 また見ることもない 山が遠ざかる 』
意味:また見ることもない山が遠ざかっていく。

【NO.17】種田山頭火
『 こころ疲れて 山が海が美しすぎる 』
意味:心が疲れていると、山が、海が美し過ぎるように見える。


【NO.19】尾崎放哉
『 うそをついたやうな 昼の月がある 』
意味:嘘をついたように真っ白な昼の月が見える。

【NO.20】富澤赤黄男
『 やがてランプに 戦場のふかい闇がくるぞ 』
意味:ランプに小さな明かりが灯っているが、やがてここも戦場になり明かりが消えて深い闇が来るぞ。

戦後の無季自由律俳句【5選】

【NO.1】成田三樹夫
『 色々の人々のうちに きえてゆくわたくし 』
意味:色々な人達の心の中に、役柄として消えていく役者の私である事だ。

【NO.2】住宅顕信
『 ずぶぬれて犬ころ 』
意味:小さな犬がずぶ濡れになっている。

作者は25歳という若さで夭折しました。俳人としてはわずか3年、白血病とた戦いながらの句です。「犬ころ」という言葉から、頼りになる犬ではなく小さく危ういものという印象を受けます。
【NO.3】住宅顕信
『 レントゲンに 淋しい胸のうちのぞかれた 』
意味:レントゲンを撮ると淋しい胸の内を覗かれた。

作者は病のために妻と離婚し、入院しながら長男を育てます。治る見込みのない病と妻のいない子育てという淋しさを、レントゲンという胸の中を見通す機械で見られている、現代ならではの俳句です。
【NO.4】住宅顕信
『 夜が淋しくて 誰かが笑いはじめた 』
意味:誰かの笑い声が聞こえる。夜が淋しいから思わず笑い始めてしまったのだ。

句集「未完成」の最後に置かれた句です。時系列順に配置されているなら絶筆の句ということになります。壮絶な闘病生活と孤独感、不安感を感じさせる句です。
【NO.5】金子兜太
『 銀行員等 朝より蛍光す 烏賊のごとく 』
意味:銀行員たちが朝から蛍光灯をつけて仕事をしている。まるでイカのようだ。

ここで例えられているイカとはホタルイカのことです。ホタルイカが発行する様子を、朝早くから蛍光灯をつけて仕事をしている銀行員たちになぞらえて詠んでいます。
以上、おすすめ無季自由律俳句集でした!


今回は、無季自由律俳句を出現期、成立期、戦後の三つの時期に分けて紹介してきました。
季語や韻律が難しいと感じる方も、感じたままを表現する無季自由律俳句に挑戦してみてはいかがでしょうか。