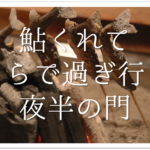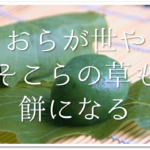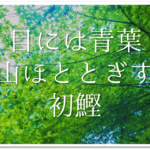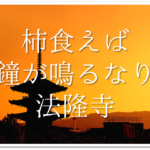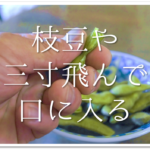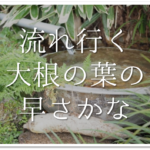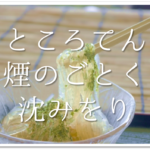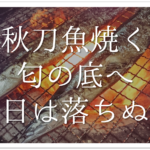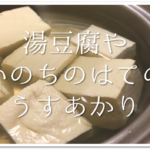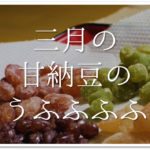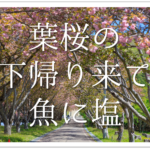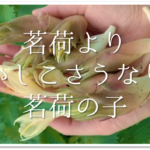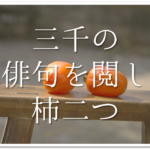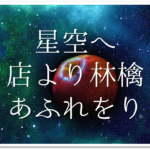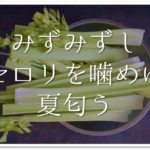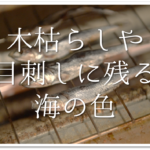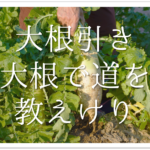四季折々の食べ物は多くが季語になっています。
そして、作者の好みや詠まれた当時の食事の様子を詠んだ面白い俳句が多くあります。
目には青葉 山ほととぎす 初鰹 pic.twitter.com/HoSaH3LFtg
— しゅうか (@LapisLazuli0531) May 11, 2014
匙なめて童たのしも夏氷 山口誓子
童じゃありません。おっさんです。はい。 pic.twitter.com/XqxL2X0Muv
— 熊沢 透 (@kumat1968) August 13, 2014
今回は、そんな「食べ物」に関するおすすめ有名俳句を30句紹介していきます。

食べ物に関する有名俳句【前編10句】

【NO.1】松尾芭蕉
『 色付くや 豆腐に落て 薄紅葉 』
季語:薄紅葉(秋)
意味:豆腐に落ちた薄く紅葉した葉で、豆腐が色付いているようだ。

豆腐には紅葉豆腐という唐辛子などを混ぜた料理もありますが、ここでは白い豆腐に紅葉した葉の色の対比を詠んでいます。ほんのりと色付いた葉で、豆腐にまで色が移ったようだという洒落た句です。
【NO.2】松尾芭蕉
『 藻にすだく 白魚やとらば 消ぬべき 』
季語:白魚(春)
意味:藻に集まる白魚は、透き通っていて取ったら消えてしまいそうだ。

白魚は春の味覚で、生きていると半透明ですが死ぬと白くなることから名付けられています。藻の緑と白魚の透明さを対比し、取れば白くなってしまうのだなと惜しんでいる句です。
【NO.3】松尾芭蕉
『 あら何ともなや 昨日は過ぎて 河豚汁 』
季語:河豚汁(冬)
意味:ああ何ともなかった。河豚汁を食べて心配していた昨日は過ぎたのだ。

作者は河豚好きとして有名でしたが、江戸時代でも河豚を食べて食中毒を起こすことは度々ありました。そんな中で、無事に朝目を覚まして何事もなかったと安心している陽気さを感じる表現です。
【NO.4】与謝蕪村
『 莟(つぼみ)とは なれもしらずよ 蕗のたう 』
季語:蕗のたう(春)
意味:自分がつぼみだとはお前も知らないだろう、顔を出した蕗の薹よ。

蕗の薹は蕗のつぼみの状態のことです。雪の中から真っ先に顔を出すその生命力もまだつぼみの状態なのだなと語りかけているような一句です。
【NO.5】与謝蕪村
『 鮎くれて よらで過行く 夜半の門 』
季語:鮎(夏)
意味:鮎をくれた友人が、寄っていけというのに寄らずに帰っていく真夜中の門だ。

「夜半」は真夜中から夜明け前までの間で、日付が変わった頃を言います。そんな遅い時間にわざわざ鮎を届けてくれた友人に休んでいってと誘ったけれど、彼は言ってしまったなぁと見送っている光景です。

【NO.6】与謝蕪村
『 鰒(ふぐ)汁の 宿赤々と 灯しけり 』
季語:鰒汁(冬)
意味:河豚汁を出す宿の明かりが赤々と灯っている。

作者は河豚が大好物で、河豚を詠んだ句がたくさんあります。河豚汁を出す店にもよく通っていたことが伺える、宿の盛況を伝える句です。
【NO.7】小林一茶
『 冷し瓜 二日立てども 誰も来ぬ 』
季語:冷し瓜(夏)
意味:冷やし瓜を準備しているが、2日待っても誰も訪ねて来ないなぁ。

【NO.8】小林一茶
『 そば時や 月の信濃の 善光寺 』
季語:そば時(秋)
意味:新蕎麦の季節だ。更科の月に照らされた信濃の善光寺に行こう。

「そば時」とは「蕎麦の食べ頃」と解釈し、新蕎麦と同じ意味の季語としました。蕎麦も更科の月も善光寺も信濃国の名物であり、キャッチコピーのような一句です。
【NO.9】小林一茶
『 おらが世や そこらの草も 餅になる 』
季語:草も餅/草餅(春)
意味:私が今生きている世の中なのだ。そこらに生えている草も餅になる。

この句は前書きに「月をめで花にかなしむは、雲の上人にして」とあります。雲上人ではなく私が生きている世の中なので、ヨモギで草餅を作って食べようという生きる活力に満ちあふれた表現です。
【NO.10】山口素堂
『 目には青葉 山ほととぎす 初鰹 』
季語:青葉(夏)/ほととぎす(夏)/初鰹(夏)
意味:視界には青葉、山ではほととぎすの声がして、初鰹を味わう季節だ。

季語が3つ重なる有名な初夏の一句です。作者の時代では初物を食べると長生きできるという風習があったため、初鰹は早馬で江戸まで送られて珍重されていました。
食べ物に関する有名俳句【中編10句】

【NO.11】正岡子規
『 柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺 』
季語:柿(秋)
意味:柿を食べていると鐘が鳴った法隆寺だ。

作者は柿好きで有名で、一度に何個も食べていたと言われています。法隆寺という長い歴史のあるお寺の鐘と、好物の柿を食べる自分とでノスタルジックな雰囲気を感じる句です。
【NO.12】正岡子規
『 枝豆や 三寸飛んで 口に入る 』
季語:枝豆(秋)
意味:枝豆を食べようとしたら、三寸ほどぽんと飛んで口の中に入った面白さよ。

三寸は約9cmで、食べようと枝豆を押したらきれいに放物線を描いて口の中に入った様子が伺えます。作者は健啖家としても知られているため、この句を詠んだときも次々と枝豆を食べていた光景が浮かんできます。
【NO.13】正岡子規
『 一匙の アイスクリームや 蘇る 』
季語:アイスクリーム(夏)
意味:一匙のアイスクリームがとても美味しいなぁ。蘇る心地だ。

【NO.14】高浜虚子
『 流れ行く 大根の葉の 早さかな 』
季語:大根(冬)
意味:川を流れていく大根の葉のなんと早いことよ。

かつては川や水路で野菜を洗うことがあり、作者よりも上流の方で大根を洗っていた人がいたのでしょう。大根の葉が流れていく日常の光景に、季節を実感している様子が伺える句です。
【NO.15】高浜虚子
『 七種に 更に嫁菜を 加へけり 』
季語:七種(新年)
意味:七草粥に、さらに「嫁菜」を加えよう、結婚のお祝いに。

この句は同級生の結婚祝いの際に作られた句です。縁起の良い七草粥に更に嫁とつく嫁菜を加えて末広がりの「八」にすることで、さらにめでたさを感じる当意即妙の句です。

【NO.16】日野草城
『 ところてん 煙のごとく 沈みをり 』
季語:ところてん(夏)
意味:押し出されたところてんが、まるで煙のように沈んでいく。

ところてんは「ところてん突き」と呼ばれる器具で細い形に押し出されます。その様子を煙に例えた一句で、器の中に沈んでいく細長いところてんを面白がっています。
【NO.17】加藤楸邨
『 秋刀魚焼く 匂の底へ 日は落ちぬ 』
季語:秋刀魚(秋)
意味:秋刀魚を焼いて出た煙や匂いの底へ、夕日が落ちていくように沈んでいく。

当時は現在のような魚焼きグリルではなく、七輪で秋刀魚を焼いていたことでしょう。煙と匂いが充満する中で、ゆっくりと夕日が沈んでいく日常を詠んだ句です。
【NO.18】山口誓子
『 匙なめて 童たのしも 夏氷 』
季語:夏氷(夏)
意味:一匙ずつなめるように食べている子供も楽しんでいるのだろう、夏のかき氷を。

「夏氷」とはかき氷のことで、明治時代以降に普及しました。一気に食べると頭が痛くなってしまうのか、少しずつ楽しみながら食べている子供のはしゃいだ様子を観察しています。
【NO.19】中村草田男
『 葡萄食ふ 一語一語の 如くにて 』
季語:葡萄(秋)
意味:葡萄を一粒ずつ食べる。まるで言葉を一語ずつ丁寧に味わうかのような心地だ。

葡萄の実は手で一粒ずつもいで食べるのが一般的です。その1つずつ味わって食べる様子を、一語ずつ言葉の意味を噛みしめる様子に重ねています。
【NO.20】久保田万太郎
『 湯豆腐や いのちのはての うすあかり 』
季語:湯豆腐(冬)
意味:湯豆腐から白い湯気が立ち上る。まるで命の果てに見える薄明かりのようだ。

この句は作者が急逝する前に詠まれた句で、家族を亡くした孤独な晩年の心境を湯豆腐に託しています。人生の終わりを意識していて、「うすあかり」という言葉に湯気がたちのぼって消えていく儚さを感じる句です。
食べ物に関する有名俳句【後編10句】

【NO.21】坪内稔典
『 三月の 甘納豆の うふふふふ 』
季語:三月(春)
意味:3月に甘納豆を食べると思わずうふふふふと笑い声がもれてしまう。

作者は12ヶ月を通して「甘納豆」をテーマに俳句を詠んでいて、この句は3月のものです。春の陽気を感じながら食べる甘納豆に思わず笑みがこぼれています。
【NO.22】日野草城
『 さくら餅 うちかさなりて ふくよかに 』
季語:さくら餅(春)
意味:桜餅が重なってふくよかに見える。

店頭に積まれている桜餅が折り重なっているのを見て、ふくよかになったと表現している面白い句です。桜餅には長命寺と道明寺の2つの形がありますが、どちらでも想像出来る句です。
【NO.23】細見綾子
『 葉桜の 下帰り来て 魚に塩 』
季語:葉桜(夏)
意味:葉桜の下を帰ってきて魚に塩を振る。

葉桜になった帰り道を通って、魚の下ごしらえをするという日常の一コマを詠んだ句です。花見という非日常から日常に帰ってきた感覚が表現されています。
【NO.24】正岡子規
『 茗荷より かしこさうなり 茗荷の子 』
季語:茗荷の子(夏)
意味:ミョウガよりも賢そうに見えるミョウガの子だ。

ミョウガは仏教説話で「食べると物忘れをしやすくなる」という逸話があります。この句では子は親に似ないように、若い芽は賢そうに見えるとどこか親心を感じさせる句になっています。
【NO.25】星野立子
『 美しき 緑走れり 夏料理 』
季語:夏料理(夏)
意味:美しい緑が走るように配置されている夏料理だ。

「夏料理」とは夏に好まれる、涼やかでさっぱりとした味付けの料理のことです。「緑」と表現していることから野菜のみずみずしさを称えています。

【NO.26】正岡子規
『 三千の 俳句を閲し 柿二つ 』
季語:柿(秋)
意味:沢山の俳句を閲覧した後に柿を2つ食べた。

ここで詠まれている「三千」とは「たくさん」という意味です。作者は雑誌「ホトトギス」の撰者をつとめていたため、多くの俳句を詠んで選評を書いていました。
【NO.27】橋本多佳子
『 星空へ 店より林檎 あふれをり 』
季語:林檎(秋)
意味:星空に向かって店に積まれたりんごがあふれそうになっている。

【NO.28】日野草城
『 みずみずし セロリを噛めば 夏匂う 』
季語:セロリ(冬)
意味:みずみずしいセロリを噛めば夏の匂いがする。

みずみずしいセロリを噛んで、季節が逆の「夏匂う」と表現しているのが面白い一句です。青々とした香りが夏を想像させたのでしょうか。
【NO.29】芥川龍之介
『 木枯らしや 目刺しに残る 海の色 』
季語:木枯らし(冬)
意味:木枯らしが吹いているなぁ。目刺しにはかつて泳いでいた海の色が残っている。

木枯らしと海は江戸時代から詠まれている組み合わせですが、この句は目刺しを介して海を感じているのがユーモアのある句です。かつて泳いでいた姿を想像して「海の色」と表現しています。
【NO.30】小林一茶
『 大根引き 大根で道を 教えけり 』
季語:大根引き(冬)
意味:大根を引き抜いて、引き抜いた大根で道を教えている。

「大根引き」とは大根を収穫している人を指す季語です。作業中の農家の人に道を尋ねたところ、引き抜いた大根であっちの方だよと教えられている様子が浮かんできます。
以上、食べ物に関する有名俳句でした!


今回は、食べ物に関する有名な俳句を30句紹介しました。
俳句には春夏秋冬のほかにも新年など、多くの時期の食べ物が登場します。
食べた時の心情やその食べ物から連想することなどいろいろな表現ができますので、ふと思いついたときに食べ物に関する俳句を詠んでみてはいかがでしょうか。