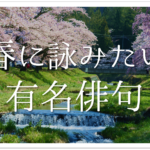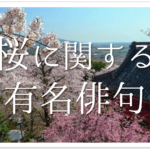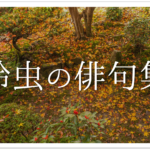「蝶(ちょう)」といえば春の代名詞です。
俳句においては「蝶」は春の季語になっていますが、春の以外にも夏秋冬の季語になっています。
「蝶」とだけあるときは春の季語ですが、「夏の蝶」など季節を頭につけるもの、「アゲハ蝶」など初夏にかけて見られる蝶の種類など、多彩な季節感を表す季語です。
今回はそんな「蝶(ちょう)」に関するおすすめ有名俳句を30句紹介していきます。
手枕や 蝶は毎日 来てくれる
ー小林一茶 pic.twitter.com/j6DhoKaUPa— はるき 能登の空から (@harukinotosora) December 23, 2018

「蝶(ちょう)」を題材にした有名俳句集【前編10句】

【NO.1】松尾芭蕉
『 起きよ起きよ 我が友にせん ぬる(寝る)胡蝶 』
季語:胡蝶(春)
意味:起きてくれ、起きてくれ。私の友になってほしい、寝ている胡蝶よ。

「起きよ起きよ」と2回繰り返しているところが、興奮しているような感情を表している芭蕉にしてはめずらしい句です。蝶と夢は切っても切れない関係性なので、中国の故事を意識しています。
【NO.2】松尾芭蕉
『 君や蝶 我や荘子が 夢心 』
季語:蝶(春)
意味:君が蝶で、私が荘子である夢を見たよ。

「胡蝶の夢」という「蝶である夢を見たが、目を覚ました自分が蝶の見る夢なのか、自分が蝶になる夢を見たのかわからない」という故事を引いています。高橋怒誰という芭蕉のスポンサーのような人物に当てた手紙にある俳句です。
【NO.3】与謝蕪村
『 釣り鐘に とまりて眠る 胡蝶かな 』
季語:胡蝶(春)
意味:釣鐘にとまって眠る胡蝶であることだ。

釣鐘は鳴らされると揺れるため、蝶がゆっくり羽を休めることはありません。しかし、この釣鐘は鳴らされないものなのか、蝶が眠っているようなのどかな風景を描いています。
【NO.4】小林一茶
『 寝ころんで 蝶泊らせる 外湯哉 』
季語:蝶(春)
意味:寝転んだ身体に蝶を泊まらせる外湯であることだ。

3月に道後温泉に旅したときに詠まれた句です。あたたかい春の陽気と外湯に、蝶も思わず誘われて寝転んで休んでいる人の近くに止まっている風景が浮かんできます。
【NO.5】小林一茶
『 又(また)窓へ 吹もどさるる 小蝶哉 』
季語:蝶(春)
意味:また窓の方に吹き戻される小さな蝶であることだ。

小さな蝶が風にさからって飛ぼうとして、何度も窓の方に吹き戻される風景を眺めている句です。「また」という表現から長い間小さな蝶の奮闘を眺めていることを表現しています。
【NO.6】宝井其角
『 猫の子の くんづほぐれつ 小蝶かな 』
季語:猫の子(春)
意味:猫の子がくんずほぐれつしてじゃれついている小さな蝶よ。

猫の子が動いている蝶に興味を示し、どうにか捕まえようとはね回っている様子を詠んだ句です。大きな蝶でないためなかなか捕まえられない様子が目に浮かびます。
【NO.7】西山宗因
『 世の中よ 蝶々とまれ かくもあれ 』
季語:蝶(春)
意味:世の中というものはなんとかなっていくものだ。「胡蝶の夢」の故事のように、花から花へとまっていく蝶の夢のようなものなのだから。

【NO.8】加賀千代女
『 雨の日は あすの夢まで こてふ哉 』
季語:こてふ(胡蝶)(春)
意味:雨の日は、眠って夢の中で胡蝶になって明日の朝まで飛んでいることしよう。

雨の日は蝶が飛ばないことと「胡蝶の夢」の故事から、雨の日は明日の朝まで眠っていようという意味になります。夢の中であれば晴れた空を自由に飛べるのに、という作者の願望を胡蝶の夢に託した表現です。
【NO.9】正岡子規
『 風吹て 山吹蝶を はね返し 』
季語:山吹(春)
意味:風が吹いて、蝶が止まろうとした山吹の花が蝶をはね返してしまった。

山吹は春の終わりに黄色の花を咲かせる低木で、花が風に散りやすい花です。そんな散りやすい山吹の花が風に吹かれて、止まろうとした蝶をはね返してしまったという面白さを詠んでいます。
【NO.10】正岡子規
『 何事の 心いそぎぞ 秋の蝶 』
季語:秋の蝶(秋)
意味:何事に心を急がせるのか、秋の蝶よ。

「秋の蝶」とは、立秋を過ぎてからみかける蝶のことで、春や夏の蝶と比べて弱々しく見えることが特徴の季語です。作者はそんな秋の蝶の姿に生き急いでいる姿を見てこの句を詠んでいます。
「蝶(ちょう)」を題材にした有名俳句集【中編10句】

【NO.11】高浜虚子
『 初蝶(はつちょう)を 夢の如くに 見失ふ 』
季語:初蝶(春)
意味:今年初めて見た蝶を、まるで夢であったように見失ってしまった。

初蝶は小さな蝶であることが多く、ひらひらと草原を舞っている蝶を見失ってしまった作者の心境を詠んでいます。本当に蝶がいたのか、蝶がいたという夢を見たのか、まさに胡蝶の夢の故事のような体験です。
【NO.12】高浜虚子
『 夏の蝶 日かげ日なたと 飛びにけり 』
季語:夏の蝶(夏)
意味:夏の蝶は、日かげや日なたをひらひらと行き交うように飛んでいる。

蝶は春のイメージですが、アゲハ蝶などの蝶は季語の分類としては夏の時期の蝶になります。暑い日なたと涼しい日かげを行ったり来たりして飛んでいる様子が表現されている俳句です。
【NO.13】高浜年尾
『 先の蝶 追うて行く蝶 我も行く 』
季語:蝶(春)
意味:先に飛んでいる蝶を追って行く蝶がいる。その蝶を私も追いかけるように行く。

【NO.14】阿部みどり女
『 初蝶を 追ふごと旅を 顧みる 』
季語:初蝶(春)
意味:春になって初めて見る蝶を追って歩くごとに、今まで旅してきたことを顧みる。

作者は北海道に生まれ、東京や鎌倉、仙台と居住地を移してきました。どの地域にいても見られる春の初めの蝶を見て、それまでの年月を思い起こしています。
【NO.15】西東三鬼
『 一粒ずつ 砂利確かめて 河原の蝶 』
季語:蝶(春)
意味:一粒ずつ砂利を確かめて回っているような、河原に蝶が飛んでいる。

季語として蝶を詠むときは草原が舞台の句が多いですが、河原の砂利の上で舞っている蝶を詠んだ句です。河原で飛んだり止まったりしている様子を、「一粒ずつ」と表現することで、小刻みに動いている様子が想像できます。
【NO.16】原石鼎
『 いとひくき 白蝶ばかり 野の原に 』
季語:蝶(春)
意味:なんと低く飛ぶのだろう。白い蝶ばかりが野原に飛んでいる。

ここで言う白蝶は、モンシロチョウなどのシロチョウ科の蝶のことです。「いと」という強調の副詞を使うほど低く飛んでいるので、草丈の低い緑の野原に白い無数の蝶が舞っている風景が浮かんできます。
【NO.17】角川源義
『 蝶さきに 真野(まの)の萱原(かやはら) 吹かれゆく 』
季語:蝶(春)
意味:蝶が先に飛んでいる。真野の萱原に風に乗って吹かれていく。

「真野の萱原」とは福島県南相馬市にある歌枕の地で、おくのほそ道でも芭蕉が訪れています。川沿いの一面の萱の野原に蝶が飛んでいく、荒涼とした風景です。
【NO.18】夏目漱石
『 初蝶や 菜の花なくて 淋しかろ 』
季語:初蝶(春)
意味:今年初めての蝶が飛んでいるなぁ。ここには菜の花が咲いていないので、寂しいだろう。

春といえばモンシロチョウに菜の花、というイメージがある人も多いのではないでしょうか。作者もその風景をイメージしていたのに菜の花がないため、蝶に自身の淋しさを託しているのでしょう。
【NO.19】山口青邨
『 とぶことの うれしととべる 紋白蝶 』
季語:紋白蝶(春)
意味:飛ぶことが嬉しいと飛んでいるモンシロチョウであることだ。

モンシロチョウは春の初めに見かけることの多い蝶です。「初蝶」と詠まれるときもモンシロチョウである場合があります。長い冬が終わって春になって飛ぶ蝶に、ようやく春が来たという作者の嬉しさを託して表現している句です。
【NO.20】水原秋桜子
『 稚子(ちし)の列 蝶がみちびき 蝶が追ふ 』
季語:蝶(春)
意味:歩いている子供たちの列を、蝶が導き、蝶が後ろから追っている。

歩いている子供たちの前に蝶が飛んでいて、後ろからも追いかけるように蝶が飛んでいる、春ののどかな風景です。子供たちは蝶を追いかけているのでしょうか、後ろから飛んでいる蝶が見守っているようにも感じます。
「蝶(ちょう)」を題材にした有名俳句集【後編10句】

【NO.21】正岡子規
『 蝶蝶や 順礼の子の おくれがち 』
季語:蝶蝶(春)
意味:蝶々が飛んでいるなぁ。順礼に行く子の中で遅れがちな子がいる。

蝶が順礼に行く子供たちの周りをひらひらと飛んでいる一句です。遅れがちな子がいることから列を成して歩いているのでしょう。
【NO.22】山口誓子
『 見初めたる あとはや次ぎの 蝶来る 』
季語:蝶(春)
意味:蝶が来たなと見初めたら、後から早くも次の蝶が来た。

蝶が飛んでいるなぁと眺めていたら、すぐに次の蝶が飛んできた様子を詠んだ句です。外を眺めていると蝶が次々と飛んで来るという風景が想像しやすい表現となっています。
【NO.23】松本たかし
『 愁(うれい)あり 歩き慰む 蝶の昼 』
季語:蝶(春)
意味:色々と悩んで愁いがある。歩きながら自分を慰める蝶が飛んでいる昼だ。

色々と思い悩むことがあり、気分転換に外を歩いている作者の様子を詠んだ句です。蝶がひらひらと舞う様子を見て心を慰めています。
【NO.24】高野素十
『 方丈の 大庇(おおびさし)より 春の蝶 』
季語:春の蝶(春)
意味:寺の四方の大きい庇から春の蝶を見る。

この句は作者が石庭で有名な龍安寺で詠んだと言われています。「方丈」は1丈(約3m)で、禅宗のお寺を示すのにも使われる用語です。
【NO.25】高浜虚子
『 線香の 煙にあそぶ 蝶々かな 』
季語:蝶々(春)
意味:線香の煙と遊んでいるような蝶々だなぁ。

立ちのぼる線香の煙で遊ぶように周囲を飛ぶ蝶を詠んだ句です。煙と共に高いところまで飛んでいったのでしょうか。
【NO.26】高浜虚子
『 山国の 蝶を荒しと 思はずや 』
季語:蝶(春)
意味:山国に飛ぶ蝶の飛び方は荒々しいと思う。

雪深い冬から春になり、蝶が飛び交うようになった風景を詠んでいます。平地の蝶よりも厳しい環境で過ごしているだけあって、荒々しい飛び方をしているように感じている一句です。
【NO.27】大野林火
『 あをあをと 空を残して 蝶分れ 』
季語:蝶(春)
意味:青々とした空を残して蝶たちが分かれていった。

【NO.28】星野立子
『 初蝶を 見て来しことを 言ひ忘れ 』
季語:初蝶(春)
意味:今年初めて蝶を見て来たことを言い忘れてしまった。

誰かと会って話していたのでしょう。話題として今年初めて蝶を見たことを話そうと思ったのにという残念がる様子がよく表れている一句です。
【NO.29】橋本多佳子
『 蝶が来る 阿修羅合掌の 他の掌に 』
季語:蝶(春)
意味:蝶が飛んでくる。阿修羅像の合掌していない他の手のひらにとまろうとして。

阿修羅像は顔が三面、腕が六本ある有名な仏像です。正面の手は合掌していますが、それ以外の手のひらにとまろうとして蝶がやってきた様子を詠んでいます。
【NO.30】大野林火
『 蝶のぼる 空たかくたかく ビルディング 』
季語:蝶(春)
意味:蝶がのぼっていく。空高く高く、あのビルディングを越えるように。

蝶がそびえ立つビルよりも高く飛んでいく様子を詠んでいます。真下から見上げているのか、少し離れたところから見ているのかで印象が変わってくる一句です。
以上、蝶(ちょう)を題材にした有名俳句でした!


今回は、蝶に関する有名俳句を30句紹介しました。
蝶は春の季語ですが、四季を通じてよく詠まれる題材です。また、胡蝶の夢の故事のように夢にまつわる表現としても使われます。
ひらひらと舞う蝶を見かけたら、ぜひ一句詠んでみてください。