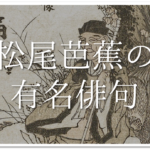俳句は日本に古くから伝わる、伝統的な表現方法の1つとして、現代になっても多くの人たちに親しまれています。
これまでに数多くの俳句が俳人により詠まれており、たくさんの作品があります。
その中でも「閑さや岩にしみ入る蝉の声」は、馴染み深く、一度は耳にしたことがあるでしょう。
「閑さや岩にしみ入る蝉の声」 芭蕉が句をよんだ場所だそうです。大垣は奥の細道のむすびの地ですが、こんな遠くから歩いて来たわけか。元気だな。 pic.twitter.com/KVbObdrU
— 片山 圭介 (@ksuke99) September 28, 2012
作者はどのような背景で句を詠んだのか、またこの俳句を口ずさんだ時の心情はどのようなものだったのでしょうか?
今回は、「閑さや岩にしみ入る蝉の声」の季語や意味・表現技法・鑑賞・作者について徹底解説していきますのでぜひ参考にしてみてください。
目次
「閑さや岩にしみ入る蝉の声」の季語や意味・詠まれた背景

閑さや 岩にしみ入る 蝉の声
(読み方:しずかさや いわにしみいる せみのこえ)
こちらの俳句は、日本を代表する俳人「松尾芭蕉」が詠んだ句です。

(松尾芭蕉 出典:Wikipedia)
松尾芭蕉は『野ざらし紀行』『おくの細道』などの紀行文で知られる江戸時代前期の俳人で、俳諧の基礎を作った人物です。一門から多くの弟子を輩出し、それぞれ個性的な作風の俳句を作り俳諧を世に広めるきっかけになりました。
それでは、早速こちらの俳句について詳しく解説していきます。
季語
こちらの俳句に含まれている季語は「蝉」で、夏の季語(夏を表現する言葉)です。
曾良の日記では、芭蕉が旧暦の5月27日にこの句を詠んだことが記載されています。
ちなみに、グレゴリオ暦(現在の暦)で見ると5月27日は【7月13日】に当たり、夏であることが分かります。
意味
この俳句の意味は、以下の通りです。
「なんて静かなのだろう。石にしみ入るように蝉が鳴いている。」
蝉の鳴き声がうるさいのに、どうして芭蕉は「閑かさや」と感じたのかという部分が不思議です。
しかし、何度か口ずさんでみると、騒がしい蝉の声を忘れてしまうほどの閑かな山奥で詠まれていることを感じます。さらに、芭蕉自身がこの世とは思えない、とても静寂な空間に引き込まれて行く様子が感じ取れます。
何も聞こえない無の世界、つまり芭蕉が己の心の中を見つめているのであろうとこの句から推察します。
それほどの無の境地の中で、芭蕉は何を考えていたのでしょう。
この句が詠まれた背景
芭蕉は1689年から門人の曽良と共に、江戸を出発し旅に出ます。

(芭蕉(左)と曾良(右) 出典:Wikipedia)
その旅は、150日間をかけて東北・北陸・関東地方を周遊するとても長いもの。芭蕉は旅の途中で見た情景や心情を数多くの俳句として残しています。
こちらの句も芭蕉が、山形県にある立石寺に立ち寄った時に詠んだものです。
宝珠山立石寺(山寺)【山形県】 松尾芭蕉が『奥の細道』で「閑さや岩にしみ入る蝉の声」という俳句を詠んだ有名な名所。 pic.twitter.com/lGkf1s3ecl
— ★厳選★世界遺産 (@gensen_isan) September 13, 2018
この長い旅の間に詠んだ句を集めた作品が、有名な『おくのほそ道』です。
その中でも「閑さや岩にしみ入る蝉の声」は、非常に優れた作品として親しまれています。
✔ 【補足情報】立石寺について
この句の舞台となった立石寺は、通称を「山寺」と言われるほど、眺めの良い場所です。
奇岩が多い山で、山全体が修行の場として使用されています。麓の登山口から大仏殿のある奥ノ院までは1時間かかり、絶景が拝める景勝地です。
芭蕉は尾花沢という場所に滞在しているときに、会う人々から「行った方がいい」と勧められて立石寺を訪れています。
「日いまだ暮れず、麓の坊に宿かり置きて、山上の堂に登る。岩に巌を重ねて山とし、松柏年ふり、土石老いて苔滑かに、岩上の院々扉を閉ぢて物の音聞えず。岸をめぐり岩を這ひて仏閣を拝し、佳景寂寞として心すみ行くのみ覚ゆ。」
『おくのほそ道』の立石寺の該当部分では、巨石の見事さや苔松や柏の樹齢、苔の美しさなどに感動しています。
「閑さや岩にしみ入る蝉の声」の表現技法

この句で使われている表現技法は・・・
- 閑かさやの部分の初句切れ
- 岩にしみ入る蝉の声の部分の暗喩
- 蝉の声の部分の体言止め
の3つです。
閑かさやの部分の初句切れ
まず、閑かさやの部分にみられる初句切れ(切れ字)は、余韻を表現する技法です。
初句切れにすることで俳句に「余韻」ができリズムが生まれます。
つまり「閑かだなあ・・・・」ということです。その後「岩にしみ入る蝉の声」と続き、余韻の中で味わう蝉の声をしっかり感じさせてくれます。
芭蕉は地の文で立石寺の静けさを述べています。実際に見聞きしていない読者にも、初句で静かであることを強調することで、しんとしたお寺の様子が浮かんでくる効果がある技法です。
岩にしみ入る蝉の声の部分の暗喩
暗喩法とは「まるで〜のような」と比喩する文章表現方法です。
この技法を使うことにより、詠んでいる状況や気持ちをイメージしやすくなります。
ちなみに、「蝉の声」など擬人化を多用するのは、芭蕉が尊敬している「杜甫(とほ)」という詩人の影響もあります。
杜甫とは中国の唐の時代(8世紀)に生きた詩人で、「詩聖」と呼ばれるほどの漢詩の達人でした。杜甫は草木や動物を擬人化させる手法を取ることがあり、芭蕉もその影響を受けています。
蝉の声の部分の体言止め
下句に体言止めを入れることで、俳句のインパクトが強くなります。
「石にしみ入る」ほどの声で蝉が鳴いていると表現されているため、「閑さや」という部分に矛盾を感じます。
この部分が、この俳句を解読する際の重要ポイントです。
芭蕉は「暗喩」の技法を用いて、精神的な「閑さや」を表現しています。
芭蕉がこの句を詠んだ山形県立正寺は、森深い静かな場所にある寺院。蝉が鳴くと山に反響し、こだまとなって戻って来ます。
つまり、蝉の声がこだまとなり戻ってくるほどに、立正寺はとても閑かな場所にあるわけです。
そのような俗世の騒がしさから離れた、異次元の閑かな世界に心が吸い込まれて行く様子をこの句では表現しています。
【番外編】文人たちの間でセミ論争が勃発

松尾芭蕉が詠んだセミには、「アブラゼミ(斎藤茂吉説)」「ニイニイゼミ(小宮豊隆説)」の2説があり、一時期セミの種類を巡って論争になりました。
アブラゼミとニイニイゼミはどちらも日本全国に生息しています。しかし、鳴き始める時期や鳴き声に違いがあり、どちらがこの一句に登場するセミか論争が続いていました。
アブラゼミは7月中旬から鳴き始め、「ジリジリジリ」と抑揚をつけて鳴きます。
一方のニイニイゼミは6月中旬から7月上旬と他のセミより早く鳴き初め、「ジィー」と一定の鳴き声なのが特徴です。
実地調査の結果として舞台となった立石寺ではニイニイゼミが優勢だったため、ニイニイゼミと断定されました。
作者「松尾芭蕉」の生涯を簡単に紹介!

(松尾芭蕉 出典:Wikipedia)
この句を書いたのは、有名な俳人である松尾芭蕉です。
松尾芭蕉は、1644年に三重県伊賀市(当時の伊賀国)で生まれました。本名は松尾宗房。松尾芭蕉という名は、俳号になります。
芭蕉の実家は、平氏の末流に当たる血筋でしたが、身分は農民に過ぎませんでした。13歳の時に父が亡くなり、兄が家督を相続。しかし、決して生活は楽ではなかったと言われています。
18歳の時に藤原良忠という人と主従関係を結び、小間使いとして働き始めます。この藤原良忠は俳句を詠むのがうまく、芭蕉が俳諧の世界に足を踏み入れるきっかけとなりました。
同じ年に主人藤原良忠と一緒に北村季吟の元に弟子入りをして、本格的に俳句の道を進んで行きます。しかし、24歳の時に藤原良忠が亡くなるという不遇の出来事が起こりました。これにより、芭蕉は俳人として一生を生きて行こうと決めたのです。
その後、北村季吟に師事し、様々な作風の俳諧を作り出します。京都ではちょっとした有名人となり、季吟から卒業の意味を持つ俳諧作法書『俳諧埋木』の伝授が行われたことにより、江戸に上京することを決意しました。ですが土地柄が変われば、芭蕉を知る人は全くいなく、いろいろと苦労をしたようです。
江戸へ入った芭蕉はそれまでの本名であった「宗房」から「桃青」という号を使うようになります。俳諧の師である宗匠となった芭蕉は、深川の「芭蕉庵」へと移り住み、号も「芭蕉」と変えて我々が現在知る「松尾芭蕉」となったのです。
ようやく江戸で認知されるようになった頃に芭蕉は俗世に嫌気がさし、旅に出て俳句を詠むことを決意しました。これが、『おくのほそ道』に続く俳諧と紀行文の誕生となります。
東海道を西に旅した『野ざらし紀行』を皮切りに、鹿島神宮へ詣でた『鹿島詣』、伊勢へ向かう『笈の小文』、京都から江戸へ戻る旅路を綴った『更科紀行』と様々な旅を続けました。
『おくのほそ道』ではそれまで関西方面への旅が多かったことに対し、東北にある名所や歌枕を旅したいという意欲が旅立ち前の文章から感じられます。
松尾芭蕉は、このように俳句の世界で生き、食中毒または赤痢により50歳でこの世を去りました。
松尾芭蕉のそのほかの俳句
(「奥の細道」結びの地 出典:Wikipedia)