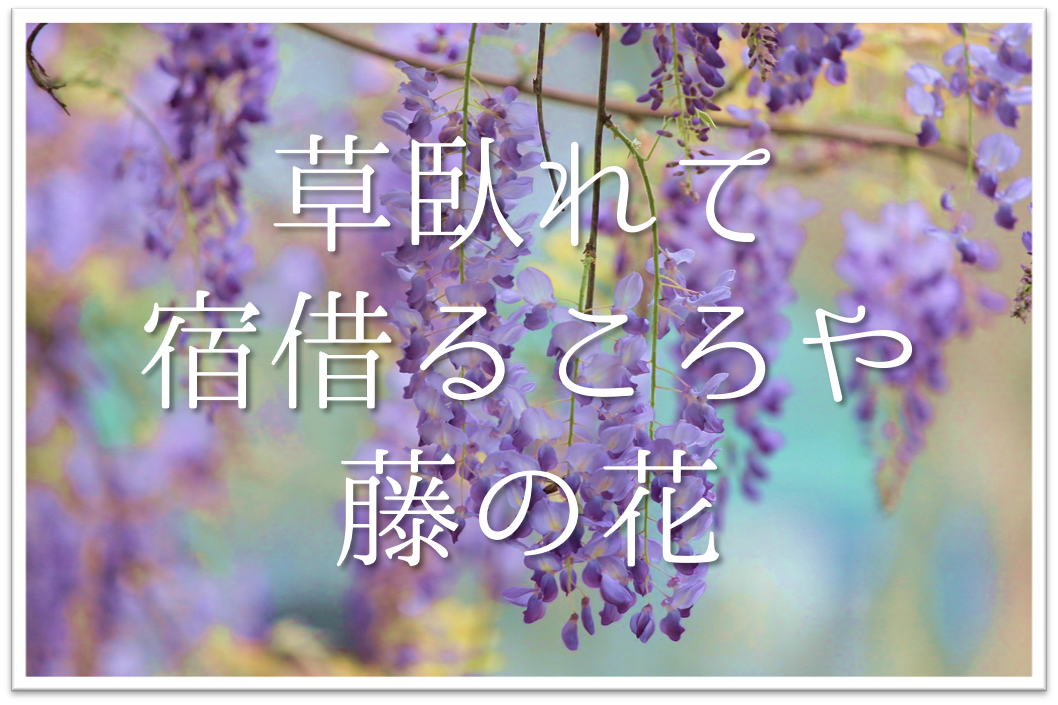
江戸時代に活躍した俳句の名人「松尾芭蕉」。
彼は後世にもその名は高く伝えられ、伝説的存在となっています。
松尾芭蕉の句も著書も、文学としての高い芸術性を持ち、多くの人を魅了し続けています。
松尾芭蕉は、時代を超えて多くの文学者から慕われ、松尾芭蕉の句や著書から影響を受けた作品も後を絶ちません。
今回は、「笈の小文」という紀行文にある、「草臥れて宿借るころや藤の花」という句をご紹介します。
草臥れて宿借る頃や藤の花
今日は芭蕉が奥の細道の旅に出発した日なのですが昨年取り上げましたので笈の小文に藤の句があるのでご紹介します。調べたら5月15日(昨日)でしたww
一日の旅に疲れ旅籠を求める黄昏。晩春の暮色の中に藤の花が咲き垂れてそこはかとない旅愁と春愁を誘う
奈良市名勝依水園 pic.twitter.com/3zfu2fvMWs
— 🍇藤原東子(N700Supreme)🍇 (@fujiwaraason2) May 15, 2019
本記事では、「草臥れて宿借るころや藤の花」の季語や意味・表現技法・作者などについて徹底解説していきます。
目次
「草臥れて宿借るころや藤の花」の季語や意味・詠まれた背景

草臥れて 宿借るころや 藤の花
(読み方:くたびれて やどかるころや ふじのはな)
こちらの句の作者は、江戸時代前期に活躍した俳人「松尾芭蕉」です。
季語
こちらの句の季語は「藤の花」、春の季語です。
藤はマメ科のつる性の植物で、木などに巻き付いて房状の花を咲かせます。
桜よりも遅い時期で、春の終わりを飾るように咲く花です。
意味
この句を現代語訳すると・・・
「歩きつかれ、くたびれてきて、そろそろ宿をとるころ合いとなってきた。ふと気づくと藤の花が見事に咲いているよ。」
という意味になります。
「草臥れて(くたびれて)」は、「くたびれて」当時の口語の表現でした。
この句が詠まれた背景
この句は、「笈の小文」という紀行文にのっています。
「笈の小文」とは、松尾芭蕉が貞享4年(1687年)の10月に江戸を出て、尾張(愛知県)・伊賀(三重県)・伊勢(三重県)・大和(奈良県)・紀伊(和歌山県)をまわり、須磨や明石(どちらも兵庫県)を旅したときの俳諧、記録をまとめた書のことです。
この句は、松尾芭蕉が大和国の八木(奈良県)で宿を求めた時に詠まれた句になります。
芭蕉の門人・服部土芳の著書には、師である芭蕉の句や門人の句への評価をまとめた「三冊子(さんぞうし)」というものがあります。
芭蕉の句の推敲の過程が分かるものもあり、興味深い資料です。
「三冊子」によると、この句は「ほととぎす宿借るころや藤の花」という句がオリジナルだったようです。
「草臥れて宿借るころや藤の花」の表現技法

(関宿 出典:Wikipedia)
この句で使われている表現技法は・・・
- 「宿借るころや」の切れ字(二句切れ)
- 「藤の花」の体言止め
になります。
「宿借るころや」の切れ字(二句切れ)
切れ字とは、感動や詠嘆を表す言葉で、その句の感動の中心を表します。
「かな」「や」「けり」などが代表的で、「…だなあ」というくらいの意味になります。
今回の句においては「宿借るころや」の「や」が切れ字に該当します。「宿を借りるころだなあ」という意味になります。
また、この句は「宿借るころや」の二句のところで切れるため、『二句切れ』の句になります。
「藤の花」の体言止め
体言止めとは、文の終わりを体言つまり名詞で終わることで、印象を強めたり、余韻を残す表現技法のことです。
「藤の花」を体言止めにすることで、余計な言葉を用いずして花の見事さを伝えています。
「草臥れて宿借るころや藤の花」の鑑賞文

この句は、「草臥れて」と言う言葉が特徴的です。
意味するところは現代語と変わりません。ふつう詩歌では文語表現を使うことが多いですが、ここは口語表現で砕けた調子になります。
一日の旅の疲れをしみじみ感じるとともに、「よくも歩いてきたもんだ。今日も無事にやってきた。」といったような充足感や達成感もにじみます。
気取りすぎず、率直な気持ちが伝わってきます。
また、「くたびれた」と言いつつ、作者の視線は見事な藤の花に惹きつけられています。
だらりと垂れ下がって咲くさまに、今日の旅程に疲れ果てた自分が重なったのでしょうか?
それでも、藤の花のみごとさ、美しさを感じる生き生きとした心の働きが句となったのでしょう。
一日旅を続けてきて、宿を借りるころになったと言うのですから、時は夕刻であると考えられます。
晩春の夕映えに、あでやかに咲き誇る藤の花。宿が慕わしく思われる疲労感。旅情あふれる句です。
作者「松尾芭蕉」の生涯を簡単にご紹介!

(松尾芭像 出典:Wikipedia)
松尾芭蕉は、江戸時代前期に活躍した俳諧師です。
寛永21年(1644年)に伊賀国、現在の三重県伊賀市で生まれました。
本名は松尾宗房(まつお むねふさ)です。宗房(むねふさ)を音読みにした宗房(そうぼう)を最初俳号としましたが、桃青(とうせい)と言う俳号をへて、芭蕉(ばしょう)という俳号を名乗るに至りました。
京都の国学者北村季吟に師事し、のちに江戸にくだります。はじめは日本橋に住んでいましたが、後深川にうつりました。
この深川の住まいには、芭蕉という植物が植えられ、深川の住まいは芭蕉庵とも呼ばれました。ちなみに、芭蕉と言う植物はバナナの仲間です。
各地を旅して、旅先での出来事や思いなどとともに句を記しました。そうした紀行文のなかで最も有名なものが「おくのほそ道」です。「おくのほそ道」で芭蕉の文学は一つの完成を見たとされ、芭蕉の作風は「蕉風」といってその高い芸術性は世界でも評価されています。
元禄7年(1694年)に大阪(当時の表記は大坂)で客死しました。
松尾芭蕉のそのほかの俳句
(「奥の細道」結びの地 出典:Wikipedia)
- 「古池や 蛙(かわず)飛び込む 水の音」
- 「夏草や 兵どもが 夢の跡」
- 「五月雨をあつめて早し最上川」
- 「荒海や 佐渡に横たふ 天の河」
- 「旅に病(やん)で 夢は枯野を かけ廻(めぐ)る」















