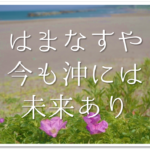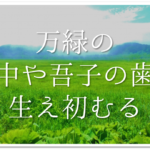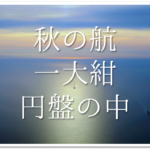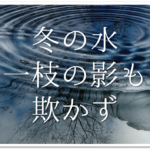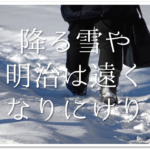五七五のわずか17音で四季の美しさや人間の心情を詠みあげる「俳句」。
最近では小学校の国語の授業の中でも取り上げられるなど、認知度は急上昇しています。テレビ番組の影響もあり、俳句を実際に作っている方も多いのではないでしょうか。
プレバト面白い🤣
特に私俳句のコーナーが好き‼️
夏井先生と梅沢富美男さんのやりとり最高😆しかも今回梅沢さん8位。
面白い結末だったとプレバト俳句ファンとしては思う。この二人の掛け合いが見れるから番組は終わることないよ!って思うのは私だけなのかな。。#プレバト pic.twitter.com/q58SfgcN4t
— マツノミユ/WEBライター (@MatsunoMiyu) October 12, 2019
今回は、強い個性と思想性で有名な「中村草田男」の俳句(代表作)を紹介していきます。

草田男氏が詠んだ数多くの俳句の中から、春、夏、秋、冬の代表的な作品をそれぞれ紹介していきます。
中村草田男の人物像や作風

中村草田男(なかむら くさたお)は、明治34年(1901年)に 清国福建省で生まれた俳人です。本名は中村清一郎といいます。
日本への帰国後は、愛媛県の松山と東京をいったりきたりしながら成長しました。
若いころの草田男はドイツの哲学者であるニーチェの著書を愛読し、西洋思想にも影響されながら、いつしか文学の道を志すことになります。
加藤楸邨や石田波郷らとともに、人間探求派の俳人といわれた草田男は、自然を写生するように観察しながら心理描写を投影していく表現方法を作り上げました。
中村草田男は、思想や観念をテーマとする現代俳句の道筋を作った人物だといわれています。
中村草田男の髪の毛なびいてるな。 pic.twitter.com/Bh99sie2EM
— やっさんブル (@atataka_yassy) November 17, 2015

次に、中村草田男の代表的な俳句を季節(春夏秋冬)別に紹介していきます。
中村草田男の有名俳句・代表作【36選】

(写真:東京都あきる野市の五日市カトリック霊園にある中村草田男の墓地)
春の俳句【9選】

【NO.1】
『 勇気こそ 地の塩なれや 梅真白 』
季語:梅(春)
現代語訳:梅は小花でもよく香りが立ちます。塩は少量でも塩辛く、少しの勇気が世界を変えるのです。

【NO.2】
『 焼跡に 遺る三和土や 手毬つく 』
季語:手毬(新年)
現代語訳:空襲で焼け落ちてしまった家の跡に、わずかに残っている三和土(たたき)。そこで子どもたちが手毬をついていることだよ。

【NO.3】
『 とらへたる 蝶の足がきの にほひかな 』
季語:蝶(春)
現代語訳:蝶を捕えたところ、蝶は逃げようと懸命に足をもがいている。全身でもがくものだから、蝶の匂いが香ってくるようだよ。

【NO.4】
『 校塔に 鳩多き日や 卒業す 』
季語:卒業(春)
現代語訳:卒業式当日。改めて校塔を見上げると、今日はなんと鳩の多いことか。

【NO.5】
『 ひた急ぐ 犬に会ひけり 木の芽道 』
季語:木の芽道(春)
現代語訳:ひた急ぐ犬にあった木の芽が芽吹いてきた春の道だ。

【NO.6】
『 春の闇 幼きおそれ ふと復(かえ)る 』
季語:春の闇(春)
現代語訳:春の闇が幼い私にとってはおそろしかったのだとふと思い出した。

【NO.7】
『 春の月 城の北には 北斗星 』
季語:春の月(春)
現代語訳:春の月が出ている。松山城の北には北極星が輝いている。

【NO.8】
『 昔日の 春愁の場(にわ) 木々伸びて 』
季語:春愁(春)
現代語訳:昔、春の愁いを伴って過ごした庭の木々があの頃よりも伸びている。

【NO.9】
『 わが背丈 以上は空や 初雲雀 』
季語:初雲雀(春)
現代語訳:私の身長以上は空だぞ、初めて空を飛ぶ雲雀よ。

夏の俳句【9選】

【NO.1】
『 蟾蜍 長子家去る 由もなし 』
季語:蟾蜍(ひきがえる)(夏)
現代語訳:一度住み着くとあまり住む場所を変えないといわれている蟾蜍(ひきがえる)のように、長子である自分が家を出る理由はない。

【NO.2】
『 はまなすや 今も沖には 未来あり 』
季語:はまなす(夏)
現代語訳:浜辺には、幼い日に見たのと同じはまなすの赤い花が咲いている。かつて海の向こうに見た未来は、今も同じように海の向こうに見える。

【NO.3】
『 万緑の 中や吾子の歯 生え初むる 』
季語:万緑(夏)
現代語訳:草木の深緑に覆われ、あたり一面緑の景色だ。そんな生命力溢れるこの時期に、わが子に初めての白い歯が生えはじめたことだよ。

【NO.4】
『 六月の 氷菓一盞の 別れかな 』
季語:六月(夏)
現代語訳:六月のある日。最後は氷菓を一緒に食し、慌ただしく別れたよ。

【NO.5】
『 松葉牡丹 玄関勉強 腹這ひに 』
季語:松葉牡丹(夏)
現代語訳:松葉牡丹が咲いている。暑さに負けて玄関で腹ばいになって勉強をしている。

【NO.6】
『 香水の 香ぞ鉄壁を なせりける 』
季語:香水(夏)
現代語訳:あの人の香水の香りだ。この香りこそが鉄壁のような感覚をもたらしている。

【NO.7】
『 毒消し飲むや わが詩多産の 夏来る 』
季語:夏来る(夏)
現代語訳:毒消し飲もう。私が詩をたくさん作る夏がやって来た。

【NO.8】
『 夜の蟻 迷へるものは 弧を描く 』
季語:蟻(夏)
現代語訳:夜に蟻たちが歩いている。迷っているものは弧を描くように違う方向へ行ってしまう。

【NO.9】
『 梅雨の夜の 金の折鶴 父に呉れよ 』
季語:梅雨の夜(夏)
現代語訳:梅雨の夜に君が折った金の折り紙の折り鶴を父におくれよ。

秋の俳句【9選】

【NO.1】
『 秋の航 一大紺 円盤の中 』
季語:秋
現代語訳:航海で私は今広い海の上にいる。見渡す限り一面海で、まるで私は一つの大きな紺色の円盤の中にいるようだよ。

【NO.2】
『 葡萄食ふ 一語一語の 如くにて 』
季語:葡萄
現代語訳:葡萄の実を一粒ずつ食べる。言葉を一語一語味わい、かみ締めるように。

【NO.3】
『 友もやや 表札古りて 秋に棲む 』
季語:秋
現代語訳:久しぶりに友を訪問したところ、表札がやや古び、落ち着いた感じの面持ちになっていた。「秋に棲む」といった表現がふさわしいほど、自然の趣が感じられるよ。

【NO.4】
『 仔馬爽やか 力のいれ処 ばかりの身 』
季語:爽やか
現代語訳:天高く、仔馬が飛び跳ねるようにして、牧場を駆け回っているよ。

【NO.5】
『 牛乳屋 ちらと睹(み)し秋暁の 閨(けい)正し 』
季語:秋暁(秋)
現代語訳:朝方にやってくる牛乳屋がちらっと見た秋の夜明けの寝室はいつも通りだ。

【NO.6】
『 空は太初の 青さ妻より 林檎うく 』
季語:林檎(秋)
現代語訳:空は大昔の頃のような青さだ。妻からリンゴを受け取る。

【NO.7】
『 妻二タ夜(ふたよ) あらず二タ夜の 天の川 』
季語:天の川(季語)
現代語訳:妻が二晩もいない。そんな二晩の間でも天の川が美しく見えた。

【NO.8】
『 撫子や ぬれて小さき 墓の膝 』
季語:撫子(秋)
現代語訳:撫子が咲いているなぁ。濡れて小さく、墓の膝辺りに咲いている。

【NO.9】
『 紅葉焚きし 灰やしばらく 火を含む 』
季語:紅葉焚き(秋)
現代語訳:紅葉を焚いたあとの灰だなあ。しばらく火を含んでいるように赤くなっている。

冬の俳句【9選】

【NO.1】
『 冬の水 一枝の影も 欺かず 』
季語:冬の水
現代語訳:冬の水をたたえる池の水面は、まるで鏡のように忠実に木々を映しているよ。枝の一本さえもごまかしなく正確に。

【NO.2】
『 降る雪や 明治は遠く なりにけり 』
季語:雪
現代語訳:雪が降ってきた。外へ飛び出していく小学生たちの姿を見て、自分が小学生だった時の明治時代にいるかのような気持ちになったよ。しかし、その時からもう20年近くも経っているのだなぁ。

【NO.3】
『 木葉髪 文芸永く 欺きぬ 』
季語:木葉髪
現代語訳:秋から冬にかけて、抜け毛が多くなる季節だ。

【NO.4】
『 あたゝかき 十一月も すみにけり 』
季語:十一月
現代語訳:11月とはいえ、まだ暖かい。そんな11月を暮らしているよ。

【NO.5】
『 雪女郎 おそろし父の 恋恐ろし 』
季語:雪女郎(冬)
現代語訳:まるで雪女郎のようだ。恐ろしい、父の恋は恐ろしい。

【NO.6】
『 寒星や 神の算盤(そろばん) ただひそか 』
季語:寒星(冬)
現代語訳:寒い冬の夜空に星だ。神様のそろばんの玉のような星は音を立てずにただ密かに輝いている。

【NO.7】
『 降誕祭 睫毛は母の 胸こする 』
季語:降誕祭(こうたんさい)(冬)
現代語訳:クリスマスだ。子供は眠くてまつ毛を母の胸にこすらせるようにむずがっている。

【NO.8】
『 白き息 はきつつこちら 振返る 』
季語:白き息/息白し(冬)
現代語訳:白い息を吐きながら相手がこちらを振り返った。

【NO.9】
『 冬空を いま青く塗る 画家羨(とも)し 』
季語:冬空(冬)
現代語訳:冬空をいま青く塗っている画家が羨ましいなぁ。

さいごに

今回は、中村草田男が残した俳句の中でも特に有名な作品を現代語に訳し、そこに込められた意味、簡単な感想を紹介してきました。
草田男氏の作品は、人々の日常生活や人間性に根ざした作風が特徴的です。
どの句も鋭い視点で描かれ、とても魅力的なものばかりですので、ぜひ他の俳句にも目を向けてみてください。
うわわー、すごいものが届きました。
中村草田男の全句を季題別に収録!
前書と註一覧、付録の自句解説など、もりだくさん。萬緑編集部最後の大仕事…感謝です。勉強がんばろ。 pic.twitter.com/MxLce5o4aU— みろく@森の座(旧・萬緑) (@miroku_cat) March 23, 2017

最後まで読んでいただきありがとうございました。