
少々古風なイメージもある俳句ですが、最近は人気タレントさんが俳句にチャレンジするバラエティー番組があったり、ペットボトル飲料のラベルにさりげなく書かれた俳句に、思わずうなってしまうこともありますよね。
基本ルールさえ押さえておけば、俳句は誰にでも簡単に楽しめます。
今回は、秋にちなんだ季語を使った俳句の簡単な作り方とコツをご紹介していきます。

目次
俳句とは?基本的なルールを知ろう!
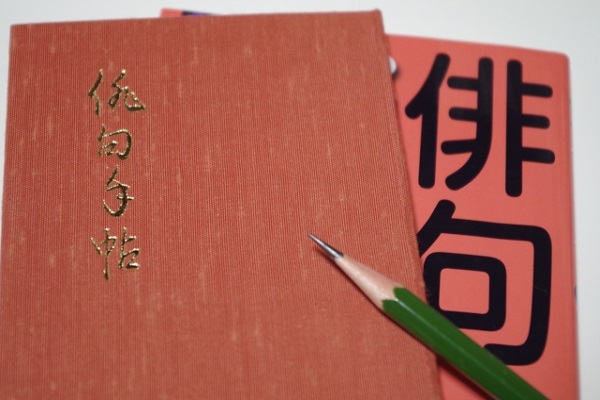
俳句は五・七・五の言葉に季節の言葉を織りまぜて作る定型詩のことで、基本ルールは・・・
①五・七・五の十七音で作る
②季語を使う
この2つだけです。
①五・七・五の十七音で作る
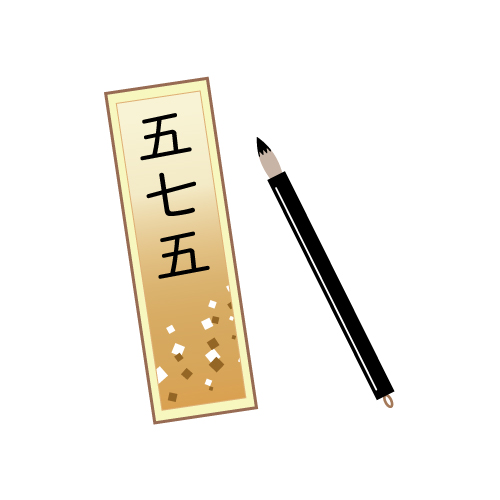
例えば
秋深き 隣は何を する人ぞ (松尾芭蕉)
- あ・き・ふ・か・き(五)
- と・な・り・は・な・に・を(七)
- す・る・ひ・と・ぞ(五)
上記のように、字数ではなく音で数えます。
五・七・五のリズムは俳句以外にも、川柳や短歌はもちろん、交通標語や歌の歌詞にも多用されていて(例:蛍の光)とても身近なリズムです。
言葉選びで迷ったときなどは、音読しながらつくってみるとリズムのよい言葉選びができます。
②季語を使う

季語とは、「春夏秋冬」その季節らしい言葉のことを言います。
【例えば】
- 春・・・「春分」「お花見」「桜」「入学式」
- 夏・・・「海」「猛暑」「梅雨」「アイスクリーム」
- 秋・・・「紅葉」「もみじ狩り」「栗」
- 冬・・・「雪」「ゆきだるま」「炬燵」などなど
はじめて俳句を作ろうとしたとき、たった十七音という限られた音のなかに季語を入れようとすると、少しせま苦しさを感じることがあるかも知れません。
季語にこだわらない無季俳句という世界もありますが、季語は四季折々のなかの様々な出来事に奥行を出してくれます。
季語を含んだ俳句の例
名月を とってくれろと 泣く子かな (小林一茶)
季語:名月
意味:子どもと月見をしていたら、あの月をとってとって、と言って子どもが泣いてしまいました。
上記の「名月」という季語の俳句を作った場合、それを鑑賞する人は、一瞬で満月にすすきが揺れている風景や、秋のスーパームーンなどそれぞれの「明月」をイメージするでしょう。
まったく同じ物ではないにしろ、作者が詠んだ秋の世界感を細かな説明なしに共有させるのが季語の役目なのです。
秋の俳句の作り方&コツをわかりやすく解説!
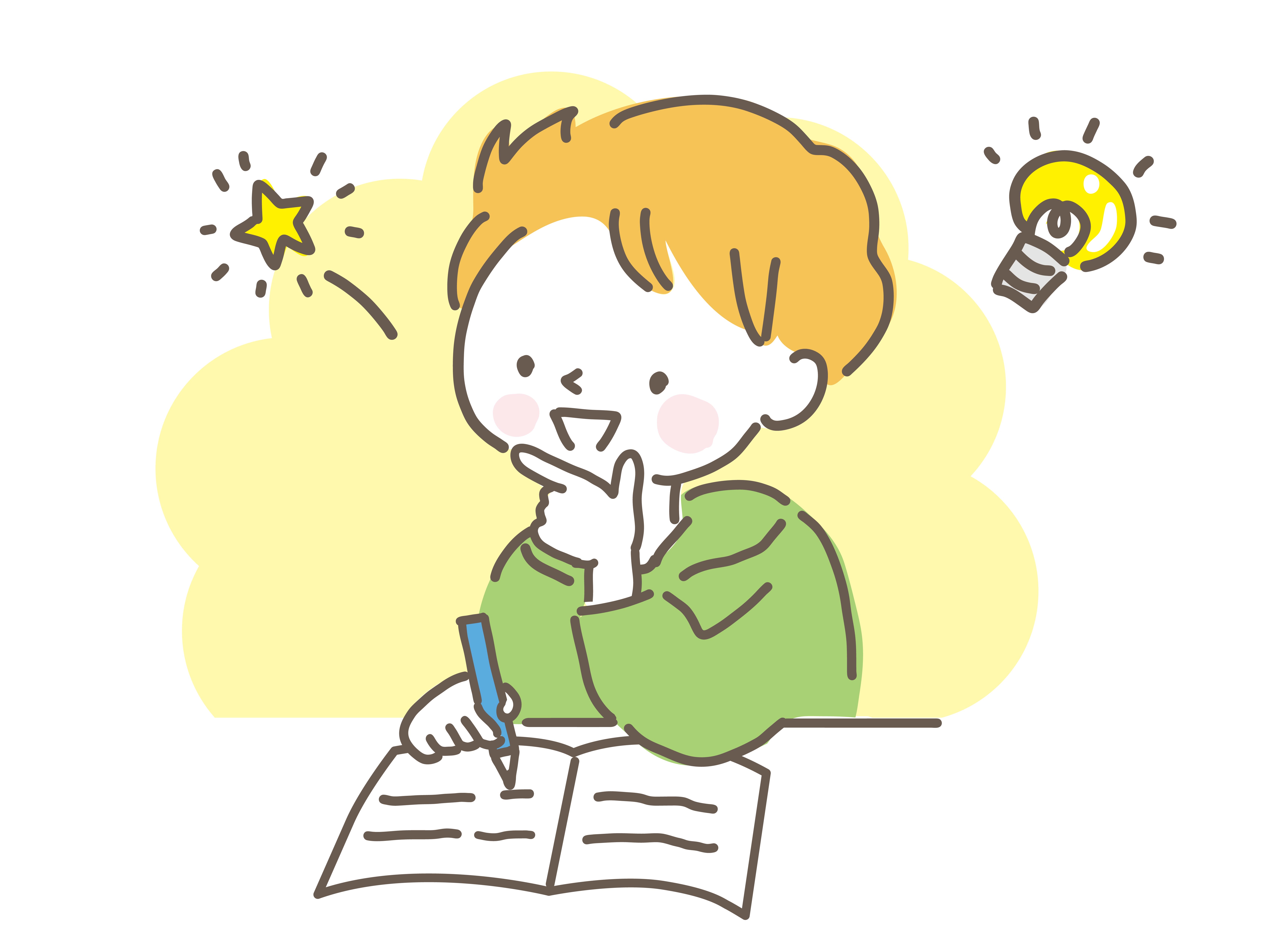
①まずは秋の季語を選ぼう!
まずは、俳句に入れる秋の季語を選びましょう。
秋の俳句には以下ののようにたくさんありますので、お好きなものを選びましょう。
秋の季語
「秋」「文月」「立秋」「残暑」「九月」「長月」「十月」「秋の日」「秋の夜」「夜長」「冷やか」「冬近し」「秋色」「秋の雲」「月」「名月」「星月夜」「天の川」「台風」「稲妻」「秋の山」「花畑」「運動会」「文化祭」「美術展」「新酒」「新米」「枝豆」「干柿」「紅葉狩」「敬老の日」「秋分の日」「体育の日」「文化の日」「七夕」「秋祭」「ハローウィン」「渡り鳥」「小鳥」「秋鯖」「秋鰹」「鰯」「秋刀魚」「鮭」「松茸」「ひぐらし」「とんぼ」「鈴虫」「金木犀」「芙蓉」「稲」「秋の七草」「秋草」「すすき」「桃」「梨」「栗」「胡桃」「柿」「林檎」「葡萄」「栗」「柚子」「レモン」「銀杏」「紅葉」「カンナ」「蘭」「朝顔」「コスモス」「菊」「鳳仙花」「萩」「葛」「桔梗」「撫子」「野菊」「西瓜」「南瓜」「馬鈴薯」「サツマイモ」「とうもろこし」「芋」「牛蒡」「生姜」など。
※他にもたくさんの季語があります。もっと知りたくなってきたら、「歳時記」という季語をまとめた本を手にとってみてください。思いもよらない季語に出会えるかもしれませんよ。
②「場面」や「気持ち」を切り取ってみよう
俳句を作ってみたくなったとき、実際にどのような内容を詠むとよいのか、最初はどうしても悩んでしまいますよね。
まずは気負わずに肩の力を抜いて、目に映るもの、耳に聞こえてくるもの、心に感じるものなど、五感をおおいに使って、いろんなものを観察してみましょう。
すると日常生活のなかや身の回りには、俳句の材料が思ったよりたくさんあることにきっと気づくでしょう。
以下に例をいくつかあげてみます。
【例:身近な自然】
- ベランダのプランターで咲いた花
- 突然の雨や雷雨
- 秋の虫の声
【例:日常の出来事や季節のイベントなど】
- お正月の家族団らん
- 旅行中の風景や出来事
- 通勤・通学中に見かけた光景
- 季節の果物や食材
【例:趣味、好きな場所、人】
- 登山やつり
- カフェやコンサート
- やさしい夫、妻、かわいい子ども
どれも平凡だし、特別な風景ではないと感じられたかもしれませんが、このように日常のどこにでもあることこそ、実は立派な俳句の材料なのです。
先に季語を決めてからでもよいですし、こういった場面や気持ちからイメージをつくって、そこに季語をあてはめてもよいのです。
そして、材料が全部そろったら、あまり深く考えず、手紙や日記を書くように「あなたのいつもの言葉」で、あえて五・七・五にこだわらずに書いてみましょう。
③伝えたい芯となるものを決める
いつもの言葉で文章ができたら、一番伝えたいことはなにかを考えて、その部分をひとつ選び出してみましょう。
俳句の世界では「1つの俳句に中心が1つ」が原則です。作者がいちばん伝えたいこと、これを「俳句の中心」といいます。
もし「俳句の中心」を絞っていくときに、どうしても削れないように思えることがあるときは、思い切ってその部分を削り、それがまた中心となる別の句を作ってみましょう。
秋深き 隣は何を する人ぞ という松尾芭蕉の有名な俳句があります。
この句の背景には、旅先で体調を崩してしまい、予定していた句会に出られなくなった芭蕉が、ある人に頼んでこの句を句会に届けたという逸話があります。
ひとりの病床で隣の人に思いをはせた「深まる秋のなか、ひとりでひっそりとしていると、どうも隣にも同じような人がいる。いったい何をしている人だろう。なにやら人恋しいものだ」という思いと同時に「晩秋を自分の余命と重ねた孤独感と人恋しさ」をも表現した句といわれています。
これらを考慮しながら「俳句の中心」を考えると、【秋が深まってきたが、私のお隣のひとは何をしているのだろう。】となりそうです。
④五・七・五の形にあてはめて読む
俳句の中心が決まったら、五・七・五のリズムになるように「俳句の中心」の言葉を考え、選んでいきましょう。
ある程度まとまっているのに、どうしても五・七・五にならないときは、同じ意味を持つ他の言葉で言いかえてみましょう。
⑤読んでみて違和感があれば、言葉を変えてみる
五・七・五にうまく言葉が整ったら、読みにくいところや、リズムに違和感がないか、何度も音読してみましょう。
また、最終確認として季語がちゃんと入っているか、そして上の句(あたまの五句)と下の句(最後の五句)を入れ替えてみたりして、わかりやすくて気持ちが伝わりやすいか、確認してみましょう。
【番外編】切れ字を使ってみよう

昔の俳句には切れ字十八字といって、言葉の切れ目(最後)の部分に「かな・もがな・し・じ・や・らん・か・けり・よ・ぞ・つ・せ・ず・れ・ぬ・へ・け・いかに」(覚える必要はありません)を使って、表現を強調したり、余韻をもたせたりしていました。
現在は「かな」「や」「けり」の3つの切れ字が存在します。
切れ字は俳句に「切れ」を出し、句のリズムも整え、作者の気持ちを表現してくれます。
例)秋深き 隣は何を する人ぞ (松尾芭蕉)
「する人ぞ」の最後にある「ぞ」が切れ字です。(※ここでの「ぞ」は疑問を表しています)
例)ひるよりも夜の汐にほふ葉月かな (鈴木真砂女)
季語・葉月
※昼間よりも夜に汐の香が強くなった。八月なのですね。
○「かな」は感動、感嘆を表現します。「~だなあ」という感じで、感動の気持ちをまとめる役割をします。
例)行く秋や手をひろげたる栗のいが (松尾芭蕉)
季語・栗
※もう秋も終りだなあ。栗のいががまるで手をひろげたようになって落ちていました。
○「や」は感嘆や呼びかけを表現します。直前の言葉を強調し、句のリズムを格調高い感じにします。
例)ほほづきのぽつんと赤くなりにけり (今井杏太郎)
季語・ほほづき(ほおづき)
※ふとみるといつの間にか、ほおづきがぽつんと赤くなっていた。
○「けり」は言い切る強い雰囲気を出します。「たしかに~だった」という感じです。ほぼ句の最後に使われます。
切れ字は特に使わなくても構いません。ただ俳句に慣れてくると自然と使ってみたくなると思いますので、その時にはぜひ使ってみて下さい。雰囲気のある句ができると思います。
また、一句できあがったら音読し、「なんだかあわないな…」と感じたら、省いたり、言葉を入れ替えてみるというパズルみたいな作業をしてみると、案外、練習になったりします。
そしてパズルがいい感じにはまったなと思える時、きっと素敵な一句が出来ているはずです。
超うまい!秋の有名な俳句&オリジナル俳句を紹介

さいごに、秋の句を代表する有名な俳句とオリジナル俳句をご紹介していきます。
【NO.1】小林一茶
『 青空に 指で字を書く 秋の暮れ 』
季語:秋の暮れ
意味:秋の暮れの青い空を見上げて、空に字を書いてみましたよ。

【NO.2】正岡子規
『 しづしづと 野分のあとの 旭かな 』
季語:野分(台風のこと)
意味:台風一過。夜が明けてしづしづと朝日が登ってきました。

【NO.3】加賀千代女
『 何着ても うつくしうなる 月見かな 』
季語:月見
意味:お月見の夜ですから、何を着ていても美しくなれるのですよ。

【NO.4】
『 幼子の顔に噛みつく西瓜かな 』
季語:西瓜
意味:まだ幼い子どもの顔を、まるで噛みつくみたいなスイカだなあ。

【NO.5】ふるてい
『 無月なり トイレに鍵を する独居 』
季語:無月
意味:トイレに入ったときに、僕は一人暮らしなのになんで鍵をしてるんだろうって思って作った句です。きっと心の奥底でなんか怖いのかなと思ったりして。僕のビビりなところと無月を掛け合わせてみました。(作者)
【CHECK!!】夏井いつきさんのおうちde俳句大賞では、季語に加えて「リビング」「台所」「寝室」「玄関」「風呂」「トイレ」の6つのテーマがあり、その「トイレ」部門での最優秀賞になります。
















