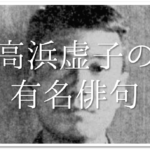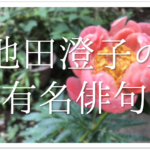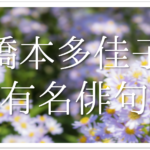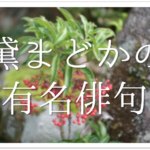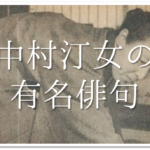俳句は四季の美しさを五七五の中に入れて自分の心情を詠むことができる日本の文学です。
五七五のリズムは心地よく、自分で俳句を詠んだりまた名句を鑑賞したりすることにも楽しみがあります。
今回は、高浜虚子を父に持ち自身も女流俳人の先駆けとして活躍した「星野立子(ほしの たつこ)」の有名俳句を30句紹介していきます。
ままごとの飯もおさいも土筆かな
星野立子「立子句集」 pic.twitter.com/Z3Lhuz8SQq— shu (@shu_wa) March 11, 2017

星野立子の人物像や作風

(星野立子 出典:鎌倉大仏殿高徳院)
星野立子(ほしの たつこ)は、高浜虚子の次女・明治から昭和にかけて生きた女流俳人です。
父譲りの俳句の才能は虚子一族の中でも群を抜いたものであり、現在でも立子の俳句は多くの人に愛されています。
立子氏は1903年(明治36年)、東京府鞠町区冨士見町(東京都千代田区)に生まれました。父は高浜虚子です。「立子」の名前は、当時三十歳の虚子が論語「三十にして立つ」に倣い命名したものです。

(星野立子と父・高浜虚子 出典:【時習26回3-7の会】)
立子は7歳のときに鎌倉へ転居し、以後人生の多くを鎌倉で過ごすことになりました。
立子は東京女子大学高等学部卒業後、鎌倉彫職人の星野義人と結婚し、長女早子を出産。1926年、立子22歳の頃に、父・虚子にすすめられ俳句を開始します。
立子の俳句の才能は、中村汀女・橋本多佳子・三橋鷹女とともに「四T」と称されるほど素晴らしいものでした。
1953年には2か月半ブラジル滞在、1956年には1か月間インド、ヨーロッパを訪問するなど政府文化使節の任務も務めました。
1956年の虚子死去後、その跡を継ぎ朝日俳壇選者となり、俳句の初心者の育成や婦人俳句の発展に貢献しました。
1969年に妹と共に再度ブラジルを訪問。その後、脳血栓で倒れ後遺症により右半身麻痺となりますが、左手で俳句活動を続け、1984年3月3日「桃の節句の日」に、直腸がんにより逝去しました。

立子氏は1926年から俳句を始め、父・虚子が提唱した「客観写生」「花鳥諷詠」を忠実に実践し虚子からも高い評価を得ていました。
立子氏の作風は、女性ならではの繊細な視点から自然の美しさや何気ない日常を詠ったものが多くあり、その明るく自由な感性は今でも支持を集めています。
星野立子の有名俳句・代表作【30選】

【NO.1】
『 ままごとの 飯もおさいも 土筆(つくし)かな 』
季語:土筆(春)
意味:ままごとの、ごはんもおかずも土筆であることだなあ。

この句は、立子が23歳の春に初めて作ったものです。
父虚子から勧められて作られたこの句は、初めてとは思えない程の才能を感じさせられます。
「おさい」は「お菜」のことで、おかず・副食を指します。
春、小さな男の子が玄関の先でままごとをしている様子を素直に詠っています。
【NO.2】
『 雛飾りつゝ ふと命惜しきかな 』
季語:雛飾り(春)
意味:雛飾りを出しながら、ふと命が惜しくなったことだ。

この句は、立子が五十歳を目前にして作ったものです。
立子が葬られた鎌倉の長福寺にある、立子の句碑にも記されています。
桃の節句にむけて雛飾りを出していると、結婚や出産、子育て子離れといった自身の女の人生がふと思い返されたのでしょう。
「命惜しきかな」の語から、「自分は人生であと何回雛飾りを出すことできるのだろうか」と作者が感じた生への切なさを感じさせます。
立子が亡くなったのは、1984年3月3日の桃の節句でした。
【NO.3】
『 囀り(さえずり)を こぼさじと抱く 大樹かな 』
季語:囀り(春)
意味:鳥たちのさえずりをこぼすまいと抱く大樹であることだ。

囀りとは、春になり求愛のために鳥たちが恋の歌をうたう様子のことです。
この句では擬人法を用い、「大樹」を人間に見立て「鳥のさえずりをこぼすまいと抱いている」と表現していいます。
春の喜びを詠うたくさんの鳥たちの鳴き声を、こぼすまいと抱く大樹の様子に作者の生への慈しみが感じられます。
【NO.4】
『 父がつけしわが名立子や 月を仰ぐ 』
季語:月(秋)
意味:父がつけた私の名前は立子である、月を仰ぐ。

「月」は、秋の季語です。
この句は、幼い頃から長年世話になったお手伝いの女性が亡くなったことを知り作ったもので、立子の代表句となっています。
この句は上の句と中の句をつなぐ「句またがり」の手法を使い「父がつけしわが名立子や」と一気に読ませています。
父からつけられた「立子」という名前とともに「月を仰ぎ」強く生きていこうとする作者の姿が浮かんできます。
【NO.5】
『 しんしんと 寒さがたのし 歩みゆく 』
季語:寒さ(冬)
意味:しんしんとした寒さを楽しみながら、歩いてゆく。

「しんしん」とは、自然の音や声、状態などを表した「オノマトペ」という表現方法で、「雪」の降る静寂さを意味します。
雪が降る日の静かな寒さを、作者は「寒さがたのし」と表現しました。
しんしんと雪が降る中、その寒さを楽しみながら歩き続ける姿は、何事にも負けず強く生きていく作者自身の人生を表しているのでしょう。
【NO.6】
『 美しき 緑走れり 夏料理 』
季語:夏料理(夏)
意味:美しい緑が走る夏料理である。

この句も、立子の代表句とされる句です。
「夏料理」とは、新鮮な野菜や果物をあしらいながら見た目にも涼しさを出した、夏の料理の総称です。
自分の前に並べられた「夏料理」の美しさに感動する作者の様子が素直に表現されています。
この句は、上五「美しき」で切れその後「緑走れり 夏料理」と一気に読まることで、句に躍動感を出しています。
【NO.7】
『 何といふ 淋しきところ 宇治の冬 』
季語:冬(冬)
意味:何という淋しいところであろうか、宇治の冬は。

この句は昭和14年に作られたものです。
「宇治」とは、京都府南部の地名のことで、平安時代から貴族の別荘地としても親しまれてきました。
「雪が降り積もった宇治の冬は、なんと淋しいところであろうか」と作者の率直な思いが伝わってきます。
【NO.8】
『 ひらきたる 春雨(はるさめ)傘を 右肩に 』
季語:春雨(春)
意味:春雨が降り始めたので、傘を右肩にゆったりとあてて開くことだ。

「春雨」とは、こまやかに降り続ける春の雨のことです。春雨が降るごとに草木は芽吹き始め、すべての生命が活動を始めてゆきます。
この句は、「ひらきたる」で始まり「右肩に」で終わる倒置法を用い、句に余韻を生ませています。
「ひらきたる」は、「傘を開く」と同時に春の暖かさに「心を開く」という二つの意味を掛けているのでしょうか。春雨の中傘をさす、女性の優美なしぐさが浮かんできます。
【NO.9】
『 午後からは 頭が悪く 芥子(けし)の花 』
季語:芥子の花(夏)
意味:午後からは頭が悪くなるように感じる。芥子の花のように。

うだるような暑さの午後、頭が働かずぼんやりとするのは誰にでもあることでしょう。
この句ではそれを、「頭が悪く」とはっきり表現しています。
「芥子の花」は5月頃に白紅紫色などの花をつける美しい花ですが、その未熟な実からは「アヘン」がとれるため栽培が禁止されている品種もあります。
「芥子の花」の麻薬性と、真夏の午後の「頭が悪く」なる様子の取り合わせが印象的です。
【NO.10】
『 大いなる 春を惜しみつ 家に在り 』
季語:春を惜しむ(春)
意味:大いなる春を惜しみながら家にいることだ。

「春を惜しむ」とは、晩春の季語で、過ぎてゆく春を惜しむ情緒を表しています。
「大いなる」とは、形容動詞「大いなり」の連体形で、「大きい、偉大な」という意味です。
大いなる春が過ぎてゆくのを惜しみながら家にいるという、何気ない風景を詠っています。

【NO.11】
『 皆が見る 私の和服 パリ薄暑(はくしょ) 』
季語:薄暑(夏)
意味:皆が私の和服を見る。パリの薄暑の中で。

「薄暑」とは、初夏の汗ばむほどの暑さを意味する、夏の季語です。
この句は、パリに日本文化使節団として派遣されたときに作られました。
和服を着てパリの街を歩く立子は、人々から注目を浴びています。その視線をくすぐったくも、薄暑の中を堂々と歩く作者の姿が浮かんできます。
【NO.12】
『 冬ばらや 父に愛され 子に愛され 』
季語:冬ばら(冬)
意味:冬ばらよ、父に愛され子に愛される。

「冬ばら」は、冬の中ぽつんと屋外で咲く薔薇のことです。「冬ばら」の花は色が濃いものが多く、冬のわびしい雰囲気の中その美しさを放ちます。
立子は、父虚子から俳句の厳しい指導を受けながらも大きな愛を受け、娘からも愛されているという人生の幸せを、美しく咲く冬ばらを見て感じているのです。
【NO.13】
『 美しく晴れにけり 春立ちにけり 』
季語:春立つ(春)
意味:美しく晴れている。立春が来たのだ。

「春立つ」とは、「立春」節分の翌日二月四日頃のことです。まだ寒さがある中、春の兆しを見つけ春の訪れを心待ちにする際に使われる季語です。
この句は、切れ字「けり」を繰り返す「脚韻(きゃくいん)法」を用いています。
俳句ではあまり使われない珍しいこの手法を用いることで、句にリズムを与え凛々しさを表現しています。
【NO.14】
『 小鳥来て 人来てこの家(や) にぎやかに 』
季語:小鳥来る(秋)
意味:小鳥が来て人が来て、この家がにぎやかになる。

「小鳥来る」は、秋に山里から人里にやってくる小鳥のことを指し、愛らしい響きをもつ季語です。
秋になり、小鳥が飛んできて来客も訪れにぎやかになった家の情景が浮かんできます。
【NO.15】
『 青麦に 沿うて歩けば なつかしき 』
季語:青麦(春)
意味:青麦に沿って歩くと懐かしい気持ちになることだ。

「青麦」とは、春の若葉が出そろい青々と成長する麦畑のことで、生命力を象徴する季語として使われます。
「青麦畑の横を歩いていると、何となく懐かしい気持ちになった」と詠う作者の、すがすがしい気持ちが伝わってきます。
【NO.16】
『 夕月夜 人は家路に 吾は旅に 』
季語:夕月夜(秋)
意味:夕月夜のもと、人は家路へ急ぎ私は旅に出る。

「夕月夜」とは、秋の季語で陰暦八月の二日月から上弦の頃までの、夕方に出る月を指します。このころの月は光が弱く、儚さがあります。
この句では、対句法を用い「人は家路に 吾は旅に」と表現しています。
対句法とは、表現が似た言葉を二つ並べ、それぞれを対称にし強調させる効果を句に与える表現方法です。
夕月夜の下、家路へ急ぐ人々と旅へ向かう自分の対比が、読み手に美しい情景となって伝わってきます。
【NO.17】
『 物指(ものさし)を もつて遊ぶ子 梅雨の宿 』
季語:梅雨(夏)
意味:ものさしを持って遊ぶ子がいる梅雨の宿のことだ。

「物指」と「子」の取り合わせが面白い句です。
作者が泊まった宿で、梅雨のために外へ出られず、「物指」で遊ぶ子どもがいたことをそのまま詠っています。
子どもは一つの物で色々な遊びを作り出します。この子どもは、「物指」で「ちゃんばら」など何の遊びをしたのだろうか、読み手に想像させます。
【NO.18】
『 ラヂオつと消され 秋風残りけり 』
季語:秋風(秋)
意味:ラジオを急に消され、そこには秋風が残ったことだ。

「つと」とは、急に何かをする様のことをいいます。
作者が家の中で聴いていたラジオを、誰かが「つと」消したのです。
ラジオの音が消され、そこには秋風だけが残っていたという秋の物静かさが伝わってきます。
【NO.19】
『 初冬の 徐々と来 木々に人に町に 』
季語:初冬(冬)
意味:初冬が徐々にやって来る。木々に人に町に。

「初冬」とは、草木が枯れ始め冬が始まる陰暦の十一月頃を指します。
この句では、「木々に人に町に」と助詞「に」を繰り返し使うことで句にリズムを持たせ、「徐々に」冬がやってくる様子を表現しています。
冬が徐々にやってくる情景を作者が楽しんでいるように感じられる句です。
【NO.20】
『 春寒し 赤鉛筆は 六角形 』
季語:春寒し(春)
意味:春寒い中、赤鉛筆は六角形をしている。

「春寒し」は、立春を過ぎて訪れる寒さを意味します。
この句は、作者が亡くなる前病室で詠んだ辞世の句で、「赤鉛筆」は立子が父虚子の跡を継ぎ、朝日俳壇の選者をしていたときに使っていたものです。
まだ寒さが残る春の日、自分が仕事で長く使ってきた赤鉛筆を眺めながら、自分の人生を走馬灯のように思い返していたのでしょうか。

【NO.21】
『 誰もみな コーヒーが好き 花曇 』
季語:花曇(春)
意味:誰もがみんなコーヒーが好きなのだ。外は桜が咲いて空が曇っている。

「花曇」とは桜が咲く頃の曇り空を表す季語です。コーヒーを飲みながら花と曇り空を眺めている様子が浮かんできます。
【NO.22】
『 時刻ききて 帰りゆく子や 春の風 』
季語:春の風(春)
意味:今何時ですかと時刻を聞いて帰っていく子がいるなぁ。春の風のようにさわやかな子だ。

礼儀正しく時間を聞いて帰っていく子供に春の風のような爽やかさを感じています。作者の家に遊びに来た子供が帰っていく様子を詠んだのでしょうか。
【NO.23】
『 鞦韆(しゅうせん)に 腰かけて読む 手紙かな 』
季語: 鞦韆(春)
意味:ブランコに腰掛けて読む手紙だなぁ。

「鞦韆」とはブランコのことで、中国での行事から春の季語になっています。ブランコに腰掛けて何となくゆらゆらと揺らしながら手紙を読んでいる様子が浮かんできます。
【NO.24】
『 アラビヤの 空を我ゆく 夏の星 』
季語:夏の星(夏)
意味:アラビヤの夏の星が出ている空を私が渡っていく。

世界各地を訪問した政府の文化使節を務めていたときに詠まれた句です。アラビヤという異国情緒あふれる空を、まるで空飛ぶ絨毯で進むように渡ることにどこかワクワクしています。
【NO.25】
『 夏の雨 明るくなりて 降り続く 』
季語:夏の雨(夏)
意味:夏の雨は空が明るくなっても降り続いていく。

どんよりとした空から降る雨ではなく、薄曇りになって日光が見えている状態で降る雨を詠んだ句です。周りが明るいのにまだ雨が降るのが夏なんだなぁという感慨深さを感じます。
【NO.26】
『 桃食うて 煙草を喫うて 一人旅 』
季語:桃(秋)
意味:桃を食べて、タバコを吸って一人旅をする。

一人旅の自由さを満喫している一句です。家族連れではなかなかできないこととして、その場で果物を買ったりタバコを吸ったりする様子を挙げています。
【NO.27】
『 先にゆく 人すぐ小さき 野路の秋 』
季語:野路の秋(秋)
意味:先の方を歩いている人がすぐに小さくなってしまう秋の野の風景だ。

「野路の秋」とは秋の野を表す季語です。空気が澄んで景色がよく、また涼しくなるため先を歩いている人も歩調が早まっているのかすぐ小さくなってしまうと感じています。
【NO.28】
『 風花を 美しと見て 憂しと見て 』
季語:風花(冬)
意味:風花を美しいと見て、雪が降ることを憂いて見て。

「美し」と「憂し」を対比させている一句です。風花は晴れた日にひらひらと落ちてくる雪のことで、美しいが雪の季節が始まるのだという憂いも同時に覚えると詠んでいます。
【NO.29】
『 余日なき 十一月の 予定表 』
季語:十一月(冬)
意味:余っている日がない。十一月の予定表は予定でいっぱいだ。

年の瀬で忙しい12月ではなく、あえて11月の予定を詠んでいるのが面白い一句です。多忙を極めているのか、もうどこにも予定を入れる余日がないと嘆いています。
【NO.30】
『 寄せ鍋の 大きな瀬戸の 蓋を開く 』
季語:寄せ鍋(冬)
意味:寄せ鍋に使っている鍋の大きな瀬戸物の蓋を開こう。

父である高浜虚子に「又例の 寄せ鍋にても いたすべし」という句があるように、作者の家では冬の寄せ鍋は恒例だったようです。大きな蓋を開ける瞬間のワクワクした感情が伝わってきます。
以上、星野立子が詠んだ有名俳句30選でした!
さいごに

今回は、星野立子のおすすめ有名俳句をたくさん紹介してきました。
星野立子は、父虚子から受け継いだ「客観写生」「花鳥諷詠」を忠実に実践し、素直に自然の美や日常を詠んだ句など多く残しています。
「愛情」「優しさ」「美しさ」など人間や自然の素晴らしさを詠った立子氏の句を、ぜひ楽しんでみてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。