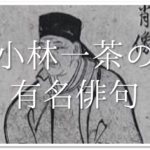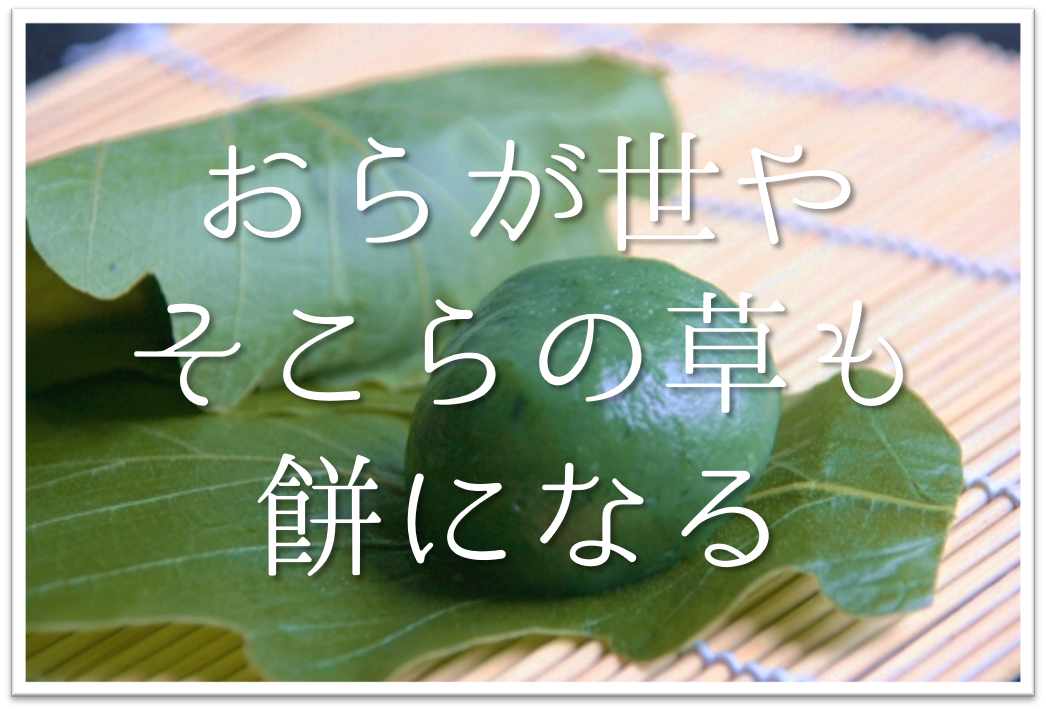
五七五のわずか17音で綴られる短い詩「俳句」。
高尚なイメージを持つ方もいらっしゃるかと思いますが、実は「俳句」は人々の生活に密着し、とても身近な文芸の一つといわれています。
今回は、日常の些細な出来事や身近な風景が描かれることが多い小林一茶の作、「おらが世やそこらの草も餅になる」という句を紹介していきます。
「おらが世や そこらの草も 餅になる 一茶」新聞で目にした句が、ふと思い出されて😅💦今日のおやつは「草餅」になりました❗️石川県民には、そこらの草餅でも食わせておけ〜!という声が聞こえて来そう❗️(笑) pic.twitter.com/m1XqomcxLU
— ありすママ (@turbokanazawa) March 25, 2019
本記事では、「おらが世やそこらの草も餅になる」の季語や意味・表現技法・鑑賞などについて徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「おらが世やそこらの草も餅になる」の季語や意味・詠まれた背景

おらが世や そこらの草も 餅になる
(読み方:おらがよや そこらのくさも もちになる)
この俳句の作者は「小林一茶(こばやし いっさ)」です。
小林一茶は「江戸時代の三大俳人」の1人と言われている人物です。江戸三代俳人とは小林一茶、松雄芭蕉、与謝野蕪村の3人を指します。
一茶の作品が芭蕉や蕪村と大きく違うところは、俳句になじみのない江戸時代の庶民でも理解できる簡潔な表現を使用していることです。

この句は一茶が52歳のときに詠んだ句で、『七番日記』に収録されています。
季語
こちらの句の季語は「草(も)餅」で、季節は「春」を表します。
草餅はヨモギ餅と呼ばれることもあり、実は平安時代から存在しています。

現代においても春を感じる和のスイーツとして、人気がありますね。
意味
この句の現代語訳としては・・・
「春ともなれば、そこら辺に生えている蓬(ヨモギ)の若草を摘んで、草餅にして食べよう。有難い世になったものだなぁ。」
といった意味になります。
この句が詠まれた背景
この句は『七番日記』によると、1815年に詠まれたもの(一茶が52歳の時)です。
一茶はこの前年の1814年に結婚していること、1815年前後に故郷の信濃を拠点とした俳諧の集会を確立させていることから、一茶の人生の中で幸福を感じていた時期だと考えられます。
この句を詠んだ頃の一茶は、俳諧師として全国的に名が知られるようになり、北信濃に多くの門人を抱えていました。父親の遺産も相続し、待望の生活の安定を得ることが出来た時期でもあったといえます。
そのため、今の自分の人生はヨモギではなくそこらの野草を使って餅を作っても幸せであるという句が誕生したのでしょう。
その心の余裕が「おらが世や」という出だしに表れていると考えられます。

しかし、1815年5月に生まれた長男が1ヶ月も経たずに夭折することを考えると、ほんのわずかな幸福の時間であったことも考えさせられます。
「おらが世やそこらの草も餅になる」の表現技法と鑑賞

切れ字「や」(初句切れ)
切れ字とは句の切れ目に用いられ、強調や余韻を表す効果があります。
特に「や・かな・けり」の三語は、詠嘆の意味が強く込められており、切れ字の代表ともいえます。
この句は「おらが世や」の「や」が切れ字に当たります。自分が生きているこの世に満足を感じ、「あぁ、有難い」といった気持ちを表現しています。
また、この句は上五「おらが世や」に切れ字「や」がついていることから、「初句切れ」の句となります。
「おらが世やそこらの草も餅になる」の鑑賞文

「おらが世やそこらの草も餅になる」は、小林一茶の句日記『七番日記』に収録されている句で、52歳のときの作と言われています。
約200年前に詠まれた句ですが、現代の私たちにも通ずる感性で描かれています。
蓬(ヨモギ)は山野に自生するのでどこでも簡単に手に入れられました。
一茶は風味豊かな蓬(ヨモギ)の若草をたっぷり使って「草餅にしよう!」そんなことを考えて、この句を詠んだのでしょう。
柔らかい蓬(ヨモギ)の葉を茹でて刻み、餅に混ぜたものが「草餅」ですが、現代の私たちにとっても季節のスイーツです。

約200年前の一茶も現代の私たちのように風味豊かな「草餅」を食べるときの至福の瞬間をイメージしてこの句を詠んだことでしょう。
「おらが世やそこらの草も餅になる」の補足情報

草餅の歴史
現代では草餅に用いされる草とは主にヨモギですが、古くは母子草(春の七草のゴギョウ)を用いて作られ、名称も草餅でなく母子餅とよばれていたとあります。
草の香りには邪気を祓う力があると信じられていて、上巳の節句(桃の節句)に母子草を混ぜ込んだ餅を食べる風習が中国より伝わってきたものと考えられています。
この風習は平安時代には宮中行事の一つとして定着していたことが9世紀に成立した『日本文徳天皇実録』よりわかっているため、かなり古い風習です。
江戸時代の上巳の節句では、餅の白と草餅の緑の二色で作られる菱餅がよく見られました。これは草餅の「緑」に邪気を祓う効果があるとされたためで、上巳の節句は「草餅の節句」と呼ばれていたとの記録もあります。
一説よると「母子」を搗くことが縁起が悪いとして避けられ、この頃から次第に母子草よりヨモギが用いられるようになっていったとされます。

新井白石が記した『東雅』(1719年)にも、かつてはハハコグサを用いたが、今日ではヨモギを用い、草餅とも蓬餅ともいうと書いてあり、この頃にヨモギへと変わっていったようです。
ヨモギの効能
ヨモギは古くから民間でも利用されてきた薬草です。
若い葉は食用としておひたしや和え物、ヨモギ飯として食され、野原や土手によく生育していることから江戸時代でもよく利用されていたことでしょう。
また生薬としても優れていて、お腹の調子を整えたり、止血や鎮痛剤として使われていたりもします。
江戸時代の医療にはかかせないお灸のもぐさとしても使用されていて、無くてはならない野草でした。

民間療法として冷湿布や風邪薬に使われているところもあるため、一茶の時代でも万能薬としてよく使用されていたものと考えられます。
作者「小林一茶」の生涯を簡単にご紹介!

(小林一茶の肖像 出典:Wikipedia)
小林一茶(1763年~1828年)は本名を小林弥太郎といい、十代将軍徳川家治の時代に信濃国(現在の長野県)に生まれました。松尾芭蕉、与謝蕪村と並ぶ江戸時代を代表する俳人の一人だといわれています。
一茶はわずか3歳の時に生母を亡くします。父の再婚相手の継母とは折り合いが悪く、次第に居場所をなくした一茶は唯一の味方であった祖母を亡くしたことを機に、15歳の時に江戸へ奉公に出されます。
俳諧師としての記録が現れ始めるのは25歳の頃で、それまでの約10年間は奉公先で非常に苦しい生活を強いられていたと一茶本人が回顧しています。
40代に入り、俳諧行脚で生計を立てられるようになりましたが、俳諧行脚での生活は非常に不安定であったと想像することができます。そのような中、独自の作風「一茶調」と呼ばれるスタイルを確立し、やがて一茶の名は当時の俳句界で広く知られるようになりました。
「おらが世やそこらの草も餅になる」が詠まれたのは一茶が52歳のときで、父親の遺産を相続し、ようやく生活の安定を図ることが出来た時期でもありました。
安定した生活もつかの間。妻との間にもうけた4人の子どもも次々と亡くし、妻にも先立たれてしまいます。その後再婚しますが、再婚相手との結婚生活は早々に破綻します。
64歳で3度目の結婚をするものの、65歳で亡くなる数カ月前に火事で相続で手にした我が家を焼失するなど、後半の人生も不幸が続きました。
人生における数々の苦労からか、一茶の句は日常のちょっとした出来事や風景が描かれることが多く、温かく、親しみを覚える内容が特徴となっています。
小林一茶のそのほかの俳句

(一茶家の土蔵 出典:Wikipedia)