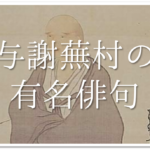五・七・五の十七音で、作者が見た景色や心情を綴り詠む「俳句」。
季語を使って表現される俳句は、作者の心情や自然の豊かを感じることができます。
今回は、与謝蕪村の有名な句の一つ「鮎くれてよらで過ぎ行く夜半の門」という句をご紹介します。
鮎くれて よらで過ぎ行く 夜半の門 (蕪村)
五月辺りから料理屋の焼物に小さな鮎がのぼり、暑さがピークになる今頃、その大きさは20cmほどの食べごろサイズになる。あのワタの苦味が何とも言えず旨い!
— 光惟 (菓子暦) (@cwjkd) July 30, 2014
与謝蕪村の「鮎くれて よらで過ぎ行く 夜半の門」という句。夜遅く、友人が釣り帰りな鮎を届けに訪ねてくれ、上がっていけと言うも、いいんだ、またなと言って去って行くという句。「粋」を楽しみ、「粋」を生きた江戸町人の精神のしなやかさに学ぶと。グッとくるなぁ。
— ほなにー (@honany) October 25, 2012
本記事では、「鮎くれてよらで過ぎ行く夜半の門」の季語や意味・表現技法・作者などについて徹底解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
「鮎くれてよらで過ぎ行く夜半の門」の俳句の季語や意味・詠まれた背景

鮎くれて よらで過ぎ行く 夜半の門
(読み方 :あゆくれて よらですぎゆく よはのもん)
この句の作者は、「与謝蕪村(よさぶそん)」です。
江戸時代中期に活躍した俳人で、松尾芭蕉や小林一茶とともに、有名な俳諧師です。画家でもあり、絵画的な物語性のある印象の俳句を詠みました。俳句と絵画を織り交ぜた「俳画」の創始者です。
季語
この句の季語は「鮎(あゆ)」、季節は「夏」です。
「鮎」は、夏の川魚の代表ともいえる魚です。キレイな水にしか生息できず、水底の苔を食べて育ちます。独特の爽やかな香りがすることから、「香魚」とも呼ばれています。

他にも季節に応じて季語があり、「若鮎」「小鮎」は春の季語、「落鮎」「錆鮎」は秋の季語として使われています。
意味
こちらの句を現代語訳すると…
「夜半に門を叩く音がして外に出てみると、釣りの帰りの友人が鮎を届けてくれた。寄って休んではとすすめたが、もう夜も更けたからといって、そのまま立ち去ってしまった。厚い友情を感じつつも、私は門のそばで立ち尽くすのみであった。」
という意味です。
「夜半」とは、午後9時を過ぎたあたりかと考えられます。
友人は釣ってきた生きのいい鮎を食べてもらいたくて、夜遅いと思いつつも、門を叩いたのでしょう。「寄っていけば?」と言っても、鮎を渡すだけでサッと帰るところに、友人と蕪村の友情の深さが感じられます。
突然の訪問と、あっという間の出来事に、蕪村が上手く対応できずに終わってしまった状況が感じられます。
この句が詠まれた背景
この句は、『蕪村句集』に収められています。明和5年(1768年)ごろ、蕪村が52歳の時に詠まれた句だと考えられています。
蕪村は画業に専念していたこともあり、本格的に俳諧に打ちこみ出したのは、55歳ごろからと言われています。
そのため、画業に専念していたころに起こった出来事を俳句にしたのかもしれません。
「鮎くれてよらで過ぎ行く夜半の門」の表現技法

「門」の体言止め
体言止めは、語尾を名詞や代名詞などの体言で止める表現技法です。
体言止めを使うことで、美しさや感動を強調したり、読んだ人を引き付ける効果があり、その言葉の印象や余韻を残すことができます。
「夜半の門」という言葉で、夜更けの自宅の門扉前で、一瞬で去ってしまった友人の後ろ姿を見送っている様子が強調されており、その様子が目に浮かびます。
句切れなし
「句切れ」とは、言葉の意味や内容、俳句のリズムの切れ目のことです。
この句は、五・七・五の十七音の中に、最後まで意味が区切れるところがありませんので、「句切れなし」となります。
「鮎くれてよらで過ぎ行く夜半の門」の鑑賞文

夜に門を叩く音が聞こえ、外に出てみると、友人が釣った鮎を持ってきてくれていました。
「家に寄っていったら?」と声をかけましたが、友人は帰ってしまい、門のところで突然の出来事に立ち尽くしているという句です。
突然の夜の訪問と、ただ鮎を渡すだけで立ち去るという行動に、作者と友人の関係の深さが窺えます。
「夜半の門」という部分がどこか寂しさを感じさせ、作者のとっさに上手く対応できなかったことに対する悔しさや、友人に対する申し訳なさのようなものが感じられます。
この俳句のたった17文字で、もらった鮎を持ちながら、帰っていく友人の後ろ姿を、門のところで見送る作者の姿が情景として目に浮かびます。
作者「与謝蕪村」の生涯を簡単にご紹介!

(与謝蕪村 出典:Wikipedia)
与謝蕪村は、享保元年(1716年)摂津国東成郡毛馬村、現在の大阪市都島区毛馬町に生まれました。本名は、谷口(または、「谷」)信章(のぶあき)といいます。
1735年、20歳頃に江戸に移り、 画や俳諧を学び、22歳の時に、早野巴人(はやのはじん)【夜半亭宋阿(やはんていそうあ)】に師事しました。
蕪村が27歳の時、師事していた巴人が亡くなり、以後10年あまりは北関東、東北などで放浪生活を送りました。放浪生活中は、絵を宿代の替わりに置き、敬い慕う松尾芭蕉ゆかりの地を巡りました初めて「蕪村」と名乗ったのは、29歳ごろと言われています。
その後36歳頃に、京に上り、42歳頃には京都での定住を決め、画業に専念しました。この頃から「与謝」と名乗り始めたと言われています。
55歳の時に、師事していた巴人が名乗っていた「夜半亭」の二世を継ぎ、本格的に俳諧に打ち込み始めました。
画業においても、その才能が認められており、当時、俳諧、画業ともに一流の存在だったと考えられます。
蕪村は、古典や歴史に俳諧の素材や構想を求めました。また、画家でもあるので、俳風は写実的で絵画的な印象の句が多いと言われています。
蕪村は、得意の絵を生かし、俳句に絵を入れる独自の形「俳画」を確立させました。俳画の『奥の細道図巻』が代表的なもので、松尾芭蕉の『奥の細道』を書き写し、挿絵を入れたものです。
その後、俳人蕪村の存在は忘れ去られていましたが、蕪村の死後、百十数年後に正岡子規が「俳人蕪村」を連載し、高く評価したことから、再び注目されるようになりました。
このような評価があったため、松尾芭蕉や小林一茶と並ぶ江戸俳諧の三代巨匠と言われるようになったのです。
与謝蕪村のそのほかの俳句

(与謝蕪村の生誕地・句碑 出典:Wikipedia)
- 夕立や草葉をつかむむら雀
- 寒月や門なき寺の天高し
- 菜の花や月は東に日は西に
- 春の海終日(ひねもす)のたりのたりかな
- 夏河を越すうれしさよ手に草履
- 斧入れて香におどろくや冬立木
- 五月雨や大河を前に家二軒
- うつくしや野分のあとのとうがらし
- 山は暮れて野は黄昏の芒かな
- ゆく春やおもたき琵琶の抱心
- 花いばら故郷の路に似たるかな
- 笛の音に波もよりくる須磨の秋
- 涼しさや鐘をはなるゝかねの声
- 稲妻や波もてゆへる秋津しま
- 不二ひとつうづみのこして若葉かな
- 御火焚や霜うつくしき京の町
- 古庭に茶筌花さく椿かな
- ちりて後おもかげにたつぼたん哉
- あま酒の地獄もちかし箱根山