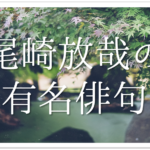俳句と聞くと深い知識を持って句の解釈をするものと感じる方が大勢いらっしゃると思います。
実際に知っておいたほうが良い決まりもありますが、俳句の中でも決まりを抜け出した自由律俳句は読むだけで伝わってくる魅力があります。
特に尾崎放哉の「咳をしてもひとり」は自由律俳句の代表としても取り上げられる句です。
熱は引いた、喉の痛みも引いてきた、しかし頭がとても痛いし鼻水も出るし…
咳をしても一人/尾崎放哉 pic.twitter.com/s0coy1OgKK
— べし (@beshiabeshi) November 2, 2014
いま仕事から帰宅。ひとりケーキを食す。
咳をしても一人 pic.twitter.com/QwrknVra— こんてい (@kontei2000) December 24, 2011
この句の魅力とは何でしょうか?
本記事では、「咳をしても一人」の季語や意味・解釈・背景・表現技法・鑑賞文・作者など徹底解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
「咳をしても一人」の季語や意味・詠まれた背景

咳を しても 一人
(読み方:せきを しても ひとり)
この句の作者は「尾崎放哉(おざきほうさい)」です。
尾崎放哉は、明治から大正にかけて活躍した俳人です。季語を使わず五七五の韻律からも外れた「無季自由律俳句」の騎手として知られています。
旅先で自由律俳句を詠み続けた種田山頭火と対照的に、寺や庵での闘病生活の中で詠まれた尾崎放哉の俳句は、「静と孤独の俳句」と呼ばれています。
季語
あえて選ぶのであれば、季語は「咳」で季節は「冬」になります。
しかし、今回の自由律俳句は季語を用いるという決まりがなく、咳が季語として成立していません。
今回の句も、単に咳をしたという内容を伝えているだけで、読み手に冬を想像させるために使用されているものではありません。
意味
この句を現代語訳すると・・・
「部屋で咳をしたが、部屋には私たった一人だ。誰が心配してくれるでもなく孤独だ。」
となります。
この句が詠まれた背景(作者の思い&解釈)
この句は尾崎放哉が亡くなる数か月前に詠んだと言われる句です。
放哉は存命中に句集を作ることはなかったため、没後に荻原井泉水の編集に句集「大空」が出版され、そちらに収録されています。
この句を詠んだ頃の放哉は晩年でした。破天荒な人生を送ってきた放哉は香川県小豆島にある西光寺の庵に住んでいました。
酒癖が悪く、金の無心をするなど周囲からの評判が良くない放哉は孤立した状態だったのです。
そして、この頃の放哉は、庵の場所を提供した住職が食べ物を与えるほどに困窮ぶりでした。
放哉は自由律俳句の代表として名を知られても、実際には一人で嫌われ者として住んでいるという孤独感があります。
どれほど孤独を感じているかを純粋に表現したのがこの句になります。
「咳をしても一人」の表現技法

自由律俳句
自由律俳句とは、五七五や季語といった定型にとらわれずに作る俳句のことです。
俳句で頻繁に使用される意味切れを作る切れ字などの技法は使いません。
自由律俳句は、口語で内面の感情を直接的表現するのも特徴の一つです。
定型俳句から自由になることが目的であり、無定型の俳句すべてが自由律俳句にはなりません。
今回の句は自由律俳句で詠まれており、定型俳句より短い九音で三・三・三というリズムによって構成されています。
九音で詠むことで、部屋でただ一人でいるという孤独感が強まってきます。
体言止め「一人」
句の最後を名詞で締めることを体言止めと呼びます。
体言止めは言葉の後に続く文章を読み手に想像させる効果があります。
今回は一人という言葉ですが、一人の後に続くとすれば「孤独を感じている」といった内容になります。
しかし、孤独という言葉を一切使わないことで孤独感を表現しています。
「咳をしても一人」の鑑賞文

【咳をしても一人】は、奔放に生きた放哉が感じた、人生の終わりの孤独について味わうことのできる句となっています。
放哉の最後は長年の不養生から病に侵され、困窮も相まって餓死に近い状態で亡くなったと言われています。
そういった状況ですから、病でも一人狭い部屋に咳が響くだけ。
三・三・三のリズムは咳をしているリズムに近いものがあります。咳をして、出し終わっても続くものがいない様子を感じ取ることができます。
さらに直接的表現を使うことで、これ以上言葉を続ける必要がないほどの孤独を読み手に感じさせます。
そして状況を考えると、放哉が狭い庵に一人でいるということは、本当に声をかける人もいないということです。
つまり、当時の様子を想像しても極めて孤独であったことがわかります。
自由律俳句の第一人者と名高くても、自由な生活をし、孤独がついてくる人生でした。
破天荒な人生の末に純粋に感じた、深い寂しさが伝わってきます。
作者「尾崎放哉」の生涯を簡単にご紹介!
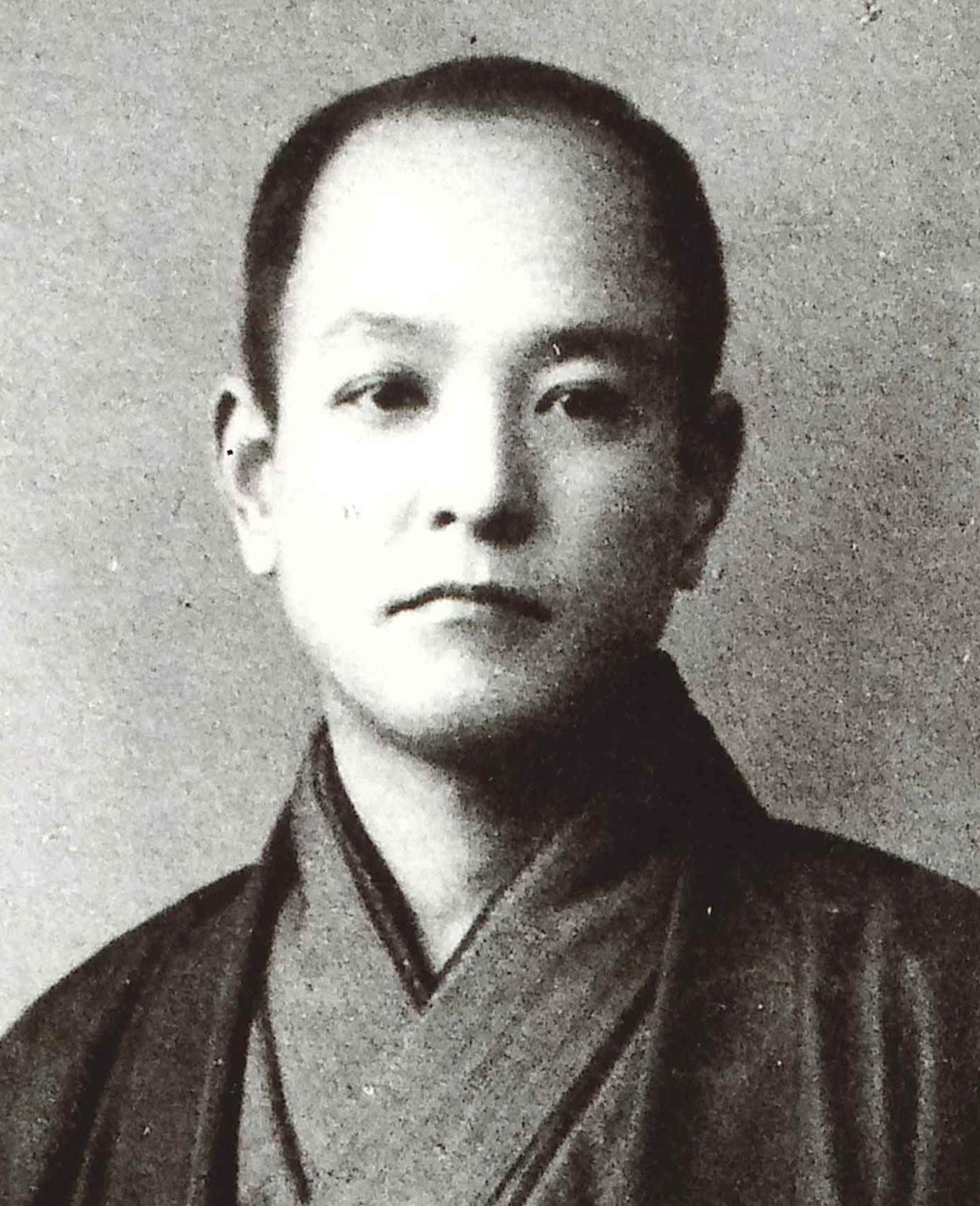
(尾崎放哉 出典:鳥取県立図書館)
尾崎放哉(おざき ほうさい)は、明治18年(西暦1885年)、現在の鳥取市に生まれました。「放哉」は俳号(俳句を詠むときに用いるペンネームのようなもの)であり、本名は「秀雄」です。
明治32年(西暦1899年)、14歳になった頃に俳句を作り始めます。明治33年(1900年)には、鳥取県第一中学校の校友会雑誌『鳥城』に俳句・随想・短歌を発表し、明治34年(1901年)には友人と一緒に共同して同人誌『白薔薇』を発行しました。
明治42年(西暦1909年)、24歳のときに東京帝国大学を卒業。通信社に入社するも1ヶ月で退職してしまいます。翌年の明治43年(1910年)に、東洋生命保険(現・朝日生命保険)に入社。明治44年(1911年)には、めでたく結婚します。
このままエリート人生の道をまっしぐらかと思われましたが、転落の一途をたどります。大正10年(西暦1921年)に、酒癖や勤務態度の悪さを理由に職務を罷免されてしまいます。大正11年(1922年)に、朝鮮火災海上保険に支配人として朝鮮に赴任。大正12年(1923年)には職務を罷免され、帰国したのちに妻と離縁します。同年に、肋膜炎を発病しています。
大正13年(西暦1924年)、39歳のときに知恩院(京都市東山区)塔頭常称院の寺男となるも、1か月ほどで同寺を追われ、須磨寺(神戸市須磨区)大師堂の堂守になります。大正14年(1925年)、須磨寺を去って小浜常高寺の寺男になります。これまた2か月ほどで常高寺を去り、小豆島霊場第五十八番札所西光寺奥の院南郷庵に入って「入庵雑記」を書き始めます。
大正15年(西暦1926年)、4月7日に逝去。享年41歳。死因は癒着性肋膜炎湿性咽喉カタルであったと言われています。
尾崎放哉の俳句には、基本のルールを順守した5・7・5に則った句も存在しますが、やはり基本となるリズムの原型をとどめていない、自由奔放な句が目立ちます。
風変わりな人柄が伺えるような不可思議な印象は、個人の好みが分かれるかもしれません。しかし、孤独感の辛辣さを訴えつつも、バッドジョークかと思えるような笑えない表現に、なぜか妙な哀愁も感じることでしょう。
もし、尾崎放哉の俳句に触れる機会がありましたら、虚無感をかもしだしたようなシニカルな作風を、ぜひ楽しんでください。
尾崎放哉のそのほかの俳句

(尾崎放哉の石碑 出典:Wikipedia)
- こんなよい月を一人で見て寝る
- 一人の道が暮れて来た
- 入れものがない両手で受ける
- うそをついたやうな昼の月がある
- 墓のうらに廻る
- 足のうら洗えば白くなる
- 肉がやせてくる太い骨である
- 考えごとをしている田螺が歩いている
- 別れ来て淋しさに折る野菊かな
- 今日一日の終りの鐘をききつつあるく
- 土くれのやうに雀居り青草もなし
- ねそべって書いて居る手紙を鶏に覗かれる
- 一日もの云わず蝶の影さす
- 淋しいからだから爪がのび出す
- 一本のからかさを貸してしまった
- いつしかついて来た犬と浜辺に居る
- 春の山のうしろから烟が出だした(辞世)