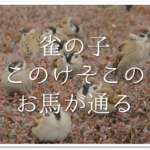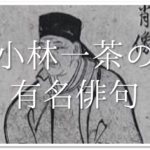俳句は日本に古くから伝わる文章の書き方の一つで、世界最短の文とも言われています。
素人から俳句を生業とする「俳人」と呼ばれる人までさまざまな人から詠まれてきたため、数え切れないほど沢山の句が存在します。
そんな沢山の俳句の中には「やせ蛙 負けるな一茶 これにあり」という有名俳句があります。
やせ蛙 負けるな一茶 これにあり。
俺もがんばろう…… pic.twitter.com/IwQUyx3k6d
— はちわれ兄弟@スーパー ヒーリング ブラザーズ。 (@tenzan0728) July 13, 2018
今回は、この「やせ蛙負けるな一茶これにあり」の季語や意味・作者は何を見てこの句を詠んだのか?など、徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「やせ蛙負けるな一茶これにあり」の作者や季語・意味

やせ蛙 負けるな一茶 これにあり
(読み方:やせがへる まけるないっさ これにあり)
この俳句の作者は「小林一茶(こばやし いっさ)」です。
小林一茶は「江戸時代の三大俳人」の1人と言われている人物です。江戸三代俳人とは小林一茶、松雄芭蕉、与謝野蕪村の3人を指します。
一茶の作品が芭蕉や蕪村と大きく違うところは、俳句になじみのない江戸時代の庶民でも理解できる簡潔な表現を使用していることです。

この表現方法は「一茶句調」と呼ばれており、俳句が庶民の間に普及するきっかけになったと言われています。
季語
この俳句に含まれている季語は「やせ蛙」の部分です。
「蛙」は通常春の季語ですが、小林一茶が詠んだこの「やせ蛙」はヒキガエルであったと考えられています。

現代語訳にしてもなかなかヒキガエルとまで訳されないので勘違いされがちですが、ヒキガエルは夏の季語ですので、この俳句は夏に詠まれたということがわかります。
意味
この句の意味は「小さくて弱そうなやせ蛙よ。負けないでくれ。私がここで応援しているぞ。」という蛙に語りかけるような形になっています。
この句が詠まれる時、2匹のオス蛙がメス蛙を狙って争いをしていたと言われています。
それをたまたま目撃した作者が、負けそうになっているやせ蛙に同情して応援しているのです。
「やせ蛙負けるな一茶これにあり」が詠まれた背景

小林一茶がこの句を詠んだ背景には、現在2つの説があると言われています。
①自らの不遇を詠んだといわれる説
1つ目は「自らの不遇を詠んだといわれる説」です。
小林一茶は、20代の頃からすでに白髪頭でその風貌から女性からモテず52歳まで結婚が出来ていませんでした。
メスを巡って争う時、痩せている弱々しい蛙は不利で、太ってどっしりとした体格の蛙の方がメスを手に入れやすいです。

そんな痩せて弱い蛙にモテない自分を重ねて詠んだ句であると考えられています。
【補足情報】この句はどこで詠まれたか?
『七番日記』によれば、一茶は文化12年(1815年)の12月に故郷に帰り、文化13年9月に再び江戸へ行っています。
そのため、この句は『七番日記』の記述を信じるのであれば故郷で詠んだことになりますが、『一茶句集』では異なる前詞が付いていて、詠んだ場所も全く異なっているのです。
『一茶句集』では、「むさしの国竹の塚といふに、蛙たたかひありけるに見にまかる、四月廿日也けり」となっていて、この句は「むさしの国竹の塚」、現在の東京都足立区竹ノ塚で詠まれたことになっているのです。
一茶は竹ノ塚にある「炎天寺」というお寺によく詣でていました。このお寺は現在は「一茶ゆかりの寺」として有名で、句碑や一茶まつりを行っていることで知られています。
『一茶句集』の前詞を採用する場合、一茶は第1子の千太郎が産まれる頃に江戸にいて、虚弱だった子供のことを知らずに「やせ蛙」の句を詠んだことになります。

『七番日記』の一茶の日記と全く異なるためどちらが本当の記録だったか確定はしていませんが、「やせ蛙」は子供のことを詠んでいなかった可能性もあります。
【補足情報】「一茶これにあり」
この句の特徴は「一茶これにあり」という表現でしょう。
「一茶はここにいるのだ」という独特な表現はめずらしく、この句をより際立たせています。
この表現は「私はここにいる」という宣言のように感じ取れますが、これには訳があります。
一茶の父が亡くなったのは5月21日で、命日が近い日に詠まれているのです。

この句を父への追善、死者の冥福を祈る句だとすれば、「やせ蛙のような一茶ではあるが、一茶は負けずにここにいますよ」と父を安心させるような意味になってきます。
②虚弱児な子供に対して詠んだといわれる説
2つ目は「虚弱児な子供に対して詠んだといわれる説」です。
小林一茶は、52歳で初めて結婚。その時に生まれた男の子は虚弱児で、生まれてからたった1ヶ月ほどで亡くなってしまいます。
その後、長女・次男・三男と生まれましたが全員幼い頃に亡くなってしまいます。

そんな自分の子供が病魔と戦っている姿を痩せている弱々しい蛙と重ねて、懸命に応援している様子を詠んだ句だとも考えられているのです。
【補足情報】第1子、千太郎との関係
この句が詠まれたのは文化13年(1816年)です。
前詞に「蛙たたかひ見ニまかる、四月廿日也けり」とあり、旧暦の4月20日に詠まれたことがはっきりとわかっています。
一茶は長らく妻子を持ちませんでしたが、文化11年に結婚し、文化13年4月14日(旧暦)に第1子の千太郎が産まれました。そのため、「やせ蛙」の句は子供が産まれて1週間ほどで詠まれたことになります。
しかし、千太郎は生後わずか28日で亡くなってしまいます。

このことから、上述のとおり「やせ蛙」とはやせ細った生後1週間の千太郎を詠んだのでは、という説が考えられました。
「やせ蛙負けるな一茶これにあり」の表現技法と感想

呼びかけ
この句の特徴は、蛙に語りかける作者の言葉をそのまま書いています。
これは「呼びかけ」という何かに呼びかけるような口調で句を詠む方法です。小林一茶の句にはこの「呼びかけ」が多く使われています。
例えば、下記の小林一茶の有名な句もその一つです。
こちらの句も直接雀に問いかけるように詠まれた句です。「呼びかけ」を使うことで、句に優しい印象を持たせることができます。

一茶はこれを意図的に用いて蛙の他に雀やアリなどの弱い動物を詠み、自分に起こった出来事や心情と照らし合わせていたのです。
初句切れ
句切れとは、意味やリズムの切れ目のことです。
句切れは「や」「かな」「けり」などの切れ字や言い切りの表現が含まれる句で、どこになるかが決まります。

この句の場合、初句(五・七・五の最初の五)に、「やせ蛙」の名詞で区切ることができるため、初句切れの句となります。
「やせ蛙負けるな一茶これにあり」の作者・小林一茶について

(小林一茶 出典:Wikipedia)
この句を詠んだのは有名な俳人である小林一茶です。
小林一茶は、1763年に信濃北部の農家に生まれました。
本名は小林弥太郎。家は、中くらいの自作農でありましたが、この土地は痩せた火山灰地であったため、生活はあまり楽ではありませんでした。
一茶の母は一茶が3歳の時に亡くなっていて、一茶の父は再婚。その後、義理の母から弟が生まれましたが義理の母と弟とは仲が悪かったそうです。
そして、そのままうまく行かず15歳で故郷を出ることになります。その後25歳の時葛飾派俳人の門人となり、その後28歳で溝口素丸に入門します。
一茶は20代の頃すでに白髪が生えていたため、その風貌からモテなかったそうで、はじめて結婚したのは52歳の時でした。
2人の間には男の子の子供ができましたが、大変な虚弱児でその後1ヶ月足らずで男の子は亡くなってしまいます。
その後も3人の子供を生みましたが全て亡くなってしまい、ついには妻まで病に倒れ亡くしてしまいます。
妻が亡くした後、2度再婚しましたが、子供は最後の妻との間にできた娘だけが残りました。
しかし、一茶は58歳の時に脳卒中で倒れ半身不随になり、そして家が火事になったりと波乱な人生を送り、1827年に生活していた土蔵の中で息を引き取りました。
小林一茶が詠んだそのほかの俳句

(一茶家の土蔵 出典:Wikipedia)