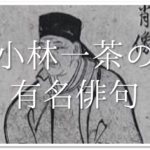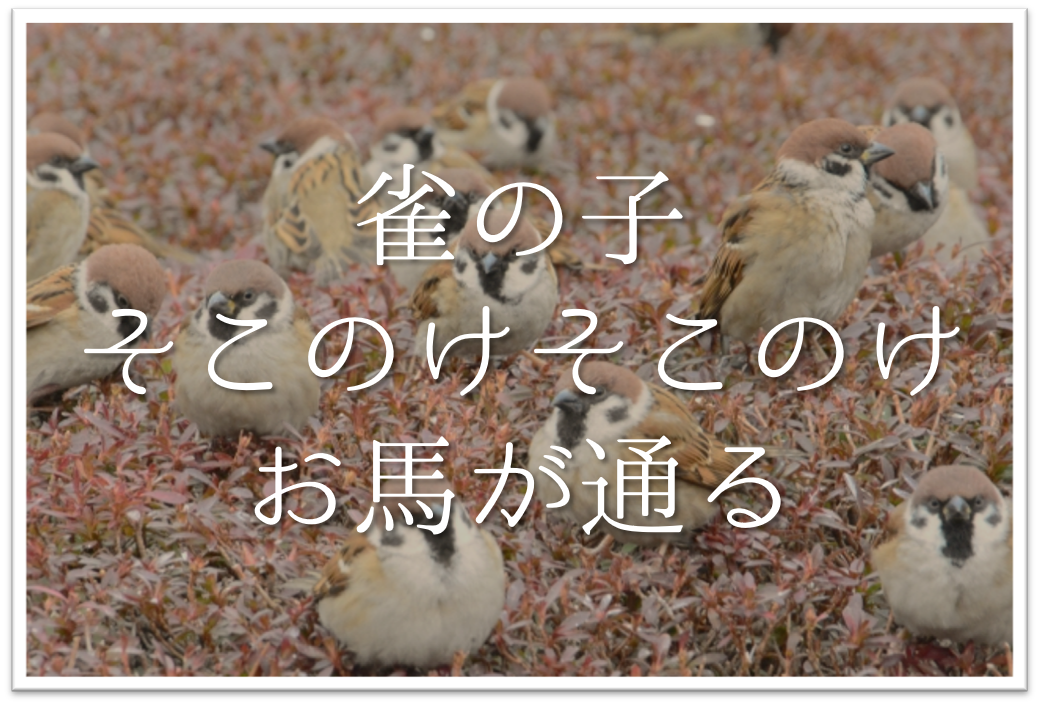
俳句は、日本に古くから伝わるなじみ深い文章表現技法の1つです。
これまでに多くの俳句が詠まれ、今尚たくさんの人たちに親しまれています。
その中でも「雀の子そこのけそこのけお馬が通る」は、俳句の知識がない方にもなじみ深い作品の1つかもしれません。
長野県信濃町のマンホール!
小林一茶はここで生まれ、ここで亡くなったということで、小林一茶記念館があるということで、あの有名な一句をデザイン化したマンホ!
「雀の子 そこのけそこのけ お馬が通る」#マンホール #マンホールの蓋 #JapanManhole #manhole https://t.co/37fBv3IdhJ pic.twitter.com/CvSbxYt9FM
— ウエチリーヌ🍖このAKAの子 (@Uechiline) August 24, 2019
作者はなにを観察し、この句を詠んだのでしょうか?またこの俳句を口ずさんだ時の心情も気になりますね。
そこで今回は、『雀の子そこのけそこのけお馬が通る』の季語や意味・表現技法や作者など徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「雀の子そこのけそこのけお馬が通る」の作者や季語・意味

雀の子 そこのけそこのけ お馬が通る
(読み方:すずめのこ そこのけそこのけ おうまがとおる)
こちらの句の作者は、日本を代表する俳人「小林一茶(こばやしいっさ)」です。
小林一茶は、松尾芭蕉や与謝蕪村とともに江戸時代を代表する俳人のひとりです。
一茶の作品は表現が簡潔なので誰にも意味が分かりやすく、生涯に2万作もの俳句を詠んだといわれています。

それでは、早速こちらの俳句について詳しく解説させていただきます。
季語
こちらの俳句に含まれている季語は「雀の子」で、春を表現する言葉です。
「雀の子」がなぜ、春を示す季語に当たるのでしょうか?
それは、雀は3月から4月に繁殖・卵を産み、ヒナとなるからです。
基本的には雀は年に2、3回ほど繁殖をしますが、日本では「初物=縁起が良い」という風潮があるため、俳句にもこちらの考えが該当し、年の初めての繁殖である「春」が季語となるのです。
意味
こちらの句を現代語訳すると・・・
「雀の子よ。早くその場所をどかないと馬に踏みつぶされてしまうよ。」
という意味になります。

またこれ以外にも、観点を変えると別の解釈ができます。
それは「馬」の部分を「竹馬で遊ぶ子供」と捉える見方です。こちらの解釈での意味は・・・
「雀の子よ。早くその場所をどかないと竹馬で遊ぶ子供たちにつぶされてしまうよ。」
になります。
ですが「馬=竹馬」にすると、季語が2つになってしまいます。参考までに竹馬は、お正月を表現する季語です。
俳句の世界では「季語は1つ」がルールですので、馬を竹馬と考える説は一般的ではありません。
この句が詠まれた背景
この句は「おらが春」の中に収集されている、代表的な俳句の1つです。
「おらが春」は、小林一茶が信濃で過ごした56歳から57歳の1年間を詠んだ俳句・俳文を集めたものです。
つまり、こちらの句も「一茶が信濃で過ごした56歳~57歳」に詠まれた俳句になります。

一茶没後25年目に白井一之が自家本として刊行。「おらが春」の表題も一茶が詠んだ俳句の名から白井一之が名付けました。
「雀の子そこのけそこのけお馬が通る」の表現技法

五八七の破調
破調とは、俳句の定型詩(五七五)で音数に多少が生じることです。俳句のルール「5・7・5」をあえて破ることで、俳句にインパクトがつきます。
この句は、「そこのけそこのけ」部分が中8文字で字余り、また、「お馬が通る」の部分が下7文字で字余りです。
字余りを用いることで、「そこをどけ そこをどけ」という感情表現が強く心に響いてきます。また、下7字を字余りにするとリズムが取りづらくなりますが、こちらの俳句は口ずさみやすい作品に仕上がっています。
「雀の子の部分」の擬人法
擬人法は、動植物を人に置き換える技法です。
擬人法を取り入れることにより、意外性や面白さがある俳句を作れます。
この句において芭蕉は「人間の子」を「雀の子」に例えて表現しています。昔は殿様や上級の武士達が、馬に乗って「そこどけ、そこどけ」と農民たちの間を通って行きました。早くどけ!と馬上から叫ばれ、遊んでいた子ども達が避ける様子を俳句に詠んでいます。
「雀の子」「そこのけそこのけ」部分の呼びかけ法
呼びかけ法にすることにより、区全体が優しいイメージになり、親しみが持てます。
句を読んでいる情景をイメージしやすく、読者が作品に共感を覚えやすくなります。
「そこのけそこのけ」部分の反復法
反復技法とは同じ言葉を繰り返す表現方法です。言葉の意味を強調し、インパクトを強める効果があります。
こちらの句でも「そこをどけ そこをどけ」と、雀の子ども達に強く呼びかけている様子が表現されています。
初句切れ
句切れとは、意味やリズムの切れ目のことです。
句切れは「や」「かな」「けり」などの切れ字や言い切りの表現が含まれる句で、どこになるかが決まります。
この句の場合、初句(五・七・五の最初の五)に、「雀の子」の名詞で区切ることができるため、初句切れの句となります。
「雀の子そこのけそこのけお馬が通る」の鑑賞文

こちらの句は、小さなすずめの子を思いやる、優しい小林一茶の人柄が伝わって来る作品です。
また、この句からはポカポカと春めいた日にすずめの子供達が、楽しそうに遊んでいる様子が浮かんできます。
この俳句を詠んだ風景をとてもイメージしやすく、親しみやすく感じられます。
そして、より深く解釈してみると「小林一茶自身を雀の子に例え、権力のある武士や殿様に対して、己の非力さをユーモラス的に詠んだ」とする説もあります。

このように解釈の仕方で、何パターンに分けて情景を想像できる点もこの句の面白い点です。
「雀の子そこのけそこのけお馬が通る」の補足情報

狂言「千鳥」との関係性
「そこのけそこのけ お馬が通る」は、字余りでありながらとてもテンポよく読める俳句です。
このフレーズには実は元ネタがあり、狂言の「千鳥」という演目の中に出てきます。
「千鳥」とは、太郎冠者が酒屋から酒をどうにかしてだまし取ろうとして、酒屋もだまされまいとしながらも応じてしまうやりとりを演じたものです。
酒屋は面白い話が大好きで、それを知っている太郎冠者は「流鏑馬(やぶさめ)」の話をして気を引こうとします。
竹を馬に見立てて馬に乗る太郎冠者(シテ)と、馬場(馬が通る場所)にいる人を追い払う酒屋の店主を演じる一幕をご紹介しましょう。
シテ「この次に、流鏑馬と云うて、馬に乗つて駈ける内に、的を射ることでござるが、なかなか面白うござる。」
酒「さあさあ、その面白い事が見たい。して見せい。」
シテ「して見ませうか。これも相手が入る。こなたは先へ廻つて、馬場退(の)け馬場退けと云うて、馬場な人を退けさせられ。身共が馬に乗つて、御馬が参る御馬が参ると云うて駈けますぞ。」
酒「心得た。さあさあ馬に乗れ。」
シテ「これに竹がござる。竹馬に乗りませう。さあ乗りました。」
洒「馬場退(の)け馬場退け。」
シテ「御馬が参る御馬が参る。」
この狂言にあるように、「馬場退け」という言葉が、馬場、ひいては馬の通り道にいる人を追い払う慣用句になっていました。

この句では実際に馬が通ったとも、「千鳥」のように竹を馬に見立てた子供が通ったとも言われていますが、「馬場」を「そこ」に言い換えて使っています。
呼びかけているのは親雀か一茶か
この句は前述のとおり、「親雀が子供に呼びかけている説」と「一茶が雀の子に呼びかけている説」の二つがあります。
この句の初案と思われる俳句が前年に作られていて、そこでは馬と雀が共通して出てきます。
「それ馬が 馬がとやいふ 親雀」
(訳:ああ馬が来る、馬が来ると言う親雀だ。)
こちらの句では雀の子に呼びかけているのは、親雀です。
しかし、「馬が来ると雀に呼びかけている」というモチーフは同じですが、「雀の子」の句と受ける印象がかなり変わってきます。
「雀の子」の句は、前述の狂言の滑稽なやり取りを踏まえつつ、調子のいいはやし立てのような雰囲気を持っているのです。
「はやし立てる」という雰囲気から言えば、やはり一茶が主体となって雀の子に呼びかけているのでしょう。

一茶は他にも「そこのけ」と入る俳句をいくつか詠んでいるので、気に入っているフレーズだと考えられます。
作者「小林一茶」の生涯を簡単にご紹介!

(小林一茶の肖像 出典:Wikipedia)
この句を書いたのは、有名な俳人である小林一茶です。
小林一茶は1763年に長野県信濃町で生まれました。本名は小林弥太郎。一茶は俳号になります。
一茶は幼少期に母を亡くし、義母になじめなかった一茶は15歳の時に江戸に奉公に出ました。
そして、20歳の時に俳句の世界に入り、葛飾派の溝口素丸らに仕えて俳句の勉強をはじめます。
その後、30歳から36歳の期間に、関西・四国・九州を旅しながら俳句の修行を積んで行きました。この旅で知り合った俳人と一緒に出版したのが句集「たびしうゐ」「さらば笠」です。
そして、39歳の時に実家に戻り、父が亡くなった後は義母と弟との相続問題に巻きこまれてしまいます。俳句の指導などでなんとか生計を維持するものの、非常に貧しかったようですが、俳人として有名になって行きました。
その後ようやく相続問題も解消し、52歳で結婚。3男1女に恵まれますが、子どもは全員幼くしてなくなり、妻まで病気で亡くしてしまします。
その後再々婚をし、次女が誕生。1827年11月29日に一茶は65歳の生涯を閉じます。
家族の縁が薄かった一茶ですが・・・
- 七番日記
- 八番日記
- 文政句帖
- おらが春
などの作品を残し、生涯に2万句も詠んだと言われています。
小林一茶のそのほかの俳句
(一茶家の土蔵 出典:Wikipedia)