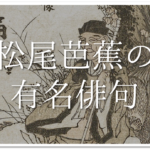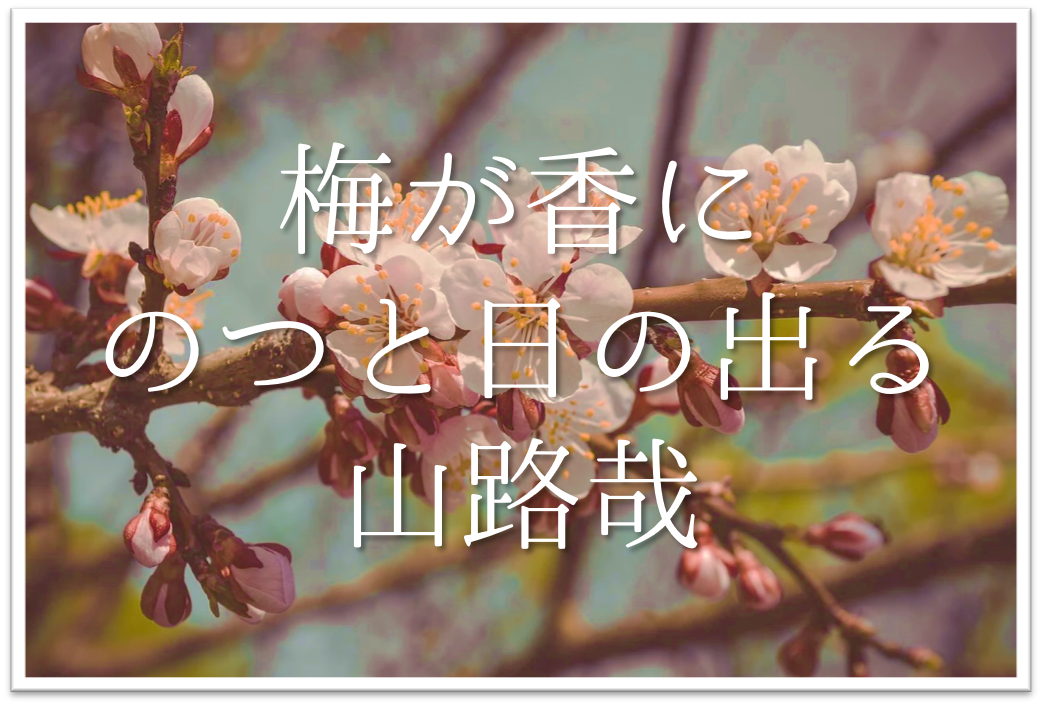
五七五のわずか17音で綴られた短い詩「俳句」。
「俳句」と聞くと、敷居が高く、気後れしてしまう方も少なくありません。しかし、「俳句」はもともと庶民の生活に密着し、人々にとても身近に親しまれていた文芸の一つです。
今回は、日本人であれば誰もが知っている松尾芭蕉の作、「梅が香にのつと日の出る山路哉」という句を紹介していきます。
おはようございます。梅が香にのっと日の出る山路哉(やまじかな)。芭蕉51歳の句。瞬間瞬間の美を感じ取る豊かな心を持って、日々精進したい今日この頃です。いい一日、いい時間を過ごしましょ!Morning! pic.twitter.com/vhDd7rgezt
— たにりり『稲作SDGs』 (@himenotable) February 14, 2017
本記事では、「梅が香にのつと日の出る山路哉」の季語や意味・表現技法・鑑賞などについて徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「梅が香にのつと日の出る山路哉」の作者や季語・意味・詠まれた背景

梅が香に のつと日の出る 山路哉
(読み方:うめがかに のつとひのでる やまじかな)
作者
この句の作者は、「松尾芭蕉」です。
芭蕉は江戸時代前期に活躍した俳諧師で、小林一茶・与謝蕪村とともに「江戸時代の三大俳人」と称される人物です。
美しい日本の風景に侘びやさびを詠みこむ作風は「蕉風」とも呼ばれ、独自の世界を切り開いていきました。

この句は1694年、芭蕉が亡くなるその年に詠まれた句になります。
季語
こちらの句の季語は「梅」で、季節は「春」を表します。
時期としては、立春を過ぎたあたりの頃を指します。
ちなみに、梅は梅でも「早梅」「寒梅」などは晩冬の季語になります。

季語を「梅」とする説と「梅が香」まで入れる説の両方がありますが、一般的に季語と解釈されることが多い「梅」を季語としました。
意味
この句の現代語訳は・・・
「早春、明け方山道を歩いていると、梅の香りに誘われたのか、山並みの向こうから朝日がのっと顔を出したよ。」
といった意味になります。
この句が詠まれた背景
この句は「松尾芭蕉」が最後の春に詠んだ句です。
肌寒さがまだ残る春の朝、朝日が梅の香りに誘われて、ひょっこり昇ってきた様子を「のつと」という口語を使って表現しています。春の訪れを喜んでいる気持ちが伝わってくる一句です。
晩年、芭蕉が提唱した「軽み(=平明な言葉で、日常のさりげない事象を描写すること)」の実践句といえます。
「梅が香にのつと日の出る山路哉」の表現技法

この句で使われている表現技法は・・・
- 切れ字「哉(かな)」
- 「のつと」という表現(擬態語)
になります。
切れ字「哉(かな)」
「切れ字」は俳句でよく使われる技法で、感動の中心を表します。代表的な「切れ字」には、「かな」「けり」「ぞ」「や」などがあります。
この句は「山路哉(かな)」の「哉(かな)」が切れ字に当たります。
この句を詠んだとき、芭蕉は山道を歩いており、起伏によって視点が変わり、太陽が山の端から突然現れたり隠れたりする(ように見える)ことを、驚きを交えてこのように表現しています。
擬態語「のつと」
芭蕉は、突然太陽が出たように見える様子と感動を表すために、「のつと」という感覚的な言葉を使っていると考えられます。
自然界におけるさまざまな状態を言語音で模写した言葉を「擬態語」といい、音と意味とが直接的に結びついているため、理性というよりも、感情に訴えかけます。そのため、擬態語は、相手に強く印象づけたいときに使うと効果的です。
この句では、薄暗い山道を歩いていて、突然明るくなる感覚を「のつと」という擬態語が巧みに表現しています。
「梅が香にのつと日の出る山路哉」の鑑賞

「梅が香にのつと日の出る山路哉」は句碑にもなっているほどの名句で、夜明け前の薄暗い中、山道を歩いているときを詠んだ句です。
日の出がいつなのか分からない中、梅の香りに誘われるがまま、薄暗い山道を歩いています。
薄暗く、足元もおぼつかない中、太陽が「のっと」突然顔を出し、薄暗くてよく見えなかった梅の花もパッとあたりに見えるようになった瞬間が見事に表現されています。
太陽が現れ、周囲が明るくなったときの安心感が伝わってきます。

また、「梅の香」で嗅覚を「のっと」という表現で視覚を刺激する読んでいて楽しい一句です。
江戸時代の句集から松尾芭蕉の作品をまったりと拾い読みしている。
梅が香に
のつと日の出る
山路哉(かな)#くずし字を自主トレ pic.twitter.com/6LrF7FL0bS— 樹下清 (@rokumeibunko1) June 5, 2021
「梅が香にのつと日の出る山路哉」の補足情報

句から受ける印象
「梅の香や」の句の季語は「梅」で春になります。しかし、この句には別の意味も込められていることが芭蕉と弟子のやり取りからわかるのです。
芭蕉の弟子である各務支考が記した『笈日記』では、この句の解釈について支考が芭蕉にこう質問しています。
「梅が香の朝日は余寒なるべし。(中略)是を一躰の趣意と註し候半と申たれば、阿叟もいとよしとは申されし也。」
(訳:梅が香の句に出てくる朝日が表すのは余寒でしょう。これをあなたの伝えようとしていることだと注釈してよろしいでしょうかと聞けば、芭蕉もそれが良いとおっしゃった。)
「梅が香や」の句では、ただ日が出るという様子のみが書かれています。しかし、その本当の目的は「余寒」、未だに寒さが残る立春後の春の初めを詠むことだったのです。

直接的に「余寒」と詠まず、梅や山などどこか寒さを感じさせる言葉で春の初めであることを感じ取るのがこの句の読み方だと至考と芭蕉は語っています。
炭俵の軽み
この句で使われた「のつと」は、「軽み」という蕉門の特徴の1つと言われています。
「軽み」とは、自然を鑑賞している時や最も心に残る情景を詠む時に、過剰に装飾せずに平明な言葉で表すことを意味します。
「梅が香や」の句は『炭俵』という俳諧集に掲載されたため、「のつと」を「炭俵の軽み」と呼ぶこともあるほど特別視されている一句です。

『炭俵』は芭蕉が亡くなる5ヶ月ほど前に発刊されており、死後に「軽み」の俳句が大流行するキッカケにもなっています。
誠ののつと
「梅が香に」という句や『炭俵』が発表されて以降、この句に追随するように「擬態語」や「畳語(じょうご)」などの繰り返し言葉を使った俳句が増えていきます。
しかし、安易にこれらの言葉を使うだけの俳句に、芭蕉の弟子たちは難色を示していました。
向井去来の記した『旅寝論』で、『おくのほそ道』にも同行した宝井其角は以下のように述べています。
「或は「すつと」「きつと」などいへり。師の「のつと」は誠の「のつと」にて、一句の主なり。門人の「すつと」「きつと」はすつともきつ共せず、尤も見苦しし。晋子是を学ぶ事なし。」
(訳:あるいは「すっと」「きっと」などを用いる。芭蕉の「のっと」は誠の「のっと」であって、「梅が香や」の句の主とも言える言葉だ。門人たちの「すっと」「きっと」はどちらも該当せず、見苦しい。私はこれを学ぶことをしない。)

ただ繰り返しの言葉や擬音の言葉を使うのではなく、俳句として意味がある言葉こそ「誠ののつと」であり、軽みであると其角は述べています。
作者「松尾芭蕉」の生涯を簡単にご紹介!

(松尾芭像 出典:Wikipedia)
松尾芭蕉(1644年~1694年)は江戸時代前期の俳諧師で、「芭蕉」は俳号、本名を松尾宗房といいます。
俳諧(連句)を芸術的な域に高め、「蕉風」と呼ばれる芸術性が極めて高い句風を確立し、後の小林一茶や与謝蕪村に多大な影響を及ぼした人物です。
芭蕉は三重県上野市(現在の伊賀市)の貧しい農家に生まれました。平氏の血筋であっそうですが、決して裕福な家庭ではなく、芭蕉自信は幼くして伊賀国上野の武士、藤堂良忠に仕えます。
奉公時代に主君良忠とともに京都の国学者北村季吟に師事し、俳諧を詠むようになったことを機に、良忠の亡き後は、芭蕉は江戸へ出て、俳諧師としての人生を歩むようになります。
40代に入ると旅に出ることを心に決め、江戸から伊賀への旅をまとめた『のざらし紀行』、江戸から伊賀さらには西の兵庫までの旅まとめた『笈の小文』などの紀行文を著し、そのスタイルは徐々に洗練されていきます。
そして、芭蕉の俳諧紀行文の最たるものが、日本人であれば誰もが聞いたこのある『奥の細道』です。
晩年旅に生きた芭蕉は1694年(元禄7年)、享年50歳で大阪の地で客死しました。
松尾芭蕉のそのほかの俳句
(「奥の細道」結びの地 出典:Wikipedia)