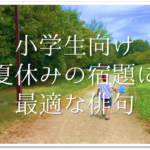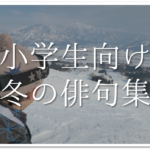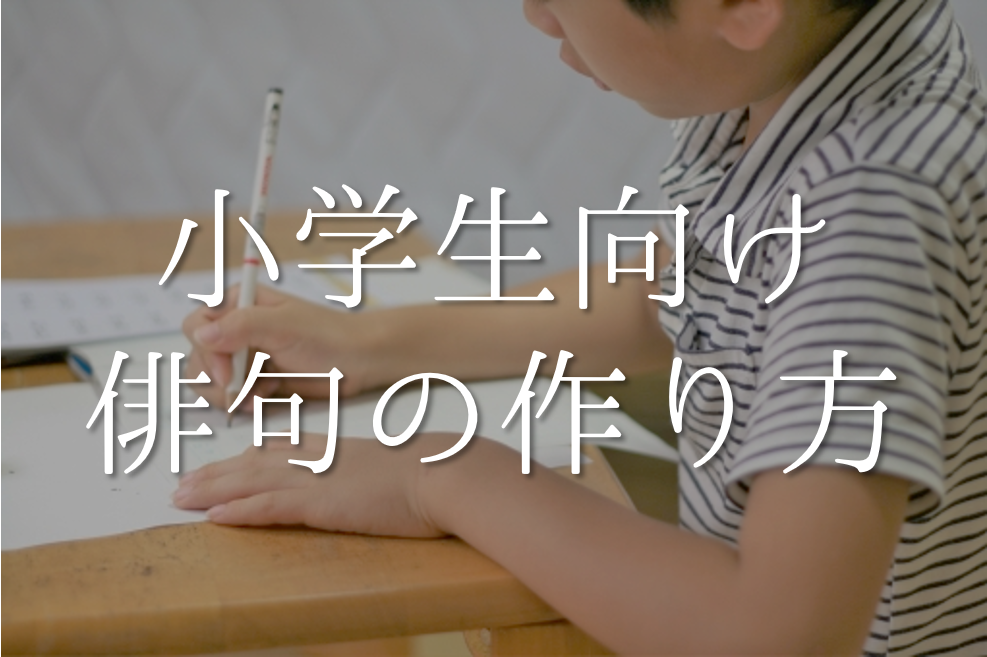
俳句とは日本に昔から伝えられている文の書き方の一つです。
5・7・5の17音という短い文で作られていて、世界で一番短い文だと言われています。
そんな短い俳句の中にも、様々なルールや作り方のコツがあります。
やはり俳句は省略やら季語のこと、色んなルールのせいで、却つて素人衆には分かり難いやうだ。
— 吉田ツグオミ (@tsuguomiyoshida) July 1, 2019
俳句難しいよ~。感性さまざま。ルールが少しわかるといい感じ。悩みながら考えて実施してるのがいいそうな。
菊枕・・・へえ。そんなのあるんだ。
知らないことが、わかると面白い♪— 妙ちゃん (@taekogreed) August 16, 2014
今回は、小学生向けに俳句の作り方やルールなどをわかりやすく説明していき、俳句をうまく書けるようになるコツも紹介していきます。

目次
俳句とは?基本的なルールを知ろう!
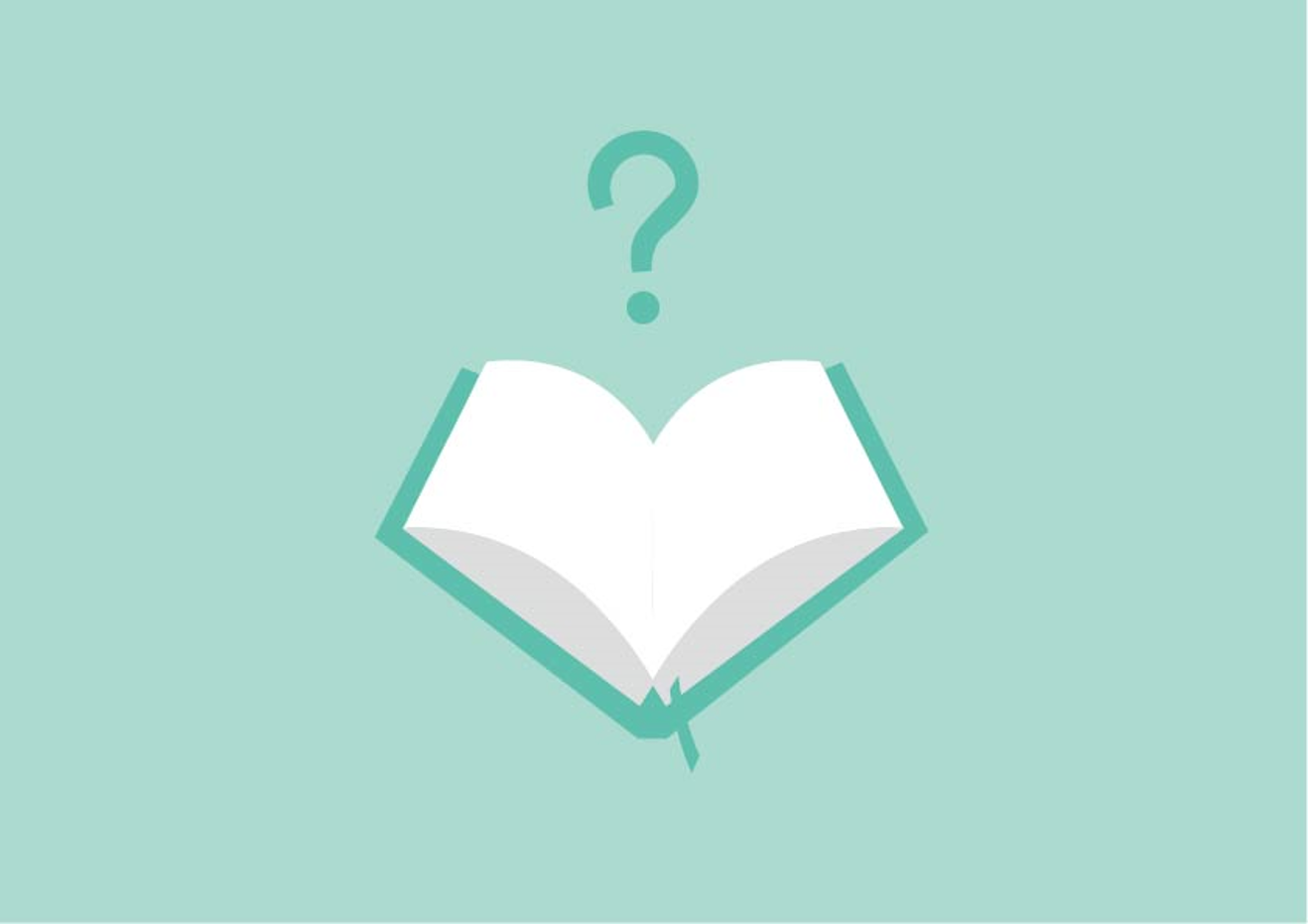
俳句には基本的なルールが2つあります。
①5・7・5の17音にすること
②「季語」を使うこと

①5・7・5の17音にすること
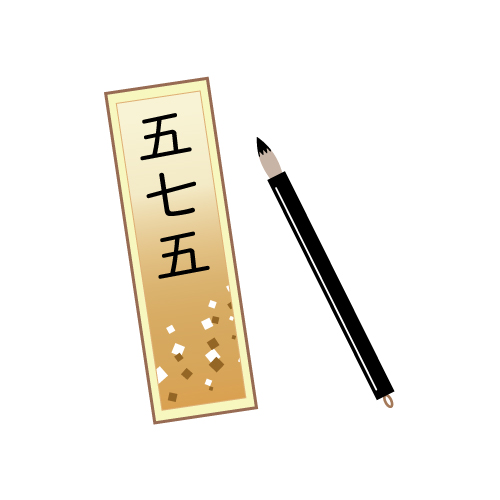
まず俳句は5・7・5の17音で作られています。
5・7・5とは何かを説明すると、俳句は「最初の文を5音、真ん中の文を7音、最後の文を5音」となっているので、まとめて5・7・5と言われています。
例:「古池や 蛙飛びこむ 水の音」
- ふるいけや(5音)
- かわずとびこむ(7音)
- みずのおと(5音)
5・7・5にすると、言葉がきれいにまとまって、短い文でも読みやすい文になるのです。
兄が小学生のときにかいた俳句がげろ面白い pic.twitter.com/xlWtkqwd5W
— (ど) (@dddooobbbb) January 12, 2016
そんな17音で作られている俳句に1つポイントがあります。
それは、「俳句は音(おと)」ということです。
みなさんは、文字を数える時、「1文字、2文字…」と数えると思います。しかし、俳句は「1音、2音…」と言います。「1文字」ではなく「1音」です。この「おと」は、俳句の書き方に関係しています。
例えば、「きょうだい」という言葉があります。「きょ」と書くと2文字です。
では、言葉に出して「きょ」と言ってみてください。みなさんは「きよ」とは言いませんよね?
「きょ」と1音で発音してしまいます。
こういう「ゃ」「ゅ」「ょ」といったものが含まれている言葉は1音となるのです。

②「季語」を使うこと

日本には春・夏・秋・冬という4つの季節があります。その季節らしい言葉がいわゆる「季語」と呼ばれるものです。
【例えば】
- 春・・・「春分」「お花見」「桜」「入学式」
- 夏・・・「海」「猛暑」「梅雨」「アイスクリーム」
- 秋・・・「紅葉」「もみじ狩り」「栗」
- 冬・・・「雪」「ゆきだるま」「炬燵」などなど
季節がある日本だからこそ広がって今も使われている言葉たちです。
これらの中から一つを俳句に入れると、どんな状況なのか、暑いのか寒いのかなど、情景がイメージがしやすくなり、自分もその場にいるように感じられる俳句になります。
このように、季語は俳句の中でも大事な役割を持っているのです。

小学生向け!俳句の作り方&コツ
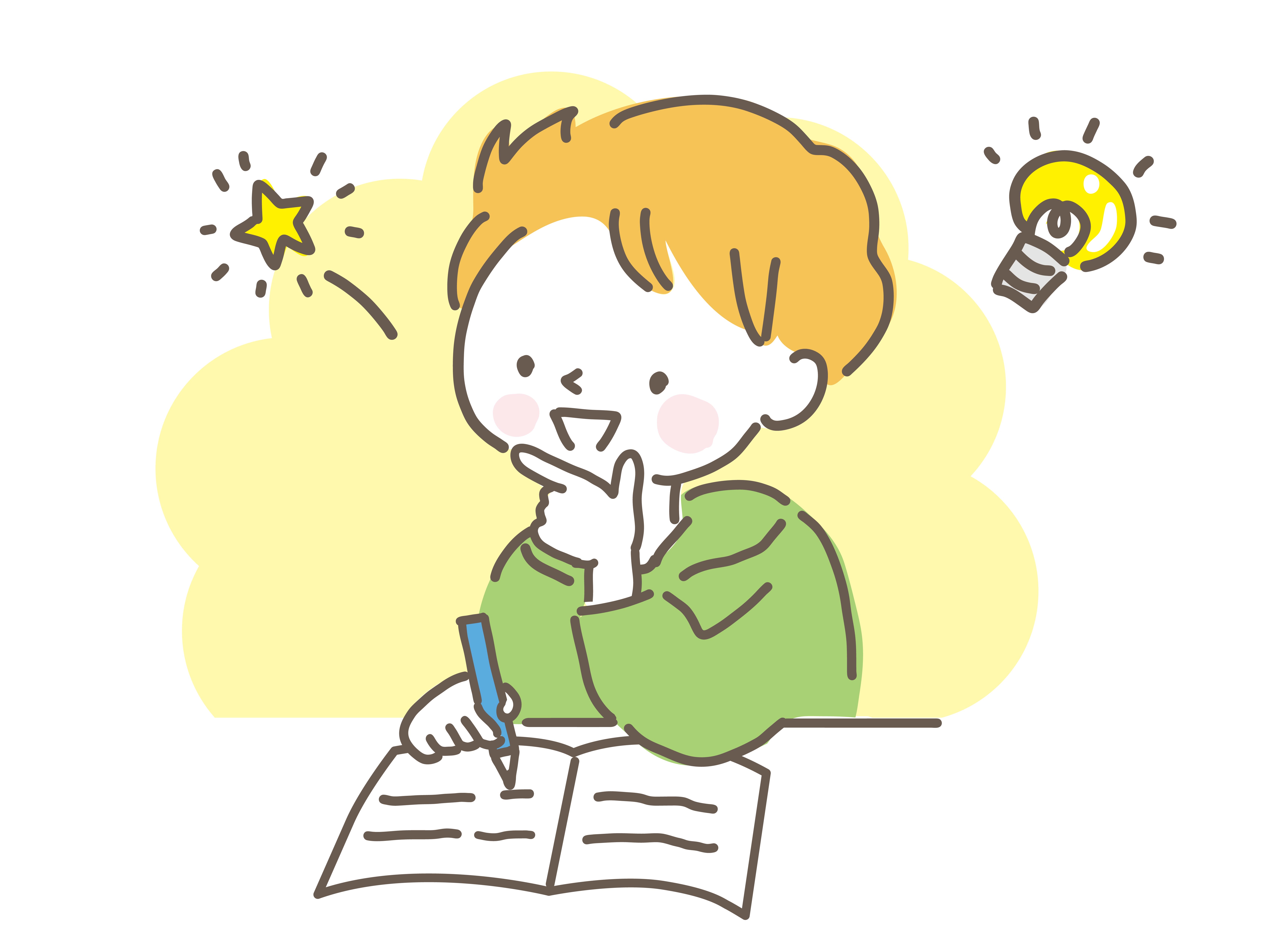
ルールを確認できたところで、さっそく俳句作りに移っていきましょう。

俳句を作る手順
- テーマ&季語を決めよう
- 「場面」や「気持ち」を切り取ってみよう
- 自分が一番伝えたいものを決めよう
- 5・7・5の形に当てはまるように読もう
- 読んでみて違和感があれば、言葉を変えてみよう

①テーマ&季語を決めよう

「テーマと季語」は俳句を作る上で、土台となる部分です。
自分が書きたいテーマを一つ選びましょう。
例えば、運動会や修学旅行といった学校の行事をテーマに決めてもいいですし、日常生活で起きた出来事でもいいでしょう。
そしてテーマが決まったら、季語を考えます。
もちろん「運動会」や「修学旅行」などを季語としてもいいです。
よりくわしく書きたい場合は、運動会や修学旅行を行った季節の季語を使うと、テーマが伝わりやすい俳句になるのでオススメです。
例えば、体育祭が夏に行われたのなら、「汗」や「日焼け」「熱中症」など夏っぽいものを沢山書いてみましょう。

②「場面」や「気持ち」を切り取ってみよう

テーマと季語を決めたら、それにはどのような場面があったか、それに対して自分はどんな気持ちになったかを思い出したり考えてみましょう。
その時は暑かったか寒かったか、何をしたか、自分は嬉しかったか悲しかったかなどを書き出すと良いです。
思いつかない場合は、テーマから連想してみるのも良いですね。
「運動会」などのテーマをまず書いて、それを聞いて何を思い浮かべるか、そこから自分にとっていいなと思うところやイヤだなと思うところをどんどん書いて広げていきましょう。
例えば、「運動会」だったら、「リレー」や「大玉転がし」「応援合戦」などの種目がありますよね。他には「応援合戦」や運動会が終わった後の「片付け」などもあります。

③自分が一番伝えたいものを決めよう

いくつか思い出したらそこから自分が一番伝えたい部分を決めましょう。
テーマを「運動会」にした場合、運動会のどの部分を俳句にしたいかを考えます。
前にもいった通り「運動会」の中にも「リレー」や「綱引き」など種目がありますし、「応援合戦」や終わった後の「片付け」もあります。
そこから一番自分が伝えたいものを考えましょう。
例えば、「リレーが一番キツかったなぁ」と思ったらそれを伝えたいものとしていいですし、「大玉転がしが楽しかったなぁ」と思ったらそれでもいいんです。

③5・7・5のに当てはまるように読もう

伝えたいことが決まったら、早速5・7・5に当てはまるように読んでみましょう。
先ほど書き出しておいた季語と自分が一番伝えたい場面や、「嬉しかった」とか「悲しかった」と言った気持ちを組み合わせ、5・7・5の形に当てはめてみましょう。
例えば、以下のような感じで作ってみてください。
【運動会 リレーで走って 疲れたよ】
【応援で 誰より大きく 声出した】
作ってみましたか?
できたら声に出して読んでみましょう。
ルールのところでも言ったように「俳句はおと」なので書くものというより読むものです。

⑤読んでみて違和感があれば、言葉を変えてみよう

季語や伝えたいものの場面、気持ちを組み合わせて読んだのに、「何か違和感を感じるな」と思った人いませんか?
もしかしたら、5・7・5の形にしっかり言葉が当てはまっていないのかもしれません。
その場合は、同じ意味を持った別の言葉を調べたり考えたりして書きましょう。
例えば「夏」という言葉にも「初夏」や「猛暑」などと言った言葉もあります。是非、似たような言葉をさがしてみてください。

お手本になる!俳句作りの参考になる一般俳句作品【5選】

ここからは、小学生が書いた俳句作品を紹介します。

【NO.1】
『 さくらんぼ 2人で食べて 仲直り 』
季語:さくらんぼ(夏)

【NO.2】
『 せんぷうき 私もいっしょに まわりたい 』
季語:せんぷうき(夏)

【NO.3】
『 ころもがえ わたしのタンス 姉の服 』
季語:ころもがえ(夏)

【NO.4】
『 こいのぼり自由になったらどこへいく 』
季語:こいのぼり(夏)

【NO.5】
『 ピチピチの 水着で知った 今の私 』
季語:水着(夏)

知っておきたい!有名俳人のおすすめ俳句【5選】

ここからは、教科書に載っているような有名な人達が詠んだ俳句をいくつか紹介していきます。

【NO.1】松尾芭蕉(まつおばしょう)
『 古池や 蛙(かわず)とびこむ 水の音 』
季語:蛙(春)
意味:古池があるなぁ。カエルがとびこんだ水の音がするよ。

【NO.2】松尾芭蕉(まつおばしょう)
『 荒海(あらうみ)や 佐渡(さど)によこたふ 天の川 』
季語:天の川(秋)
意味:荒い海だなぁ。佐渡に横たわる天の川だ。

【NO.3】与謝蕪村(よさぶそん)
『 菜の花や 月は東に 日は西に 』
季語:菜の花(春)
意味:菜の花が咲いているなぁ。月が東からのぼり、日は西にしずんでいく。

【NO.4】小林一茶(こばやしいっさ)
『 雀(すずめ)の子 そこのけそこのけ お馬がとおる 』
季語:雀の子(春)
意味:雀の子よ、そこをおどきなさい、そこをおどきなさい。お馬が通りますよ。

【NO.5】正岡子規(まさおかしき)
『 柿食へば 鐘(かね)が鳴るなり 法隆寺(ほうりゅうじ) 』
季語:柿(秋)
意味:柿を食べると鐘が鳴った法隆寺だ。

さいごに

今回は、俳句の作り方やコツについて解説しました。
宿題で俳句を作ることになってどう作ったらいいのか分からなかったという人が多いのではないでしょうか?
俳句は自分の思ったこと伝えたいことを短い文の中でどう表現するかによって変わってきます。