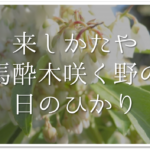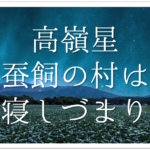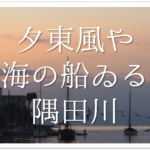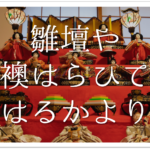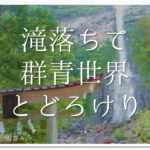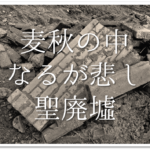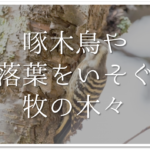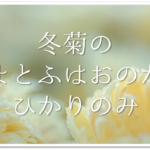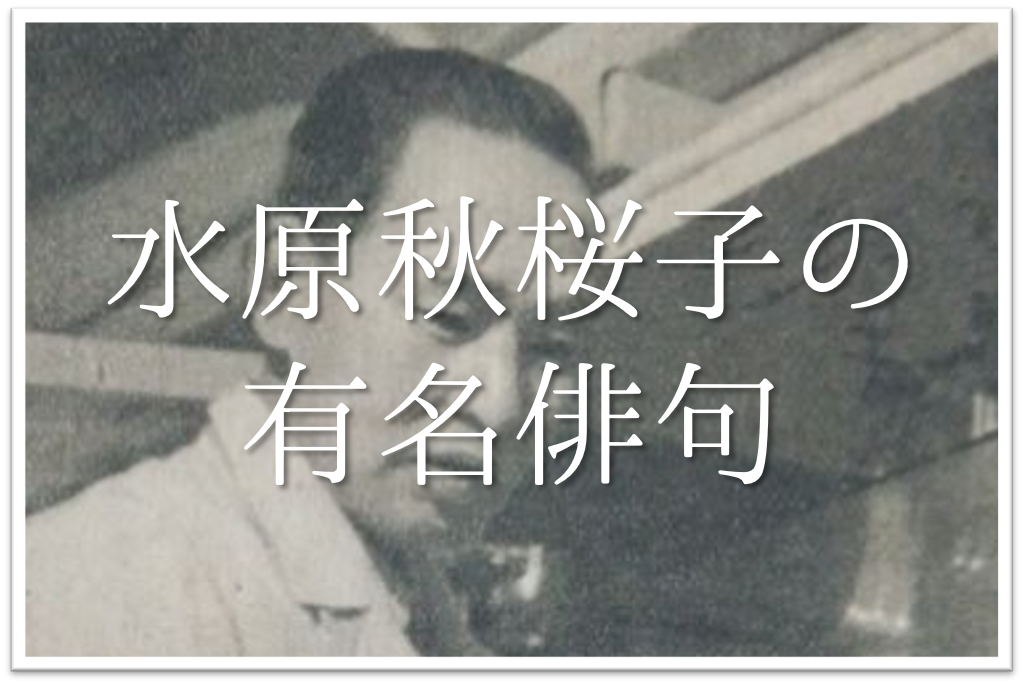
五・七・五の十七音の中に、美しい自然の光景や四季の移ろいを描いた「俳句」。
今回は、医師という本業を持ちつつ、日本の俳壇の中心でも活躍した水原秋桜子の有名俳句(代表作品)を36句ご紹介します。
俳人、水原秋桜子(1892年生)の生まれた日。
医学博士でもある。
高浜虚子に師事し、客観写生。
「馬酔木」主宰。「来しかたや馬酔木咲く野の日のひかり」
「啄木鳥や落葉をいそぐ牧の木々」
「冬菊のまとふはおのがひかりのみ」 pic.twitter.com/MWTzpe7U5P— 咲良 (@sakuranotabi) October 8, 2015
水原秋桜子の人物像や俳句の特徴
(水原秋桜子 出典:Wikipedia)
水原秋桜子(みずはら しゅうおうし)は、大正時代から昭和後期にかけて活躍した俳人です。
高浜虚子の俳句論に興味を持ち俳句雑誌『ホトトギス』を購読し、投句するようになります。高浜虚子から直接手ほどきを受け、昭和の初期には、高野素十、阿波野青畝、山口誓子らとともに「ホトトギスの四S」と称されるなど、ホトトギス派の代表的俳人として名を馳せました。
しかし、あくまで客観写生を称揚する高浜虚子に対して、主観写生的で、抒情的な調べをもつ句を求めた水原秋桜子は反発を強め、ホトトギス派から離脱、反ホトトギスを標榜する新興俳句の先駆者的な存在ともなりました。
水原秋桜子の作風は、日本最古の歌集である「万葉集」を思わせる古風な調べ、抒情的で、あかるく清明な句で知られています。
本業は医師で、現在の昭和大学の前身、昭和医学専門学校で教鞭をとり、また家業の産婦人科病院を継いで病院経営でも業績を残しました。そして昭和30年(1955年)には、医業から引退、句作に専念します。
その後は俳人協会会長を務める、勲三等瑞宝章を受章するなど、文化人としての功績が高く評価されました。昭和56年(1981年)、急性心不全で死去、88歳の生涯でした。

(染井霊園内の水原秋桜子の墓 引用:syrinxブログ編)
水原秋桜子の有名俳句・代表作【36選】

(水原秋桜子 引用:有名人の墓巡り)
春の俳句【9選】

【NO.1】
『 天わたる 日のあり雪解 しきりなる 』
季語:雪解(春)
現代語訳:天空を渡る太陽の光に照らされて、雪解けがさかんに進むことだ。

【NO.2】
『 来しかたや 馬酔木(あしび)咲く 野の日のひかり 』
季語:馬酔木咲く(春)
現代語訳:歩いてきた方向を振り返ってみると、馬酔木の白い花が咲き乱れる春の野に、さんさんと日が降り注ぐ美しい光景が広がっていることだ。

【NO.3】
『 旅の夜の 茶のたのしさや 桜餅』
季語:桜餅(春)
現代語訳:旅にあって、夜に一杯の茶を楽しむことのなんと楽しいことか。今宵の茶菓子は桜餅である。

【NO.4】
『 高嶺星 蚕飼(こがい)の村は 寝しづまり 』
季語:蚕飼(春)
現代語訳:山頂に星が輝いている。蚕を飼って生計を立てている村は寝静まっている夜だ。

【NO.5】
『 夕東風(ゆうごち)や 海の船ゐる 隅田川 』
季語:夕東風(春)
現代語訳:夕暮れに東風が吹いてきたなぁ。隅田川には海からやってきた船がいるようだ。

【NO.6】
『 雛壇や 襖(ふすま)はらひて はるかより 』
季語:雛(春)
現代語訳:立派な雛壇があるなぁ。襖が取り払われて遠くからでも見える。

【NO.7】
『 葛飾や 桃の籬(まがき)も 水田べり 』
季語:桃(春)
現代語訳:葛飾にやってきた。水田沿いに桃の木が垣根になっている。

【NO.8】
『 山桜 雪嶺天に 声もなし 』
季語:山桜(春)
現代語訳:山桜が里に咲いている。視線を上に向けるとまだ雪が積もっている山が見えて、声もないほどだ。

【NO.9】
『 暮雪(ぼせつ)飛び 風鳴りやがて 春の月 』
季語:春の月(春)
現代語訳:夕暮れの雪が飛ぶように降り、風が音を立てて鳴っていると思えばやがて春の月が顔を見せる。

夏の俳句【9選】

【NO.1】
『 ふるさとの 沼のにほひや 蛇苺 』
季語:蛇苺(夏)
現代語訳:ふるさとの沼のにおいがふと思い起こされることだ、赤い蛇苺の実を見かけると。

【NO.2】
『 滝落ちて 群青世界 とどろけり 』
季語:滝(夏)
現代語訳:滝がとうとうと滝つぼに向かって流れ落ち、青々とした葉をつける森林に水音をとどろかせている。

【NO.3】
『 麦秋の 中なるが悲し 聖廃墟 』
季語:麦秋(夏)
現代語訳:時は麦を刈るころ合いであるのに、被爆した浦上天主堂の廃墟が何と悲しいさまであることか。

【NO.4】
『 蕗生ひし 畦に置くなり 田植笠 』
季語:田植え(夏)
現代語訳:フキが生い茂る畔においた田植笠になんとも風情をかんじることだ。

【NO.5】
『 雪渓は 夏日照るさへ さびしかり 』
季語:雪渓(夏)
現代語訳:万年雪の残る高山の渓谷は、夏の陽ざしが当たってもなお寂しげに見えることだ。

【NO.6】
『 ナイターの 光芒大河 へだてけり 』
季語:ナイター(夏)
現代語訳:ナイターの強い光が大きな川に隔てられている。

【NO.7】
『 誰も来て 仰ぐポプラぞ 夏の雲 』
季語:夏の雲(夏)
現代語訳:誰もが傍に来て仰ぐポプラがこの木だ。夏の雲も見える。

【NO.8】
『 月見草 神の鳥居は 草の中 』
季語:月見草(夏)
現代語訳:月見草の花が咲いている。神の通る鳥居は草の中に埋もれてしまった。

【NO.9】
『 紫陽花や 水辺の夕餉(ゆうげ) 早きかな 』
季語:紫陽花(夏)
現代語訳:紫陽花が咲いているなぁ。水辺で取る夕飯はいつもより早い時間であることだ。

秋の俳句【9選】

【NO.1】
『 啄木鳥や 落葉をいそぐ 牧の木々 』
季語:啄木鳥(秋)
現代語訳:キツツキが木をつつく音が聞こえることだ。牧場の木々は、冬に備えて急ぐかのように葉を散らしている。

【NO.2】
『 はたはたの 羽音ひまなし 月待てば 』
季語:はたはた(秋)
現代語訳:月を眺めようと空を眺めつつ待っていると、バッタが飛び交う羽音がひっきりなしに聞こえてくる。

【NO.3】
『 暗きまま 黄昏れ来り 霧の宿 』
季語:霧(秋)
現代語訳:薄暗くはっきりしない天気のまま、黄昏時が迫ってますます暗くなり、宿の周りも深い霧に閉ざされていくことだ。

【NO.4】
『 竜胆や 月雲海を のぼり来る 』
季語:竜胆(秋)
現代語訳:竜胆の濃い青紫の花が咲いているよ。月は、雲海を抜けて空にのぼっていくことだ。

【NO.5】
『 わがいのち 菊にむかひて しづかなる 』
季語:菊(秋)
現代語訳:私の命をこめて菊に向かって静かに句を作っている。

【NO.6】
『 雨ながら 朝日まばゆし 秋海棠(しゅうかいどう) 』
季語:秋海棠(秋)
現代語訳:雨が降っているが、朝日もまばゆく見える中で秋海棠の花が咲いている。

【NO.7】
『 月山(がっさん)の 見ゆと芋煮て あそびけり 』
季語:芋煮(秋)
現代語訳:月山を見ようと芋を煮ながら遊んでいる。

【NO.8】
『 萩の風 何か急かるる 何ならむ 』
季語:萩(秋)
現代語訳:萩の花が風に吹かれているのを見ると、何かを急かされている気がする。これはなんだろう。

【NO.9】
『 秋晴や 釣橋かかる 町の中 』
季語:秋晴(秋)
現代語訳:秋晴れだなぁ。吊り橋がかかっている町の中だ。

冬の俳句【9選】

【NO.1】
『 山茶花の 暮れゆきすでに 月夜なる 』
季語:山茶花(冬)
現代語訳:山茶花の咲く道は夕闇にまぎれ、月夜となってきたことだ。

【NO.2】
『 冬菊や まとふはおのが ひかりのみ 』
季語:冬菊(冬)
現代語訳:冬菊が咲いている。冬菊は、冬の日を浴びて、自らが放つ光の衣を身に纏っているようだ。

【NO.3】
『 薄氷の このごろむすび 蓮枯れぬ 』
季語:蓮枯れる(冬)
現代語訳:池のおもてには最近では薄く氷が張るようになり、蓮もかれたことだ。

【NO.4】
『 北風や 梢離れし もつれ蔓 』
季語:北風(冬)
現代語訳:北風が強く吹き付けることだ。梢を離れて、もつれた蔓が吹き飛ばされていく。

【NO.5】
『 ぬるるもの 冬田になかり 雨きたる 』
季語:冬田(冬)
現代語訳:これまでは冬の田んぼに濡れるようなものはなかったのだ。雨が降ってきている。

【NO.6】
『 寒苺 われにいくばくの 齢のこる 』
季語:寒苺(冬)
現代語訳:冬の赤い苺を見ていると、私にはあとどれだけの寿命が残っているのかと考える。

【NO.7】
『 羽子板や 子はまぼろしの すみだ川 』
季語:羽子板(新年)
現代語訳:羽子板だなぁ。幻の子供に出会ったという隅田川の伝説が思い起こされる。

【NO.8】
『 鰭酒(ひれざけ)も 春待つ月も 琥珀色 』
季語:鰭酒(冬)
現代語訳:ヒレ酒も春を待つ月も同じ琥珀色をしている。

【NO.9】
『 むさしのの 空真青なる 落葉かな 』
季語:落葉(冬)
現代語訳:武蔵野の空が真っ青で美しい。そんな空を見上げていると、落ち葉がひらひらと落ちてくる。

さいごに

今回は、水原秋桜子の代表的な俳句を36句紹介しました。
水原秋桜子は医師としても功績をあげる傍ら、20を超える句集・随筆・紀行文など、多くの著作を残しました。
アララギ派の黄金時代を作る一人となりながらも、その後アララギを離れて新興俳句へ、そして日本の俳壇のなかで一座を閉めるようになりました。
大正時代から昭和の後期にかけて長い作句人生を送り、さまざまな句を詠んだ水原秋桜子。今なお、彼の俳句は多くの人々の共感を呼んでいます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。