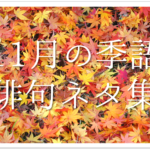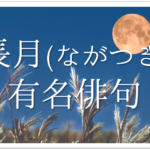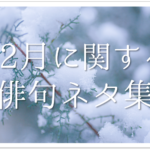俳句は五七五の韻律を持つ十七音の詩で、季語を詠むことによってさまざまな季節の風景を表します。
今回は、11月の季語を使ったおすすめ有名俳句を30句紹介していきます。
【冬紅葉:11月の季語】散り遅れて、冬が到来してもなお美しく残っている紅葉のこと。
冬紅葉海の十六夜照りにけり(水原秋櫻子)
夕映に何の水輪や冬紅葉(渡辺水巴)
侘びつつも酒の粕焼く冬紅葉(椎本才麿) pic.twitter.com/T0Ui8IsVhe— うちゆう (@nousagiruns) November 29, 2014

それじゃあ早速見ていこう!
俳句に11月らしさを出す!11月の季語を知ろう

俳句には、重要な役割を担っている「季語」というものがあります。
季語とは、いかにもその季節らしい言葉のことで、例として春なら「桜」夏なら「向日葵」などが挙げられます。
俳句ではその時その時の季語を用いることにより、期間が具体的にわかりその時の情景をよりリアルに伝えることができます。
ここでは、11月の季語をいくつか紹介していきます。
【初冬】
読み方:しょとう
意味:冬の始まり
【目貼】
読み方:めばり
意味:冬の寒さや風、雪を防ぐために、窓や戸棚の隙間に紙などを貼ること。
【熊穴に入る】
読み方:くまあなにはいる
意味:熊が雪が積もる頃から春彼岸の雪解けの頃まで、木の穴や洞窟で冬眠に入ること。
【綿虫】
読み方:わたむし
意味:アブラムシのうち、白腺物質を分泌する腺が存在するものの通称
【紅葉散る】
読み方:もみじちる
意味:冬の訪れとともに散っていく紅葉のこと。
上記のように、11月は冬の始まりを知らせる季語が多いように感じます。
今は秋だというイメージが強いのですが、昔は冬の始まりを告げる月だったのですね。

11月の季語【一覧】
神無月 / 立冬 / 水始めて氷る / 小春 / 冬浅し / 冬めく /凩 / 星の入東風 / 神渡し / 初時雨 / 時雨 / 初霜 /後の更衣 / 冬構 / 北窓塞ぐ / 霜除 / 風除 / 炉開 / 塗炉縁 / 敷松葉 / 口切 / 蕎麦刈 / 大根引 / 大根干す / 切干 / 蕪引 / 干菜 / 蓮根掘る / 麦蒔 / 牡丹焚火 / 棕櫚剥ぐ / 馬下げる / 注連作 / 木の葉髪 / 年貢納 /氷魚の使 / 孟冬の旬 / 炉炭を進る / 射場始 / 新嘗祭 / 明治神宮祭 / 鎮魂祭 / 勤労感謝の日 / 九州場所 / 亥の子 / 十日夜 / 案山子揚 / 杜氏来る / 下元 / 七五三 / 神の旅 / 神在祭 / 神迎え / 恵比寿講 / 厳島鎮座祭 / 御火焚 / 鞴祭 / 尻摘祭 / 山の神祭 / 酉の市 / 出雲大社新嘗祭 / 神農祭 / 納の庚申 / 智積院論義 / 十夜 / 興福寺法華会 / 維摩会 / 栂尾虫供養 / 吉祥院八講 / 鉢叩 / 大師講 / 別時念仏 / 感謝祭 / 待降節 / 聖ザビエルの日 / 宗鑑忌 / 東叡山開山忌 / 達磨忌 / 浪化忌 / 芭蕉忌 / 嵐雪忌 / 東福寺開山忌 / 几董忌 / 白秋忌 / 亜浪忌 / 勇忌 / 八一忌 / 波郷忌 / 一葉忌 / 三島忌 /落鱸 / 柳葉魚 / 霜降かます / 蟷螂枯る / 冬の虫 / 冬の蝗 /帰り花 / 山茶花 / 八手の花 / 柊の花 / 茶の花 / 冬紅葉 / 落葉松散る / 朴落葉 / 銀杏落葉 / 冬葵 / 紫甘藍 / 山牛蒡 / 寒竹の子 / 麦の芽 / 石蕗の花 / 寒葵 / 寒蘭 / 雪割茸 / 榎茸
11月の季語を使った有名俳句集【20選】

それでは早速、11月の季語を使った俳句を20句紹介していきます。
【NO.1】中村草田男
『 あたゝかき 十一月も すみにけり 』
季語:十一月(冬)
意味:あたたかい十一月もすぎてしまった。

【NO.2】服部嵐雪
『 木がらしの 吹き行くうしろ 姿かな 』
季語:木がらし(冬)
意味:木枯らしが旅立っていく芭蕉の後ろ姿を吹き過ぎてゆく。

【NO.3】小林一茶
『 母親を 霜よけにして 寝た子かな 』
季語:霜よけ(冬)
意味:霜よけのように母親に抱かれながら子は眠ってしまったのだな。

【NO.4】水原秋桜子
『 返り花 満ちてあはれや 山ざくら 』
季語:返り花(冬)
意味:暖かくて穏やかな日に今の季節に咲くはずのない山ざくらが満開に咲いていて愛しいと思う。

【NO.5】星野立子
『 初時雨 人なつかしく 待ちにけり 』
季語:初時雨(冬)
意味:初時雨が降るなかで、人恋しく待っていた。

【NO.6】正岡子規
『 初霜に 負けて倒れし 菊の花 』
季語:初霜(冬)
意味:初霜の重さに耐えられず、倒れてしまっている菊の花。

【NO.7】松尾芭蕉
『 旅に病んで 夢は枯れ野を 駆け巡る 』
季語:枯れ野(冬)
意味:旅の途中で病気になってしまい、見る夢は私が枯れ野を駆け巡る夢ばかりである。

【NO.8】正岡子規
『 白露や 茨の針に ひとつづつ 』
季語:白露(秋)
意味:朝露が降りる秋の朝、茨の針の先にはひとつずつ露の玉が輝いている。

【NO.9】森川許六
『 行きあたる 谷のとまりや 散る紅葉 』
季語:散る紅葉(冬)
意味:行き当たった谷に止まると、紅葉が散っていた。

【NO.10】秋元不死男
『 鳥わたる こきこきこきと 缶切れば 』
季語:鳥わたる(秋)
意味:鳥が渡っていく。缶詰切るコキコキコキという音に合わせて鳥がジグザグと飛んでいます。


【NO.11】池西言水
『 木枯らしの 果てはありけり 海の音 』
季語:木枯らし(冬)
意味:木枯らしにも果てはあるんだなあ。海の音で木枯らしの音がかき消されている。

【NO.12】小林一茶
『 大根引き 大根で道を 教えけり 』
季語:大根引き(冬)
意味:大根を収穫している人たちが、引き抜いた大根で道を教えている。

【NO.13】松尾芭蕉
『 人々を しぐれよやどは 寒くとも 』
季語:しぐれ(冬)
意味:人々よ、どんなにこの場所が寒くなろうとも時雨を楽しもうではないか。

【NO.14】山口誓子
『 海に出て 木枯らし帰る ところなし 』
季語:木枯らし(冬)
意味:海に出ても木枯らしには帰るところがないのだなぁ。

【NO.15】加藤楸邨
『 木の葉ふりやまず いそぐな いそぐなよ 』
季語:木の葉ふり/木の葉降る(冬)
意味:木の葉がはらはらとふりやまない。いそぐな、いそぐなよ。

【NO.16】芥川龍之介
『 木枯らしや 目刺しに残る 海の色 』
季語:木枯らし(冬)
意味:木枯らしが吹いているなぁ。目刺しには海の色が残っているように感じる。

【NO.17】星野立子
『 大勢の 中に我あり 冬紅葉 』
季語:冬紅葉(冬)
意味:大勢の中に私がいるのだ、冬紅葉のように主張している。

【NO.18】村上鬼城
『 小春日や 石を噛み居る 赤蜻蛉 』
季語:小春日(冬)
意味:暖かい小春日だ。石を噛むようにそこに居る赤とんぼよ。

【NO.19】松本たかし
『 玉の如き 小春日和を 授かりし 』
季語:小春日和(冬)
意味:玉のように貴重な小春日和を授かった。

【NO.20】友岡子郷
『 跳び箱の 突き手一瞬 冬が来る 』
季語:冬(冬)
意味:跳び箱を飛ぶ時に手を突いた、その一瞬に冬が来るのを感じる。

11月の季語を使った一般おすすめ俳句作品集【10選】

ここからは、一般の方が詠んだ俳句作品を10句紹介していきます。是非俳句作りの参考にしてみてください。
【NO.1】
『 文化祭 短冊前に 筆重く 』
季語:文化祭(秋)

【NO.2】
『 犬小屋の 奥まで日差す 小春かな 』
季語:小春(冬)

【NO.3】
『 バス好きが バスで帰るも 七五三 』
季語:七五三(冬)

【NO.4】
『 パン食べて 一人の夜長 もてあます 』
季語:夜長(秋)

【NO.5】
『 教会の 夕べの鐘や 秋の風 』
季語:秋の風(秋)

【NO.6】
『 初霜や 畑の野菜を 輝かす 』
季語:初霜(冬)

【NO.7】
『 石段を 余すことなく 紅葉散る 』
季語:紅葉散る(冬)

【NO.8】
『 人よりも 防寒している 神無月 』
季語:神無月(冬)

【NO.9】
『 立冬や 朝刊くばる バイク音 』
季語:立冬(冬)

【NO.10】
『 口切や ゆくゆくは継ぐ 和菓子職 』
季語:口切(冬)



11月という短い期間の中でも、たくさんの俳句があり沢山の人の気持ちが込められています。
ぜひこの機会に一句詠んでみてはいかがでしょうか?