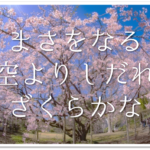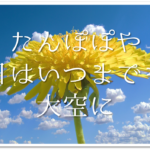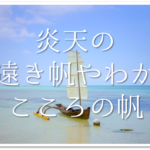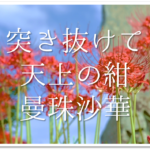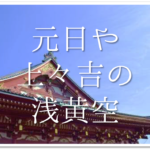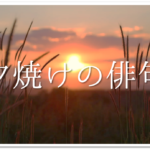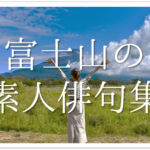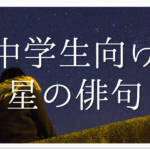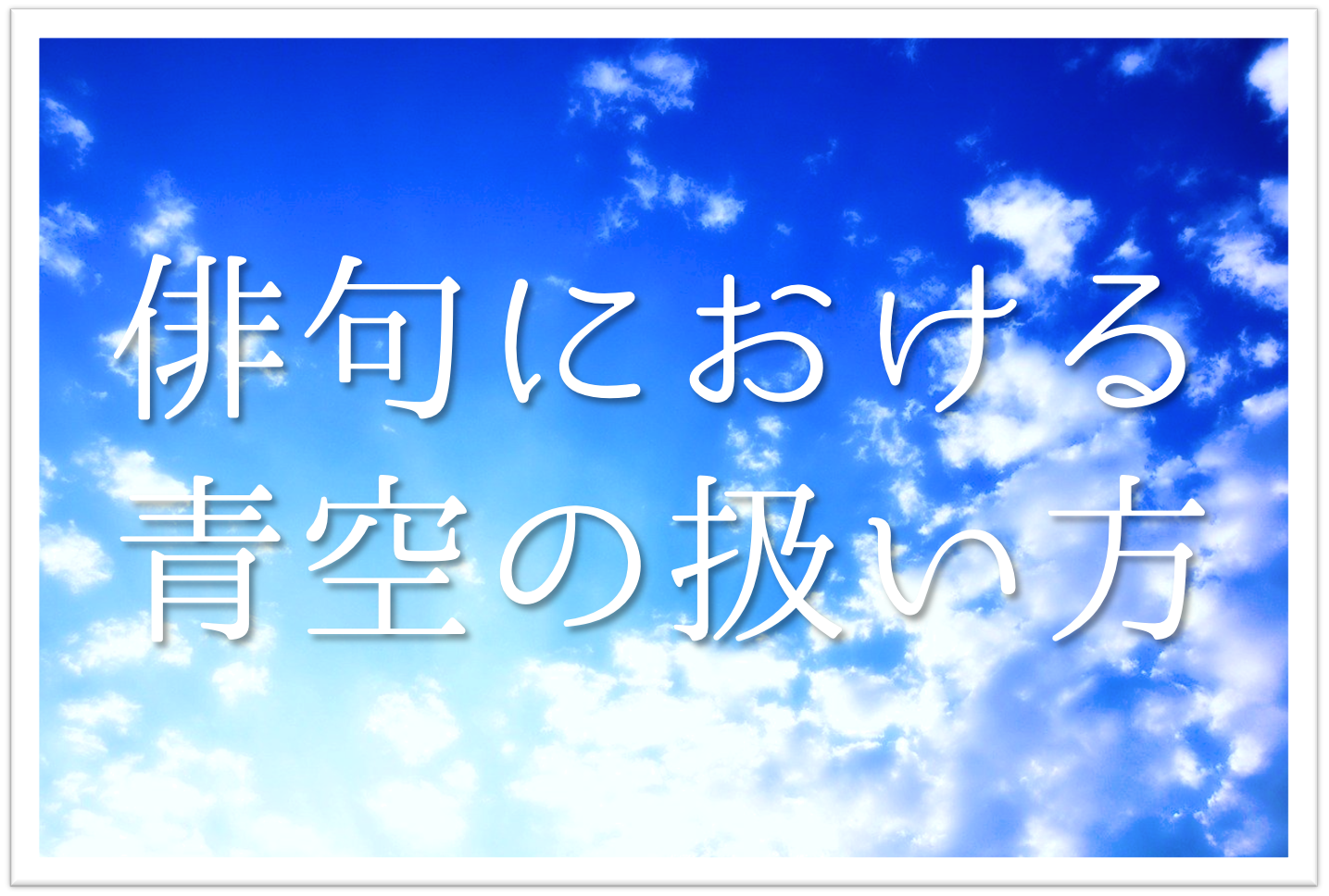
五・七・五の十七音に季節を表す季語を入れ、心情や風景を詠みこむ「俳句」。
ちょっとした季節の移り変わりを、俳句によって感じることができるのも俳句の魅力の一つです。
そんな俳句の中でも、青空をテーマにした俳句は数多く存在します。
青空のやうな帷きたりけり (あおぞらのようなかたびらきたりけり) 小林一茶
just like the blue sky
light summer kimono
that I'm wearing#俳句 #jhaiku #Issa pic.twitter.com/ccq9G7tXeV— Ted Z. (@TeddyBearPL) May 29, 2015
しかし、俳句において「青空」という単語は少し扱いが難しいです。
そこで今回は、俳句における青空の扱いや季語を使って青空を表現する方法を簡単にわかりやすく解説していきます。

目次
青空という季語は存在しない

(1)季語とは
そもそも季語とは、春夏秋冬の季節を示す語として、俳句の中に詠みこむように定められた言葉をさします。
例えば、春の季語であれば、「桜」や「チューリップ」など、その季節を表す言葉が季語となります。
季語は、時候・天文・地理・人事・行事・忌日・動物・植物の9項目に分類されます。先ほど挙げた春の季語「桜」はこの分類だと、植物です。しかし、桜を鑑賞する「お花見」は行事に分類されます。
このように、誰もが知っている言葉が季語となります。
また、季語は5000語あるとされています。俳句の季語は、俳句季語辞典や俳句歳時記などを使って調べると、たくさんの季語が出てきます。
(2)青空は季語にならない
私たちがほぼ毎日、目にしている「青空」は、どの季節の季語にあたるでしょうか。
「青空」は、晴れて青く見える空のことですが、春、夏、秋、冬、いろいろな青空があります。
こうして考えてみると、どの季節にも青空は存在します。

このように、どの季節にも存在するものは特定の季節の季語にはなりません。そのため、「青空は季語ではない」のです。
青空をテーマにした有季俳句を詠む方法

「青空は季語ではない」ならば、春の少し青色の薄い空や、夏の爽やかな青空、冬の冷たい空気に澄んだ真っ青な空は、どのように表現したらいいのでしょうか?

青空をテーマとした「有季俳句(季語を含む俳句)」を詠みたい場合は、以下の3つの方法があります。
(1)季節を表す語とセットにする
1つ目は、季節を表す春夏秋冬を「青空」の前につけることです。
「春の青空」「夏の青空」「秋の青空」「冬の青空」といった形にすれば、季語となります。
(2)空にまつわる季語を使う
2つ目は、空にまつわる季節特有の語を使うことです。
わかりやすいものだと、「春の空」という語があります。
季節の「春」を「空」につけただけではないかと思うかもしれませんが、この「春の空」は季語となります。「春天」などともいいますが、これは春の青空を表します。
春は、大気が水分を含んでいてちょっと霞がかったような青空になりますが、この「春の空」の季語ひとつで、そのような空の状況を表すことができるのです。

「夏の空」は、梅雨明けしたときのような青色の原色のような空をさします。「夏の天」「夏空」ともいわれます。
(3)季節特有の語で空を表現する
3つ目は、青空という語を使わずに季節特有の語で季節の青空を表現している語を使う方法です。
中国で古くから使われている「天高く馬肥える秋」という表現があります。
これは「秋の高いところまで澄み切った空の下、馬は健康に肥っている」という意味で、爽やかで心身ともに心地の良い秋を表現しています。
この「天高し」という表現は、秋の季語です。この一語で、大気が澄んで空が高くなったように感じる秋の空をさします。
「秋高し」「空高し」の表現も同じ意味です。秋の空をさして「空青し」という表現がありますが、こちらは秋の季語ではありません。青空と同様に、どのような季節の状況にも当てはまるため、季語とは言えません。

このように、青空という語をいれなくても空にまつわる季節の語をいれることで、季節の青空を表現することができます。
青空をテーマにした有名俳句【16選】

ここでは、季節の青空をテーマにした俳句を紹介していきます。

春の俳句
【NO.1】高浜虚子
『 春の空 人仰ぎゐる 我も見る 』
読み仮名:はるのそら ひとあおぎいる われもみる
季語:春の空(春)
意味:春の空を人が仰ぎ見ていて、私も思わず同じように見てしまった。

「ゐる」と「見る」でリズムをとっている一句です。皆につられるように空を見る作者の様子が伝わってきます。
【NO.2】稲村汀子
『 春の空 見上げ心に 通ふもの 』
読み仮名:はるのそら みあげこころに かようもの
季語:春の空(春)
意味:この春の霞がかった空を見上げて、心に通うものがある。

春の空に何か思うところがある作者の心情を表しています。少しぼんやりとした空の様子が晴れない心を代弁しているかのようです。
【NO.3】中村草田男
『 春空に 身一つ容るる だけの塔 』
読み仮名:はるぞらに みひとついるる だけのとう
季語:春空(春)
意味:薄く霞がかった春の空に、身が一つ入るだけのような小さな塔が立っている。

この「塔」が何を表しているのかは読む人によって変わってくるでしょう。風景としての塔なのか、雲などが塔に見えたのか、どちらを思い浮かべたでしょうか。
【NO.4】富安風生
『 まさをなる 空よりしだれ ざくらかな 』
読み仮名:まさをなる そらよりしだれ ざくらかな
季語:しだれざくら(春)
意味:真っ青な空から枝垂れ桜が垂れてきている様だなぁ。

この句では、「真っ青な」ではなく「まさをなる」という古文に近い用語を使っています。一時的に枝垂れ桜の樹齢400年という時の流れを思い出しているような一句です。
【NO.5】中村汀女
『 たんぽぽや 日はいつまでも 大空に 』
読み仮名:たんぽぽや ひはいつまでも おおぞらに
季語:たんぽぽ(春)
意味:たんぽぽの花が咲いているなぁ。日が長くなり、いつまでも大空に日が照っていることだ。

この句は、たんぽぽという春の花を見ながら、日が長くなりずっと野原を散策できるという楽しみを詠んでいます。散策日和というところから、青空なのだろうと連想することも可能です。
夏の俳句
【NO.1】飯田蛇笏
『 夏空に 地の量感 あらがへり 』
読み仮名:なつぞらに ちのりょうかん あらがえり
季語:夏空(夏)
意味:真っ青な夏の空に負けないほど張り合っている大地の大きさよ。

空と大地を詠んだダイナミックな一句です。「量感」と詠んだのが個性的で、スケールの差を比べています。
【NO.2】中塚一碧樓
『 山一つ 山二つ三つ 夏空 』
読み仮名:やまひとつ やまふたつみつ なつぞら
季語:夏空(夏)
意味:真っ青な夏の空に、山が1つ、2つ、3つとそびえている。

山の繰り返しと、一つ二つ三つという数え方でテンポよく読める一句です。見渡す限りの山々と夏の空が浮かんできます。
【NO.3】山口誓子
『 炎天の 遠き帆やわが こころの帆 』
読み仮名:えんてんの とおきほやわが こころのほ
季語:炎天(夏)
意味:この暑さの中で遠くに見えるあの帆こそ、私の心の帆なのだ。

この句は作者の心の中の風景を詠んでいます。終戦直後、かつ療養中であった作者は、青く広がる空とこれからの自分の道を比べ、「遠き」と判断したのでしょう。
秋の俳句
【NO.1】正岡子規
『 すさまじき 雲の走りや 秋の空 』
読み仮名:すさまじき くものはしりや あきのそら
季語:秋の空(秋)
意味:すごい勢いで雲が走っている、もう夏も終わり秋の空が広がっている。

秋の雲は筋状の雲が増えるため、それを指して「走り」と称しています。もくもくとした入道雲からの移り変わりを感じる一句です。
【NO.2】正岡子規
『 絶頂や 頭の上に 秋の空 』
読み仮名:ぜっちょうや あたまのうえに あきのそら
季語:秋の空(秋)
意味:頭の上に、天まで届くほど高く秋の空が広がっている。

登山で山頂に立ったときの感動を詠んでいます。見渡すかぎりの青い空が浮かんでくるようです。
【NO.3】高浜虚子
『 秋天に われがぐんぐん ぐんぐんと 』
読み仮名:しゅうてんに われがぐんぐん ぐんぐんと
季語:秋天(秋)
意味:天高く澄み切っている秋の空を見上げていると、自分も一緒にぐんぐんと昇っていくようだ。

「ぐんぐん」を繰り返すことで、青空に吸い込まれるような体験を読者にも伝えています。雲がなく、どこまでも見渡せるような空だったのでしょうか。
【NO.4】山口誓子
『 突き抜けて 天上の紺 曼珠沙華 』
読み仮名:つきぬけて てんじょうのこん まんじゅしゃげ
季語:曼珠沙華(秋)
意味:突き抜けるような天上の紺色に、曼珠沙華の赤が映えている。

この句は秋の深い青空を表す「天上の紺」と、赤い「曼珠沙華」が対比になっています。青と赤の美しいコントラストを詠んだ句です。
冬の俳句
【NO.1】永井荷風
『 冬空や 風に吹かれて 沈む月 』
読み仮名:ふゆぞらや かぜにふかれて しずむつき
季語:冬空(冬)
意味:冬の澄み切った寒さの空に 月が風に吹かれて沈むようだ。

冬の空は地域によりますが、美しい月が見られます。吹きすさぶ風に押されるように沈んでいく月が詩的にあらわされた一句です。
【NO.2】飯田龍太
『 いつとなく 葡萄の国も 冬の空 』
読み仮名:いつとなく ぶどうのくにも ふゆのそら
季語:冬の空(冬)
意味:どこまでもつづく このブドウの産地にも 冬の空が続いている。

ブドウ畑とその上に続く冬の空を詠んでいます。地平線まで続いているのではないかと錯覚させるほど雄大な風景を詠んだ一句です。
【NO.3】小林一茶
『 元日や 上々吉の 浅黄空 』
読み仮名:がんじつや じょうじょうきちの あさぎぞら
季語:元日(新春)
意味:元旦はこの上なく縁起のいい浅黄色の空だ。

「上々吉」はこの上なく縁起が良い様子を表します。「浅黄色」とは青に近い藍色で、深い青空のことです。
さいごに

私たちがいちばん季節の移り変わりを感じるのは、天気予報かもしれません。
俳句を始めてみると季節の移り変わりが、より一層身近に感じられます。
ぜひ、みなさんも天気予報だけでなく、今日の空を見上げて季節を感じ、俳句を詠んでみてください。