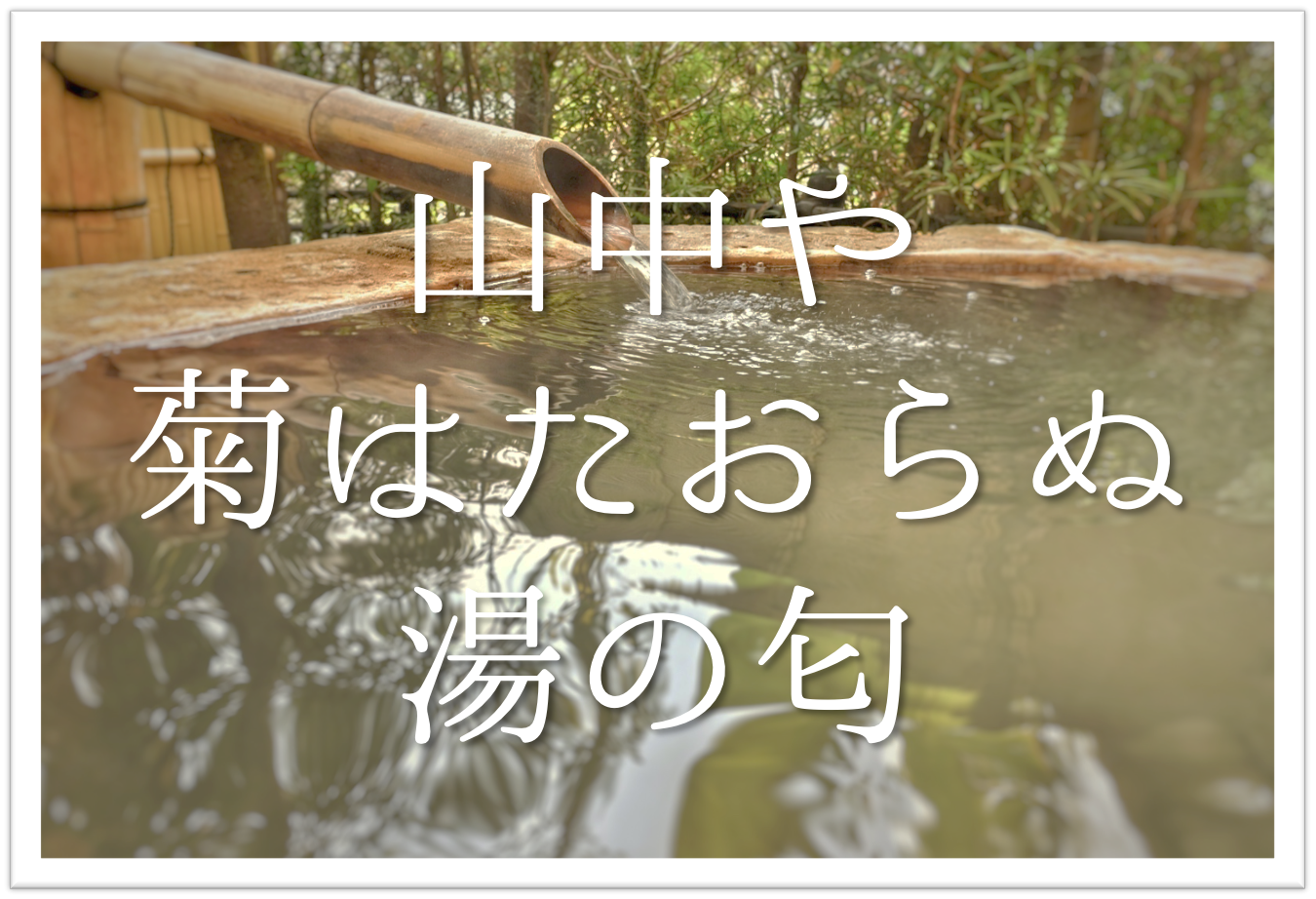
五・七・五のわずか十七音に心情や風景を詠みこむ「俳句」。
詠み手の心情や背景に思いをはせて、いろいろと想像してみることも俳句の楽しみのひとつかもしれません。
今回は、有名な句の一つ「山中や菊はたおらぬ湯の匂」という句をご紹介します。
今日は、重陽の節句。幸せや長寿を願って菊の花を飾ったり菊の花びらを浮かべたお酒を酌み交わすそうです。山中や 菊はたおらぬ 湯の匂(松尾芭蕉「奥の細道」) pic.twitter.com/MJfVktVpuQ
— 諸戸佑美 (@yumi_moroto) September 9, 2013
本記事では、「山中や菊はたおらぬ湯の匂」の季語や意味・表現技法・作者などについて徹底解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
「山中や菊はたおらぬ湯の匂」の俳句の季語や意味・詠まれた背景

山中や 菊はたおらぬ 湯の匂
(読み方:やまなかや きくはたおらぬ ゆのにおい)
この句の作者は、「松尾芭蕉(まつおばしょう)」です。
江戸時代前期の俳諧師で、数多くの旅を通して名句を生み出し、俳諧の世界に新しい道を開きました。与謝蕪村や小林一茶などと並び称される江戸俳諧の巨匠の一人です。
季語
この句の季語は「菊」、季節は「秋」です。
菊は、桜とともに日本の国花となっており、日本の秋を象徴する花です。
江戸時代になって、観賞用としての菊づくりが盛んになりました。主に秋に咲き、花の色や形などにより非常に多くの品種があります。
菊紋は皇室の家紋にもなっており、50円硬貨のデザインにも使われていることから、みなさんにも馴染みが深い花ではないでしょうか。
俳句の季語としてもたくさん使われ、様々な俳句が詠まれてきました。季語に菊が使われていると、一本の素朴さからたくさん咲き誇る華やかさまで、その香りともに感じられるように思います。
意味
こちらの句を現代語訳すると…
「この山中、温泉に入ると命も延びたように思われ、湧き出る湯の匂いは、寿命が延びるという菊の香も及ばないほどだ。これなら、菊を折るにも及ばないことだ。」
という意味です。
この句に出てくる「菊」は、秋を象徴する花というだけではなく、長寿や無病息災という意味もあります。
9月9日は五節句の1つの、重用の節句です。旧暦ではちょうど菊が咲く季節であることから、「菊の節句」とも呼ばれています。
平安時代の初めに中国より伝わり、日本でも菊を鑑賞しながら、菊の花びらを散らしたお酒を飲み、無病息災や長寿を願いました。
この句が詠まれた背景
この句は、「おくのほそ道」に収められています。
元禄2年(1689年)ごろ、芭蕉が46歳の頃に詠まれたとされています。
7月27日(旧暦9月10日)に、石川県加賀市の山中温泉に、同行の曾良とともに訪れ、曾良の体調が思わしくないため9日間、長逗留しました。その時に、詠まれた句です。
「山中や菊はたおらぬ湯の匂」の表現技法

「山中や」の「や」の切れ字
切れ字は「や」「かな」「けり」などが代表とされ、文を強調したり、詠嘆や感動するときに使います。
この句は「山中や」の「や」が切れ字にあたります。
俳句の切れは、文章だと句読点で句切りのつく部分にあたります。
「や」で句の切れ目を強調することで、山中温泉にゆったり浸かり、「ああ…」とその癒しをしみじみ感じていることを表しています。
また、五・七・五の五の句、つまり初句に句の切れ目があることから、「初句切れ」となります。
「湯の匂」の体言止め
体言止めは、語尾を名詞や代名詞などの体言で止める表現技法です。
体言止めを使うことで、美しさや感動を強調する、読んだ人を引き付ける効果があります。
芭蕉が、「この湯は菊の香りにも負けないほど、寿命が延びたように思われる」と、その湯の癒しや効果に感動する様子を強調しています。
「山中や菊はたおらぬ湯の匂」の鑑賞文

この句が詠まれたのは、3月末に江戸を出て始めた旅も終盤に差し掛かる7月末〜8月のはじめのことです。
長い旅の疲れが出たのか、同行の曾良の体調が思わしくないことが、芭蕉の心の中に常にあったのでしょう。
この句を目にした時、菊の花とともに、湯気のたつ温泉の情景がパッと目に浮かびます。
旅をともにする曾良のことを想い、無病息災や長寿を願う意味のある「菊」を季語に使い、曾良の回復を願いながらこの句を詠んだのでしょう。
作者「松尾芭蕉」の生涯を簡単にご紹介!

(松尾芭像 出典:Wikipedia)
松尾芭蕉は、寛永21年(1644年)伊賀国、現在の三重県伊賀市に生まれました。
本名を松尾宗房(むねふさ)といいました。13歳の時に父親を亡くし、そののち19歳の時に、藤堂藩伊賀村の侍大将藤堂良清の息、良忠の近習(君主の側に仕える役)になりました。
その良忠が俳人であったため、芭蕉も俳諧の道に入ったとされています。
ところが、良忠が25歳の若さで没したため、23歳だった芭蕉も、まもなく藤堂家を退き、江戸に向かい、江戸で修行をしました。
江戸での修行と甲斐あって、俳諧宗匠になるものの、37歳の時に深川に移り住みました。
俳諧宗匠としての安定した生活を捨てて、厳しい暮らしの中に身を投じ、文学性を追求しようとしたとされています。こののち、芭蕉は数々の旅に出て、俳句を詠みます。
そして、46歳の時に、「もしかしたらもう戻ってくることはできないかもしれない」という覚悟を決め、家も売り、おくのほそ道への旅に出ました。
おくのほそ道は、松尾芭蕉が46歳の時に門人の曾良とともに江戸を発ち、約5ヶ月間、約2400キロメートルもの芭蕉の一生の中で最も長い旅をまとめた俳諧紀行文です。
その旅の中で、多くの優れた句を作りました。旅から5年後、おくのほそ道が完成した元禄7年に、芭蕉は51歳で亡くなりました。
俳号は、はじめは宗房(そうぼう)と名乗り、次に桃青(とうせい)、そして芭蕉(ばしょう)と改めました。
芭蕉は、俳諧を優れた芸術にまで高めました。自然と対比させながら、「人間のありよう」を深く探求していきました。数多くの旅を通して名句を生み、俳諧の世界を広げた日本を代表する俳人で、古典文学の作者でもあります。
松尾芭蕉のそのほかの俳句
(「奥の細道」結びの地 出典:Wikipedia)

















