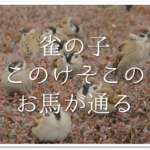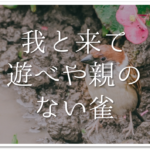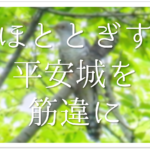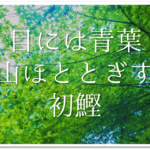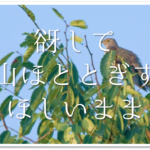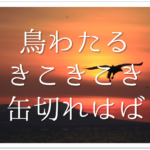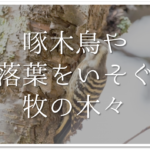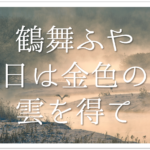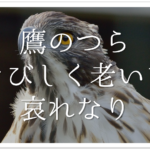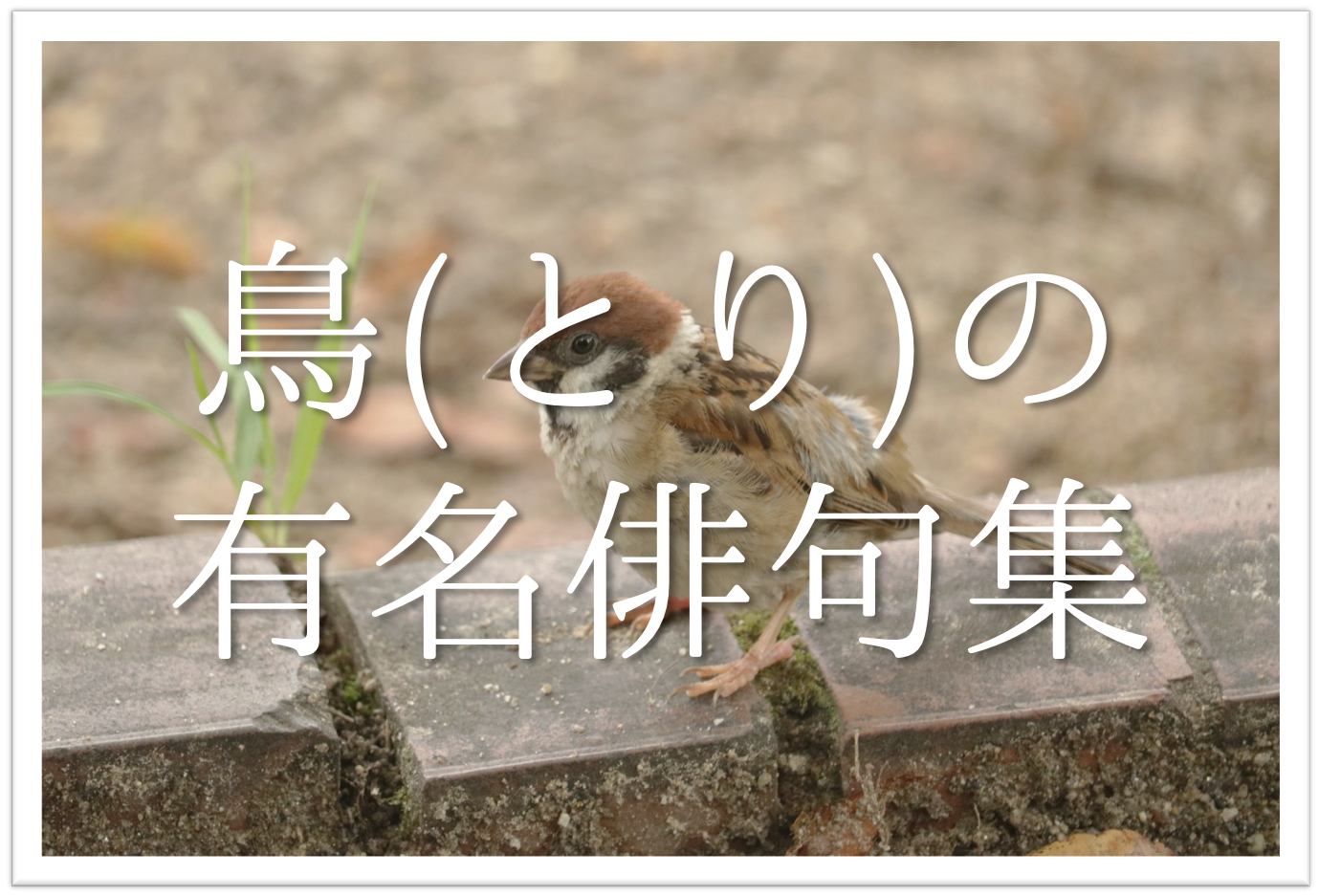
鳥の飛んでいる姿や鳴き声は、昔からさまざまな俳句に詠まれてきました。
今回は、そんな「鳥」をテーマに詠まれた有名俳句を30句紹介していきます。
雀の子
そこのけそこのけ
お馬が通る
小林 一茶 pic.twitter.com/6RMmmM0S91
— 桃花 笑子 (@nanohanasakiko) February 17, 2014

お気に入りの俳句を探してみてね!
目次
鳥をテーマにした有名俳句集【春編 7選】

【NO.1】内藤丈草
『 鶯や 茶の木畠の 朝月夜 』
季語:鶯(春)
現代語訳:鶯が鳴いている。月が残っている明け方の茶畑で。

ウグイスは早朝から鳴き出す鳥です。明け方の茶畑の風景を的確にとらえた歌になっています。
【NO.2】松尾芭蕉
『 雲雀(ひばり)鳴く 中の拍子や 雉子(きじ)の声 』
季語:雲雀(春)、雉子(春)
現代語訳:雲雀が鳴く中で、拍子を打つように雉子の声もする。

ヒバリの鳴き声の合間に拍子を打つようにキジの声がするという春の風景を詠んだ一句です。お互いに示し合わせたように鳴きあっていたのでしょう。
【NO.3】小林一茶
『 雀の子 そこのけそこのけ お馬が通る 』
季語::雀の子(春)
現代語訳:雀の子よ、そこを退かないと馬が通ってしまうよ。

有名な一茶の句です。お馬を馬ととらえるか、子供たちの竹馬のような遊び道具にとらえるかで、どんな道だったかいろいろと想像できます。
【NO.4】与謝蕪村
『 大和路の 宮もわら屋も つばめかな 』
季語:つばめ(春)
現代語訳:春の大和路では、お宮にも藁葺き屋根にもツバメが巣を作っていることだなぁ。

【NO.5】上島鬼貫
『 雨だれや 暁がたに 帰る雁(かり) 』
季語:帰る雁(春)
現代語訳:軒先に雨水が落ちてくるなぁ。そんな明け方に雁が帰っていく。

【NO.6】小林一茶
『 我と来て遊べや 親のない雀 』
季語:親のない雀/雀の子(春)
現代語訳:私と来て遊びましょう、親のない雀の子よ。

【NO.7】正岡子規
『 鶯や 朝寝を起す 人もなし 』
季語:鶯(春)
現代語訳:鶯が鳴いているなぁ。朝寝を起こす人もいない。

鳥をテーマにした有名俳句集【夏編 8選】

【NO.1】松尾芭蕉
『 京にても 京なつかしや ほととぎす 』
季語:ほととぎす(夏)
現代語訳:見慣れた京の都だが、ホトトギスの声を聞くと古の都の人達も聞いていたのだなぁと懐かしさを感じることである。

【NO.2】水原秋櫻子
『 雪加(せっか)鳴き 端居(はしい)にとほき 波きこゆ 』
季語:雪加(夏)
現代語訳:雪如が鳴いている。縁側の端で涼んでいると、波の音が遠くから聞こえてくる。

【NO.3】正岡子規
『 誰やらが 口まねすれば 目白鳴く 』
季語:目白(夏)
現代語訳:誰かが口真似で鳴き声を真似ると、目白も鳴きだした。

【NO.4】堀麦水
『 飛び習ふ 青田の上や 燕の子 』
季語:燕の子(夏)
現代語訳:青い田んぼの上を、燕の子たちが飛ぶ練習をしていることだ。

【NO.5】大須賀乙字
『 山雲を 谷によぶなり 閑古鳥 』
季語:閑古鳥(夏)
現代語訳:閑古鳥(カッコウ)が鳴くと山にかかっていた雲が谷まで降りてくるようだ。

【NO.6】与謝蕪村
『 ほととぎす 平安城を 筋違に 』
季語:ほととぎす(夏)
現代語訳:ホトトギスが平安城を筋違いに飛んで行った。

【NO.7】山口素堂
『 目には青葉 山ほととぎす 初鰹 』
季語:青葉(夏)/ほととぎす(夏)/初鰹(夏)
現代語訳:目には青葉が映り、ホトトギスの鳴き声が聞こえ、初鰹の美味しい季節だ。

【NO.8】杉田久女
『 谺(こだま)して 山ほととぎす ほしいまま 』
季語:ほととぎす(夏)
現代語訳:山々にこだまを響かせながら、ホトトギスが思うままに鳴いている。

鳥をテーマにした有名俳句集【秋編 8選】

【NO.1】松尾芭蕉
『 稲雀(いなすずめ) 茶の木畠や 逃げ処 』
季語:稲雀(秋)
意味:稲が実った田んぼで雀の群れがその稲穂をねらっている。人が追うと一斉に群れをなして逃げて茶畑に隠れる。

稲雀は稲が実る頃に啄みにやってくる雀のことで、季語として使用したのは芭蕉のこの句が初めてと言われています。
【NO.2】小林一茶
『 木啄の けいこにたたく 柱哉 』
季語:木啄(キツツキ/秋)
意味:キツツキが稽古に叩いているような柱であることだ。

【NO.3】桃水
『 椋鳥(むくどり)や 枝に来るほど 木の葉散る 』
季語:椋鳥(秋)
意味:椋鳥よ、お前たちが渡ってきて枝にとまるほど木の葉が散っていく。

【NO.4】川端茅舎
『 身をほそめ とぶ帰燕(きえん)あり 月の空 』
季語:帰燕(秋)
意味:身を細めて飛んで帰っていく燕がいる。あの月の空に。

【NO.5】宝井其角
『 雁の腹 見すかす空や 船の上 』
季語:雁(秋)
意味:船の上からみあげると、雁のお腹が見えるような空であることだ。

【NO.6】石田波郷
『 鳥わたる こきこきこきと 缶切れば 』
季語:鳥わたる(秋)
現代語訳:こきこきこきと缶詰を切りながら空を見上げると、渡り鳥が飛んでいく。

【NO.7】加藤楸邨
『 燕はや 帰りて山河 音もなし 』
季語:燕(はや)帰り/燕帰る(秋)
現代語訳:燕は早くも帰ってしまい、山河には鳴き声の音もなくなってしまった。

【NO.8】水原秋桜子
『 啄木鳥や 落葉をいそぐ 牧の木々 』
季語:啄木鳥(秋)
現代語訳:キツツキがいる。つつかれることで葉が急いで落ちているように感じる牧場の木々だ。

鳥をテーマにした有名俳句集【冬編 7選】

【NO.1】松尾芭蕉
『 いらご崎 似るものもなし 鷹の声 』
季語:鷹(冬)
意味:伊良湖崎で聞く鷹の声は、他に比べるもののないほどに素晴らしいものである。

【NO.2】杉田久女
『 ふり仰ぐ 空の青さや 鶴渡る 』
季語:鶴(冬)
意味:ふり仰ぐと空がとても青いことだ。白い鶴が飛んできている。

【NO.3】軽部烏頭子
『 梟(ふくろう)の ねむたき貌(かお)の 吹かれける 』
季語:梟(冬)
意味:フクロウが眠たそうな顔で風に吹かれていることだ。

目を閉じそうになっているフクロウを見かけたのでしょうか、眠そうな顔という表現が面白いです。
【NO.4】正岡子規
『 鴨鳴くや 上野は闇に 横たはる 』
季語:鴨(冬)
意味:鴨が鳴いている。そんな鴨が鳴く上野は夜の闇に横たわっている。

鴨が鳴いている上野の夜ですが、人間たちは静かに眠っている対比が効いています。
【NO.5】中村草田男
『 白鳥と いふ一巨花を 水に置く 』
季語:白鳥(冬)
意味:白鳥という名前の大きな花が水の上に置かれている。

優雅に水面に浮かぶ白鳥を、一つの大きな花に例えた一句です。浮かぶ鳥を花に例える感性が光っています。
【NO.6】杉田久女
『 鶴舞ふや 日は金色の 雲を得て 』
季語:鶴(冬)
現代語訳:鶴が舞っているなぁ。太陽は金色に染まった雲をまとっている。

鶴に金色の雲というおめでたい要素を集めた一句です。この句は作者が鶴の群生地に訪れたときに詠まれたと言われています。
【NO.7】村上鬼城
『 鷹のつら きびしく老いて 哀れなり 』
季語:鷹(冬)
現代語訳:鷹の顔つきが厳しく老いているように見えて哀れに思った。

鷹は精悍な顔つきをしている鳥です。作者はその顔つきを「老いている」と表現することで、鷹と誰かを重ねているように感じます。
以上、鳥をテーマにした有名俳句集でした!


今回は、四季の鳥の季語を使った有名俳句を30句紹介しました。
渡り鳥や雛や巣など、同じ鳥でも季節によって季語が違うのが、鳥の俳句の面白いところです。
この機会にぜひあなたも一句詠んでみてはいかがでしょうか?