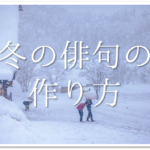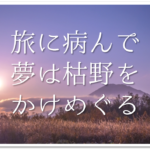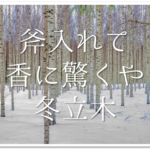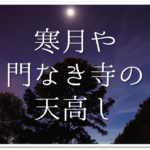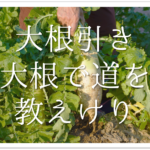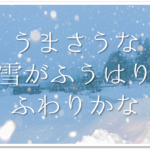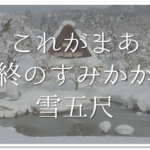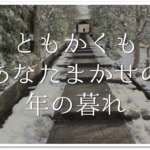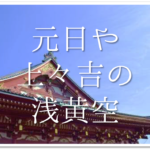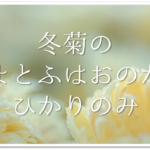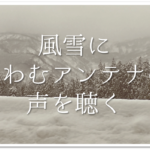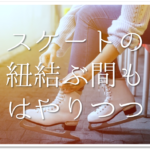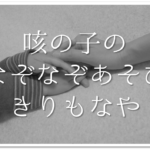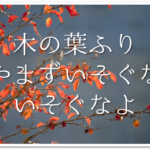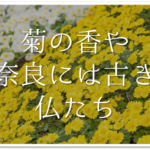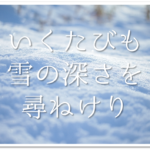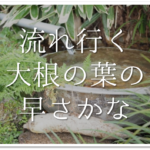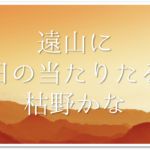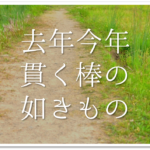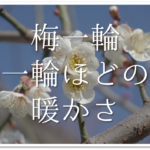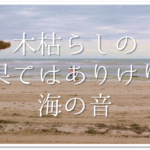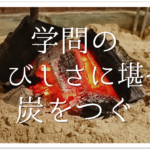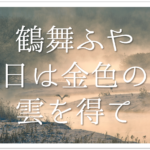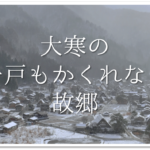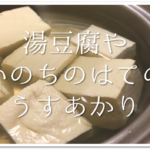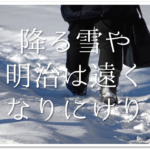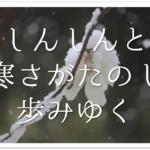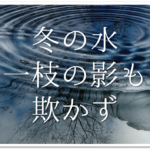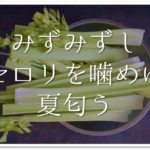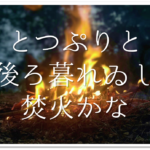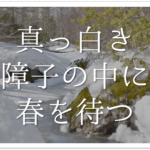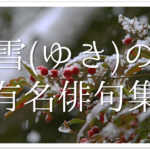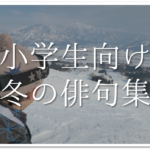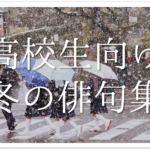冬は寒さや雪などを詠むほかに、温かい食べ物や冬が旬の食べ物などが季語として詠まれます。
また、冬の季語には年の暮れや正月を含むため、年の瀬の寂しさと元旦の華やかさなど様々な句が詠まれているのが特徴です。
今回は「冬の季語」を含む有名オススメ俳句を40句紹介していきます。
降る雪や明治は遠くなりにけり(中村草田男)#俳句 pic.twitter.com/mSKUD4YVyI
— koma (@niyan1go) December 26, 2016

俳句には、季節を表す「季語(きご)」を入れて詠むという決まりがあります。
冬の季語は、旧暦で10月から12月、現在の暦では11月から2月の初め頃のものを指します。
冬の季語には、次のようなものが挙げられます。
【冬の季語】
冬・凍る・寒し・冷たし・雪・氷・霰・オリオン・霜・寒月・北風・枯野・霜柱・山眠る・熱燗・おでん・懐炉・風邪・コート・炭・雑炊・ストーブ・蕎麦湯・冬籠・湯豆腐・鶴・河豚・ハヤブサ・鷹・ウサギ・鳰・鴨・牡蠣・大根・冬木立・南天の実・セロリ・枯木・小春・立冬・時雨・初氷・大根引・神の旅・七五三・落葉・大寒・柚子湯・冬至・春近し・寒梅・雪見・節分・水仙・年の暮れ・元日・初日・七種

七五三や節分も冬の季語になることに注意しよう。
冬のおすすめ有名俳句【前編20句】

【NO.1】松尾芭蕉
『 いざさらば 雪見にころぶ 所まで 』
季語:雪見(冬)
意味:さあ降り出した雪を見に行きましょう。うっかり転んでしまっても一興、転んでしまう場所まで。

【NO.2】松尾芭蕉
『 あら何ともなや 昨日は過ぎて 河豚汁(ふくとじる) 』
季語:河豚汁(冬)
意味:ああ何ともなかったようだ。河豚汁を食べた昨日は朝になって過ぎていった。

【NO.3】松尾芭蕉
『 人々を しぐれよやどは 寒くとも 』
季語:しぐれ(冬)
意味:句会の会場が寒くなろうとも、皆とともに時雨を見たいものだなぁ。

【NO.4】松尾芭蕉
『 いざ子ども はしりありかん 玉霰 』
季語:玉霰(冬)
意味:さあ子供たちよ。走り回ろう、玉のような霰が降ってきたぞ。

霰が降り出したことで喜んで外に出て駆け回る子供たちを詠んだ句です。雪ではなく霰であることが子供たちをより一層喜ばせているように感じます。
【NO.5】松尾芭蕉
『 旅に病んで 夢は枯野を かけめぐる 』
季語:枯野(冬)
意味:旅の途中で病に倒れたが、夢の中の私はなお枯れ野をかけめぐっている。

【NO.6】与謝蕪村
『 斧入れて 香におどろくや 冬木立 』
季語:冬木立(冬)
意味:枯れているように見える木に斧を入れると、とたんに立ちのぼる木の香りに驚かされる冬の木立だ。

【NO.7】与謝蕪村
『 寒月や 門なき寺の 天高し 』
季語:寒月(冬)
意味:冬の寒い夜空に月がのぼっているなぁ。門のない小さいお寺はさえぎるものがなく天が高く見える。

【NO.8】与謝蕪村
『 西吹けば 東にたまる 落葉かな 』
季語:落葉(冬)
意味:西に風が吹けば、東の方にたまる落ち葉であることよ。

【NO.9】与謝蕪村
『 暮まだき 星の輝く 枯野かな 』
季語:枯野(冬)
意味:日没前のほんのひと時だ。星が輝いている枯れ野が広がっているなぁ。

【NO.10】与謝蕪村
『 水仙や 寒き都の ここかしこ 』
季語:水仙(冬)
意味:水仙が咲いているなぁ。冬になって寒い街のここかしこに咲いていて心を和ませる。


【NO.11】小林一茶
『 大根引き 大根で道を 教えけり 』
季語:大根引き(冬)
意味:大根を引き抜いて収穫している農家の人に道を尋ねたところ、持っていた大根で道を示されたことだ。

【NO.12】小林一茶
『 うまさうな 雪がふうはり ふわりかな 』
季語:雪(冬)
意味:おいしそうな雪が空からふわりふわりと落ちてくるなぁ。

【NO.13】小林一茶
『 これがまあ 終(つひ)の栖(すみか)か 雪五尺 』
季語:雪(冬)
意味:このような家がまあ、自分の終の住処であることか。五尺もある雪に埋もれている。

【NO.14】小林一茶
『 ともかくも あなたまかせの 年の暮れ 』
季語:年の暮れ(冬/暮)
意味:今年も1年いろいろとあったけれども、すべては仏様におまかせして年の暮れを迎えよう。

【NO.15】小林一茶
『 元日や 上々吉の 浅黄空 』
季語:元日(冬/新年)
意味:元日を迎えたなぁ。この上なく縁起の良い浅黄色の空だ。

【NO.16】水原秋桜子
『 冬菊の まとふはおのが ひかりのみ 』
季語:冬菊(冬)
意味:冬の菊が纏うのは自分の光だけだ。

【NO.17】山口誓子
『 風雪に たわむアンテナの 声を聴く 』
季語:風雪(冬)
意味:風雪にたわんでいるアンテナの音を聞いている。

【NO.18】山口誓子
『 スケートの 紐結ぶ間も はやりつつ 』
季語:スケート(冬)
意味:スケート靴の紐を結ぶ間も早く滑りたいと気持ちが逸る。

【NO.19】中村汀女
『 咳の子の なぞなぞあそび きりもなや 』
季語:咳(冬)
意味:咳をしている子供となぞなぞ遊びをしているが、キリがないなぁ。

【NO.20】加藤楸邨
『 木の葉ふりやまず いそぐな いそぐなよ 』
季語:木の葉ふり/木の葉降る(冬)
意味:木の葉がハラハラと降り止まない。いそぐな、いそぐなよ。

冬のおすすめ有名俳句【後編20句】

【NO.1】正岡子規
『 日のあたる 石にさはれば つめたさよ 』
季語:つめたさ(冬)
意味:日が当たっている石はあたたかいのかと触ってみればなんとつめたいことよ。

【NO.2】正岡子規
『 菊の香や 月夜ながらに 冬に入る 』
季語:冬に入る(冬)
意味:菊の花の香りがするなぁ。月も出ているが、季節はもう立冬で冬を迎えたのだ。

【NO.3】正岡子規
『 団栗の 共に掃かるる 落葉哉 』
季語:落葉(冬)
意味:ドングリが一緒になって掃かれている落ち葉であるなぁ。

【NO.4】正岡子規
『 いくたびも 雪の深さを 尋ねけり 』
季語:雪(冬)
意味:何度も何度も雪がどれだけ深く積もったのかを尋ねているなぁ。

【NO.5】正岡子規
『 鶏頭(けいとう)の 黒きにそそぐ 時雨かな 』
季語:時雨(冬)
意味:鶏頭が黒く枯れているところに注ぐように降る時雨であることだ。

【NO.6】高浜虚子
『 流れ行く 大根の葉の 早さかな 』
季語:大根(冬)
意味:目の前の川を流れていく大根の葉のなんと早いことか。

【NO.7】高浜虚子
『 遠山に 日の当たりたる 枯野かな 』
季語:枯野(冬)
意味:遠くの山に夕日が当たっているが、目の前には日が暮れている枯れ野が広がっていることだ。

【NO.8】高浜虚子
『 去年今年 貫く棒の 如きもの 』
季語:去年今年(冬/新年)
意味:去年と今年を貫いている棒のようなものが時間という概念であり、私の信念なのだ。

【NO.9】服部嵐雪
『 梅一輪 一輪ほどの 暖かさ 』
季語:梅/寒梅(冬)
意味:冬の寒い日に梅が一輪咲いているのを見ると、その一輪ぶんの暖かさを感じることだ。

【NO.10】池西言水
『 木枯らしの 果てはありけり 海の音 』
季語:木枯らし(冬)
意味:野山を吹く木枯らしにも果てはあったのだなぁ。ごうごうと音を立てる海の音がする。

平地を吹いている木枯らしが海へと到達し、海の音にかき消されていく様子を詠んでいます。この句は評判を呼び、作者は「木枯らしの言水」として名声を得ました。

【NO.11】山口誓子
『 学問の さびしさに堪へ 炭をつぐ 』
季語:炭(冬)
意味:一人でやらなければならない学問の寂しさに堪えながら、火鉢に炭をついでいる。

【NO.12】杉田久女
『 鶴舞ふや 日は金色の 雲を得て 』
季語:鶴(冬)
意味:鶴が舞っているなぁ。太陽が照らす光で金色に輝く雲を得て、美しい風景だ。

【NO.13】飯田龍太
『 大寒の 一戸もかくれなき 故郷 』
季語:大寒(冬)
意味:大寒という寒い日に、草木が枯れて家の1軒も隠すことなくよく見える我が故郷よ。

木々や草が枯れて、遮るものがなく故郷が見渡せる風景を詠んでいます。作者は山梨県の笛吹市で生まれているため、その周辺の当時の光景を詠んだのでしょう。
【NO.14】久保田万太郎
『 湯豆腐や いのちのはての うすあかり 』
季語:湯豆腐(冬)
意味:湯豆腐から立ちのぼる湯気が見えるなぁ。その湯気の色は、きっと人生の終わりのような薄明かりの色なのだろう。

湯豆腐から立ちのぼる薄く白い煙に、自分の人生の終わりを感じ取っている名句です。作者はこの句を詠んだときに内縁の妻や子を亡くしていて、命の儚さをよく知っていました。
【NO.15】中村草田男
『 降る雪や 明治は遠く なりにけり 』
季語:雪(冬)
意味:雪が降ってきたなぁ。昭和の今から考えると、明治の時代は遠くなったものだ。

【NO.16】星野立子
『 しんしんと 寒さが楽し 歩みゆく 』
季語:寒さ(冬)
意味:しんしんとした寒さが楽しいなぁ、道を歩いていく。

【NO.17】中村草田男
『 冬の水 一枝の影も 欺かず 』
季語:冬の水(冬)
意味:冬の水面は、木々の枝の一つもそのままに映し出している。

【NO.18】日野草城
『 みずみずし セロリを噛めば 夏匂う 』
季語:セロリ(冬)
意味:瑞々しいセロリを噛めば、冬でも夏の匂いがするようだ。

セロリの瑞々しさをまるで夏のようだと例えた一句です。セロリは冬の季語ですが、噛めば夏を感じられるという季節の逆転が面白い句になっています。
【NO.19】松本たかし
『 とつぷりと 後ろ暮れゐし 焚火かな 』
季語:焚火(冬)
意味:とっぷりと背後が暮れていく焚き火であることだ。

焚き火の周りだけが明るくて気がつけば周りが暗くなっている、という経験をしたことがある人も多いでしょう。炎を見ていたらいつの間にか暗くなるアウトドアの醍醐味を詠んだ句です。
【NO.20】松本たかし
『 真っ白き 障子の中に 春を待つ 』
季語:春を待つ(冬)
意味:真っ白い障子の中で春を待っている。

以上、「冬の季語」を含むオススメ有名俳句40選でした!


食べ物から風物詩まで…多くの冬の季語が出てきましたね。また、他の季節の季語も詠むことで冬を強調するものも多かったように思います。
冬は寒いだけではなく色々な行事もあるので、思いついた時にぜひ一句詠んでみてはいかがでしょうか?