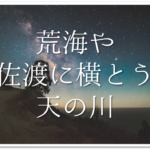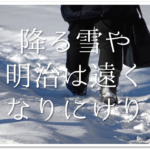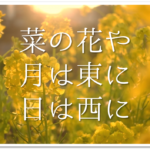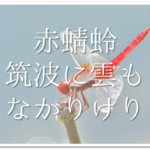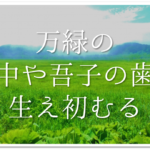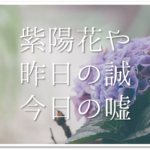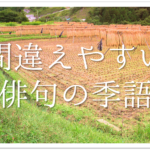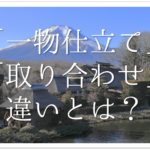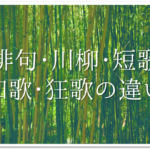突然ですが、次の俳句のうちどちらの方が好きですか?
【1】殻の内 ごうごうとして かたつむり (作:星野一郎)
【2】まるまるが 多い文章 かたつむり (作:三宅やよい)
2句とも夏の季語である「かたつむり」が使われていますが、句の構成が異なります。
俳句の構成には大きく分けて2つあり、1句目は「一物仕立て」、2句目は「取り合わせ」という構成でできています。
一物仕立てはひとつの季語についてのみ詠みます。取り合わせの句では、季語に加えて別の要素についても詠みます。
今回は2句目の「取り合わせ」について意味や効果などを簡単にわかりやすく解説していきます。
紅葉に桜の稀有な取り合わせ発見した。😁
時雨ふるもみじに混じる春のゆめ#utautau #haiku pic.twitter.com/U6mffvGap0
— utautau_mono (@utautau_mono) November 28, 2019

俳句の取り合わせとは?意味や効果

取り合わせとは、「適度に意味の離れた二つの言葉を俳句の中に詠み込むこと」を言います。
これではわかるにくいので、次の句を例に見てみましょう。
【作者】水原秋櫻子
『 花冷えや 剥落しるき 襖の絵 』
季語:花冷え(春)
意味:桜の咲く時期なのに冷え込むなあ。襖の絵はかなりの部分が剝げ落ちている
季語の「花冷え」と襖の絵が剥げてしまっていることには、本来何のつながりもありません。
しかしこのように一句の中に詠まれると、「花冷え」の空気の冷たさや寒さと襖の絵が剥げてしまっている光景の寂しさや寒々しさが重なり合うように感じませんか。
このように意味の離れた言葉(本来関係のない言葉)を組み合わせることで言葉どうしが響き合い、相乗効果で句のイメージが豊かになることが取り合わせの効果です。
✏俳句(Haiku)
季語は秋「杜鵑草(ほととぎす)」しづかなる花の盛りを杜鵑草
髙田正子杜鵑草(ほととぎす)。花の内側に紅紫色の斑点があり、鳥のホトトギスの羽根の模様に似ているなあ。しかし、鳥のようには鳴かず、静かに咲いている。小さな鐘のように可愛い。「鳥」と「草」の文字の取り合わせ。 pic.twitter.com/hULwY15nt1
— Mari/マリ (@MariPsychiatris) October 17, 2020

次に、俳句の取り合わせの使い方やコツについて解説していきます。
俳句の取り合わせの作り方&コツ

テレビ番組「プレバト!!」で活躍なさっている夏井いつき先生は、取り合わせの作り方について次のように仰っています。
① 十二音で日記を書く。この時季語は入れない。心情を表す言葉も入れない。
② 十二音で書いた部分の心情を分析し、心情に合う季語をつける。
②の心情に合う季語というのが、やや難しいかもしれません。
例えば、先ほどの「花冷え」なら寂しさなどのやや暗めの心情、同じ春の季語でも「春めく」ならうきうきするような明るめの心情を表せます。
心情ごとに季語を分類しておくといざ俳句を作るときにアイディアの引き出しが増えて良いかもしれません。
また、二つの言葉を組み合わせる時には意味や関係性が近すぎても遠すぎても面白い句にはなりません。

意外性のない組み合わせや、共感しづらい突拍子の無い組み合わせにならないよう心がける必要があります。
取り合わせを使った有名俳句【10選】

【NO.1】松尾芭蕉
『 荒海や 佐渡によこたふ 天(あまの)河(がわ) 』
季語:天河(秋)
意味:日本海は暗く荒れているなあ。佐渡島の空には天の川が横たわっている。

【NO.2】高浜虚子
『 亀鳴くや 皆愚かなる 村の者 』
季語:亀鳴く(春)
意味:亀が鳴いているなあ。村の者たちは皆愚かだ。

【NO.3】村上鬼城
『 露涼し 形あるもの 皆生ける 』
季語:露涼し(夏)
意味:草木にとどまっている露が何とも涼しげだ。形あるものは皆生きている。

【NO.4】中村草田男
『 降る雪や 明治は遠く なりにけり 』
季語:雪(冬)
意味:しんしんと降り積もる雪よ。明治という時代は遠くなってしまったなあ。

【NO.5】長谷川櫂
『 白団扇 夜の奥より 怒涛かな 』
季語:白団扇(夏)
意味:何も描かれていない真っ白な団扇がある。夜の闇の向こうから荒れ狂う波が押し寄せているなあ。

【NO.6】与謝蕪村
『 菜の花や 月は東に 日は西に 』
季語:菜の花(春)
意味:菜の花が咲いているなぁ。月が東から昇り、日は西に沈んでいく。

この句は「菜の花が咲いている様子」と、「月の出、日の入り」を詠んでいるため取り合わせの俳句になります。一面の菜の花畑に月と太陽が同時に存在しているダイナミックな様子を詠んだ句です。
【NO.7】正岡子規
『 赤蜻蛉 筑波に雲も なかりけり 』
季語:赤蜻蛉(秋)
意味:赤蜻蛉が飛んでいるなぁ。筑波山には雲もかかっていない。

この句では、「飛んでいる赤蜻蛉」と「筑波山」を詠んでいる取り合わせの俳句です。実際に赤蜻蛉の近くに筑波山があったのか、遠く見える筑波山に思いを馳せているのか、解釈が分かれます。
【NO.8】中村草田男
『 万緑の 中や吾子(あこ)の歯 生え初むる 』
季語:万緑(夏)
意味:野山は緑に覆い尽くされる中で、初めて我が子の歯が生えてきた。

この句では「万緑」と「我が子の歯」を詠んでいます。歯が生え初める様子を「万緑」と例えているような言い回しが面白い一句です。これから乳歯が生え揃うことを楽しみにしている親の気持ちが表れています。
【NO.9】正岡子規
『 紫陽花や 昨日の誠 今日の噓 』
季語:紫陽花(夏)
意味:紫陽花が咲いているなぁ。昨日の花の色が誠の色だとしたら、今日の色は嘘なのだろうか。

この句は紫陽花の花のことを一貫して詠んでいるように思えますが、紫陽花の花自体を詠むのではなく、色の話をしているため取り合わせとする説が有力です。紫陽花の花は土壌によって色が変わるため、昨日見た色と今日見た色が違っていて、どちらが本当の紫陽花の花なのだろうと考えています。
【NO.10】水原秋桜子
『 旅の夜の 茶のたのしさや 桜餅 』
季語:桜餅(春)
意味:旅の夜に飲むお茶は楽しいなぁ。桜餅も食べられる。

この句は旅の夜に旅館などでお茶を楽しんでいる様子と、桜餅という茶菓子を詠んでいます。お茶菓子としての桜餅として一貫しているように見えますが、「旅の夜」とあるため、ここでは「旅の最中」と「桜餅」の話をしているため取り合わせの俳句になります。
以上、俳句の取り合わせについてでした!