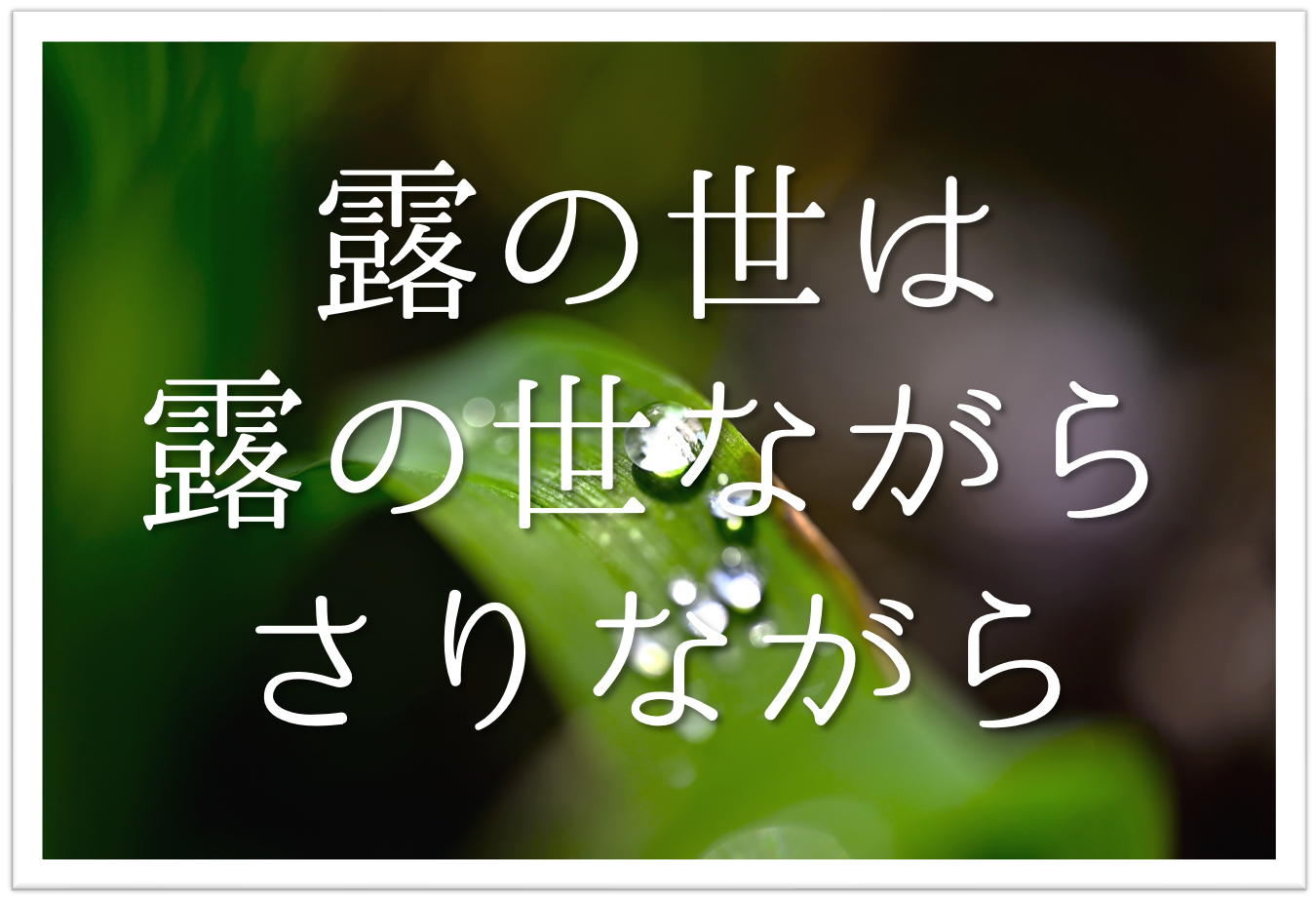
先人達が残した作品には、作者のどこにもぶつけようのない悲しみが詠まれた句も数多く見受けられます。
今回は、子を失った小林一茶の悲しみが詠まれている句「露の世は露の世ながらさりながら」をご紹介します。
露の世は
露の世ながら
さりながら 小林一茶
#秋の俳句#小林一茶 pic.twitter.com/Na6a6p2WSu
— 菜花 咲子(ナバナサキコ) (@nanohanasakiko2) September 3, 2016
本記事では、「露の世は露の世ながらさりながら」の季語や意味・表現技法・作者などについて徹底解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
目次
「露の世は露の世ながらさりながら」の俳句の季語・意味・詠まれた背景

露の世は露の世ながらさりながら
(読み方: つゆのよは つゆのよながら さりながら)
この俳句の作者は「小林一茶(こばやし いっさ)」です。
小林一茶は「江戸時代の三大俳人」の1人と言われている人物です。江戸三代俳人とは小林一茶、松雄芭蕉、与謝野蕪村の3人を指します。
一茶の作品が芭蕉や蕪村と大きく違うところは、俳句になじみのない江戸時代の庶民でも理解できる簡潔な表現を使用していることです。この表現方法は「一茶句調」と呼ばれており、俳句が庶民の間に普及するきっかけになったと言われています。
この句は「露の世」をテーマにしていますが、人の命を露に例えて詠まれている作品です。
季語
この句では「露(つゆ)」が季語になっているため、季節は「秋」になります。
露は一年を通して発生する気象現象ですが、もっとも頻度の多い時期が「秋」なので、「秋」を表現する季語に属します。
露に関連する季語としては、初露・白露・夜露・上露・下露・露の玉・露の秋などがあり、いずれも秋を表現する言葉です。
意味

こちらの句を現代語訳すると…
「露の世界は露の世だからはかないものとはわかっているが、あまりにも不条理である。」
という意味です。
この句は、天然痘に罹って亡くなった娘(さと)の命を露に例えて、命とは露のようにはなないものであることを詠んでいます。
この句が詠まれた時代背景
この句は一茶の句集「おらが春」に収録されていますが、年月日については特定することはできません。
一方で、この句は愛娘の死をテーマにしていることから、おおよそいつ頃に詠まれた作品であるかはわかります。
一茶の娘(さと)は、文永2年(1819年)6月21日に天然痘に罹って亡くなっており、これ以降に詠まれた作品です。
娘の死からくる悲しみを乗り越えることができない、現実を受け入れることができない、未練がましい、そんな弱い自分をあるがままに俳句にしています。娘を失ったいきどころのない一茶の悲しみがひしひしと伝わってきます。
「露の世は露の世ながらさりながら」の表現技法

反復法
この句では、上句「露の世」と中句「露の世」に、同じ言葉が2回繰り返して使われています。
このように、同じ言葉や類似する単語を2回繰り返して使用する技法を「反復法」と言います。
俳句でなくとも、同じ言葉がリフレインされている文章を読むと、その内容が記憶に残りやすくなります。つまり、反復法とは、その言葉の印象を強めたり、文章全体にリズムを出したい時に使われる技法です。
また、同様に中句「露の世ながら」と下句「さりながら」では、「ながら」の部分に反復法が使用されています。句の締めくくりに使われる反復法には、文章のリズムをそろえる働きと、作者が自分の思いを読者に伝える役割があります。
「露の世は露の世ながらさりながら」は、先人達が残した多くの作品のなかでも、反復法が効果的に使われている俳句と言えるでしょう。
「露の世は露の世ながらさりながら」の鑑賞文

この句を鑑賞するポイントは、どのような目的で「露」が用いられているかということです。
前述しましたように、この句は文永2年(1819年)6月に天然痘に罹って亡くなった長女(さと)の死をテーマにしている作品です。
つまり、人間の命を露に例えて、人の命とはこうも儚いものであったのかと詠んでいます。
「親しい者を亡くすことはつらいとは知っていたが、娘を亡くすまではこんなにも我が子との永遠の別れが悲しいものであるとはわからなかった…。かわいい娘を亡くして、家族との別れがいかに悲しくつらいものであるかを知ることができた。」
一茶は、儚い露に娘の命を例えて、自分の悲しみを表現したのでしょう。「露の世」というフレーズを反復させることで、一茶の悲しみと、やるせない思いが読者にしっかりと伝わってきます。
作者「小林一茶」の生涯を簡単にご紹介!

(小林一茶の肖像 出典:Wikipedia)
小林一茶は、1763年(宝暦13年)に長野県信濃町にある農家に生まれました。
一茶は俳人としては成功しますが、その人生は不運続きで家庭運に薄かったといわれています。
一茶は、経済的に恵まれて幼少期を過ごしますが、家庭運には恵まれておらず、幼い頃に大切な母と祖母を失ってしまいました。そして亡き母のあとに来た義母と馬が合わなかったため、15歳で実家を離れて江戸に奉公に出されてしまいます。
その奉公先で出会った主君「二六庵」が俳句の名人であったことから、一茶もその影響を受けて俳句の世界に足を踏み入れます。江戸時代の俳人は旅に出て句作する習わしがあったため、一茶も同じように27歳から諸国を旅して数々の作品を詠みました。
その俳句修行中に主君であり、俳句の師匠である二六庵と父を亡くすといった、つらい別れもありました。しかし、これらの悲しみを乗り越えて一茶は修行に励みます。
そのような修行の成果があり、一茶は俳句の難しい表現を取っ払って、わかりやすい言葉で句作する「一茶調」を築きました。また、松尾芭蕉とも信仰が深く、芭蕉の句風にも大きな影響をもたらしたと言われています。
俳人としては早くからその才能を発揮した一茶ですが、結婚に関しては遅咲きでした。51歳で結婚して、子宝にも恵まれた一茶にも、人並みの幸せが訪れるのではと思われましたが、そう長くは続きませんでした。当時たくさんの死亡者を出した「天然痘」に妻と子どもたちが掛かり、愛する家族を亡くしてしまったのです。
3度目でようやく手に入れた妻と子との生活も、結婚した翌年に発生した柏原の大火によって、自宅を失ってしまいました。
それでも、一茶は残された自宅の敷地の一角で、俳句の師匠をしながら余生を過ごし、65歳でこの世を去りました。
死後、一茶の功績をたたえて門人たちの力により、柏原に句碑が建てられています。また、没後「一茶発句集」なども刊行されて、今なおその作品は後世に語り継がれています。
小林一茶のそのほかの俳句
(一茶家の土蔵 出典:Wikipedia)
















