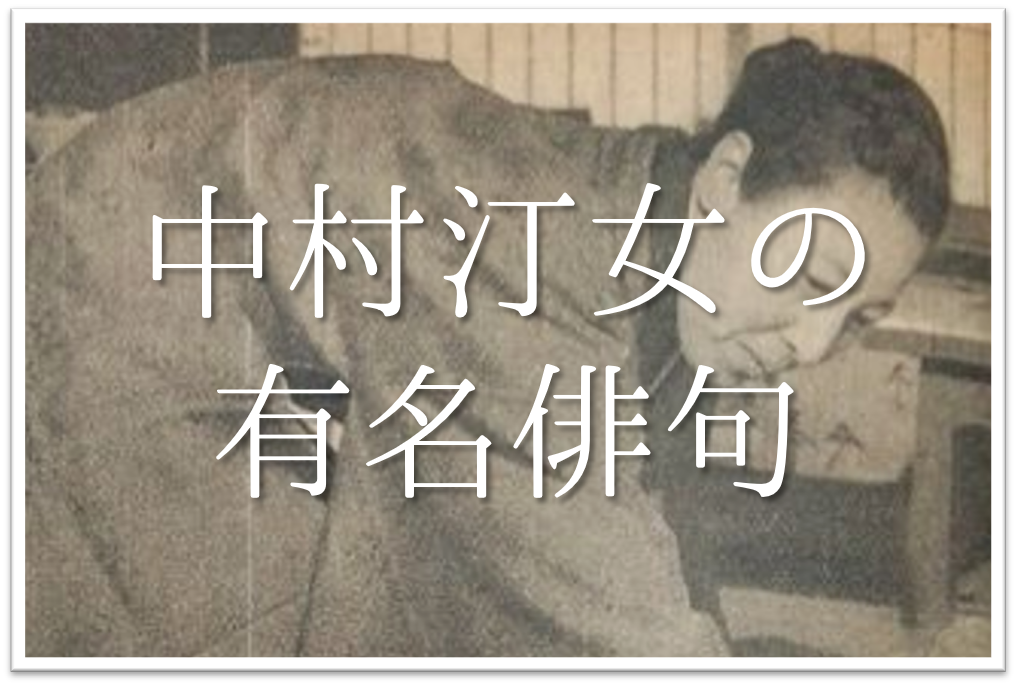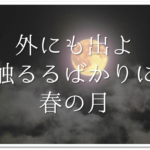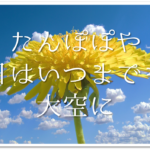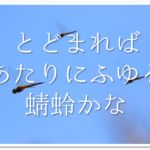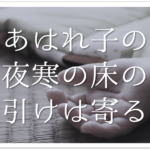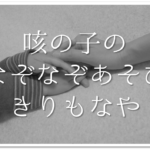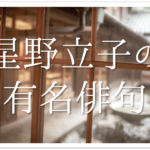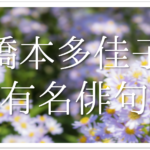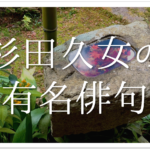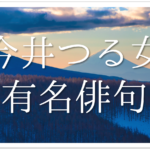五・七・五の十七音に四季を織り込み、詠み手の心情や情景を詠みこむ俳句の世界。
文学的な知識がなければ楽しめないと、敬遠する方も多いかもしれませんが決してそうではありません。
家庭俳句の開拓者として知られる中村汀女(なかむらていじょ)は、日常生活を題材にしながら、豊かな感性と表現力で芸術性を高めた句を多く残しています。
今回は、中村汀女が詠んだ名句を季節(春夏秋冬)別に36句紹介していきます。
![]()
俳句仙人
まずは、中村汀女の生涯や人物像を簡単に紹介していきます。
中村汀女の人物像や作風
![]()
(中村汀女 出典:Wikipedia)
中村汀女(1900~1988年)は、昭和期に活躍した女流俳人です。
高浜虚子に師事し、「星野立子」「橋本多佳子」「三橋鷹女」とともに「四T」と称されました。
汀女は18歳の頃に詠んだ句【吾に返り見直す隅に寒菊紅し】が絶賛されたことで、本格的に俳句を学び始めました。
結婚・出産により句作を一時中断しますが、32歳の頃に再開します。生活に密着した叙情的な作品は多くの共感を呼び、当時の家庭婦人が俳句に親しむきっかけとなりました。
しかし、俳句の世界ではいまだ男性優位が続いており、汀女の詠む俳句はときに「台所俳句」だと蔑まされることもありました。そんな批判に「それでよし」と毅然とした態度で受け入れ、主婦目線でありふれた生活を詠む姿勢を崩そうとはしませんでした。
自身の随筆『汀女自画像』の中でも「私たち普通の女性の職場ともいえるのは家庭であるし、仕事の中心は台所である。そこからの取材がなぜいけないのか」と訴えかけ、家庭婦人の生活を肯定します。
汀女は穏やかな良妻賢母の姿だけでなく、周囲の目に臆することのない気丈さを併せ持つ女性だったのです。
![]()
俳句仙人
次に、中村汀女の代表的な俳句を季節(春夏秋冬)別に紹介していきます。
中村汀女の有名俳句・代表作【36選】
![]()
(中村汀女 出典:俳句データベース)
春の俳句【9選】
![]()
【NO.1】
『 外にも出よ 触るるばかりに 春の月 』
季語:春の月(春)
現代語訳:外に出てごらんなさい。手を伸ばせば触れられそうなほどの春の月がある。
![]()
俳句仙人
穏やかな春の夜に浮かぶ、触れんばかりの大きな月。家の中に入る子ども達にも見せてやろうと、母親が呼びかけます。外に飛び出してきた子ども達と一緒に夜空を見上げる、そんな幸せな家族のひとときが描かれています。「春の月」と体言止めで結ぶことで、朧げに輝く美しい月にいたく感動した汀女の心情が余韻深く表現されています。
【NO.2】
『 たんぽぽや 日はいつまでも 大空に 』
季語:たんぽぽ(春)
現代語訳:足元にたんぽぽが咲いているなぁ。大空には太陽が悠々ととどまっており春の日の長さが感じられる。
![]()
俳句仙人
陽だまりに咲くたんぽぽと、日の長くなった太陽の姿を重ね合わせ、穏やかな春の訪れを表しています。桜や梅といった風雅を象徴する花ではなく、生活に身近なたんぽぽを題材とするところに、汀女らしさが感じられます。戦争が続く時代に詠まれた句であることから、「いつまでも」という語が平和の尊さをかみ締める切実な祈りにも聞こえてきます。
【NO.3】
『 手渡しに 子の手こぼるる 雛あられ 』
季語:雛あられ(春)
現代語訳:子供の手に雛あられをのせたところ、手があまりにも小さいためこぼれ落ちてしまったよ。
![]()
俳句仙人
自分の手にはおさまっていた雛あられも、子供の手に渡してやるとポロポロとこぼれ落ちてしまいます。なんてことはない日常風景ではありますが、子供という小さな存在に対する感慨が詠み取れます。「もっとちょうだい」と雛あられをせがむ、愛らしい手のひらが見えてくるような微笑ましい一句です。
【NO.4】
『 引いてやる 子の手のぬくき 朧かな 』
季語:朧(春)
現代語訳:繋いでいる子供の手が温かく感じる。今夜の春の月はぼんやりと霞んでいるなあ。
![]()
俳句仙人
子供は眠くなると手足が温かくなりますよね。足取りが重くなってきた子供に、「もう眠いのね」とその手を繋ぐ母親の優しい微笑みが想像できます。そんな母子の姿を朧月が優しく包み込んでいるかのような一句。「引いてやる」という表現が母の愛情を際立たせており、小さな手から伝わる温もりもより愛おしいものに感じられます。
【NO.5】
『 ゆで玉子 むけばかがやく 花曇 』
季語:花曇(春)
現代語訳:ゆで卵をむくと、つるんとした白さが美しく輝いている。花曇の花の下で。
![]()
俳句仙人
ゆで卵の光沢ある白い輝きと、花曇のにび色のコントラストが美しい句です。当時はまだ卵が貴重な食品であり、庶民の家庭ではめったに食べられるものではありませんでした。花曇とあることから、桜が満開の頃、家族でお花見を楽しんでいる時の句でしょうか。家族の視線が注がれる中、ご馳走であるゆで卵の殻を丁寧にむく母親の姿が読み取れます。
【NO.6】
『 ときをりの 水のささやき 猫柳 』
季語:猫柳(春)
現代語訳:ときおり水がささやくように流れていく。猫柳も揺れて返事を返している様だ。
![]()
俳句仙人
春になって穏やかに流れる川の水と、水辺に咲く猫柳を詠んだ一句です。猫柳は銀色の花穂が特徴的で、春の日差しと水の照り返しを受けて美しく輝いている様子が想像できます。
【NO.7】
『 花疲(はなづかれ) 泣く子の電車 また動く 』
季語:花疲(春)
現代語訳:花見に疲れて泣いている子のいる電車がまた動いていく。
![]()
俳句仙人
「花疲(はなづかれ)」とは花見をして疲れてしまった様子のことを表す季語です。疲れてぐずってしまっている子供を乗せた電車が帰路を走っていく様子を、母親の目線で詠んでいます。
【NO.8】
『 春寒や 出でては広く 門を掃き 』
季語:春寒(春)
現代語訳:春なのに寒いなぁ。外に出ては少し広めに門の前を掃いていく。
![]()
俳句仙人
作者の特徴である主婦目線の「台所俳句」の真骨頂です。春の朝や門の風景ではなく、いつもの家事として門の前を掃除する様子を詠んでいます。
【NO.9】
『 春暁や 今はよはひを いとほしみ 』
季語:春暁(春)
現代語訳:春の暁の光だなぁ。今となってはこの老齢の身も愛おしいものだ。
![]()
俳句仙人
作者が詠んだ最後の句と考えられている一句です。万物が息を吹き返すように栄えていく春の夜明けを見ていると、年老いた我が身も愛おしく思えてくるという人生への満足感を感じさせる句になっています。
夏の俳句【9選】
![]()
【NO.1】
『 真円き 月と思へば 夏祭 』
季語:夏祭(夏)
現代語訳:今宵の月はまん丸だなと眺めていると、そうか、今日は夏祭りだったと思い出した。
![]()
俳句仙人
「真円き」は「まんまるき」と読みます。欠けることなく光輝く月を眺めていると、楽しげな祭囃子が聞こえてきたのでしょうか。もしくは満月の頃といえばお祭りの時期だったのかもしれません。なぜ作者が夏祭りだったと気付いたのかまでは描かれていませんが、作者の心弾む様子が伝わってくるようです。
【NO.2】
『 地中海 夕焼も白き 船も消え 』
季語:夕焼(夏)
現代語訳:地中海の美しい夕焼けも、白い船も消えてしまった。
![]()
俳句仙人
夕焼けとは一年を通して見られるものですが、梅雨が明ける頃が最も鮮やかに見えることから夏の季語として用いられてきました。夕焼けの名所である地中海を題材に、夕日の赤と船の白のコントラストが絵画のように表現されています。そんな眩しいほどの美しい光景をいつまでも眺めていたのでしょう。「夕焼けも白き船も消え」と詠むことで、ゆっくりとした時の経過が感じられます。
【NO.3】
『 早打ちや 花火の空は 艶まさり 』
季語:花火(夏)
現代語訳:夜空は次々と打ち上がる早打ちの花火に彩られ、たいそう艶やかである。
![]()
俳句仙人
間髪入れず打ち上がる花火が、迫力ある音とともに夜空一面に広がっていきます。夏の夜のなんとも華やかな光景を詠んだ一句です。花火に彩られた空を、美しく風情のある様子を現代語訳する「艶まさり」と表現するところに、女性らしい情趣が感じられます。
【NO.4】
『 あひふれし さみだれ傘の 重かりし 』
季語:さみだれ(夏)
現代語訳:行き合って傘が触れた。五月雨で濡れた傘は重く感じる。
![]()
俳句仙人
「あひふれし」とは「合い触れし」といった、行き合う最中に少し傘と傘が触れてしまった様子のことです。雨に濡れた傘はどこか重く感じますが、他人の傘はより一層重く感じている面白い一句になっています。
【NO.5】
『 真上なる 鯉幟(こいのぼり)まづ 誘ひけり 』
季語:鯉幟(夏)
現代語訳:真上にひらひらと泳ぐ鯉のぼりがまず目を誘うことだ。
![]()
俳句仙人
「誘ひけり」という表現から、目を奪われるような大きな鯉のぼりがひらひらと空を舞っている様子が浮かんできます。現在でも大きな鯉のぼりを観光名所としている場所もあり、読んでいる人にも想像しやすい句ではないでしょうか。
【NO.6】
『 梅干して 人は日陰に かくれけり 』
季語:梅干し(夏)
現代語訳:梅を干して、人間は暑さを避けて日陰に隠れている。
![]()
俳句仙人
現在の梅干しのレシピでは天日干しを省略しているものがありますが、保存性を高めるために日に干すのが一般的でした。この句では梅を干した張本人はちゃっかり日陰に避難している様子を詠んでいます。
【NO.7】
『 菖蒲湯の 香のしみし手の 厨(くりや)ごと 』
季語:菖蒲湯(夏)
現代語訳:菖蒲湯の香りが染みている手で料理をする。
![]()
俳句仙人
菖蒲湯の支度をしたあとに夕食の準備をしている様子が想像できる句です。現在のように蛇口をひねればお湯が出るわけではないため、菖蒲と長く触れていてすっかり匂いが染み付いてしまったと詠んでいます。
【NO.8】
『 地下鉄の 青きシートや 単物 』
季語:単物(夏)
現代語訳:地下鉄のシートが目も覚めるような青だなぁ。単物だろうか。
![]()
俳句仙人
日本で本格的な地下鉄が誕生したのは1927年に開業した銀座線です。作者は結婚後に夫とともに東京や仙台など大都市を転々としており、青いシートが整然と並ぶ地下鉄に驚いている様子が着物である単物を例えに出していることから伺えます。
【NO.9】
『 なほ北に 行く汽車とまり 夏の月 』
季語:夏の月(夏)
現代語訳:ここよりなお北に行く汽車が止まる。空には夏の月が出ている。
![]()
俳句仙人
北へ向かう夜行列車が思い浮かぶ一句です。夜行列車は明治中期には既に運行されていて、現在より速度の出ない列車では遠くへ行くために夜行となることが多く、ここより遥か遠い地へ向かう列車に思いを馳せています。
秋の俳句【9選】
![]()
【NO.1】
『 とどまれば あたりにふゆる 蜻蛉かな 』
季語:蜻蛉(秋)
現代語訳:ふと立ち止まりあたりを見渡すと、蜻蛉が何匹飛んでいた。
![]()
俳句仙人
日常生活の中にふと訪れる季節の移ろいを、蜻蛉を題材にして詠んだ一句です。残暑厳しい日、道を歩いていると目の前を蜻蛉が横切ったのでしょうか。思わず歩を止めると、周りには蜻蛉が数を増して飛んでいることに気付き、秋の気配を実感しています。詩ごころを率直に詠んだものですが、「あたりにふゆる」という語を用いることでのびのびとした空間の広がりを持たせています。
【NO.2】
『 秋雨の 瓦斯が飛びつく 燐寸かな 』
季語:秋雨(秋)
現代語訳:秋雨の降る暗く湿った台所で、燐寸をすり火をつけようとしたところ、瓦斯の方から飛びついてきたようだなあ。
![]()
俳句仙人
まだガスが自動点火ではなく、マッチで着火していた昭和初期に詠んだ句です。「秋雨の」とあることから、湿った空気が漂う台所では火付きも悪かったのでしょう。マッチの炎がガスに燃え移るというよりも「瓦斯が飛びつく」と表現し、「ボッ!」という一瞬の大きな音やかすかなガスの臭いまでが漂ってくるようです。まさに日々繰り返す動作に着目した「台所俳句」でありながら、透徹した観察眼で鮮やかな句に仕上げています。
【NO.3】
『 あはれ子の 夜寒の床の 引けば寄る 』
季語:夜寒(秋)
現代語訳:晩秋の夜、ふと寒さを感じ子供の眠っている様子を見ると、いかにも寒そうだ。布団を自分の方に引くと、すっと寄ってきたよ。
![]()
俳句仙人
秋も深まったある夜、肌寒さを覚えふと目が覚めた時に、我が子が寒くはないかと心配する母親が、子供の布団を自分の方に引き寄せるという母性溢れた一句です。子供の思わぬ軽さにぐっと胸を打たれ、深い愛情がこみ上げる様子を「あわれ子の」と表現しています。
【NO.4】
『 泣きし子の 頬の光りや とぶ蜻蛉 』
季語:蜻蛉(秋)
現代語訳:泣いていた子供の頬につたう涙は乾ききっておらず、日の光が当たって輝いている。あたりには蜻蛉が飛んでいることだ。
![]()
俳句仙人
泣いていた子の激情も収まり、落ち着きを取り戻しつつありますが、まだ涙の跡は乾ききっていません。「とぶ蜻蛉」と続けることで、「蜻蛉まで何事かと飛んできたみたいね」と我が子の目を楽しませ、和やかにさせる効果を持たせています。母親らしい穏やかな雰囲気が漂う一句です。
【NO.5】
『 目をとぢて 秋の夜汽車は すれちがふ 』
季語:秋の夜(秋)
現代語訳:秋の夜に汽車に乗り目を閉じていると、反対方向からやってきた別の汽車とすれ違った。
![]()
俳句仙人
この句は、仙台から東京へ引っ越す際に乗車した汽車でのことを詠んでいます。「目をとぢて」仙台で過ごした日々の回想や、東京での新しい生活への想いや不安をめぐらせているのでしょうか。そんな想いを打ち破るように、大きな轟音を響かせ反対方向から汽車が走り去っていきます。列車がすれ違うという瞬間を「俳句的場面」と捉えた汀女の、表面的な平易さとは別に、句に込められた深い余情が感じられます。
【NO.6】
『 銀杏が 落ちたる後の 風の音 』
季語:銀杏(秋)
現代語訳:銀杏(ぎんなん)が下に落ちた後、風の音が聞こえてきた。
![]()
俳句仙人
「銀杏」はイチョウとも読めますが、実を指す場合は「ぎんなん」と読みます。晩秋の頃になると、さくらんぼ程の小さな実が黄色く熟れ、自然と落下しはじめます。鈴なりだった実が地面に落ちると、木々の間に吹く風の音もことさら大きく感じられたのでしょう。「カサカサ」と葉を鳴らす音に、もうすぐやってくる冬の気配も感じられます。
【NO.7】
『 稲妻の ゆたかなる夜も 寝(ぬ)べきころ 』
季語:稲妻(秋)
現代語訳:稲妻があちこちで鳴り響いている夜も、もう寝るべき頃合ですよ。
![]()
俳句仙人
「稲妻がゆたか」という面白い発想から詠まれている一句です。雷を怖がっているよりもどこか楽しんでいる様子が伺えますが、もう寝なくてはいけないと我に返っています。
【NO.8】
『 夜霧とも 木犀の香の 行方とも 』
季語:木犀(秋)
現代語訳:夜霧が入ってきたのかとおもったら木犀の香りがする。ちょうど流れ去っていくところなのだろうか。
![]()
俳句仙人
霧に紛れて木犀のよい香りがする夜の様子を表しています。香りが霧とともに流れて動いていくように感じる様子はどこか神秘的で、木犀の甘い香りが思い浮かぶようです。
【NO.9】
『 霧見えて 暮るるはやさよ 菊畑 』
季語:菊畑(秋)
現代語訳:だんだんと霧が見えてきて、日が暮れる早さを実感するなぁ。菊畑に日が落ちる。
![]()
俳句仙人
菊の花畑を見ているうちにだんだんと霧が出てきて、日が暮れていく様子を詠んだ映像のように美しい一句です。夕日に照らされていた菊の花が霧に覆われていく風景が目に浮かびます。
冬の俳句【9選】
![]()
【NO.1】
『 咳の子の なぞなぞあそび きりもなや 』
季語:咳(冬)
現代語訳:咳をする我が子となぞなぞ遊びをする。やめようと思うが子供にせがまれ、きりがないことだなあ。
![]()
俳句仙人
咳をしながらも「もっとなぞなぞを出して」とせがむ子供からは、体調の悪さよりも親に遊んでもらえる喜びが勝っているようです。そんな甘えを汲み取ってか、「もう終わりよ」と言えず付き合ってやる母親の優しさを、詠嘆の切れ字を用いて「きりもなや」と表現しています。そして同時に、手のかかる子供との幸せな時間はいつまでも続くものではないと、どこか冷静な眼差しも含まれています。
【NO.2】
『 咳をする 母を見上げて ゐる子かな 』
季語:咳(冬)
現代語訳:咳の出る母親のことを、我が子が心配そうに見上げているよ。
![]()
俳句仙人
先述した句【咳の子の なぞなぞあそび きりもなや】と対を成す句としても詠みとれます。「見上げている」という語からは、我が子は幼児であることがわかります。苦しそうに咳き込む母親を何とか助けたいと考えるも、何もできずただただ見上げることしかできない子供。そんないじらしい姿に母親は慰められ、子供への愛情をいっそう強めています。
【NO.3】
『 竈猫 打たれて居りし 灰ぼこり 』
季語:竈猫(冬)
現代語訳:竈の中で眠っている猫は、うたれてもそこに居て灰の埃まみれになっている。
![]()
俳句仙人
「竈猫」はカマドの余熱の温かさにひかれて居座る猫を表す季語です。追い払われようともずっとそこにいたために、灰で汚れてしまっています。
【NO.4】
『 靴紐を むすぶ間も来る 雪つぶて 』
季語:雪つぶて(冬)
現代語訳:靴紐を結んでいる間も飛んでくる雪玉だ。
![]()
俳句仙人
「雪つぶて」は雪合戦に使われる雪玉です。靴紐がほどけてしまって結び直している間は無防備になってしまうのに、容赦なく雪玉が飛んできている子供たちの活発な様子を詠んでいます。
【NO.5】
『 さし寄せし 暗き鏡に 息白し 』
季語:息白し(冬)
現代語訳:近づけた鏡は周りが暗くてよく見えないけれど、息が白いのはよく見える。
![]()
俳句仙人
屋内や夜で周りが暗いときに鏡を見てもあまりよく見えませんが、寒さで白くなっている息だけがよく見えると詠んでいる一句です。鏡というぼんやりとした明かりもない薄暗い場所を映し出す道具によって、一緒に映っている白い息が際立っています。
【NO.6】
『 橋に聞く ながき汽笛や 冬の霧 』
季語:冬の霧(冬)
現代語訳:橋から聞こえてくる長い汽笛だなぁ。冬の霧で汽車はよく見えない。
![]()
俳句仙人
霧の中を走る列車が、安全確認のためか長めの汽笛を鳴らして運行している様子を詠んだ句です。霧のかかる中に橋の上を通過する汽車という映画の一幕のような一句になっています。
【NO.7】
『 慈善鍋 昼が夜となる 人通り 』
季語:慈善鍋(冬)
現代語訳:慈善鍋の募金活動が始まると、昼間なのに夜のように人がいなくなる人通りだ。
![]()
俳句仙人
「慈善鍋」とは救世軍というキリスト教の団体が設置する募金のための鉄鍋のことです。普段は人通りが多い場所なのに、募金を避けるかのように人がいなくなってしまう様子を詠んでいます。
【NO.8】
『 枯芒 ただ輝きぬ 風の中 』
季語:枯芒(冬)
現代語訳:枯れたススキが日に照らされてただ輝いている風の中だ。
![]()
俳句仙人
ススキは穂が出ている秋には銀色に輝くことで有名ですが、この句では枯れたススキを詠んでいます。例え枯れたススキでも風の中で輝けるのだという作者の価値観が伺える句です。
【NO.9】
『 次の子も 屠蘇を綺麗に 干すことよ 』
季語:屠蘇(正月)
現代語訳:次の子もお屠蘇をきれいに飲み干したことよ。
![]()
俳句仙人
「お屠蘇」とは現在では新年に飲む日本酒を指すことが多いですが、昔は「屠蘇散」という漢方を日本酒や味醂に漬け込んだ薬草酒でした。頑張って飲み干した子供たちへの優しい目線が「干すことよ」という表現から伝わってきます。
さいごに
![]()
今回は、中村汀女代表的な俳句を36句紹介しました。
中村汀女は季節を感じながら過ごす日々の中で、心に響いたものを柔らかく、慎ましやかな気持ちで十七文字に表現してきました。
これらの句を詠むと、俳句とは難解なものではなく、誰もが楽しめる親しみやすい文芸だというのも頷けます。
彼女の特徴でもある子供を詠んだ句は、母親としての優しさや温かさが強く伝わってきますね。わが子への深い愛情は、時代を経ても変わらず心打たれるものでしょう。
![]()
俳句仙人
こちらの記事もおすすめ!