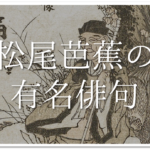俳句は五・七・五の十七音で表現する短い詩です。
季節の出来事を表す季語を詠み込むことによって、多彩な表現や感情を表現します。
今回は、松尾芭蕉の有名な俳句の一つである「野を横に馬牽むけよほととぎす」を紹介していきます。
郷福寺境内の芭蕉句碑。「野を横に馬引き向けよほととぎす」 pic.twitter.com/IGtAb5bD0s
— onody (@fujinosirayuki) November 6, 2017
本記事では、「野を横に馬牽むけよほととぎす」の季語や意味・詠まれた背景・表現技法・作者について徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「野を横に馬牽むけよほととぎす」の作者や季語・意味・詠まれた背景

野を横に 馬牽むけよ ほととぎす
(読み方:のをよこに うまひきむけよ ほととぎす)
この句の作者は「松尾芭蕉(まつおばしょう)」です。
『おくのほそ道』などの紀行文で知られる江戸時代前期の俳人で、江戸三大俳人の1人に数えられています。
一門から多くの弟子を輩出し、江戸時代の俳句文化の中心となった人物です。
季語
この句の季語は「ほととぎす」、季節は「夏」です。
ホトトギスは初夏の5月に南の方から渡ってくる渡り鳥で、夏の到来を告げる鳥として万葉集の頃から詠まれていました。

俳句でも初夏の俳句に多く使われていて、初めての鳴き声を「初音」、夜に忍んで鳴く声を「忍び音」と呼びます。
意味
この句を現代語訳すると・・・
「馬に乗って野原を横切っているとホトトギスの鳴き声が聞こえる。馬を鳴き声の方に向けよ。」
という意味です。
この「野」とは栃木県那須町の那須野のことです。ホトトギスが聞こえたまさにその瞬間のような臨場感のある句で、『おくのほそ道』の中ではめずらしい即興で詠まれた俳句になります。
この句が詠まれた背景
この句は『おくのほそ道』の旅で、栃木県を旅している最中に馬に乗りながら詠まれた俳句になります。
芭蕉は1689年4月19日、現在の栃木県の那須湯本にある「殺生石(せっしょうせき)」という名所を訪れています。
「殺生石」とは平安時代に九尾の狐が退治されて石となって飛び散ったものとされ、火山性ガスを噴出する付近にあるため「生き物を殺す石」として名付けられました。

(殺生石 出典:Wikipedia)
この句には前書きとして「是より殺生石に行。館代より馬にて送らる。此口付のおのこ、「短冊得させよ」と乞。」とあり、馬の口を引く馬子が一句を求め、芭蕉が即興で応じたことが伺えます。
「野を横に馬牽むけよほととぎす」の表現技法

(殺生石園地 出典:Wikipedia)
「馬牽むけよ」の切れ字「よ」
切れ字は「や」「けり」「かな」などが有名です。
詠嘆や命令を表す終助詞が多く用いられ、言い切ることで直前の言葉を強調します。
この俳句では、「馬牽むけよ」の「よ」が切れ字になります。「よ」は詠嘆を表す終助詞である場合もありますが、ここでは「呼びかけ」として用いられているのが特徴です。
馬子に請われて即興で詠んでいるため、実際に馬を引いている馬子への呼びかけの形で表現されています。
「ほととぎす」の体言止め
体言止めは、語尾を名詞や代名詞などで止める技法です。
また、ホトトギスの鳴き声を聞いて馬を横に向けよと語りかけているので、倒置法でもあります。
「ほととぎす」を冒頭に詠まずに体言止めとして表現することで、より一層ホトトギスの鳴き声を際立たせている効果があります。

初夏の那須野の風景が浮かんでくるようです。
「野を横に馬牽むけよほとゝぎす」の鑑賞文

この句は即興で詠まれたもので、馬の口を引く馬子への呼びかけとも、ホトトギスの鳴く方へと行ってみようという提案とも取れる句です。
短冊を求められたときの芭蕉は「やさしき事を望侍るものかなと(訳:なんと風流なことを求められたものだなぁと)」という感想を持っています。
馬子は人や荷物を乗せた馬を運ぶ職業で、江戸時代など流通が活発になると多くの人達が職につきました。
普段は肉体労働が多く風流とは縁のない生活を送っていた人たちを芭蕉も見ていたのかもしれません。

だからこそ、一句求められたことに新鮮な驚きと感動を覚え、「牽むけよ」と躍動感のある俳句を詠んでいます。
「野を横に馬牽むけよほとゝぎす」の補足情報

那須の道
この句では、「ホトトギスが鳴いた方向へ馬を向けてくれ」という、とても開けた場所を歩いている様子が描写されています。
今のような幹線道路ではなく、自由に馬を移動させられる道のような印象を受ける表現ですが、実際の江戸時代の那須はどのような道が通っていたのでしょうか。
現在の栃木県から福岡県にある白河関に向かう道には、奥州街道があります。江戸の日本橋から宇都宮で日光街道に分岐し、白河関へと通じる街道です。
芭蕉は日光や雲巌寺といった奥州街道からは外れた場所へ寄り道をしながら最終的に白河関にたどり着きますが、途中で通過する那須にはさまざまな道が縦横無尽に走っている場所がありました。
「野を横に」の句が詠まれたのは奥州街道の鍋掛宿の近くから殺生石へと向かう道中になっており、進行方向には殺生石のある那須連山が高くそびえています。
通った道筋は、現在では田んぼが広がる場所ですが、かつては広大な草原だったと言われています。

これらの地形関係を踏まえてこの句を読むと、「野」がどこまでも続く那須の草原と進行方向にある高くそびえる那須連山を、「横」が道を外れても続く平らな空間を表していて、即興ながらダイナミックに那須の様子を詠んでいることがわかるでしょう。
西行法師と那須
芭蕉は『おくのほそ道』において、西行法師が旅をしたとされる道や歌枕に立ち寄っていることはよく知られています。
殺生石へ向かう道中で「遊行柳」へと立ち寄り、「田一枚 植えて立ち去る 柳かな」という俳句を『おくのほそ道』に残していることは有名です。
しかし、那須にはもう1箇所西行法師の伝説を残す場所がありました。
それは、芭蕉たちが半月滞在した黒羽の近くの鍋掛にある「境の紅葉」です。
かつて西行法師が藤原秀郷を訪ねた帰りに鍋掛に立ち寄り、楓の評判を聞きつけて見物に行きました。
その際に詠まれたのが下記の句です。
「尋ぬれば 青葉の梢色濃くて 何もたへせぬ にしきなるらん」
(訳:美しいと名高い楓を尋ねていけば、青葉の梢の色がとても濃く、紅葉ではないけれど絶えず錦のように美しいものだ)
鍋掛という宿泊場所の黒羽に近い場所にあること、半月滞在していることから、芭蕉一行もこの伝説を聞いて境の紅葉を見に行ったかもしれません。

『おくのほそ道』を読むにあたって、西行法師の辿った道を知ることは不可欠です。さまざまな場所に残る西行法師伝説を調べてみると意外な発見があります。
作者「松尾芭蕉」の生涯を簡単にご紹介!

(松尾芭像 出典:Wikipedia)
松尾芭蕉は1644年伊賀国上野、現在の三重県伊賀市に生まれました。俳号は、初めは宗房(そうぼう)を称し、次いで桃青(とうせい)、江戸の芭蕉庵に移ったときに芭蕉と改めています。
10代後半で当時京都に滞在していた北村季吟に師事して俳諧を学び始めました。この頃の芭蕉の句は、テンポ良い音律と奔放さに加え、小唄などの流行の言葉を多く使っています。1674年に北村季吟から卒業を言い渡され、これを機に芭蕉は江戸へ向かいました。
江戸に到着した芭蕉は職業的な俳諧師である宗匠となり、江戸の深川にある芭蕉庵へと居住を移して「芭蕉」の俳号を使用し始めます。漢詩を下敷きとした新しい俳句の模索などさまざまな作風を生み出しましたが、最終的に「侘び」を重視する作風の俳句が増えるようになります。
向井去来や服部嵐雪、河合曽良など多くの有名な門弟を取りますが、1684年の『野ざらし紀行』から1689年の『おくのほそ道』の旅まで、旅をしながら俳句を詠む生活を送るようになりました。
『おくのほそ道』の旅から帰還した芭蕉は、今まで書きためた紀行文や俳句を整理して出版する作業を行っていましたが、次第に体調を崩し1694年10月12日に旅先の大阪で亡くなりました。芭蕉の絶筆の句が有名な「旅に病んで夢は枯野をかけ廻る」です。芭蕉は最後までこの句を「枯野を廻るゆめ心」にするか推敲をしていたとされるほど、旅と俳諧に生きた人生でした。
松尾芭蕉のそのほかの俳句
(「奥の細道」結びの地 出典:Wikipedia)