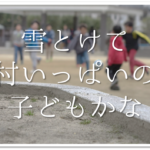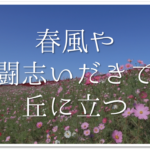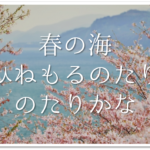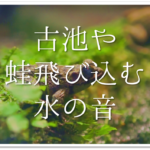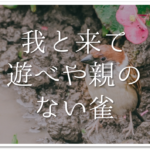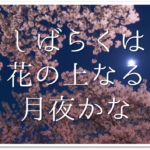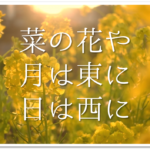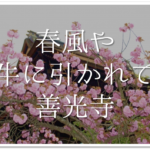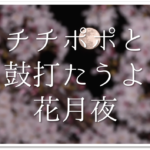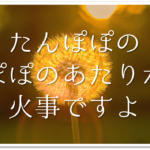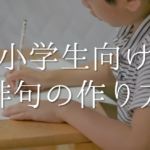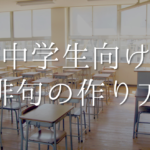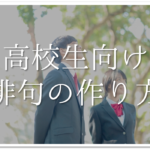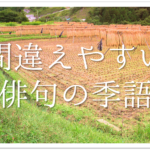俳句が一般的な趣味として定着してから、かれこれ60年になります。
最近はバラエティー番組の俳句コーナーが大人気で、これまでにない俳句ブームが到来しています。
思っていたよりも俳句を身近に感じ、実際に作ってみたいと思われている方も多いと思います。そして、今は春の季節!俳句を詠むのには絶好の季節です。
いつもより のどかな春に 桜咲く#haiku pic.twitter.com/mt38R5zgIO
— 竹田康一郎 (@tahtaunwa) March 21, 2020
☆春爛漫桜吹雪の中に居る
(もう幸せ~🌸🌸🌸)#haiku #kigo #俳句 #jhaiku pic.twitter.com/4dvDCCr77S
— shiose🌺 華 (@kuricyan8787) April 4, 2020
そこで今回は、春にちなんだ季語を使った俳句の簡単な作り方とコツを紹介していきます。

目次
俳句とは?基本的なルールを知ろう!

俳句とは五・七・五のリズムで作る定型詩ですが、必ず知っておかなければならないルールが2つです。
- 五・七・五の十七音で作る
- 季語を入れる

①五・七・五の十七音で作る
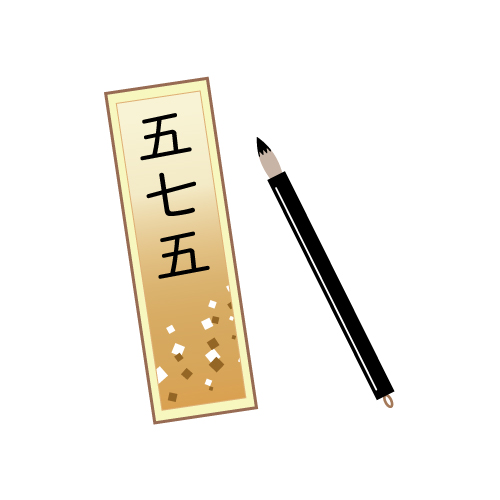
与謝蕪村の以下の作品から簡単に説明していきますね。
【作者】与謝蕪村
『 菜の花や 月は東に 日は西に 』
季語:菜の花
意味:愛らしい菜の花をしばらく見ているうちに夕暮れになり、東の空には月がのぼり、西の空は夕日がしずみつつあります。
こちらの句を五・七・五の十七音で見てみると・・・
- な・の・は・な・や (五)
- つ・き・は・ひ・が・し・に(七)
- ひ・は・に・し・に(五)
上記のように、十七文字は字数ではなく音で数えます。
万葉集の昔から使われてきた五と七を組み合わせるリズムは俳句の他にも短歌や川柳、歌の歌詞などの表現に使われている日本古来のものです。

ちなみに、強調して表現するために五・八・五などになっているものを「字余りの句」といいます。
②季語を使う

2つ目のルールが季語を使うことです。
季語とは、季節を感じさせる言葉のことです。
季語の例
- 春・・・「桜」や「雛祭り」「入学式」
- 夏・・・「海」や「プール」「夏休み」
- 秋・・・「紅葉」や「文化の日」「運動会」
- 冬・・・「雪」や「正月」「バレンタインデー」
短歌や川柳には「季語」を使うルールはないため、「季語」を用いる俳句はむずかしいと思われがちです。
それに季節にこだわると表現の幅が狭くなってしまうと感じる方もいるでしょう。
しかし、実のところたった十七音の俳句では「季語」があるからこそ、「ああ、この感じ、わかるなあ」という共感が生まれます。
先ほど紹介した蕪村の句の季語「菜の花」を見るだけで、鑑賞する人の脳裏には多少の個人差はあれど、色鮮やかな菜の花畑や早春のぽかぽかしたのどかな感じが浮かぶでしょう。
このように、「季語」は鑑賞する人の五感に訴えかけ、詳しい説明をしなくても、鑑賞するひとの想像力を助けてくれます。

簡単に作れる!春の俳句の作り方&コツを紹介
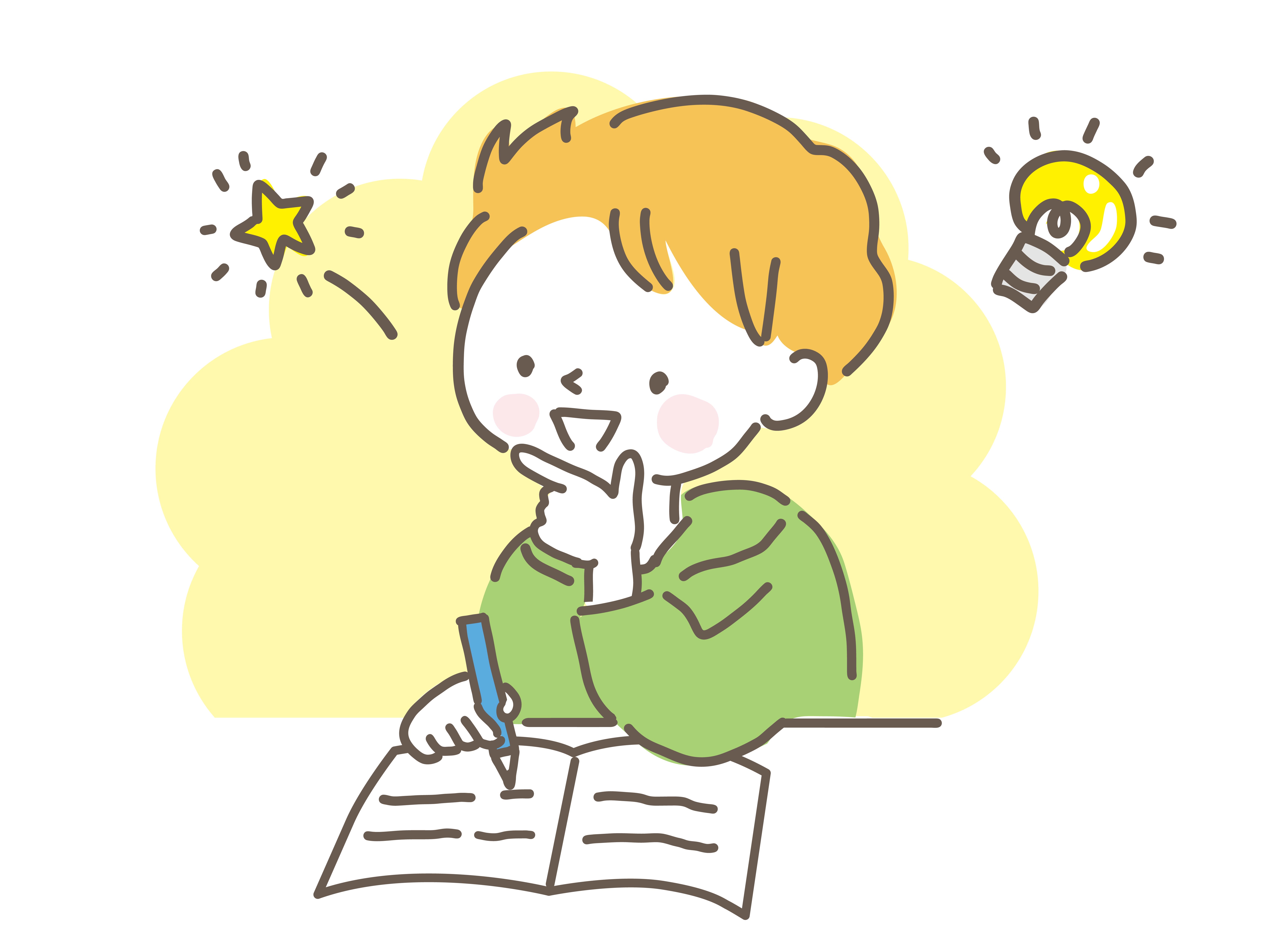
それでは早速、春の季語を用いた俳句の作り方やコツについて解説していきます。
① まずは春の季語を選ぼう!

まずは、俳句に入れる春の季語を選びましょう。
春の俳句には以下ののようにたくさんありますので、お好きなものを選びましょう。
春の季語【一覧】
「春」「春の~」「~の春」「二月」「如月」「三月」「弥生」「四月」「雨月」「暖か」「うららか」「春めく」「朧月夜」「蜃気楼」「木の芽時」「春暁」「春の宵」「春日和」「春北斗」「花冷え」「八十八夜」「淡雪」「朧月」「陽炎」「霞」「風光る」「東風」「春北風」(はるならい)「春雨」「啓蟄」「春一番」「彼岸」「山笑う」「野焼き」「朝寝」「風車」「シャボン玉」「ブランコ」「春眠」「摘草」「風船」「春セーター」「猫の恋」「蝶」「蜂」「蜂の巣」「つばめ」「うぐいす」「ひばり」「雀の子」「鳥の巣」「猫の子」「青海苔」「若芽」「白魚」「はまぐり」「しじみ」「あさり」「伊予柑」「ネーブル」「桜餅」「クレソン」「春大根」「木の芽和」(きのめあえ)「若芽和」(わかめあえ)「せり」「アスパラガス」「種まく」「雛菊」「椿」「すみれ」「木蓮」「アネモネ」「スイートピー」「桜」「梅」「チューリップ」「ミモザ」「ヒヤシンス」「猫柳」「蒲公英」「土筆」「かすみ草」「菜の花」「バレンタイン」「ひな祭り」「ゴールデンウィーク」「建国記念日」「みどりの日」「入学」「遠足」「卒業」「春分の日」「花見」「夜桜」
*「花」「花の~」など、春の季語として「花」を使う場合は桜を意味することになります。

②「場面」や「気持ち」を切り取ってみよう!

使ってみたい季語がみつかったら、早速一句ひねってみたいところですが、実はもうひとつ大事なことがあります。
句の「場面」や「気持ち」の材料をいくつか集めてみましょう。
具体的にどんな場面のことを伝えたいのか、どんな気持ちなのか、リラックスした状態で、その時の空気感、目に映っている風景、聞こえてくる声や音、そして心に浮かんだことなど、感じたことを簡単に書きとめてみましょう。
材料は日常の身近な出来事からたくさんキャッチすることが出来ます。五感をフルに活用して材料をたくさん集めてみましょう。
たとえばこんな身近なところに…
【身近な自然】
- 窓から見える景色 雲の流れ
- 散歩中にみつけた草花 庭にある花
- 家庭菜園 プランター菜園
【日常的な出来事やイベント】
- ショッピング フリーマーケット
- 断捨離してみたこと
- 今日の晩ご飯
【趣味、お気に入りの場所、人】
- 旅行 習い事 ウォーキングをはじめた
- 公園 本屋さん 八百屋さん
- 大好きな家族 大好きな友達 大事なペット
日常の何気ない風景は誰にでも共通するところがあるので、とりあげるには平凡すぎると感じられるかもしれません。
ですが、日常の何気ない風景のなかにこそ、人それぞれの感性が生き生きとあらわれるものです。
先ほど選んだ季語とここで集めた句の材料がそろったら、気持ちにそって伝えたいことを簡単で短い文章にしてみましょう。

③ 五・七・五の形にあてはめて読む

次に、五・七・五のリズムにあう言葉で俳句を組み立てていきましょう。
なかなかうまくいかないときは、同じ意味を持つ他の言葉を探して入れ替えてみるのもよいでしょう。

④読んでみて違和感があれば、言葉を変えてみる

リズムがそろったら、次は必ず音読してみましょう。
何度も音読してみることでリズムの良し悪しがわかりますし、時にはもっとぴったりくる別の言葉を思いついたりすることもあります。
また、この時点で必要であれば季語を変えてみてもよいですし、気持がしっかりあらわれているか、伝わりやすいかをよく確認してみましょう。

【番外編】切れ字を活用してみよう!

昔の俳句には、切れ字十八字といって言葉の切れ目に「かな」「や」「けり」を入れ、強調させたり余韻を残させたりする手法もあります。
例)雪溶けて 村いっぱいの 子供かな (小林一茶)
季語・雪溶け
※暖かくなって雪が解けてきた。春を待ちかねていた子供たちがいっせいに外で遊びはじめ、村がにぎやかです。こんなにたくさんの子どもがいたのだなあ。
○「かな」は感動や感嘆を意味します。「~だなあ」という感じで、感動の気持ちをまとめます。
例)春風や 闘志いだきて 岡に立つ (高浜虚子)
季語・春風
※この春風のなか私はひとり丘に立ち、闘志をもって進むと心に決めました。
○「や」は感嘆または呼びかけを意味します。句のリズムを格調高くしたり、直前の言葉を強調したりします。
例)春の夜は 桜に明けて しまひけり (松尾芭蕉)
季語・春の夜 桜
※夜桜を見ているうちに、気がついたら春の一夜が明けてしまっていた。
○「けり」は「たしかに~だった」という意味で、強く言い切った感じの雰囲気を出します。す。ほぼ句の最後に使われます。
ただ、切れ字は必ずしも使わなければならないものではありません。
いつの間にか、気がついたら使っていたということもあると思いますが、句のリズムを整えたいときにとても役立ちますし、俳句に「切れ」という味わいを持たせてくれますのでわざわざ修正する必要はありません。

春のおすすめ有名俳句【9選】

ここでは、参考のために春に関する有名俳句を9つ紹介していきます。
【NO.1】与謝蕪村
『 春の海 終日(ひねもす)のたり のたりかな 』
季語:春の海
意味:うららかなで穏やかな春の海は、一日中、波がゆったりうねるように寄せては返しているなあ。

【NO.2】松尾芭蕉
『 古池や 蛙飛び込む 水の音 』
季語:蛙(かわず)
意味:古池に蛙が飛び込んだ音が聞えましたよ。

【NO.3】小林一茶
『 我と来て 遊べや親の ない雀 』
季語:子雀(親のない雀)
意味:こちらに来て母を亡くした私と遊ぼう、母雀にはぐれた子雀よ。

【NO.4】松尾芭蕉
『 しばらくは 花の上なる 月夜かな 』
季語:花(春)
意味:しばらくは桜の花の上に出る月夜になるなぁ。

【NO.5】与謝蕪村
『 菜の花や 月は東に 日は西に 』
季語:菜の花(春)
意味:菜の花が咲いているなぁ。月は東から昇り、日は西に沈んでいく。

【NO.6】小林一茶
『 雪とけて 村いっぱいの 子どもかな 』
季語:雪とけ(春)
意味:雪がとけて、村にいっぱいの子供たちが出てきたなぁ。

【NO.7】小林一茶
『 春風や 牛に引かれて 善光寺 』
季語:春風(春)
意味:春風が吹いているなぁ。牛に引かれて善光寺参りに行こうか。

【NO.8】松本たかし
『 チチポポと 鼓打たうよ 花月夜 』
季語:花月夜(春)
意味:チチポポと鼓を打とうよ、この美しい花月夜に。

【NO.9】坪内稔典
『 たんぽぽの ぽぽのあたりが 火事ですよ 』
季語:たんぽぽ(春)
意味:たんぽぽの「ぽぽ」のあたりが火事ですよ。

春のおすすめ一般俳句作品集【9選】

ここからは、春に関する一般オリジナル俳句作品を9つ紹介していきます。
【NO.1】
『 はにかみ屋 肩寄せ合って シクラメン 』
季語:シクラメン(春)
意味:鉢植えのシクラメンを見ていると、花がみんなうつむいているので、はにかみやさんたちが肩を寄せ合っているようにみえました。

【NO.2】
『 柑橘を 枝にさし待つ 春の鳥 』
季語:春の鳥(春)
意味:オレンジを庭木の枝にさして、小鳥が来ないかなと待っています。

【NO.3】
『 駅寒く コートにかくれ 春の服 』
季語:春の服(春)
意味:せっかく薄手で明るい色をした春の洋服を着ているのに、まだ朝の駅が寒いのでコートを着ないといけないのがちょっぴり残念です。

【NO.4】
『 雨傘に 桜の花が ひとしずく 』
季語:桜(春)
意味:雨傘に桜の花が舞い落ちた。

【NO.5】
『 たんぽぽの くすぐり合える 犬の鼻 』
季語:たんぽぽ(春)
意味:たんぽぽの綿毛とくすぐりあっている犬の鼻だ、

【NO.6】
『 春風で 友達呼んで 遊びたい 』
季語:春風(春)
意味:春風で友達を呼んで遊びたいなぁ。

【NO.7】
『 寒いねと 友と交わせし 春浅し 』
季語:春浅し(春)
意味:寒いねと友人と言葉を交わすまだまだ春の始まりの頃だ。

【NO.8】
『 春星に お疲れさんの 帰り道 』
季語:春星(春)
意味:春の星にお疲れさんと言われているような帰り道だ。

【NO.9】
『 雨の朝 うす暗く春 暮れ行けり 』
季語:春暮れ/春の暮(春)
意味:雨の朝だ。辺りは薄暗く、春が終わっていく。

さいごに

春は景色が色鮮やかになり、さまざまなイベントも多く、新しい出会いの季節でもあります。
生活にちょっとした変化があったり、はじめてのところへ出かけていく事もあるかもしれません。
そんなときのことを軽い気持ちで俳句にしてみましょう。
体験したことを俳句に詠むと具体的な表現を使うので、いきいきとした俳句が生まれます。