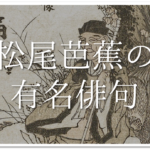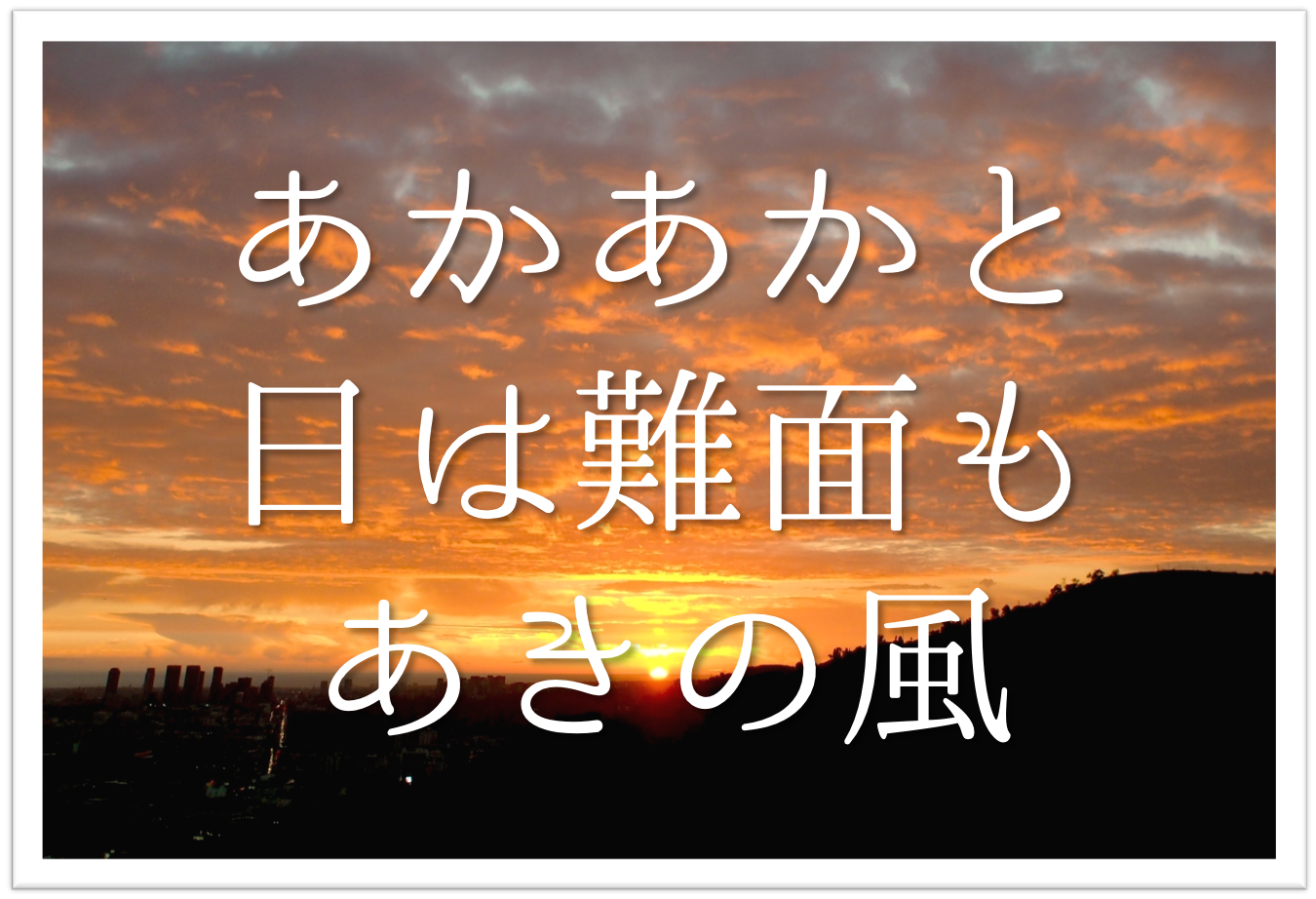
みなさんは、秋がくると思い浮かぶ俳句はありますか?
春夏秋冬、それぞれの季節で、趣のある素敵な句がたくさんあるかと思います。
今回は、有名句の一つ「あかあかと日はつれなくも秋の風」を紹介していきます。
あかあかと日はつれなくも秋の風…葉月も26日、メッキリ冷えこむ朝晩。蚊の嫌いな私には、それだけでいい季節だ。 pic.twitter.com/XUIRaT7OdC
— Taisuke (@tiny_biggy) August 25, 2016
本記事では、「あかあかと日はつれなくも秋の風」の季語や意味・表現技法・作者などについて徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「あかあかと日はつれなくも秋の風」の俳句の季語や意味・詠まれた背景

あかあかと 日はつれなくも 秋の風
(読み方:あかあかと ひはつれなくも あきのかぜ)
※難面も(つれなくも)とも書きます。
この句の作者は、「松尾芭蕉」です。
江戸時代のはじめに活躍し、日本史上最高の俳諧師の一人とされています。紀行文「奥の細道」の作者としても有名です。
季語
この句の季語は「秋の風」、季節は「秋」です。
風はそのままでは季語ではありませんが、「秋の風」「冬の風」など季節を表す語をともなうことで、季語となります。
「秋の風」は、残暑を運ぶ初秋の風、仲秋の爽やかな風、晩秋の冷たい空気を含んだ風と、吹く時期によって3種類に分かれます。
この句は、旧暦の7月(現在の8月)に詠まれた句とされています。そのため、吹いていた風は「残暑を運ぶ初秋の風」と考えられます。
意味
こちらの句を現代語訳すると以下のようになります。
「もう立秋も過ぎて秋がくるのに、夕日は真っ赤に照り付けていて残暑は厳しい。けれども、さすがに吹いてくる風には秋の気配を感じる。」
「あかあかと」は、漢字の意味で考えると「赤赤と」だと「真っ赤に」、「明明と」だと「きわめて明るい」という意味になります。この句の場合「日」は、夕日をさすため、「赤々と」の意味で訳しています。
「つれなく」は「つれなし」の活用形で「素知らぬ、冷淡だ、ままならない」などの意味があります。この句の場合は、秋が来ているのを素知らぬような、残暑の厳しい「あかあかと」した「日」だとも解釈することができます。
また、「つれなし」という言葉には「変わらない」という意味もあり、そちらの意味としてこの俳句を詠むこともできます。
芭蕉は『おくのほそ道』の中でこの句を「途中吟」という金沢から小松への旅の途中で詠んだ句と前書きしていますが、芭蕉のほかの資料では「秋立つけしき」という立秋の頃の様子であるとしたものあります。
この場合は「秋の太陽の日差し」と「秋の風」を同列に詠んでいることになり、芭蕉がこの句を気に入っていたことがよくわかります。
この句が詠まれた背景
この句は、「奥の細道」に収められています。
「奥の細道」とは、松尾芭蕉と弟子の河合曾良が江戸を出発して、東北から北陸を経て美濃国の大垣までを巡った155日間の旅を記した紀行文です。
この句は、元禄2年(1689年)旧暦の7月に金沢からの旅の途中に詠まれたとされています。
金沢では、加賀蕉門という芭蕉の俳句の流派の人たちが芭蕉を迎えました。門人の1人が、「ぜひ泊まってほしい」と芭蕉が来るのを待っていましたが、前年に亡くなってしまい、追悼の意を込めた句会に参加しました。
芭蕉は、滞在する土地で句会を開き、地域の人々や門人と交流を深めながら俳句を普及していました。
「あかあかと日はつれなくも秋の風」の表現技法

「秋の風」の体言止め
体言止めは、語尾を名詞や代名詞などの体言で止める技法です。体言止めには、美しさや感動を強調する、読んだ人を引き付ける効果があります。
「秋の風」の名詞で体言止めすることで、厳しい残暑にふっと吹いてきた風を強調しています。
「つれなくも」の「も」の助詞
切れ字ではありませんが、「~だけれども」という意味を表す接続助詞が使われています。
この助詞の使い方が、より「秋の風」を引き立たせています。
句切れなし
俳句では、意味やリズムの切れ目を句切れといいます。
この句には、切れ字や言い切りの表現が含まれないため、「句切れなし」となります。
「あかあかと日はつれなくも秋の風」の鑑賞文

この句は、古今和歌集で藤原敏行朝臣が詠んだ「秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞ驚かれぬる」を踏まえた句ではないかと言われています。
訳は、「(立秋の日が来ても)秋が来たと、はっきりと目には見えないけれども、風の音で、ああ秋が来たのだとはっと気づいた」となります。
芭蕉は、残暑の中に秋の風をふっと感じる、そうした何気ない一瞬を十七音に込めました。
もし、古今和歌集を踏まえた句であったとしたら、季節の移り変わりの一瞬をとらえ、かつ和歌を踏まえるという芭蕉の発想の広がりと、俳句のうまさが光る句です。
毎日変わらずに沈んでいく夕日と、確実に移り変わる季節に「わび・さび」を感じ俳句にする芭蕉の「不易流行」の理念も感じられます。
夏の終わりのさみしさと秋の始まりの待ち遠しさを、しみじみと感じることができます。
ちなみに、芭蕉自身もたいそう自分の詠んだ句を気に入って、この句の画賛(絵に俳句を書き添えたもの)を多く残したとされています。
改変された俳句とその理由

この句は、芭蕉の自筆本では「いまだ残暑はなはだなりしに旅のこころを…」という文章の後に詠まれています。
しかし、その後に貼り紙で訂正がされ・・・
「ある草庵にいざなはれて
秋涼し 手毎にむけや 瓜茄子(うりなすび)」
(意味:秋の涼しさの中で、瓜や茄子を各々の手で向いて食べよう)
という前書きと句、そして「あかあかと」の句の前の「途中吟」という前書きの3行が追加されています。
この改変が行われた理由については、ある俳人の死が関わっていました。芭蕉は、金沢で一笑という俳人と会うことを楽しみにしていましたが、前年に亡くなってしまっていることを知ります。
一笑の兄が開いた追悼の句会で、以下の句を詠みました。
「塚も動け 我が泣く声は 秋の風」
(意味:塚よ動いてくれ。あなたを悼み泣く私の声はまるで秋の風のようだ)
この後の3行が貼り紙によって訂正されて、「瓜茄子」の俳句と「あかあかと」の前書きが追加されているため、金沢での出来事は一笑の死とその追悼の面を強く出したかったのでしょう。
前述の「瓜茄子」の句は、精霊馬も連想させます。芭蕉は句の順番を変えることで、一笑の追悼句による死の衝撃から「瓜茄子」の句で立ち直り、「あかあかと」という句で旅を再開して次の句で小松に到着した、という一連の流れを表現しているのです。
『おくのほそ道』は、旅程に忠実に書かれたものでは無いことが随行した河合曾良の日記からもわかっています。「あかあかと」の句も金沢に到着する前に「秋立つけしき」を題材とした俳句として詠んでいたのでしょう。
句の順番と前書きを変更して4句並べることで、芭蕉の心の動きをよく表している場面です。
会いたかった人の死を嘆きながら旅を続けた芭蕉の心を思うと、「秋の風」という体言止めにもどこか悲しい風情を感じます。
作者「松尾芭蕉」の生涯を簡単にご紹介!

(松尾芭像 出典:Wikipedia)
松尾芭蕉は1644年伊賀国上野、現在の三重県伊賀市に生まれました。
本名は松尾忠右衛門、のち宗房(むねふさ)といいます。
13歳で父親を亡くし、藤堂家に仕え10代後半の頃から京都の北村季吟に弟子入りし俳諧を始めます。俳句の道を志し、28歳になる頃に、北村季吟より卒業を意味する俳諧作法書「俳諧埋木」を伝授されました。若手俳人として、めきめきと頭角をあらわした芭蕉は、江戸へと下りさらに修行を積んでいきます。
40歳を過ぎる頃には日本各地を旅し、行く先々で俳句を残し作品を発表しています。46歳の時に弟子の河合曾良と「奥の細道」の旅へと出発。150日間で行程2400㎞を旅したことや、生まれが伊賀であったことから、忍者ではなかったかという説が出たこともあります。
旅から戻った芭蕉は、「奥の細道」の執筆や句会を催し俳句を詠みながら、大津、京都、故郷の伊賀上野などを転々としました。
1694年、旅の途中の大阪にて体調を崩し51歳にて死去しました。
松尾芭蕉のそのほかの俳句
(「奥の細道」結びの地 出典:Wikipedia)