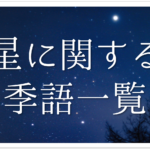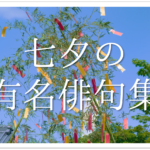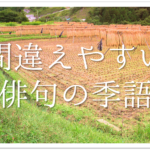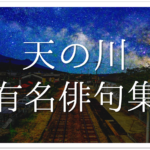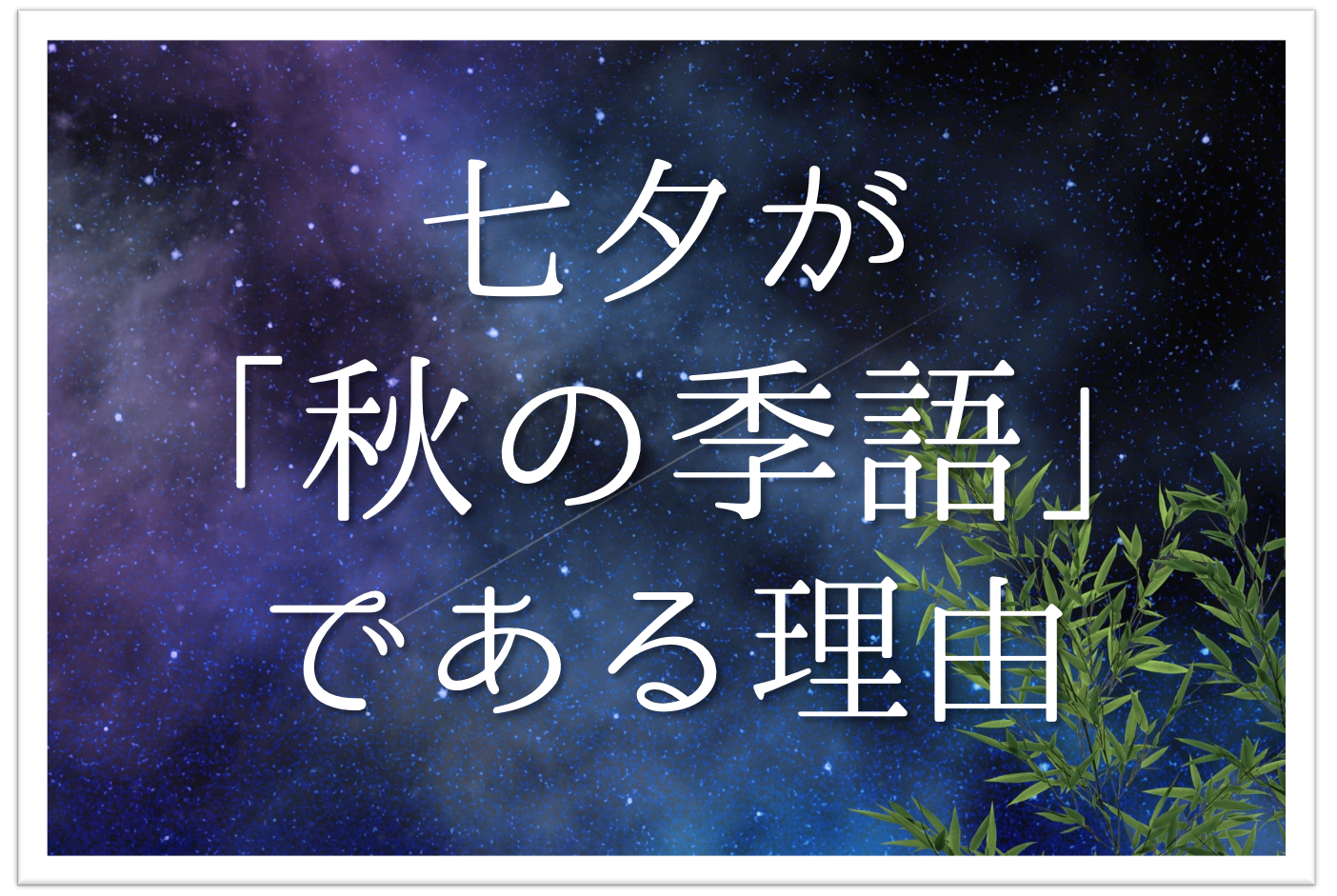
7月7日といえば「七夕(たなばた)」です。
7月は夏のイメージがありますが、七夕は【秋の季語】つまり秋の風物詩なのです。
「七夕は秋の季語」 #4コマ漫画 #横書き漫画 pic.twitter.com/2JffvF2Zsq
— かなりひこくま (@kanarihikokuma) July 7, 2017
なぜ夏の季語ではないのでしょうか?
今回は、七夕が秋の季語である理由を簡単に分かりやすく解説していきます。

目次
七夕が秋の季語である理由は「旧暦とのズレ」

現在は新暦、昔は旧暦だった
日本は明治時代のはじめまで「太陽太陰暦」という暦を使っていました。これを「旧暦」と言います。
旧暦の季節の決め方は、厳密には立春、立夏、立秋、立冬の日付けで決まります。現在の暦に直すと、立春は2月4日頃、立夏は5月5日頃、立秋は8月7日頃、立冬は11月7日頃です。
しかし、明治時代に万国共通の「グレゴリオ暦」が導入されます。これは現在も私達が使っている暦、つまり「新暦」です。
新暦の季節の決め方は春分、夏至、秋分、冬至があります。春分は3月20日頃、夏至は6月21日頃、秋分は9月22日頃、冬至は12月22日頃のため、旧暦に比べて季節感覚の違いはあまりありません。
新暦と旧暦には約1〜2カ月のズレがある

この旧暦と新暦にずれがあることで、季語のイメージと歳時記の季節区分に差が生まれます(歳時記の季節区分は旧暦に基づいています)。
このイメージと季語の季節区分との差はなぜ生まれるのでしょうか。
旧暦は明治5年12月2日まで使われていましたが、新暦は明治6年1月1日から導入されました。この時点で旧暦と新暦に29日のずれが生じます。
次に関係するのは「閏年(うるうどし)」です。
旧暦は1年を354日と定めており、これは新暦の365日より11日も少なく、ここでまたずれが生じます。

このずれは2年目に22日、3年目には33日にものぼります。旧暦は3年に1度閏月を設けて1年を13ヶ月にするので、4年目にずれは11日間に戻ります。
したがって年によりますが、旧暦と新暦には最大33日分のずれが生じます。

以上のことから、新暦が導入された際のずれと旧暦の閏年によるずれを合わせると、旧暦と新暦には約1〜2ヶ月分のずれが生じることになります。
これを踏まえて旧暦の七夕を現在の月に換算すると、新暦の7月下旬〜9月上旬のどこかに七夕があることになります。

旧暦の季節区分は1〜3月が春、4〜6月が夏、7〜9月が秋、10〜12月が冬なので、七夕は秋の季語になるのです。
七夕をテーマにした有名俳句集【5選】
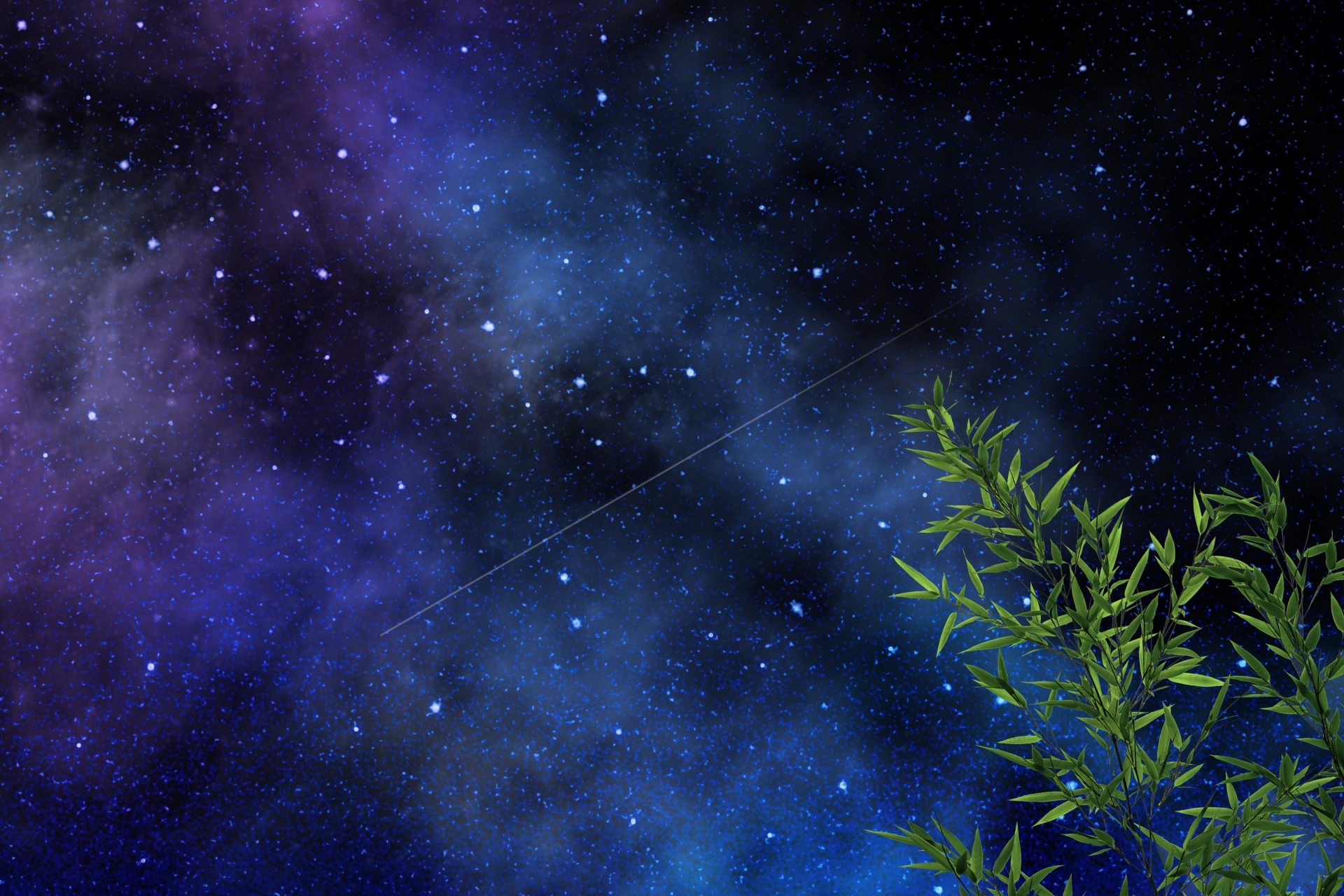
【NO.1】小林一茶
『 七夕や 野にもねがひの 糸すすき 』
季語:七夕(秋)・すすき(秋)
現代語訳:今日は七夕だなあ。竹竿には願いの糸、野原にも願いの糸のようなすすきが揺れている

【NO.2】山口青邨
『 七夕の 一粒の雨 ふりにけり 』
季語:七夕(秋)
現代語訳:七夕の日に一粒雨が降ったのだなあ

【NO.3】遠藤若狭男
『 七夕や 渚を誰も 歩み来ず 』
季語:七夕(秋)
現代語訳:七夕だなあ。渚は誰も歩いてこない

【NO.4】高橋淡路女
『 ぬばたまの くろ髪洗ふ 星祭 』
季語:星祭(秋)
現代語訳:ぬばたまのように真っ黒な髪を洗う。今日は星祭の日だ

【NO.5】品川鈴子
『 希ふこと 少なくなれり 星祭 』
季語:星祭(秋)
現代語訳:今日は七夕だが、昔に比べて願うことが少なくなった

旧暦のズレで生じる間違えやすい季語【8選】

バレンタイン(春)
バレンタインは、2月14日に行われる行事です。
感覚的にはまだ冬ですが、立春を過ぎているため春の季語として扱われます。
どうしても冬であることを表したい場合は、季重なりになりますが寒さなど冬を表す季語を使うとよいでしょう。
ゴールデンウィーク(春)
ゴールデンウィークは年によって日にちが変わりますが、だいたい4月の終盤から5月5日頃にかけての長期休暇です。
ちょうど春から初夏に移り変わる季節ですが、立夏である5月5日よりも前に始まるため、春の季語として扱われます。
こどもの日や端午の節句はちょうど立夏にあたるため夏の季語になることにも注意しましょう。
苺(夏)
現在のイチゴはハウス栽培のものが主流となっているため、一年中流通しています。
しかし、普通に栽培すると旬の季節は5月から6月となるため、夏の季語として扱われます。
栽培方法の変化により季節感を間違いやすい作物があるので、旬の時期を調べてみるとわかりやすいですよ。
五月雨(夏)
季語に5月と入っているので、5月に降る春の雨という印象をもつかもしれません。
しかしこれは旧暦の5月なので、季節は1〜2ヶ月ずれます。
五月雨とは梅雨の雨のことで、夏の季語になります。同じく「五月晴れ」も5月のからっとした晴れのことではなく、梅雨の晴れ間を表す夏の季語です。
朝顔(秋)
朝顔といえば夏の花。
夏休みの自由研究で育てた方も多いのではないでしょうか。
朝顔は7〜9月に花を咲かせますが、旧暦の季節に当てはめるとこれらの月は秋の季語になります。
朝顔は秋の訪れを告げる花として詠まれていたのです。
盂蘭盆会(秋)
盂蘭盆会(うらぼんえ)とは、「お盆」の正式名称です。
8月中旬に行われるこの行事は、現在では夏休みの期間中になるため夏だと思いがちですが、立秋を過ぎているため季語の世界では秋の行事です。
同じように「盆踊り」「盆休み」なども秋になるので、暑さを詠みたいときは別に季語を入れて強調しましょう。
紅葉散る(冬)
「紅葉」は秋の季語ですが、紅葉した葉が散る様子は冬の季語になります。
葉を詠むか散っていく様子を詠むかによって季節が変わってしまうため、どちらが主題なのか意識して取り入れましょう。
七五三(冬)
七五三のお参りといえば、11月15日に行われます。
現在では11月は秋と考えますが、旧暦の11月は新暦の11月下旬から1月上旬に相当するので、冬の季語になります。
さいごに

今回は七夕が秋の季語である理由について解説してきました。
新暦と旧暦で季節が異なる季語は他にもあります。
歳時記の索引を眺めるだけでもたくさん見つけられるので、ぜひ歳時記のページを繰って季語に関する知識を深めていきましょう。