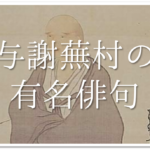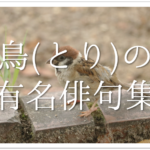俳句は令和となった現代でも愛好家の多い詩歌です。
俳句を実際にたしなむ人はもちろん、鑑賞するだけの人もたくさんいらっしゃると思います。
普段さほど俳句に興味がないという人でも名句ともなればおのずと記憶に刻み込まれている句がいくつかはあるでしょう。
今回は与謝蕪村の有名な一句、「夕立や草葉をつかむむら雀」を紹介していきます。
夕立や
草葉をつかむ
むら雀 与謝蕪村 pic.twitter.com/snmPzq14bF
— 桃花 笑子 (@nanohanasakiko) July 20, 2014
本記事では、「夕立や草葉をつかむむら雀」の季語や意味・表現技法・作者などについて徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「夕立や草葉をつかむむら雀」の季語や意味・詠まれた背景

夕立や 草葉をつかむ むら雀
(読み方:ゆうだちや くさばをつかむ むらすずめ)
こちらの句の作者は「与謝蕪村(よさぶそん)」です。
与謝蕪村は江戸時代中期に活躍した俳人の一人です。大阪に生まれ江戸で俳句を学び旅をすることも多く、晩年は京都で暮らしました。
季語
この句の季語は「夕立」、季節は夏です。
夕立は、夏の午後から夕方にかけて起こる荒れた天気のことです。
現代では午後から夕方のにわか雨のことを言いますが、古来は雨がふらなくても突風や雷だけでも夕立ということがありました。

また、夕立は別名を白雨(はくう・ゆうだちと読ませることもある)ともいいます。
意味
こちらの句を現代語訳すると・・・
「夕立がやってきたことだ。雀の群れが雨宿りのために草の葉をつかんで隠れようとしている。」
という意味になります。
「むら雀」は、漢字で書くと「群雀」。雀が一羽ではなく、集団、群れになっているということです。

「ムラスズメ」という鳥がいるわけではありません。
この句が生まれた背景
こちらの句は、与謝蕪村が安永5年(1776年)の時に詠んだ作品になります。
この年、蕪村は61歳。弟子も多く作風も完成を見て、俳人・与謝蕪村として熟していた時の作であるといえます。
この句は、「続明烏」(ぞくあけがらす)という句集に収められています。

続明烏は与謝蕪村の弟子でもあり、公私にわたってつきあいの深かった高井几菫(たかい きとう)という人物が蕪村の一門の俳人の句を集めて編集した句集のことです。
実は、「続明烏」に収録されたときは「白雨や草葉を握むむら雀」という表記でした。
「白雨」とは、先ほどご説明した通り「夕立」のことです。空が白い・明るいのに降る雨ということです。
「はくう」と音読みにしたり、「しらさめ」とそのまま訓読みにしたりする例もありますが、「白雨」と書いて「ゆうだち」と読ませることもありました。
その後、この句は天明4年(1784年)刊行の「蕪村句集」には「夕だちや草葉をつかむむら雀」の表記で収められています。

「蕪村句集」は、天明3年(1783年)に亡くなった蕪村の一周忌の時に弟子の高井几菫が蕪村の句をまとめた句集です。
「夕立や草葉をつかむむら雀」の表現技法

こちらの句で用いられている表現技法は・・・
- 「夕立や」での切れ字「や」の初切れ
- 「むら雀」の体言止め
になります。
「夕立や」での切れ字「や」の初切れ
切れ字とは、俳句の用語で、「…だなあ」という意味の感動の中心を表す言葉です。
(※「かな」「や」「けり」が切れ字の代表的なものです)
この句は「夕立や」の「や」が切れ字にあたります。
「夕立がやってきたことだなあ。」「激しい夕立だなあ。」というように、作者は夕立に心を動かされてこの句を詠んでいます。
また、切れ字のあるところで句が切れることを句切れと言います。この句は初句に「や」がついて、そこで切れるため、「初句切れ」の句であるといえます。
この句のように「や」は初句にくることが多く、リズムを調える働きもあります。
「むら雀」の体言止め
体言止めとは、体言つまり名詞で文を終了することです。
体言止めを用いることで印象を強めたり、余韻を残したりする働きがあります。
今回の句では「むら雀」という言葉で終わる体言止めの句になります。
「夕立や」という初句で夕立が急に降ってきたことやその激しさに対する驚きがあり、作者の視線は空に向けられています。
しかし、その後気づくのは雨を避ける雀たちの姿。句を体言止めで終え、その余韻で小さな生き物へのいとおしみの視線も感じられます。
「夕立や草葉をつかむむら雀」の鑑賞文

【夕立や草葉をつかむむら雀】の句は、夕立のはげしさとそれに耐えようとするけなげな雀たちの様子が詠まれた句です。
急な天候の変化を前に、雀たちは非力です。それでもなんとか雨を避けようと草の葉の陰に隠れようと必死です。
草の葉をつかんで隠れたところでどれだけ雨を避けられるのか、はたまた体の小さい雀には有効な雨宿りの方法なのかと微笑ましく眺めたのかもしれません。
弱いものもそれなりに置かれた環境の中で生き抜く知恵を凝らし、困難状況に立ち向かっているのです。
「つかむ」という言葉に、必死さや自らの力で困難を乗り越えようとする小さきものたちの逞しさが感じられます。
急な激しいにわか雨とそれに慌てふためいて草の葉に隠れようとする小さな雀たち。光景が絵のように浮かんできます。
実際、与謝蕪村は絵を描いて生計を立てていたこともあり、俳句を賛した(書き添えた)絵、俳画を始めた人物でもあります。

独学で絵を習得したようなので、生まれ持っての才能があったのでしょう。
「夕立や草葉をつかむむら雀」の補足情報

「雀」は季語にならない
雀は一年を通して見られる身近な鳥の一つであるため 、「雀」という言葉単独では特定の季節の季語になりません。
しかし、他の言葉と結びつくことで、季節ごとの姿に応じて様々な季語として詠まれます。
ここでは、他の言葉と結びついて季語になった雀に関する季語をいくつか紹介していきます。
- 「雀の子」「子雀」: 春に生まれた雛のことです。親鳥に見守られながらよちよちと歩く姿や、黄色い嘴で餌をねだる様子は、春ののどかで微笑ましい情景を象徴します。
- 「親雀」: 子育てに励む親鳥の姿で、雛を見守る愛情深い様子が詠まれます。
- 「雀の巣」: 人家の軒先などに巣を作る様子から、新しい生活の始まりや春の訪れを感じさせます。
- 「稲雀」「秋雀」: 黄金色に実った稲穂に群がる雀のことです。 農家にとっては厄介な存在ですが、たわわに実った稲穂と雀の群れは、秋の豊かな風物詩として多くの俳句に詠まれてきました。
- 「寒雀」「冬雀」: 冬の寒さの中、餌を探して人家の近くに集まる雀のことです。もともとは食用としての雀を指す言葉でしたが、現在ではその愛らしい姿が詠まれることが多くなっています。
- 「ふくら雀」: 寒さをしのぐために羽毛に空気を含ませ、丸々と膨らんだ雀の様子です。厳しい冬の中にも温かみや愛らしさを感じさせる季語です。
このように、雀は季節ごとに俳句の世界に彩りを与えてきました。

暮らしのすぐそばにいる雀の姿を通して、季節の移ろいを感じ取ることができるのです。
「群雀」の俳句を紹介
「むら雀」「群雀」を詠んだ句は数が少なく、「夕立や」の句もめずらしい部類です。
ここでは、「群雀」が詠まれた俳句を2つ紹介していきましょう。
【No.1】飯田蛇笏
「案山子(かかし)たつれば 群雀空に しづまらず」
季語:案山子(秋)
意味:案山子を立てると、雀の群れが空で静まらずに飛び交っている音がする。

案山子は主に鳥避けとして立てられるもので、秋の季語です。雀たちは穀物を食べたがっていますが案山子があることで降りてこられず、空を飛び交っている様子を詠んだ句です。
【No.2】佐野美智
「晴れし日の 群雀沈め 葱(ねぎ)畑」
季語:葱畑(冬)
意味:晴れた日に、雀の群れが沈んでいるネギ畑だ。

作者「与謝蕪村」の生涯を簡単にご紹介!

(与謝蕪村 出典:Wikipedia)
与謝蕪村は、享保元年(1716年)摂津国、現在の大阪府に生まれました。
本名を谷口信章といい、蕪村は40歳近くなってから名乗った雅号です。江戸中期に活躍した俳人、画家です。
江戸時代のはじめに活躍し俳諧の祖と言われる松永貞徳や、その後の江戸前期に活躍し俳諧の芸術性を高めていった松尾芭蕉に強くあこがれていたといわれます。
写実的で絵のような句をよくし、俳画(俳句を賛した絵)を始めたともいわれています。
あこがれの芭蕉の足跡をたどる旅をしたり、丹後地方、讃岐にいたこともありましたが、その後は京都に永住。天明3年(1784年)68歳で永眠しました。
与謝蕪村のそのほかの俳句

(与謝蕪村の生誕地・句碑 出典:Wikipedia)
- 鳥羽殿へ五六騎いそぐ野分かな
- 花いばら故郷の路に似たるかな
- さみだれや大河を前に家二軒
- 菜の花や月は東に日は西に
- 笛の音に波もよりくる須磨の秋
- 涼しさや鐘をはなるゝかねの声
- 稲妻や波もてゆへる秋津しま
- 不二ひとつうづみのこして若葉かな
- 春の海終日(ひねもす)のたりのたりかな
- 御火焚や霜うつくしき京の町
- 寒月や門なき寺の天高し
- 古庭に茶筌花さく椿かな
- ちりて後おもかげにたつぼたん哉
- あま酒の地獄もちかし箱根山
- 夏河を越すうれしさよ手に草履
- ゆく春やおもたき琵琶の抱心
- 斧入れて香におどろくや冬立木