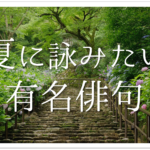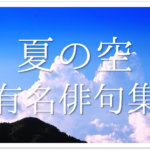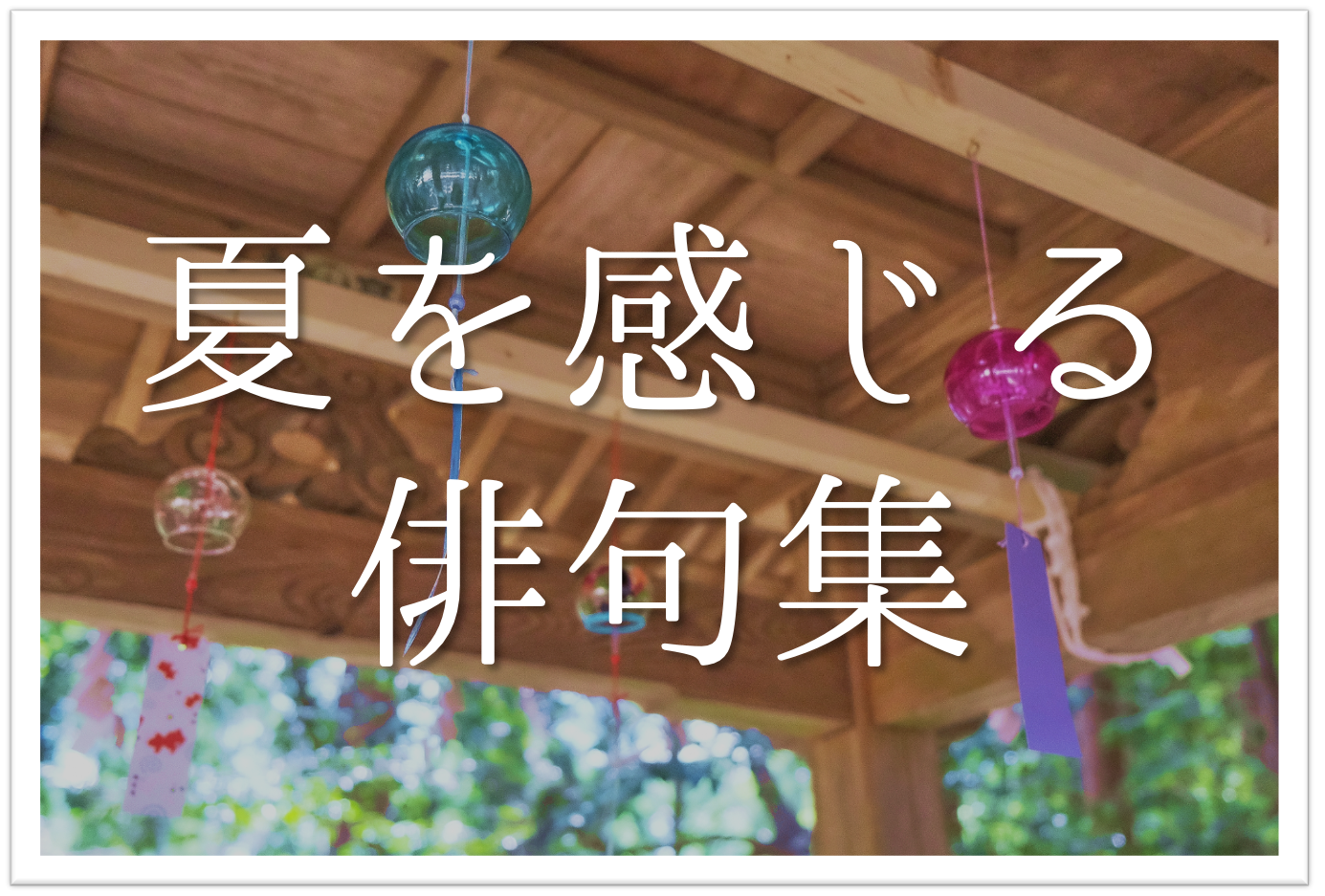
夏には自然現象から行事まで、多くの種類の季語があります。
古くから使われる季語や、最近になって夏の季語として認められたものなど、バラエティ豊かです。
今回は、そんな夏を感じる季語を含むオススメ俳句を30句紹介していきます。
息苦しいほどの熱風。
『匙なめて 童たのしも 夏氷』山口誓子(やまぐち せいし)
『夏河を 越すうれしさよ 手に草履』与謝野蕪村…ちょっと「涼」を感じる夏の俳句 pic.twitter.com/We5pXcC6G5
— シェルワンコ (@cher_wanko) July 3, 2018
時間がゆっくり流れる病院にいると、一段と凄く感じる蝉の鳴き声。
が、うるさいとは思わない。
蝉の生態を小学生の時に知った。
以下のような俳句を作って先生に褒められてたな~
夏になると思い出す…「短命に
思い切り泣く
蝉の声」 pic.twitter.com/wRC9ZLcQnd— えいりあんぼぶ (@alienbob_tweet) August 17, 2016

夏を感じる季語を含む有名俳句【10選】


【NO.1】 井原西鶴
『 長持へ 春ぞ暮れ行く 更衣(ころもがえ) 』
季語:更衣(夏)
意味:長持に春の服をしまうと、春が暮れていってしまう気がする衣替えの日よ。

春物の洋服をしまって夏物を出していると、春が終わってしまったなぁという気持ちになるのは江戸時代の頃から変わらないようです。
【NO.2】正岡子規
『 ほろほろと 手をこぼれたる いちごかな 』
季語:いちご(夏)
意味:ほろほろと手からこぼれていくイチゴであることよ。

イチゴの旬は冬と思われがちですが、本来は初夏が旬です。そのため、季語も初夏のものとなっています。正岡子規の時代はまだハウス栽培のものはなかったため、露地もののイチゴをたくさん渡されたのでしょうか。
【NO.3】日野草城
『 樹も草も しづかにて梅雨 はじまりぬ 』
季語:梅雨(夏)
意味:木も草も静かにしている。梅雨が始まった。

【NO.4】松尾芭蕉
『 駿河路や 花橘も 茶の匂ひ 』
季語:花橘(夏)
意味:駿河の道よ。良い香りのする橘の花までもお茶の香りのようだ。

橘とは6月の梅雨の頃に咲く強く甘い香りのする花です。そんな橘の花でも、お茶の名産地として名高い駿河、現在の静岡県ではお茶の香りに負ける、というユーモアあふれる句になっています。
【NO.5】松尾芭蕉
『 閑さや 岩にしみ入る 蝉の声 』
季語:蝉(夏)
意味:山寺の静けさよ。大きな岩にしみ入るような蝉の声がする。

芭蕉の有名な一句です。山形県の立石寺で詠まれた一句で、とても多い石段を登った先の蝉の声しかしない静寂の風景を詠んでいます。
【NO.6】炭太祇
『 炎天に 照らさるる蝶の 光りかな 』
季語:炎天(夏)
意味:炎天下に照らされている蝶の羽根が反射している光であることよ。

炎天下のすべてが日の光によって照らされている中で、ひときわ光を反射しているものが蝶の羽根であるという、幻想的な光景を詠んでいます。
【NO.7】夏目漱石
『 雲の峰 雷を封じて 聳え(そびえ)けり 』
季語:雲の峰(夏)
意味:入道雲が、雷をその雲の中に封じてそびえ立っている。

雲の峰とは入道雲のことです。入道雲の下は雷雨になりますが、外から見ているとまるで雷を封じているように見える、詩的な表現の句になっています。
【NO.8】高浜虚子
『 温泉の 客の皆夕立を 眺めをり 』
季語:夕立(夏)
意味:温泉に来ていた客が、みんな夕立を眺めている。

急な夕立で傘を持っていなくて困っているのか、夕立を眺めながら風呂上がりの火照った体を冷ましているのか、どちらにも取れる句です。作者の視野には入っていない温泉に入っているお客さんも、お風呂の中から夕立を眺めているかもしれません。
【NO.9】山口素堂
『 目には青葉 山ホトトギス 初鰹 』
季語:青葉(夏)・ホトトギス(夏)・初鰹(夏)
意味:目に映るのは青葉、聞こえてくるのは山にいるホトトギス、味覚は初鰹の夏が来た。

季語が三つも重なる夏の有名な俳句です。視覚、聴覚、味覚の三つを同時に詠むことはめずらしく、この句をより有名にしています。
【NO.10】与謝蕪村
『 夏河を 越すうれしさよ 手に草履 』
季語:夏河(夏)
意味:夏の川を素足で越える嬉しさよ。手に草履を持って。

川遊びか、増水した川を越えようとしているのか、どちらにしても草履を脱いで素足で川を渡っています。素足で川に入るという子供の頃を思い返しているのか「うれしさよ」と句切れで強調しているのが特徴です。
夏を感じる季語を含む一般俳句作品【10選】


【NO.1】
『 父ビール 僕はラムネの 夏休み 』
季語:ラムネ(夏)
意味:父はビールを飲み、僕はラムネを飲む夏休みだ。

【NO.2】
『 浴衣掛け 宿下駄からころ 夜の湯町 』
季語:浴衣(夏)
意味:浴衣を引っ掛け、宿で借りた下駄をからころと音を立てながら夜の温泉街を歩く。

伝統的な温泉街に行った際の句です。これから温泉巡りをするのか、一風呂浴びたあとに浴衣を引っ掛けてお土産屋さん巡りをするのか、いろいろな光景が浮かんできます。
【NO.3】
『 暗やみに 開演を待つ 扇子かな 』
季語:扇子(夏)
意味:明かりが消えた劇場で、開演を待っている扇子であることよ。

明かりが消え、まさにこれから開幕といったところで扇子がクローズアップされています。今まで扇いでいた扇子を閉じ、ぎゅっと握って開演を待つ、そんな無意識の行動を読んだ句です。
【NO.4】
『 大空を 星に返して 蛍消ゆ 』
季語:蛍(夏)
意味:あの大空の星に返ってしまったのだろうか、蛍の光が消えてしまった。

蛍を星に例えている句です。実際には羽休めなどで光を発しなくなった光景を、大空の星に返ってしまったという感性が光ります。
【NO.5】
『 寺の軒 夕立避ける 鳩の列 』
季語:夕立(夏)
意味:寺の軒先に、夕立を避けるように鳩が列をなして止まっている。

急な夕立で作者もお寺の軒先を借りたのでしょうか、同じように夕立をやり過ごすように鳩が列をなして止まっている、そこに自分も並んでいるという面白さがあります。
【NO.6】
『 水面打つ 雨を底より 見るプール 』
季語:プール(夏)
意味:水面を打つ雨を、水の底から潜水して見上げるプールの面白さよ。

水面に当たる雨を下から見るという、普段は見られない光景を詠んでいます。泳いでいる最中に雨が降ってきてしまっても、水の中にいれば雨粒を受けない面白さがある句です。
【NO.7】
『 百葉箱 閉じてノートに 記す虹 』
季語:虹(夏)
意味:百葉箱を閉じて、ノートに虹が出たと記録する。

百葉箱とは、温度計などを直射日光や飴、雪などから守る白い箱です。記録として付けるノートに、雨の後に虹が出たと書く青春の一頁の句になります。
【NO.8】
『 島の子も 旅の子も日焼け かゆいかゆい 』
季語:日焼け(夏)
意味:島に住む子供も、旅行で来た子供も、みんな日焼けしてかゆいかゆいと言っている。

レジャーに訪れた先で、現地の子供たちと仲良くなって遊び、日焼けしている夏休みの風景です。「かゆいかゆい」と二回繰り返しているあたりからお互いに背中をかきあっているような可愛らしさを感じます。
【NO.9】
『 うどん打ち 讃岐路に寄る 麦の秋 』
季語:麦の秋(夏)
意味:うどんを打つ、香川県に寄り道する麦の秋よ。

小麦といえばうどん、うどんといえば香川県ということで、麦の秋である初夏の爽やかな香川県の道を連想させます。
【NO.10】
『 紫陽花まみれ かつてナウマンゾウの庭 』
季語:紫陽花(夏)
意味:紫陽花がたくさん咲いている。かつてここはナウマンゾウの庭だった。

ナウマンゾウとは、1万5千年ほど前まで日本に生息していた大型のゾウで、野尻湖の発掘が有名です。野尻湖以外にも、東京都心の新宿などからも見つかっているので、紫陽花が咲いているまさにその場所をかつてはナウマンゾウが闊歩していたのでしょう。
夏を感じる季語を含む一般俳句作品【おまけ10句】


【NO.1】
『 夏休み 告げて確かな 草いきれ 』
季語:夏休み(夏)
意味:夏休みが来たことを確かに告げるような草いきれだ。

【NO.2】
『 近づきし 小さな小さな 夏祭り 』
季語:夏祭り(夏)
意味:開催が近づいている小さな小さな夏祭りだ。

「小さな」を2回繰り返していることから、地域で行う夏祭りよりもさらに小規模なお祭りが想像できます。小さなお寺や神社で行われる夏祭りでしょうか。小さなお祭りでも子供たちにとっては楽しみなお祭りです。
【NO.3】
『 宿題もおやつも 金魚鉢の前 』
季語:金魚鉢(夏)
意味:宿題もおやつを食べるのも金魚鉢の前でやる。

金魚鉢の前に陣取って、宿題をしておやつを食べている様子を詠んでいます。中の金魚をながめてリラックスしている様子が浮かぶ句です。どんな時でも金魚鉢の前から離れないため、作者は金魚が好きな子供なのでしょう。
【NO.4】
『 スイカ割り 地面を割って やいのやんや 』
季語:スイカ割り(夏)
意味:スイカ割りをしている。地面に棒を叩きつけてやいのやんやとヤジが飛ぶ。

スイカ割りで方向を間違え、地面を打ってしまったときの様子を詠んでいます。「やいのやんや」という表現から大勢が様子を見守って楽しんでいる様子が伺える一句です。
【NO.5】
『 晩夏暮れ プールの匂いの 子ども駆け 』
季語:晩夏(夏/)プール(夏)
意味:夏の終わりの夕暮れに、プールの匂いをさせた子供たちが駆け抜けて行く。

プールは衛生上塩素の匂いがかなりキツく付きます。そんなプールの匂いをさせた子供たちがかけていく中で、ゆっくりと夏の終わりの夕日が暮れていく郷愁の念を掻き立てる一句です。
【NO.6】
『 朝顔の 点眼するよに 沁みる青 』
季語:朝顔(秋)
意味:朝顔の青色が、目薬をさしたように目に沁みるなぁ。

目に飛び込んできた鮮やかな青い朝顔を目薬に例えた面白い一句です。はっと目が覚めるような青色は、目薬をさしたあとの爽やかさも視覚に与えたことでしょう。美しい青だったことが伺えます。
【NO.7】
『 とりあえず ありおりはべり 夏期講習 』
季語:夏期講習(夏)
意味:とりあえず「ありおりはべり」を覚える夏期講習だ。

「ありおりはべり」とは古文の文法を覚える時に使われる言葉です。とにかく基礎を暗記するところから始めようと、暑いさなかの夏期講習で頑張っている学生たちの様子が浮かんできます。
【NO.8】
『 元気良く 向日葵の花 微笑んで 』
季語:向日葵(夏)
意味:元気よく向日葵の花が微笑むように咲いている。

暑い真夏では植物もどこかぐったりとしがちです。そんな中で背を伸ばして黄色の大きな花を咲かせている向日葵は、元気よく微笑むように咲いているなぁと感心している一句になります。
【NO.9】
『 友を待つ カフェの窓越し 道路炎(も)ゆ 』
季語:炎ゆ(夏)
意味:友人を待つカフェの窓越しに見る道路は、熱気で揺らめいて見える。

「炎ゆ」とは炎天下など暑い夏の日に道路が揺らめいて見える現象を表した季語です。作者はカフェという涼しい室内にいるからこそ、内と外の対比が想像できる一句になっています。
【NO.10】
『 陶枕に 居座るねこの ほぼ溶けて 』
季語:陶枕(夏)
意味:陶器で出来た枕に居座る猫は暑さのあまりほぼ溶けたような格好をしている。

「陶枕(とうちん)」とは夏に涼しさを求めて使う陶器でできた枕ですが、ここでは猫のための涼しいグッズでしょう。冷たい場所にいるのに猫は暑さを感じて溶けるように眠っている様子が伺える句です。
以上、夏を感じるおすすめ俳句集でした!


今回は、夏を感じる季語の俳句を、有名なもの10句、オリジナル俳句を20句紹介しました。
昔から使われている季語からラムネ、プールなど最近の季語まで幅広く取り上げてみました。
夏の俳句を詠むときはカタカナの季語も使ってみてはいかがでしょうか。