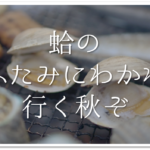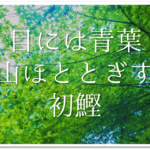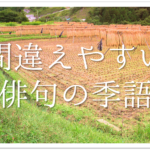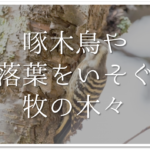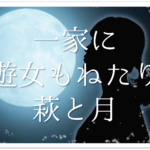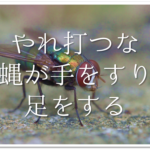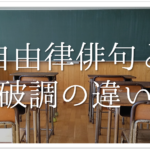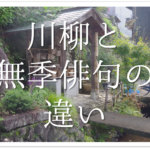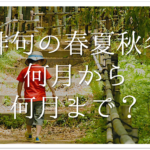俳句と言えば、季語を1つ入れて5・7・5の17音が基本の定型詩になります。
しかし、中には1つの俳句の中に2つ以上の季語が存在することもあります。
向日葵も陰に入りたし酷暑かな
( … うーむ、これでは季重なり🤔 )
#photography #coregraphy#俳句 #写真俳句 pic.twitter.com/bZ6ABcldqo
— あおぞらMew (@SkyBlueSky1010) July 25, 2018
季語の使い方を誤ると季語それぞれの持ち味がぶつかり合い、双方の良さを殺してしまい、良くない俳句が出来上がってしまいます。
そこで今回は、俳句における季重なりのルールや注意点などについて簡単に分かりやすく解説していきます。

目次
俳句の季重なりとは

季重なりとは、1つの俳句の中に2つ以上の季語が存在することを言います。
例えば、以下の句・・・。
【作者】松尾芭蕉
『 蛤の ふたみにわかれ ゆく秋ぞ 』
季語:蛤(春の季語)・ゆく秋(秋の季語)
この俳句の中には「蛤(はまぐり)」と「ゆく秋」という2つの季語が入っています。そのため、この句は季重なりと言えます。

この句の場合は「蛤」は「ふたみ」という掛詞を詠むために使用されています。「ハマグリの蓋と身が分かれるように私も二見浦へ旅立とう」という意味のため、主な季語は「ゆく秋」となるのです。このように、季重なりの中でも特定の言葉に掛けるために季語を2つ使用することもあります。
ちなみに、この句は季重なりの中でも、全く異なる季節の季語を入れた俳句なので、「季違い」とも呼ばれています。
俳句の季重なりには2パターン(種類)がある

季重なりには、「同じ季節の季語を重ねる場合」と「違う季節の季語を重ねる場合」があります。
同じ季節の季語を重ねる場合
まずは、同じ季節の季語を重ねている例として松尾芭蕉の句を挙げます。
【作者】松尾芭蕉
『 山里は 万歳遅し 梅の花 』
季語:万歳(春の季語)・梅の花(春の季語)
この句には「万歳」「梅の花」という2つの春の季語が含まれています。

「万歳」とは新年を祝う行事で、主役の万歳大夫と脇役の才蔵との二人組で行われ、その家が千年も万年も栄えるようにと賀詞を述べるものです。才蔵の鼓に合わせて舞ったり歌ったり、滑稽な問答を交わしたりもします。
これらは本来であれば新年に来るべき行事ですが、山里では梅の花が咲く頃にようやく巡業が回ってくる、という意味になるため、主題は「梅の花」となります。
強い季語であるため、この句の季語は「梅の花」です。
違う季節の季語を重ねる場合
次に、季節の違う季語を重ねている場合をみていきましょう。時期の違う季語がある例として高浜虚子の句を挙げます。
【作者】高浜虚子
『 花の如く 月の如くに もてなさん 』
季語:花(春の季語)・月(秋の季語)

この句は4月下旬に詠まれているため、ここで詠まれている「花」は桜であるという暗黙の了解が働きます。春の季語である「花」と秋の季語である「月」が並んでいますが、先に「花」を詠んでいるため、春の様子を詠んでいると判断されてこの句の季語は「花」になるのです。
違う時期の季語が並ぶ場合は、作者がどちらの季節を詠みたいと思っているか、意味を考えてみましょう。
俳句の季重なりのルール

俳句に季語は何個までOK?
もちろん季語は1つの俳句につき基本的には1個ですが、季重なりの句でもほとんどの場合は2個以内です。
ただ、かなり珍しい3個の季語を使った有名な俳句がありますので、ここで紹介します。
【作者】山口素堂
『 目には青葉 山ほととぎす 初鰹 』
季語:青葉・ほととぎす・初鰹(夏の季語)
この俳句の中には、「青葉・ほととぎす・初鰹」という3つの夏の季語が使われています。

「青葉」は目で鑑賞するもので視覚を刺激し、「山ほととぎす」の声は耳で聞き聴覚を刺激する、そして「初鰹」は口で味わうものであり、味覚を楽しませてくれます。この句は五感の中の3つまで盛り込んだ、実に感覚的な句であるという高い評価を受けています。
季語の重複(かぶり)は良くない?
季語は俳句の最も重要な構成要素なので、むやみやたらに季語を重複させてしまうと、鑑賞する側はどの季語に焦点を当てて読めば良いのかわからなくなってしまいます。
季重なりにすることでそれぞれの季語が互いに持ち味を打ち消し合い、一句を台無しにしてしまうことがあるのです。
しかし、中にはそれぞれの季語がお互いを活かし合うような絶妙な取り合わせの俳句や、季節同士がお互いを邪魔し合わずに共存している句もあります。
そのため、一概に季語の重複は良くないとは言い切れない部分があります。
季重なりでもOKな句とダメな句の違い
名句とされるものの中には、季重なりのものも数多くあるため、必ずしも季重なりが悪いという訳ではありません。
俳句の中に明らかに「強い季語」と「弱い季語」があり、どちらが主役か明確である場合には、季語同士がお互いを邪魔しないという理由で季重なりがOKとなります。
【OKな句】
猫の子が 手でおとすなり 耳の雪
→「雪」という強い冬の季語があることで、「猫の子」という弱い春の季語が、強い季語を支える役割を担っている。
【NGな句】
新じゃがや 野風の先の 青葉山
→「新じゃが」という季語が持つ土臭さが、「青葉」という季語の持つ清々しさに負けてしまっている。
初心者は季重なりをしない方が良い

俳句には「季語は1つ」という考え方がスタンダードです。
そのため、俳句のルールに厳しい句会などでは、季重なりの俳句というだけで、内容を吟味せずに問答無用でダメとなる可能性もあります。
また、そもそも季語同士が相乗効果を発揮するような季重なりの句を作るのは、かなり上級者でないと難しいです。

そのため、初心者の方は失敗する可能性が高いので、季重なりの句は作成しない方が無難と言えるでしょう。
『現代俳句大事典』の季重なりの項。
季重なりが好まれない理由が一応述べられている。要するに主題がボヤケる!と。でも無条件に排されている訳ではないようだ。チョット曖昧な説明だなぁ…#俳句 #haiku #jhaiku #kigo pic.twitter.com/tt5VGsbnqr— 蘭ノ丞 (@akugyo_zanmai) May 29, 2018
また、自分で俳句を作るときには【季語の季節】に気をつける必要があります。
例えば「花火」や「朝顔」は秋の季語ですが、「夏祭り」や「夏休み」など夏の時期であることを主張したいというときもあるでしょう。この場合は夏を意味する季語を入れて夏であることを強調する必要があります。

季語は旧暦に従って設定されているため、1ヶ月程度のズレが発生してどうしても現在の気候と合わないものが出てきてしまいます。そのような時に季重なりという形でどちらの季節を詠みたいかを主張する方法もあると覚えておいてください。ただし、季語を重ねることは上級者向けのため、どうしても主張したいことがあるという場合に留めておきましょう。
季重なりの有名俳句【5選】

【NO.1】水原秋桜子
『 啄木鳥や 落ち葉をいそぐ 牧の木々 』
季語:啄木鳥(秋)
意味:キツツキが木を叩く音が聞こえる。そして冬支度を急ぐように牧場の木々が落葉している。

【NO.2】松尾芭蕉
『 一家に 遊女もねたり 萩と月 』
季語:月、萩(秋)
意味:同じ一軒の宿に遊女と泊り合わせた。おりしも庭には萩の花が咲き、月も照らしているよ。

【NO.3】内藤鳴雪
『 夕月や 納屋も厩も 梅の影 』
季語:梅(春)
意味:月は秋ほど美しくないかもしれないが、春も出る。しかし梅の花は秋には咲かない。

【NO.4】上島鬼貫
『 行水の 捨てどころなし 虫の声 』
季語:虫の声(秋)
意味:行水をしてタライの水を捨てようと思ったが、庭のあちこちで虫の声がしていて、虫を驚かせたり流してしまったりするのが可哀想で捨てられない。

【NO.5】与謝蕪村
『 みじか夜や 毛虫の上に 露の玉 』
季語:みじか夜(夏)
意味:夏の短い夜が明け始めた庭先では、毛虫の毛の上で露がキラキラと輝いているよ。

以上、俳句の季重なりについて解説しました!
季重なりを上手く使いこなせるようになれば、俳句の表現の幅が広がりますが、初心者のうちは少し難しいです。