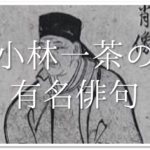五・七・五の十七音に、季節の語や心情を詠みこむ「俳句」。
国語の授業だけでなく趣味としても親しまれ、作品を応募するコンクールも増えています。
今回は、有名俳句の一つ「大根引き大根で道を教えけり」という句を紹介していきます。
2017.11.16 定点📷 比叡山
『大根引大根で道を教へけり』
一 茶◇生活感あふれる一茶さんらしい情景が見えるハム🐭 pic.twitter.com/8wjKlJn7vJ
— とりあん(ツイ時々不具合、フォロー制限中。お返事忘れますのでご寛恕のほど。) (@torian48) November 16, 2017
本記事では、「大根引き大根で道を教えけり」の季語や意味・表現技法・作者などについて徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「大根引き大根で道を教えけり」の俳句の季語や意味・詠まれた背景

大根引き 大根で道を 教えけり
(読み方:だいこひき だいこでみちを おしえけり)
この句の作者は、「小林一茶(こばやし いっさ)」です。
小林一茶は「江戸時代の三大俳人」の1人と言われている人物です。江戸三代俳人とは小林一茶、松雄芭蕉、与謝野蕪村の3人を指します。
一茶の作品が芭蕉や蕪村と大きく違うところは、俳句になじみのない江戸時代の庶民でも理解できる簡潔な表現を使用していることです。

この表現方法は「一茶句調」と呼ばれており、俳句が庶民の間に普及するきっかけになったと言われています。
季語
この句の季語は「大根引き」、季節は「冬」です。
「だいこん」の読み方が一般的ですが、「だいこ」「おおね」とも言います。
「大根」は、アブラナ科の野菜で、古くから日本でも好まれており、たくさん栽培されてきました。品種が多く、おでんの具材としても冬の食卓にかかせない存在です。
意味
こちらの句を現代語訳すると・・・
「大根を引き抜いている農家の方へ道を尋ねると、抜いた大根を持ったまま「あっち」と大根で方角を指し示して教えてくれたよ」
という意味です。
「大根引き」というのは、大根の収穫、もしくは大根を収穫している人という意味です。引き抜いた大根を持ったまま大根で方角を指し示したとされています。
この句が詠まれた背景
この句は、「七番日記」に収められており、文化11年(1814年)に詠まれました。一茶が50歳前後の作品とされています。
「七番日記」は、一茶の48歳から56歳までの9年間にわたる句日記(自筆稿本)です。一茶の句日記としては、最大のもので代表作も数多く含まれています。
一茶は俳諧行脚をして生活を立てていましたが、収入は不安定でした。この「七番日記」から「おらが春」を執筆していたころが、一茶の最も充実した時期とされ俳諧者として名が知られるようになり収入も安定していきました。
作品も一茶独自の境地で「一茶調」と呼ばれる多彩な作品が多く生み出されました。

この句もユーモアあふれる一茶調の句であり、行脚の途中での出会いを詠んだものと考えられます。
「大根引き大根で道を教えけり」の表現技法

「教えけり」の「けり」の切れ字
切れ字は「や」「かな」「けり」などが代表とされ、句の切れ目(文としての意味の切れ目)や、作者の感動の中心を強調するときに使います。
「けり」は詠嘆の表現に使われる言葉です。
句切れなし
意味やリズムの切れ目を句切れといいます。
この句では、三句(五・七・五の最後の五文字)の最後に切れ字が含まれるため、句切れなしとなります。
「大根引き大根で道を教えけり」の鑑賞文

一茶は江戸に住んでいましたが、俳諧行脚をして各地を巡り、句を詠んでいます。
この句も、道中で出会った大根の収穫をしているお百姓さんとのやり取りの情景を詠んでいます。
せっせと働くお百姓さんは、とても忙しかったのでしょうか。大根を持ったまま、道を教えてくれています。
そんな1コマを切り取った、くすっと笑ってしまう一茶の様子や一生懸命なお百姓さんの様子が目に浮かぶ句です。
一茶の句は、時に子供のような童心あふれるユーモアやひがみ・自嘲・弱者への同情などの感情をこめて庶民生活をわかりやすく詠んでいます。

次に、この句に関連する豆知識(補足情報)を紹介していきます。
「大根引き大根で道を教えけり」の補足情報

この句は「川柳」にもなっている
川柳とは、創始者「柄井川柳」が始めた五・七・五の形式の表現です。
川柳は俳句とは違い、季語や切れ字などの約束事がなく、口語を用いて自由に表現します。時事風刺や笑いを中心に、作品を作ります。
明和二年(1765年)に発行された「俳風柳多留」という川柳集に「ひんぬいた大根で道を教えられ」という川柳が載っています。
一茶の俳句がここから着想を得たものなのか、または川柳を俳句にしたのか、たまたま一致したのかはわかっていません。
ただ、この俳句と川柳が表現する違いは、一茶の俳句が全体の情景を詠んでいるのに対して、川柳は「大根で道を教えるため方角をさしたおもしろさ」を表現しているところです。
この句が詠まれた場所はどこ?
この句では、前詞にも具体的な地名がなく、どこで詠まれた俳句なのかよくわかっていません。
しかし、『七番日記』での一茶の滞在歴と文化11年12月に詠まれたという記録を付き合わせると、一茶は文化11年8月に俳諧本出版のために江戸に訪れ、12月に故郷へ帰郷していることがわかります。
そのため、この句は信州への帰省途中に詠まれた句なのかもしれません。

江戸時代の道は現在のように管理されているものが少なく、細い道や脇道も多くあったので、土地の人に道を聞くシチュエーションがよくあったのでしょう。
江戸近郊と野菜

大根として有名な品種に「練馬大根」があります。
江戸時代では、江戸という巨大都市に供給するために現在では宅地化されている郊外で小松菜や大根、人参、ナス、ウリ、ゴボウ、枝豆などさまざまな野菜が作られていました。
ここで一茶が会った農家の人も、おそらく江戸へ売るための大根を作っていたものと考えられます。
こうして作られた野菜は朝になると江戸の街へ売りに出されたり、惣菜を作る店に卸されたりして、江戸という大都市の食を支えていました。
一茶は江戸暮らしが長かったため、こういった野菜や惣菜によくお世話になっていたことでしょう。

農家に対するどこか気安い道を聞く口調に思えるこの句も、長い江戸暮らしで培った経験があってこそなのかもしれません。
江戸時代の大根
江戸時代の江戸で有名な大根としては、前述の「練馬大根」や「亀戸大根」「高倉大根 」「東光寺大根」「志村みの早生ダイコン」「汐入大根」などが知られています。
それぞれ地名の通り、練馬や亀戸・八王子市高倉・日野東光寺・板橋区志村・隅田川流域で作られていた大根です。
一茶が江戸から信濃へと帰ろうとしている最中に道を聞いたとするならば、おそらく甲州街道を使ったのでしょう。
甲州街道には日野宿や八王子宿があるため、「高倉大根」や「東光寺大根」の生産者に話しかけたのかもしれません。
これらの大根は現在のように太く長い大根ではなく、細い大根でした。

そのため、「大根引き」で抜かれた大根は細く、道を示すのには分かりやすい形をしていたのかもしれませんね。
作者「小林一茶」の生涯を簡単にご紹介!

(小林一茶の肖像 出典:Wikipedia)
小林一茶は1763年に信濃国(現在の長野県)に生まれました。本名を、小林弥太郎といいます。
3歳の頃に生母を亡くし、5年後に父は再婚しますが継母になじめず、15歳で江戸へと奉公に出されます。奉公先で俳句に出会い、俳句を学んだとされていますが、記録があまり残っていません。
29歳で14年ぶりに故郷へと帰り、父が他界します。父の遺産相続問題で12年もの間、継母や弟と争うこととなりました。この争いは、一茶の作風にも影響を与えています。
その後、信濃へ定住し遺産問題も和解したため、52歳で結婚します。その後、2度結婚して5人の子供を授かりますが、最後に生まれた娘以外、みな幼くして亡くなっています。
晩年は家庭の不遇や火事など、苦労が絶えませんでした。そして1828年、65歳にて亡くなりました。
小林一茶のそのほかの俳句

(一茶家の土蔵 出典:Wikipedia)