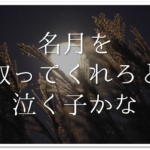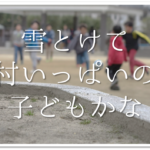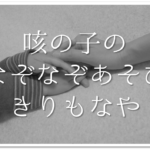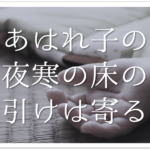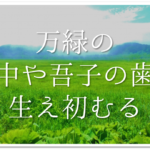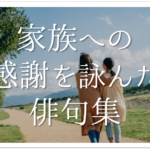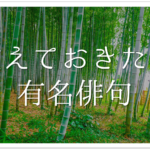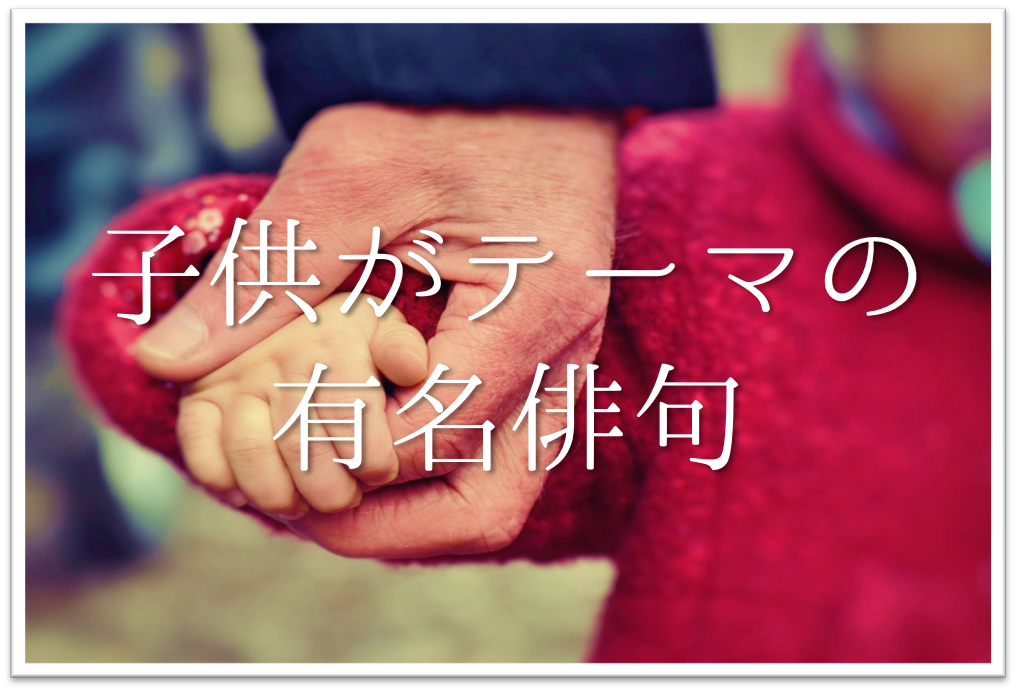
日常のちょっとした出来事やその時に感じたこと、季節の風景など、俳句にはさまざまなテーマがあります。
どの時代にも、子供や赤ちゃんをテーマとする俳句が数多く詠まれています。
子供の笑顔や泣き顔、成長を感じたときに生まれた物語は、俳句という一つの形を通して、語り継がれています。
今回は、子供をテーマにしたおすすめの有名俳句20句と一般オリジナル俳句作品10句をご紹介いたします。
楊洲周延 Yoshu Chikanobu. 名月をとってくれろと泣く子かな ‘gimme that harvest moon’ cries the crying child. 俳句 haiku poem by 一茶 Issa pic.twitter.com/folHgJ8z89
— 阿部 隆 Abe Takashi (@abeaten_) June 18, 2016

子供をテーマにした有名俳句【前半10句】

【NO.1】小林一茶
『 鳴く猫に 赤ん目をして 手まりかな 』
季語:手まり(新年)
現代語訳:猫が女の子が遊ぶ手鞠にじゃれついて、遊んでほしいと鳴いてきた。女の子は猫に「アッカンベー」をして、鞠つきをしているよ。

【NO.2】小林一茶
『 寝せつけし 子の洗濯や 夏の月 』
季語:夏の月(夏)
現代語訳:子供が寝静まった夏の晩。洗濯物を干そうと外に目をやると、あぁ、今夜は月がきれいだなぁ。

【NO.3】小林一茶
『 名月を とってくれろと 泣く子かな 』
季語:名月(秋)
現代語訳:背中に背負われた幼な子が、煌々と輝く満月を指し「お月様を取ってくれ」とねだっているよ。

【NO.4】小林一茶
『 雪とけて 村いっぱいの 子どもかな 』
季語:雪とけて(春)
現代語訳:長い長い冬がようやく終わり、待ちかねていた春の到来。村の方々から子供たちが出てきて遊びまわっていることよ。

【NO.5】小林一茶
『 あこが手に 書て貰ふや 星の歌 』
季語:星の歌(秋)
現代語訳:吾が子の手に、星の歌を書いてもらったよ。

【NO.6】中村汀女
『 咳の子の なぞなぞあそび きりもなや 』
季語:咳(冬)
現代語訳:風邪を引いた子供の看病でなぞなぞ遊びの相手をしているが、なかなか放してくれないよ。

【NO.7】中村汀女
『 咳をする 母を見上げて ゐる子かな 』
季語:咳(冬)
現代語訳:咳をする母親のことを心配そうに見上げている子供がいるよ。

【NO.8】中村汀女
『 引いてやる 子の手のぬくき 朧かな 』
季語:朧(春)
現代語訳:繋いでいる子の手が温く感じられる。空を見上げると、今夜は朧月の夜だなぁ。

【NO.9】中村汀女
『 あはれ子の 夜寒の床の 引けば寄る 』
季語:夜寒(秋)
現代語訳:晩秋の夜、寒さを感じ、子供の眠っている様子を見ると、いかにも寒そうだ。布団を自分の方に引くと、すっと寄ってきたよ。

【NO.10】中村汀女
『 手渡しに 子の手こぼるる 雛あられ 』
季語:雛あられ(春)
現代語訳:子供の手のひらに雛あられを乗せたところ、手があまりにも小さく、雛あられがこぼれてしまったよ。

子供をテーマにした有名俳句【後半10句】

【NO.11】中村草田男
『 万緑の 中や吾子の歯 生え初むる 』
季語:万緑(夏)
現代語訳:万緑鮮やかな夏のある日、抱き上げた我が子の口の中に、白い歯が生えているのをみつけたよ。

【NO.12】中村草田男
『 赤んぼの 五指がつかみし セルの肩 』
季語:セル(夏)
現代語訳: 赤ん坊の小さな手がセルを着る自分の肩をしっかりとつかんでいることよ。

【NO.13】中村草田男
『 馬多き 渋谷の師走 吾子と佇つ 』
季語:師走(冬)
現代語訳:師走に子供と一緒に訪れた渋谷は、いつもよりも馬の往来が多いな。

【NO.14】中村草田男
『 童話書く セルの父をば よぢのぼる 』
季語:セル(夏)
現代語訳:童話を書く父親の背中によじ登ってくる子供がいる。

【NO.15】中村草田男
『 朧三日月 吾子の夜髪ぞ 潤へる 』
季語:朧三日月(春)
現代語訳: 朧三日月の夜、我が子の髪の毛が艶やかに潤っている。

【NO.16】斉藤三樹雄
『 赤ん坊に 太陽が来る 髭が来る 』
季語:無季
現代語訳:赤ん坊に太陽が来る、そして父親となる。

【NO.17】山西雅子
『 子の冬や 吸切啜の喉 波打てる 』
季語:冬(冬)
現代語訳: 寒い冬、乳首に吸い付き、ごくごくと喉を波打たせながら母乳を飲む我が子。

【NO.18】中林明美
『 小春日の 鐘撞堂から 赤ん坊 』
季語:小春日(冬)
現代語訳:小春日和のある日、鐘撞堂を訪れると、中から赤ん坊が出てきたよ。

【NO.19】橋本幹夫
『 羽子板の うらに長女の 名前書く 』
季語:羽子板(新年)
現代語訳:初めて生まれた女の子。羽子板を買ってあげたので、裏にその名前を書いたよ。

【NO.20】黒澤麻生子
『 ひとの子の 思わぬ重さ 春満月 』
季語:春満月(春)
現代語訳:自分の子ではないけれど、抱っこをしてみたら、意外と重たかった。あぁ、今日は満月だなぁ。

子供をテーマにした一般俳句作品【10句】

【NO.1】
『 啓蟄や 追いかけっこの 子供たち 』
季語:啓蟄(春)
意味:啓蟄の日になったなぁ。子供たちが追いかけっこをしている。

【NO.2】
『 如月の 雨子の声も 透きとおり 』
季語:如月(春)
意味:如月の日に降る雨だ。子供の声も透きとおる気がする。

【NO.3】
『 子供らは 夕陽追いかけ 暮遅し 』
季語:暮遅し(春)
意味:子供たちは夕日を追いかけている。日が暮れるのが遅くなったなぁ。

【NO.4】
『 庭先で 子供と食べる 柏餅 』
季語:柏餅(夏)
意味:意味:庭先で子供と食べる柏餅だ。

【NO.5】
『 手花火や 闇に明るき 子らの声 』
季語:手花火(夏)
意味:手で持つ花火で遊んでいる。花火に照らされた闇に明るい子供たちの声がする。

【NO.6】
『 健やかな 園児らの声 五月晴 』
季語:五月晴(夏)
意味:健やかな園児たちの声がする五月晴れだ。

過ごしやすい気候で窓を開けているのか、子供たちの元気な声が聞こえてきています。爽やかな陽気を感じさせる句です。外で遊ぶ子供たちの様子が浮かんでくる一句です。
【NO.7】
『 枝豆や 下戸も子供も 手を伸ばし 』
季語:枝豆(秋)
意味:枝豆がある。お酒を飲まない下戸も子供も手を伸ばしている。

【NO.8】
『 子供たち 笑顔戻りし ハロウィン 』
季語:ハロウィン(秋)
意味:子供たちにも笑顔が戻ったハロウィンの日だ。

【NO.9】
『 立冬や 今日も子供は 半ズボン 』
季語:立冬(冬)
意味:立冬が来たなぁ。今日も子供は半ズボンだ。

【NO.10】
『 息白し 子供は窓で 絵を描いて 』
季語:息白し(冬)
意味:息が白くなるくらい寒い。子供は窓に絵を描いている。

息が白くなるくらい寒くなると、外と中の気温で結露が生じ、指で絵を描けるようになります。寒さをものともせずに絵を描く子どもの姿が可愛らしい一句です。どのような絵を描いているのか気になるところです。
以上、子供をテーマにしたおすすめ俳句集でした!

母が子を、子が母を想う気持ちは、いつの時代も、誰にでもある普遍的なものです。
今回は、江戸時代の作品から現代の作品まで、子供をテーマとする俳句を厳選して紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?