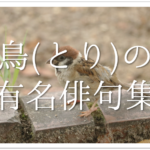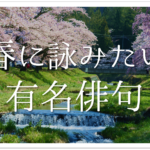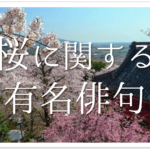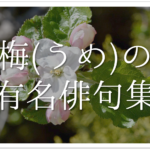鶯(ウグイス)は春を代表する鳥で、古くから「梅と鶯」の題材で親しまれてきました。
鶯は季語の分類としては春を通して使える「三春」であり、俳句が成立した江戸時代から現代まで多くの句が詠まれているのが特徴です。
【鶯:2月の季語】平地で鳴き始める季節が早春であることから、春告鳥の別名がある。
鶯の声遠き日も暮にけり(与謝蕪村)
鶯や柳のうしろ藪の前(松尾芭蕉)
鶯や朝寝を起す人もなし(正岡子規) pic.twitter.com/aNTcuIc3ym— うちゆう (@nousagiruns) February 27, 2014
今回は、そんな「鶯(ウグイス)」を季語に使ったおすすめ俳句を30句紹介していきます。

鶯(ウグイス)を季語に使った有名俳句【15選】


【NO.1】 松尾芭蕉
『 鶯を 魂にねむるか 矯柳(たおやなぎ) 』
季語:鶯(春)
意味:嬌やかに眠るように糸をたらしている柳は、夢の中で鶯となって鳴いているのだろうか。

矯柳とはしなやかな柳という意味です。風に揺られてゆったりと眠っている柳を人に例えて、鳴いている鶯を柳の夢に見立てる幻想的な俳句になっています。
【NO.2】宝井其角
『 鴬の 身を逆(さかさま)に はつね哉 』
季語:鶯(春)
意味:鶯が宙返りをしながら初めての鳴き声を聞かせていることだ。

同じく春の鳥で逆さまに枝に止まることのあるメジロと混同している句とも、春が来て活発に動き回って鳴いている鶯を詠んだ句とも言われています。客観的な描写に欠けるとの批判もある句ですが、作者の楽しげな様子が伝わってくる一句です。
【NO.3】与謝蕪村
『 鶯の 声遠き日も 暮にけり 』
季語:鶯(春)
意味:鶯の声を聞いているうちに声が遠くなり、日が暮れてきてしまった。

【NO.4】井上士朗
『 どこでやらで 鶯なきぬ 昼の月 』
季語:鶯(春)
意味:どこからか鶯がないている。昼の月が見える空に。

周りを見渡しても昼の白い月が見えるばかりの空に、どこからともなく鶯の鳴き声が聞こえてくる一句です。鶯の声はよく通るため、周りに木がないのに聞こえてくるという不思議さを表しています。
【NO.5】正岡子規
『 鶯や 籔(やぶ)の隅には 去年の雪 』
季語:鶯(春)
意味:鶯が鳴いている。薮の隅にはまだ去年降った雪が残っているのに。

鶯の鳴き始めである初春の句でしょうか。春を告げる鳥が鳴いている片隅にはまだ去年の雪という冬が残っている、対比が面白い俳句です。
【NO.6】高浜虚子
『 鶯や 文字も知らずに 歌心 』
季語:鶯(春)
意味:鶯が鳴いている。文字も知らないだろうに、素晴らしい歌心を持っていることだ。

鶯の鳴き声を歌に例えた擬人化の句です。文字を知らないだろう鶯が、自分よりも歌心を持っているかのような音色を奏でていることへの驚きを歌っています。
【NO.7】川端茅舎
『 鶯の 声澄む天の 青磁かな 』
季語:鶯(春)
意味:鶯の済んだ鳴き声が響いている、その空はまるで青磁のような美しい青だ。

青磁とは焼き物の一種で、美しい淡い青色をしています。鶯の鳴き声が高らかに響く青空という美しい春の光景です。
【NO.8】泉鏡花
『 うつくしや 鶯あけの 明星に 』
季語:鶯(春)
意味:美しいことだ。鶯の鳴き声が明けの明星と共に聞こえてくる。

明けの明星とは、明け方の空に東からのぼってくる金星のことです。空が白み始める寸前の金星が輝く夜明けから、鶯の声が聞こえてくる幻想的な風景を詠んでいます。

【NO.9】水原秋桜子
『 鶯や 雨やむまじき 旅ごろも 』
季語:鶯(春)
意味:鶯よ。雨がやみそうもない旅装を整えた旅であるよ。

「やむまじき」とは「やみそうもない」という意味です。雨で鶯と共に雨宿りしているのでしょうか、通り雨ではなく長雨に降られてしまった旅の途中を表しています。
【NO.10】星野立子
『 鶯や 起きねばならぬ 窓明り 』
季語:鶯(春)
意味:鶯が鳴いている。まだ眠いが起きなければならない、窓の外も明るくなってきた。

これは身に覚えがある方も多いのではないでしょうか。春眠暁を覚えずとも言いますが、眠いけれど鶯の鳴き声と外の明るさでどうにか起きなければならない、朝の葛藤が手に取るようにわかります。
【NO.11】 日野草城
『 ほがらかに 鶯啼きぬ 風の中 』
季語:鶯(春)
意味:ほがらかにウグイスが風の中で鳴いている。

おだやかな春風に乗って聞こえてくるウグイスの鳴き声を詠んだ一句です。春ののどかさを存分に感じさせる句になっています。
【NO.12】山口青邨
『 鶯は近く 妻もしづか 吾もしづか 』
季語:鶯(春)
意味:ウグイスが近くで鳴いている。妻は静かになり、私も静かになった。

夫婦で話している中でウグイスの声が聞こえてきた時の一句です。ウグイスの鳴き声を聞こうと2人ともそっと耳を澄ませている様子が伺えます。
【NO.13】原石鼎
『 鶯に 雲一つなき 夜明かな 』
季語:鶯(春)
意味:ウグイスが鳴く空は雲一つない夜明けであるなぁ。

【NO.14】久保田万太郎
『 うぐひすや 西にかはりし 風の冷え 』
季語:うぐひす(春)
意味:ウグイスが鳴いている。西から吹いてくる風に変わって冷えてきた。

暖かな風から冷たい風に変わる様子をウグイスの鳴き声と共に詠んでいます。ずっと外でウグイスの鳴き声を聞いていたのか、にわかに天気が急変しているのか、色々な想像ができる句です。
【NO.15】飯田蛇笏
『 遠ければ 鶯遠きだけ 澄む深山 』
季語:鶯(春)
意味:ウグイスが遠くから鳴くほど深い山々に澄んだ声が響く。

この句は作者の実感から詠まれています。遠くから聞こえるウグイスの声と、春を迎えた山々の澄んだ空気が感じられる一句です。
鶯(ウグイス)を季語に使った一般俳句作品【15選】


【NO.1】
『 鶯の 声聞きうれし 朝餉(あさげ)かな 』
季語:鶯(春)
意味:鶯の鳴き声が聞こえてきて嬉しい朝ごはんであることだ。

【NO.2】
『 鶯の 声追いかける ウォーキング 』
季語:鶯(春)
意味:鶯の鳴いている声を追いかけるウォーキングをしよう。

公園か住宅地でしょうか。鶯が鳴いている方に向かってウォーキングをする、寒い冬ではなく春ならではの楽しさを感じる句です。
【NO.3】
『 鶯の 四十五度に 鳴く姿勢 』
季語:鶯(春)
意味:鶯が45度におじぎをして鳴いている姿勢であることよ。

鶯がちょうど鳴いているところを目撃している句です。前傾姿勢で無く鳥ですが、それがまるで45度傾ける丁寧なおじぎをしているように見えたという面白い発想に繋がっています。
【NO.4】
『 うぐいすの 訪ねて回る 谷戸の家 』
季語:うぐいす(春)
意味:鶯が鳴きながら訪ねて回っているよ。谷間の集落の家を。

「谷戸」とは谷間の集落のことで、三方を丘陵や耕作地に囲まれている場所のことです。そんな谷間の家々を訪ねて回るように鶯が鳴きながら飛び回っている長閑な春の風景を詠んでいます。
【NO.5】
『 よく咲きて 鶯の来し 老樹かな 』
季語:鶯春)
意味:よく花が咲いて、鶯がやって来る老樹であることだなぁ。

時期的に梅の樹でしょうか。毎年のように鶯がやってきて、満開の花の中で鳴いている風景が目に浮かびます。毎年の楽しみであることを詠嘆の「かな」から感じる一句です。
【NO.6】
『 鶯の さえずりさえも ただの青 』
季語:鶯(春)
意味:鶯のさえずりさえもただ青空の青の中に吸い込まれていくことだ。

ただひたすらに広がる青い空の下で、どこからか聞こえてくる鶯のさえずりさえ吸い込まれていく、そんな情緒あふれる風景です。「ただの青」という体言止めが、圧倒されるほどの青空を連想させます。
【NO.7】
『 老鶯(ろうおう)や 千年水を もらい水 』
季語:老鶯(春)
意味:5月に鳴く鶯よ。千年水という湧き水をもらい水として飲んでいる。

老鶯とは春をすぎて鳴いている鶯のことで、夏の季語になります。実際に年老いている鶯というわけではないでしょうが、「千年水」という各地にある湧き水を飲んでいることから「老い」「千年」と掛けています。
【NO.8】
『 老鶯の まっただ中の 棚田かな 』
季語:老鶯(春)
意味:夏の鶯の鳴き声の真っ只中にある棚田であることだ。

田植えの頃の田んぼの風景が目に浮かびます。初夏に鳴く鶯は声量がけたたましくなってきますが、その大きな鳴き声の真っ只中の棚田という日本の原風景の俳句です。

【NO.9】
『 未来思へば 鶯の近づくよ 』
季語:鶯(春)
意味:未来を思うと、鶯が鳴く季節が近づいてくるよ。

卒業や別れを連想させる破調の一句です。段々と近づいてくる春という未来に思いを馳せる、そんな感慨深さが破調として表れています。
【NO.10】
『 ウグイスの 声響きいざ 第一歩 』
季語:ウグイス(春)
意味:鶯の鳴き声が響く季節になった。いざ、第一歩を踏み出そう。

春が来て、卒業や入学など新たな環境に身を置く希望にあふれた俳句です。「いざ第一歩」が句またがりになっています。鶯の鳴き声に背を押されるように一歩を踏み出そうという力強さを感じる句です。
【NO.11】
『 吊り橋を 渡れば鶯 やんややんや 』
季語:鶯(春)
意味:吊り橋を渡ればウグイスがやんややんやとはやし立てるように鳴いている。

【NO.12】
『 鶯の 声で目覚める 清き朝 』
季語:鶯(春)
意味:ウグイスの声で目覚める清い朝だ。

ウグイスの鳴き声で目を覚ます、とても良い一日の始まりの様子を詠んだ句です。明け方から鳴き始めるため、空気が澄んでいたのでしょう。
【NO.13】
『 鶯や 団地に響く リコーダー 』
季語:鶯(春)
意味:ウグイスが鳴いているなぁ。団地にはリコーダーの音が響いている。

小学生のときにリコーダーを持って帰って練習したことがある人も多いでしよう。ウグイスの鳴き声とともに、リコーダーが響く微笑ましい一句です。
【NO.14】
『 ウグイスが 鳴いた気がして 澄ます耳 』
季語:ウグイス(春)
意味:ウグイスが鳴いた気がして耳を澄ましている。

「今ウグイスが鳴いた気がする」と耳を澄ましています。初めてウグイスが鳴く「初音」だったのかもしれません。
【NO.15】
『 鶯は テレビかもしや 裏山か 』
季語:鶯(春)
意味:今のウグイスの声はテレビから聞こえてきたのか、もしや裏山で鳴いているのか。

テレビの音なのか、実際に鳴った音なのか分からないという体験をしたことがある人も多いのではないでしょうか。今の鳴き声はどちらだと耳を澄ませています。
以上、鶯(ウグイス)をテーマにした俳句集でした!


今回は、「鶯(ウグイス)」を題材にした俳句を、有名なもの15選とオリジナルの俳句15選にわけて紹介してきました。
鶯は「春の象徴」としてまた「春の訪れという別れと出会いの季節の象徴」としてなど、多くの題材で詠まれる季語です。
鶯の鳴き声が聞こえてきたら、その時に感じたことを俳句にしたためてみてはいかがでしょうか。