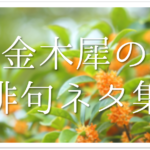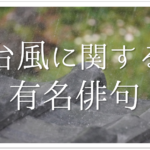古くから日本人に愛され、多くの文学に題材として描かれる「月(つき)」。
月見、朧月、月光、中秋の名月、宵月夜、雨月、十六夜、立待月などなど…俳句も例外ではなく、月に関する季語は多くあります。
そこで今回は、「月」に関する有名俳句&一般俳句作品【全40句】を紹介していきます。
![]()
リス先生
有名俳句だけではなく、一般の方が作った作品まで紹介していくよ!ぜひ最後まで読んでね!
月の季語を使った有名俳句【20選】
![]()
【NO.1】松尾芭蕉
『 鎖(じょう)あけて 月さし入れよ 浮御堂 』
季語:月(秋)
現代語訳:満月寺の僧よ、錠を開けてこの素晴らしい月の光を御堂の中に入れよ。
![]()
俳句仙人
月は四季それぞれに趣がありますが、最も美しいとされるのは秋の月なので、単に「月」とあればそれは秋の季語になります。浮御堂とは満月寺の建物で、琵琶湖の湖上に突き出す形で建立されています。琵琶湖に浮かぶように立つ浮御堂に降り注ぐ月光は、さぞ幻想的でしょう。芭蕉はその美しい光を御堂の中の観音様に届けたかったのかもしれません。
【NO.2】正岡子規
『 藍色の 海の上なり 須磨の月 』
季語:月(秋)
現代語訳:藍色の海の上にあるのだなあ、須磨の美しい月は。
![]()
俳句仙人
海の色を藍色という深い色で描くことで、月の輝きが際立ちます。須磨は兵庫県にある海辺の町。正岡子規は須磨の保養院で療養していたそうです。須磨の月の美しさに心を癒されていたのでしょうか。
【NO.3】富安風生
『 大空の 月の歩みの やや斜め 』
季語:月(秋)
現代語訳:大空に上る月の軌道はやや斜めになっている。
![]()
俳句仙人
月が真上に出ているのではなく、低い位置にある様子を詠んだ句。月の軌道を「歩み」と擬人法で表したところが面白いです。
【NO.4】高浜虚子
『 ふるさとの 月の港を 過るのみ 』
季語:月(秋)
現代語訳:故郷である月の出ている港を、私は横切るだけだ。
![]()
俳句仙人
助詞「の」にはたくさんの意味があるので複数の解釈ができます。今回は二つ目の「の」を「港」を修飾するものととらえました。自分の故郷の港は月が出ていて美しく心惹かれる。にもかかわらず通り過ぎるだけ。何か帰れない理由があるのでしょうか。郷愁が感じられます。
【NO.5】夏目漱石
『 影参差(しんし) 松三本の 月夜かな 』
季語:月夜(秋)
現代語訳:三本の松の影が不揃いである月夜だなあ。
![]()
俳句仙人
「参差」は不揃いな様のこと。月の明るい光に照らされた三本の松。松は背丈や大きさが異なるのでしょう。三本の影が不揃いな様子で地面に映し出されます。木々は一本一本違っているので、影の形が異なるのも当たり前のことなのですが、その当たり前なところに気づいたところに素朴な趣があります。
【NO.6】炭太祇
『 三日月や 膝へ影さす 舟の中 』
季語:三日月(秋)
現代語訳:ほっそりと形のよい三日月よ。舟に乗っていると私の膝へ光が差した。
![]()
俳句仙人
この句の「影」は月光という意味で解釈しました。三日月は細く満月ほど明るくはありませんが、舟で真っ暗な海の上にいれば三日月の光も鮮明に届くのでしょう。
【NO.7】金子兜太
『 三日月が めそめそといる 米の飯 』
季語:月光(秋)
現代語訳:三日月のようにやせ細った体でめそめそしながら飯を食べる。
![]()
俳句仙人
「飯」といえば普通は米のことなので、わざわざ「米の飯」とは言いません。十七音しかない俳句ではなおさら言葉の無駄遣いと言われてしまいます。しかしそこをあえて「米の」とするということは何か意味があるのでしょう。昔は麵やパンが主流で今のように米を当たり前には食べられない時代があったようです。今ほど飽食でない時代、食べ物に飢えていた人がありがたくお米を食べる。その人の様子を三日月と表現したのかもしれません。
【NO.8】渡辺水巴
『 月光に ぶつかつて行く 山路かな 』
季語:月光(秋)
現代語訳:歩みを進めていくと、まるで月光にぶつかるような山道だなあ。
![]()
俳句仙人
夜の山道を上っていくとどんどん標高が高くなって、少しずつ月に近づいていくような気がします。月には触れられなくても、降り注ぐ月光には体が当たっているような感じがします。
【NO.9】宝井其角
『 名月や 畳の上に 松の影 』
季語:名月(秋)
現代語訳:素晴らしい月よ。畳の上には松が影を落としている。
![]()
俳句仙人
「名月」は旧暦八月十五日の中秋の名月を指します。一年の中でこの月が最も澄んでいて美しいとされています。畳に松の影があるということは、作者は庭などに面した戸を開け放って月を見ているのでしょう。月明かりが部屋の中まで差し込む様子が見えます。
【NO.10】加賀千代女
『 川音の 町へ出づるや 後の月 』
季語:後の月(秋)
現代語訳:川の音の響く町へ出ようか。十三夜の月がのぼっている。
![]()
俳句仙人
「後の月」とは旧暦九月十三日の夜に出る月のこと。肌寒さを感じる頃の月で、華やかな名月と異なり寂しい趣があります。寒々しく川音の響く町は、暗くうらぶれた町なのかもしれません。
【NO.11】小林一茶
『 浴(ゆあみ)して 我が身となりぬ 盆の月 』
季語:盆の月(秋)
現代語訳:湯浴みをしてやっと私を取り戻した。盂蘭盆の月が出ている。
![]()
俳句仙人
「盆の月」は旧暦七月十五日の盂蘭盆の夜の月のこと。まだ暑さの厳しいころに出る月なので、「浴」の心地よさが際立ちます。盂蘭盆は先祖の供養で忙しい日だったようで、一日を終えて湯浴みすることで供養の儀式や人とのやりとりの慌ただしさからやっと解放されて我に返った様子が端的に表現されています。
【NO.12】正木ゆう子
『 水の地球 すこしはなれて 春の月 』
季語:春の月(春)
現代語訳:水の惑星と呼ばれるこの地球の少し離れたところに、春の月がある。
![]()
俳句仙人
秋の月が澄んでいる様子を愛でられるのに対し、春の月は柔らかく濡れたような風情を愛でます。それを思うと水の惑星である地球としっとりとした春の月は似た者同士で、距離がぐっと縮まった感じがします。「すこしはなれて」というひらがな表記も、春の空気や月のやわらかい雰囲気を醸しています。
【NO.13】黒田杏子
『 木の家に 棲み木の机 おぼろ月 』
季語:おぼろ月(春)
現代語訳:木製の家に暮らし、机も木製のものを使っている。外にはぼんやりとした月が出ている。
![]()
俳句仙人
「おぼろ月」とは春の霞んだ月のことで、薄い絹に包まれているようなやわらかさが感じられます。木の家も木製の机も温かみのある素材でできたもので、そのぬくもりとおぼろ月のやわらかさが響きあう句になっています。
【NO.14】阿部みどり女
『 夏の月 昇りきつたる 青さかな 』
季語:夏の月(夏)
現代語訳:夏の月の昇りきった輝きはなんと青いことか。
![]()
俳句仙人
「夏の月」は暑い夜に青白く輝く涼しげな月、または赤みを帯びてのぼる月のことです。この句は「青さ」とあるので前者のことでしょう。夏の空の高い位置で輝く月はいかにも涼しげです。
【NO.15】山本洋子
『 冬の月 あまり高きを かなしめり 』
季語:冬の月(冬)
現代語訳:白々と輝く冬の月は、あまりに高いところにあり、私はそのことを悲しんでいる。
![]()
俳句仙人
「冬の月」は冴えわたった空気の中で研ぎ澄まされたように輝く月のこと。その煌々と輝く月が空高くのぼっていると、高さが一層際立ちます。月が遠く感じられてしまって悲しいのでしょうか。
【NO.16】松尾芭蕉
『 名月や 池をめぐりて 夜もすがら 』
季語:名月(秋)
現代語訳:名月が出ているなぁ。月を見ながら池の周りを歩いていたら夜が明けてしまった。
![]()
俳句仙人
月を見ながら池を散歩していたところ夜が明けてきたという、映像のような一句です。月の光が池の水面に反射して、美しい風景だったことでしょう。
【NO.17】与謝蕪村
『 寒月や 門なき寺の 天高し 』
季語:寒月(冬)
現代語訳:冬の寒い夜空に月が出ているなぁ。門のない寺からは空が高く見える。
![]()
俳句仙人
門のない小さなお寺から冬の月を眺めている一句です。さえぎる人工物のない美しい夜空が思い浮かびます。
【NO.18】小林一茶
『 名月を 取ってくれろと 泣く子かな 』
季語:名月(秋)
現代語訳:あのお月様を取っておくれと泣く子がいるよ。
![]()
俳句仙人
この句は作者が自分の娘を背負っているときに月を取ってくれとせがまれた様子を詠んでいます。幼いわが子の可愛らしい主張を詠んでいる様子から、子煩悩であることが伺える句です。
【NO.19】中村汀女
『 外にも出よ 触るるばかりに 春の月 』
季語:春の月(春)
現代語訳:外に出て見てごらんなさい。触れるような大きな春の月が出ている。
![]()
俳句仙人
友人の家から夜帰宅するときに空を見上げた時の一句です。触れられそうな程に大きくみごとな月に、思わず皆に呼びかけている様子を詠んでいます。
【NO.20】松本たかし
『 チチポポと 鼓打たうよ 花月夜 』
季語:花月夜(春)
現代語訳:チチポポと鼓を打って遊ぼうよ、この満開の花の月夜の下で。
![]()
俳句仙人
作者は病で舞台に立つことはありませんでしたが能役者の一家の生まれです。個人的に鼓を打つなどの遊びをしていたようで、この句では満開の桜と月夜の美しさに喜んでいる様子が伝わってきます。
月の季語を使った一般俳句作品【20選】
![]()
【NO.1】
『 月白や 船でくぐりし 大鳥居 』
季語:月白(秋)
意味:月の出る頃の白んだ空よ。その時私は船で大鳥居をくぐった。
![]()
俳句仙人
海にある大鳥居ということは厳島神社の鳥居でしょうか。夜の海の闇、白んだ空、船から見上げる大鳥居の赤。色彩の豊かな一句です。
【NO.2】
『 月光を 直立させて 神の滝 』
季語:月光(秋)
意味:月光を直立させたかのように神聖な滝が一直線に流れている。
![]()
俳句仙人
埼玉に丸神の滝という名瀑があるそうです。詠まれているのはその滝かどうかはわかりませんが、きっと落差の大きい厳かな雰囲気の滝なのでしょう。その立派な柱のような滝に月光が降り注げば、まるで月光が真っ直ぐに立っているように見えます。
【NO.3】
『 月光の 青き世界の 魚となり 』
季語:月光(秋)
意味:月光の降り注ぐ青い世界。私はその世界の中で魚になった。
![]()
俳句仙人
景色が月明かりに満たされると、そこはまるで水槽か海の中かのように錯覚することがあります。その中を魚になって泳げたら心地よさそうです。
【NO.4】
『 待宵や 自転車一つ あぜ道に 』
季語:待宵(秋)
意味:待宵月が出ているなぁ。自転車が1つぽつんとあぜ道に停まっている。
![]()
俳句仙人
「待宵」とは旧暦八月十四日の夜のことで、名月を明日に控えています。満月一歩手前の月に照らされながら畦道にぽつんと止まっている自転車も、翌日の満月を待っているのでしょうか。
【NO.5】
『 十五夜や 天まで届く 松並木 』
季語:十五夜(秋)
意味:今日は十五夜だなあ。名月に照らされた松並木は天まで届きそうだ。
![]()
俳句仙人
名月である十五夜の月。その澄んだ美しい光に照らされた松並木は、どこまでも高くそびえたつように見えます。
【NO.6】
『 名月が コップに入り のめないや 』
季語:名月(秋)
意味:コップを空にかざすと月がコップの中にあるみたいだ。これでは中身を飲めないなあ。
![]()
俳句仙人
素晴らしい月についガラスのコップをかざしたのでしょうか。コップに浮かぶ月の美しさに見とれ、飲むのがもったいなくなります。それともお酒を飲むときのような丸い大きな氷を名月に例えているのでしょうか。氷が大きいと中の飲み物はちびちび飲まざるを得ず飲みづらいです。
【NO.7】
『 諍(いさか)いの 星のかたわら 望の月 』
季語:望の月(秋)
意味:喧嘩する星の横に満月が出ている。
![]()
俳句仙人
「望の月」は満月のこと。星たちが競うように光を放つ横で、満月は悠々と豊かな光を放ちます。星同士の喧嘩がちっぽけに見えます。
【NO.8】
『 海に出る 満月赤く 尾をひけり 』
季語:満月(秋)
意味:海上に出ている満月は赤く尾を引いているなあ。
![]()
俳句仙人
月の位置が低いと大きく赤く見えることがあります。水平線近くに赤く真ん丸な月が大きく出ているのでしょう。尾を引いているということはまわりの空も夕焼けで赤いということでしょうか。
【NO.9】
『 抱きしめられても きっと足りない 春の月 』
季語:春の月(春)
意味:抱きしめられたとしてもきっと足りないだろうなぁ、春の月が輝いている。
![]()
俳句仙人
誰かに抱きしめてほしいけれど、それだけでは私の寂しさは埋まらない。夜はそんな感傷的な気分になります。寂しさも感傷もすべて春の月が包み込んでいるような、甘いやわらかさのある句です。
【NO.10】
『 月おぼろ 杭一本の 船着場 』
季語:月おぼろ(春)
意味:月がぼんやりと霞んでいる。船着場には一本の杭がある。
![]()
俳句仙人
川でしょうか海でしょうか。船着場には霞んだ月が出て全体を淡く照らしています。そこには船を繋いでおく杭が一本あります。一本しかないということは船の数の少ない小さな船着場であるのでしょう。こじんまりとした船着場が淡い月光にすっぽり包まれている穏やかな光景が目に浮かびます。
【NO.11】
『 朧月 シリアの街の 瓦礫にも 』
季語:朧月(春)
意味:抱きしめられたとしてもきっと足りないだろうなぁ、春の月が輝いている。
![]()
俳句仙人
内戦の絶えないシリア。人々は争いで傷つき、街も瓦礫まみれ。そんな傷ついた街にも春の月は淡い光を降らせます。現地の人々を慈しむ気持ちの伝わる句です。
【NO.12】
『 ウミガメは わたしであなたは 夏の月 』
季語:夏の月(夏)
意味:ウミガメのような私を導いてくれるあなたは、まるで夏の月のよう。
![]()
俳句仙人
実態とは異なるそうですが、ウミガメは満月の夜に産卵すると昔から言われています。青い月に導かれて浜にやってくるウミガメに自分を重ね、導いてくれる月を大切な人に重ねているのでしょうか。
【NO.13】
『 どこまでを 秘密としよう 夏の月 』
季語:夏の月(夏)
意味:私のもっている秘密はどこまで打ち明けようか。空には青白い月がのぼっている。
![]()
俳句仙人
清々しいほど青い夏の月の前では、すべて見透かされそうな気もします。秘密を打ち明けてしまおうか、このまま内緒にしておこうか、少しだけ話してしまおうか。そんな風に悩むのは恋の駆け引きでしょうか。
【NO.14】
『 寒月や 外湯巡りに 打って出る 』
季語:寒月(冬)
意味:澄み切った輝きを放つ月よ。私は外湯を巡りに出るよ。
![]()
俳句仙人
「打って出る」という言葉が思い切って寒さに立ち向かう様子を表現していて共感できます。冬の外湯は入るまでに思い切りがいりますが、熱い湯に浸かって月を眺めるのは至福の時間です。
【NO.15】
『 冬三日月 こどもの孤独 おとなの孤独 』
季語:冬三日月(冬)
意味:冬の三日月が出ている。こどもにはこどもの、おとなにはおとなの孤独がある。
![]()
俳句仙人
冬の三日月は細いながらも白い光を鋭く放っています。その様子が孤独な一匹狼に見え、人々の孤独と重なり合うのかもしれません。月も子どもも大人も皆それぞれの孤独を抱えていて、その孤独に思いを馳せています。
【NO.16】
『 夏の月 ライトに見立て リハーサル 』
季語:夏の月(夏)
意味:夏の月をライトに見立ててリハーサルをしよう。
![]()
俳句仙人
文化祭の準備をしているときの一句です。夏は夜になるのも遅く、かなり暗い時間帯まで準備に余念が無い学生たちの様子を詠んでいます。
【NO.17】
『 ストレッチ 見上げる窓の 春の月 』
季語:春の月(春)
意味:ストレッチをしながら見上げた窓には春の月が見えた。
![]()
俳句仙人
ストレッチをする際には数秒ほど動きを止める必要があるため、どこか1点を見つめています。ふと窓の外を見ると月が昇ってきていた様子を詠んだ句です。
【NO.18】
『 名月や 今晩だけは わたくしと 』
季語:名月(秋)
意味:空に輝く中秋の名月よ、今晩だけは私と一緒にいてくれないか。
![]()
俳句仙人
「わたくしと」で止める省略した形が印象的な一句です。1人で名月を見上げている寂しさが伝わってきます。
【NO.19】
『 海境(うなさか)を 照らすべくある 月一つ 』
季語:月(秋)
意味:海と空の境目を照らすためにあるあのひとつの月だ。
![]()
俳句仙人
「海境」とは海と空や地上の境目のことですが、古くは海の神の領域と人の世界を分けるという意味でもありました。空と海を照らす月がその境界を照らしているという幻想的な一句です。
【NO.20】
『 寒月の 生みだしたるは 青き影 』
季語:寒月(冬)
意味:冬の月が生み出しているのは青い影だ。
![]()
俳句仙人
冬の冴え冴えとした月が作る影が青く見えるという作者のイメージを詠んだ句です。寒色というイメージから青を連想したのでしょうか。
以上、月をテーマに詠まれたオススメ俳句集でした!
![]()
リス先生
今回は、月をテーマに詠まれた俳句を40句紹介したよ!
月に関する季語は今回紹介したもの以外にもたくさんあるよ!なんだか日本人の月を愛でる思いの強さを感じるね。
みんなも歳時記を参考に、お気に入りの句を見つけてみてね!!
こちらの記事もおすすめ!