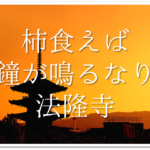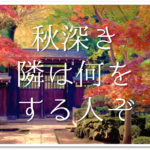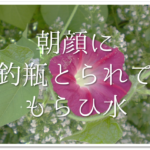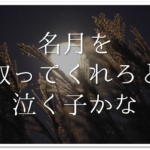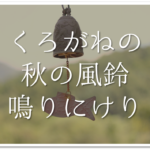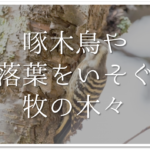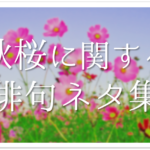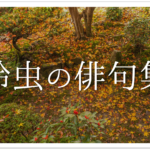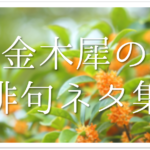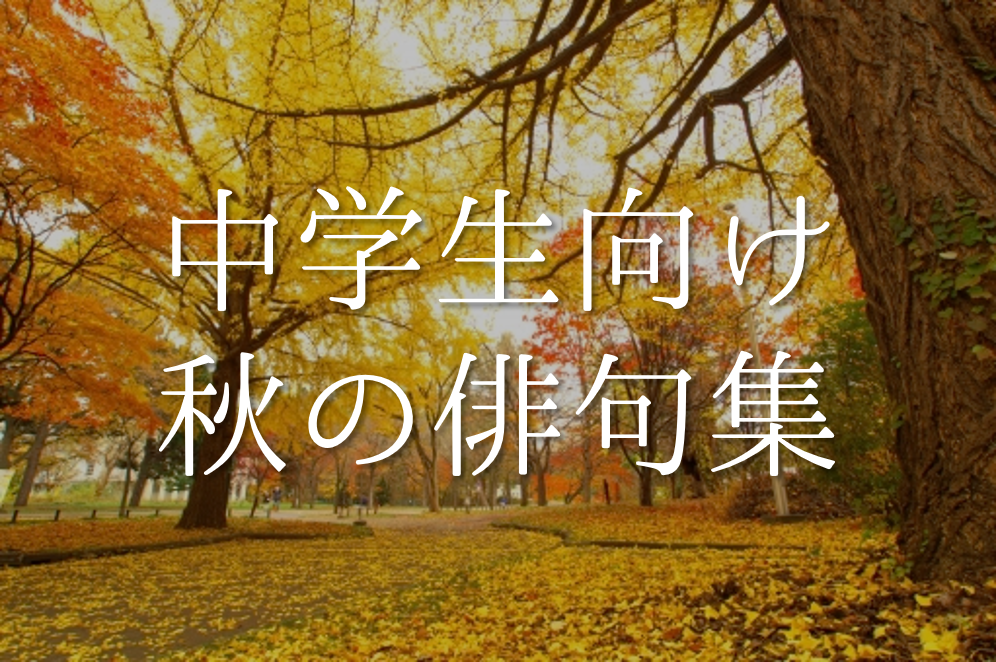
世界最短の文といわれる「俳句」。
最近は俳句ブームともいわれていますが、実際、中学校の授業で俳句鑑賞があったり、宿題に俳句が出たりすることもありますよね。
そこで今回は、中学生向けの「秋の季語」を使ったオススメ俳句を紹介していきます。
山辺に
柿食ひ行けば
風涼し#ファインダー越しの私の世界#写真好きな人と繋がりたい#俳句#秋#山辺の道 pic.twitter.com/tzGcDAR7RY— 観照 融真 / Kwansho Akizane (@nunquevadros) October 7, 2016

俳句に秋らしさを出す!秋の季語を知ろう

俳句には、季節を表す「季語(きご)」を入れて詠むという決まりがあります。
日本には、春夏秋冬と4つの季節があり、それぞれの季節には様々な特徴があります。その特徴を表した言葉…つまり、その「季節らしい言葉」が季語と呼ばれるものです。
例えば、春なら「桜」、夏なら「トマト」などがあります。
その季節を感じさせるものであれば、基本的にどんな言葉を使ってもよいことになっていますが、仮に「スイカ」をつかって夏の俳句を詠もうとしても「スイカ」はひと昔前、お盆すぎから収穫される果物であったため、季語としては秋のものに分類されています。

夏にはスイカであたりまえなのに…と、現代の私たちは季節のずれを感じます。
ですがその逆に、時代の流れに沿って新たに加えられていく季語もあります。(例:「ハローウィン(秋の季語)など」)
現在、季語は「歳時記(さいじき)」という本にまとめられており、季語の辞典のような役割を果たしています。

【補足】無季俳句と有季定型俳句
「無季俳句(あえて季語を使わない俳句)」というものもありますが、通常、季語は俳句を作る上でとても大きな役割を果たします。
例えば、「桜」という季語だと、その色や、はらはらと散る様のはかなさ、あるいは楽しいお花見の情景など「桜」という文字自体が様々なイメージを持ち、それでいて「桜」しか持ちえないイメージを持っています。
作者はそのイメージを使って自分の思いを詠むことができますし、また鑑賞する側にとっても、作者が見た風景や心情を思い浮かべるカギとなります。
まずは季語を含む十七音という基本の有季定型俳句から作ってみましょう。

代表的な秋の季語を紹介!

では実際の秋の季語には、どのようなものがあるのでしょうか?
ここでは、代表的な秋の季語をたくさん紹介していきます。

秋の季語【一覧】
「秋」「月」「名月」「十三夜」「天の川」「流れ星」「星月夜」「残暑」「朝顔」「コスモス」「菊」「秋草」「ほおずき」「つゆ草」「むくげ」「紅葉」「銀杏」「桐一葉」「ねこじゃらし」「梨」「柿」「りんご」「葡萄」「秋刀魚」「南瓜」「栗」「柚子」「小豆」「きのこ」「澄む水」「秋の山」「台風」「美術展」「霊むかえ」(お盆)「鈴虫」「赤とんぼ」「きりぎりす」「蜩」「小鳥来る」「きつつき」「渡り鳥」「白露」「赤い羽根」「運動会」「さわやか」「冬近し」「秋日和」
中学生向け!!有名な秋の俳句集【20選】

【NO.1】正岡子規
『 柿くえば 鐘が鳴るなり 法隆寺 』
季語:柿(秋)
意味:旅で訪れた法隆寺の茶店で一服し柿を食べていると、法隆寺の鐘の音が響いてきた。静寂と澄んだ秋の空気に響くその鐘の音にほのかな旅情を感じます。

【NO.2】松尾芭蕉
『 秋深し 隣は何を する人ぞ 』
季語:秋深し(秋)
意味:秋がすっかり深まった。隣りの人は何をして過ごしているのだろう。なにやら人恋しいものだなあ。

【NO.3】加賀千代女
『 朝顔に 釣瓶とられて もらひ水 』
季語:朝顔(秋)
意味:水を汲もうと井戸にいくと、朝顔のつるが釣瓶に巻きついていました。つるをほどくと折れてしまうのが忍びなく、近所で水を貰うことにしました。

【NO.4】小林一茶
『 名月を とってくれろと 泣く子かな 』
季語:名月(秋)
意味:子どもと十五夜の月見をしていたら、夜空に美しく、くっきりと浮かんでいる月を「取ってくれ、取ってくれ」としきりにせがんで泣いてしまいました。

【NO.5】高浜虚子
『 一枚の 紅葉かつ散る 静かさよ 』
季語:紅葉かつ散る(秋)
意味:ふと見ると一枚の葉が紅葉しているが、散ってゆくものもある。枝にとどまって美しく紅葉する葉もあれば、静かに散る葉もあることを、秋の静寂のなかでしみじみ感じました。

【NO.6】夏目漱石
『 肩に来て 人懐かしや 赤蜻蛉 』
季語:赤蜻蛉(赤とんぼ)(秋)
意味:赤とんぼが偶然肩にとまったので、横目で様子をそっとみてみると、まるで懐かしい人に会って安心してはねを休めているように見えましたよ。

【NO.7】飯田蛇笏
『 くろがねの 秋の風鈴 鳴りにけり 』
季語:秋(秋)
意味:いつしか夏が過ぎ去って、季節外れになった鉄の風鈴は今、涼やかな秋の風に揺られて鳴っています。

【NO.8】山口誓子
『 秋の雲 はてなき瑠璃の 天をゆく 』
季語:秋の雲(秋)
意味:秋の空を見上げていると、雲がちっとも留まらずに、青より深い瑠璃色の空をどこまでも流れていくようだ。

【NO.9】与謝蕪村
『 白露や 茨の棘に ひとつづつ 』
季語:白露(秋)
意味:秋も深くなり、庭一面に朝露が降りました。茨に近づいてみると、鋭い棘のひとつひとつにまで露が付いていました。

【NO.10】水原秋櫻子
『 啄木鳥や 落葉をいそぐ 牧の木々 』
季語:啄木鳥(秋)
意味:啄木鳥(きつつき)が盛んに木をつついています。その軽快な音に誘われたかのように牧場の木々がひらひらと葉を落としています。


【NO.11】松尾芭蕉
『 荒海や 佐渡に横たふ 天の川 』
季語:天の川(秋)
意味:目の前には荒れた海があるなぁ。佐渡の島の上には天の川が横たわっている。

【NO.12】与謝蕪村
『 子狐の かくれ貌なる 野菊哉 』
季語:野菊(秋)
意味:子狐たちがかくれんぼをしているような野菊の咲く花畑だなぁ。

【NO.13】小林一茶
『 ほろほろと むかご落ちけり 秋の雨 』
季語:秋の雨(秋)
意味:ほろほろとむかごが落ちていく秋の雨の日だ。

【NO.14】飯田蛇笏
『 たましひの たとへば秋の ほたる哉 』
季語:秋のほたる(秋)
意味:人の魂とは例えば秋の蛍のようなものなのだろう。

【NO.15】夏目漱石
『 あるほどの 菊投げ入れよ 棺の中 』
季語:菊(秋)
意味:あるほどの菊を投げ入れてくれ、その棺の中に。

【NO.16】中村草田男
『 秋の航 一大紺 円盤の中 』
季語:秋(秋)
意味:秋の航海は、紺色の海が拡がって大きな円盤の中を進んでいるようだ。

【NO.17】正岡子規
『 砂の如き 雲流れゆく 朝の秋 』
季語:朝の秋(秋)
意味:砂のように薄く見える雲が流れていく秋の朝だ。

【NO.18】橋本多佳子
『 星空へ 店より林檎 あふれをり 』
季語:林檎(秋)
意味:星空に向かって店に積まれたリンゴがあふれている。

【NO.19】山口誓子
『 突き抜けて 天上の紺 曼珠沙華 』
季語:曼珠沙華(秋)
意味:突き抜けるような紺色の空に、赤い曼珠沙華が咲いている。

【NO.20】坪内稔典
『 がんばるわ なんて言うなよ 草の花 』
季語:草の花(秋)
意味:がんばるわなんて言わないでくれよ、野に咲く草の花よ。

中学生向け!一般の方のオススメ俳句集【25選】

【No.1】
『 どんぐりを 隠した場所で 待ち合わせ 』
季語:どんぐり(秋)
意味:キャンプなのか、森の散策なのか。どんぐりを友達と拾って遊んだ。友達と自分しかしらない場所にどんぐりを隠してあるのでそこで待ち合せしたという、非常にほほえましい一句です。
【No.2】
『 自転車で のぼる坂道 秋の風 』
季語:秋の風(秋)
意味:自転車をこいで坂道を登っていると、今日は顔に当たる風がひんやりとして心地良く、もう秋なのだなあと思いました。
【No.3】
『 恐竜も きっと眺めた 流れ星 』
季語:流れ星(秋)
意味:秋の夜空を眺めていて、流れ星を見ました。夜空は太古の昔からなにもかわっていないのだから、きっと恐竜もこのような流れ星を眺めていたのだろう。
【No.4】
『 西瓜独り 野分を知らぬ 朝(あした)かな 』
季語:西瓜、野分(秋) ※野分は台風のこと
意味:台風一過の朝、強い風で木や草がなぎ倒されているなかで、もともと畑の地面に転がっていたスイカは平然とどっしりとしています。
【No.5】
『 蜻蛉(とんぼう)や 飛び直しても 元の枝 』
季語:蜻蛉(秋)
意味:トンボはなわばりをもっていて、見張りやすい枝からパトロールのように飛び立っては、また戻ってくる。人間も似て、他のなにかをやってみたいと思っても、気がついたらまた同じ事をやっているというようなことも思い起させる句です。
【No.6】
『 栗飯の まつたき栗に めぐりあふ 』
季語:栗(秋)
意味:皮がきれいにむけた大粒の栗が、炊きあがりの湯気立つご飯のなかにあればうれしい、という気持ちを詠った句。「まつたき」(まったき)は完全なという意味。栗ごはんを食べていると、きれいな大粒の栗が出てきて、思わずニンマリしているといった感じでしょう。
【No.7】
『 夕月夜 スマホの君は 下を向き 』
季語:夕月夜(秋)
意味:夕方に出た月が薄明りの宵に沈みかけていて、とても美しいのに、君はスマホに無中でうつむいたまま。せっかくの夕月夜なのになあ。という心情でしょうか。
【No.8】
『 桜紅葉 さまざまな人 通りゆく 』
季語:桜紅葉(秋)
意味:秋の明るい光の中に、真っ赤な桜紅葉の並木が続いています。さまざまな人が、桜紅葉の美しさに見とれながら通ってゆきます。
【No.9】
『 散歩道 三日来ぬ間に キンモクセイ 』
季語:キンモクセイ(秋)
意味:いつもの散歩道。3日ほど散歩しなかったら、今日はもうキンモクセイが香っている。たった数日で季節は移り変わったのだなあという思いを一句にこめています。
【No.10】
『 去ぬつばめ 忘れないでね 日本を 』
季語:去ぬつばめ(秋)
意味:小学5年生の俳句。女の子の純粋な心情が、一句の中に込められています。子育て中のつばめにはみな関心があるものの、次第にそれは薄れていきます。作者は旅立っていくつばめに語りかけるようにさようならを言っています。また来年おいでね、という気持ちでのさようならなのでしょう。
【No.11】
『 ペットボトル 二本飲み干す 残暑かな 』
季語:残暑(秋)
意味:暦はもうとっくに秋なのに、まだまだ暑くて、気がついたらペットボトル飲料を2本飲んでいた。残暑がきびしいことを、どこかひょうひょうと、しかも絶妙に詠んだ一句です。
【No.12】
『 松ぼくり 夢はワールドカップかな 』
季語:松ぼくり(松ぼっくり)(秋)
意味:ピクニックの最中でしょうか。子どもが道に落ちている松ぼっくりを器用に蹴って追いかけている。いずれはサッカーに夢中な少年へ、そして世界の舞台を夢みる青年になっているのかもしれません。

【No.13】
『 どんぐりを 隠した場所で 待ち合わせ 』
季語:どんぐり(秋)
意味:キャンプなのか、森の散策なのか。どんぐりを友達と拾って遊んだ。友達と自分しかしらない場所にどんぐりを隠してあるのでそこで待ち合せしたという、非常にほほえましい一句です。
【No.14】
『 放課後の ピアノはやまず 秋深し 』
季語:秋深し(秋)
意味:芸術の秋。感性が研ぎ澄まされて、ピアノの練習にも熱が入ります。その音を聴いている作者もまた秋を深く感じているのでしょう。
【No.15】
『 どんぐりを たどり会ひたし トトロかな 』
季語:どんぐり(秋)
意味:山へ散策に行くと、どんぐりが点々と落ちている。一つ一つ拾って、たどっていった先でトトロにあえると嬉しいなという、とてもかわいらしさにあふれた一句です。
【No.16】
『 名月は 時間厳守で 上りたり 』
季語:名月(秋)
意味:秋の名月は時間厳守で昇ってくる。満月の月の出は決まっているので、時間厳守と表現しているところが面白い一句です。
【No.17】
『 絹衣の やうな雲なり 今日の月 』
季語:今日の月(秋)
意味:「今日の月」とは仲秋の名月を表す季語の1つです。月は見えていますが、絹の衣のような薄い雲がかかっている様子を詠んだ句です。
【No.18】
『 踏む音も 色も鮮やか 柿紅葉 』
季語:柿紅葉(秋)
意味:柿の木の落ち葉を踏むと、パリパリと大きな音がして色も鮮やかに紅葉している様子を詠んでいます。音を鮮やかと表現しているユーモアのある句です。
【No.19】
『 満員の 紅葉馬車ゆく 出湯の街 』
季語:紅葉(秋)
意味:温泉街を走る満員の観光馬車から紅葉がよく見えている風景を詠んでいます。馬車と温泉街というノスタルジックな組み合わせと紅葉の美しさを称えた一句です。
【No.20】
『 天の川 飲んだらきっと ソーダ味 』
季語:天の川(秋)
意味:あの天の川を飲んだらきっとソーダ味がするんだろうなぁと想像しながら夜空を見上げています。ミルキーウェイとも呼ばれる天の川ですが、まだ暑い夜だったのか冷たいソーダを連想している句です。
【No.21】
『 星月夜 誰のためでも ない祈り 』
季語:星月夜(秋)
意味:「星月夜」とは月が出ていないにも関わらず星明かりで空が明るい夜を意味する季語です。たくさんの星に、誰のためでもない祈りを捧げています。
【No.22】
『 葡萄狩り そっととろうね 落ちぬよう 』
季語:葡萄狩り
意味:ブドウ狩りを楽しんでいる最中に注意を促している一句です。粒が房から落ちないように、そっと摘んで楽しむ様子が浮かんできます。
【No.23】
『 胸いっぱい 林檎の香満る 宵嬉し 』
季語:林檎(秋)
意味:たくさんのリンゴを目の前にして、りんごの香りがする夜にどう料理しようか楽しみにしている様子を詠んでいます。アップルパイやジャムなど、美味しそうな料理を作るのでしょう。
【No.24】
『 コスモスの 空どこまでも 澄み渡る 』
季語:コスモス(秋)
意味:コスモスが咲いている空がどこまでも青く澄み渡っている、写真のような一句です。コスモスのピンクと空の青が対比になっています。
【No.25】
『 波音の 空から聞こゆ 秋の雲 』
季語:秋の雲(秋)
意味:波音が空から聞こえるという表現は、いわし雲から連想されています。たくさんのイワシが空にいるのだから波音が聞こえてきそうだというユーモアのある一句です。