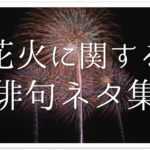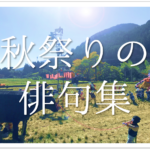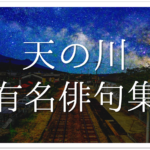お盆とは「盂蘭盆会」と呼ばれる仏教の行事で、現代の暦では8月13日から8月16日に行われています。
現在の感覚では夏ですが、季語の季節としては「初秋」に分類されています。
お盆には「盆の月」「盆花」などの関連した季語の他に「踊」という盆踊りを意味する季語があり、多くの種類があるのが特徴です。
今回は、「お盆」に関する有名な俳句を30句紹介していきます。
送り火や母が心に幾仏(高浜虚子) #俳句 #お盆 pic.twitter.com/z6CoSdXA6e
— iTo (@itoudoor) August 16, 2014

お盆に関する有名俳句【前編10句】

【NO.1】加藤暁台
『 草枕 故郷の人の 盆会(ぼんえ)かな 』
季語:盆会(秋)
意味:旅の途中の侘しい仮宿だ。故郷の人達はお盆の行事をしている頃だろうか。

「草枕」とは草で編んだ枕のことで、旅の途中の仮宿や侘しい宿に泊まっていることを言います。旅の途中でお盆の日を迎え、故郷の人たちは今頃お盆の行事をしているのかと、故郷に思いを馳せている一句です。
【NO.2】小林一茶
『 浴(ゆあみ)して 我が身となりぬ 盆の月 』
季語:盆の月(秋)
意味:湯浴みをして、ようやく一息ついて自分の心が落ち着いた。お盆の月が出ている。

「盆の月」とは旧暦7月15日の、お盆の最中の月のことです。お盆の準備に忙しい時期が終わり、一息ついてようやく自分の時間が持てると安心して月を眺めている心情を詠んでいます。
【NO.3】小林一茶
『 御仏(みほとけ)は さびしき盆と おぼすらん 』
季語:盆(秋)
意味:どれだけ盛大にお盆の行事をしても、亡くなった御仏はお盆を寂しいと思っているのだろう。

お盆はお供えものや花、迎え火や送り火など亡くなった人の霊を迎えるために盛大に準備して行われるものです。しかし、どんなにもてなされても霊は送り火とともに帰らなくてはならないため、家族を置いて去る寂しさを想像した句になっています。
【NO.4】伊藤信徳
『 盆の夜は 餅つく音も あはれなり 』
季語:盆(秋)
意味:お盆の夜は、餅をつく景気の良い音でもあわれに思えてくることだ。

お盆の期間中は餅をついて来客に振る舞ったり、先祖にお供えしたりする習慣の地域があります。そんな地域ではお盆でも餅つきをしますが、お正月ならば景気の良い音に聞こえるだろう音が、お盆という死者との対面の行事ではあわれに感じるという寂しさを詠んだ一句です。
【NO.5】小林一茶
『 盂蘭盆(うらぼん)や 無縁の墓に 鳴く蛙 』
季語:盂蘭盆(秋)
意味:盂蘭盆会の時期だ。お参りの絶えた無縁の墓に蛙が鳴いている。

かつてお盆は先祖の霊を迎えるために、墓から家までの道の草を刈って道を作る「盆路」を作る風習がありました。その道が作られていない墓は、お参りする人が絶えてしまった無縁の墓です。そんな誰も訪れない墓の前で、ただ蛙が鳴いているという侘しい情景が感じられます。
【NO.6】正岡子規
『 盆の月 亡者の帰る 鉦(かね)の音 』
季語:盆の月(秋)
意味:お盆の月だ。亡くなった人の霊が帰ってくるのを助けるような鉦の音がする。

「鉦(かね)」とは平たい円盤のような形をした金属製の打楽器で、お祭りやお囃子などで鳴らされるものです。民間の仏教の行事や盆踊りなどでも使われるため、お盆の行事に相応しい楽器の音が月夜に響いています。
【NO.7】高浜虚子
『 町中に 少し入りこみ 盆の寺 』
季語:盆の寺(秋)
意味:町中から少し入り込んだところに、お盆の行事をするお寺がある。

【NO.8】高浜虚子
『 此月(このつき)の 満れば盆の 月夜かな 』
季語:盆の月(秋)
意味:この月が満ちればお盆の月夜になるなぁ。

盆の月は旧暦の7月15日ですが、太陰暦は月齢で決まるためにこの日にちは必ず満月になる日でした。そのため、今は満ちていく月が満月になればお盆だ、という季節感を表しています。
【NO.9】山口誓子
『 漂着の 平家供養の 盆踊 』
季語:盆踊(秋)
意味:漂着した平家の落ち武者を供養するための盆踊りだ。

平家の落ち武者伝説は日本各地に存在します。敗者である平家の武士の霊を慰めるための盆踊りという、由緒正しく少し物悲しい盆踊りを詠んだ句です。
【NO.10】中村汀女
『 盂蘭盆や 葵(あおい)も高く 花を終ふ 』
季語:盂蘭盆(秋)
意味:盂蘭盆会の日だ。葵の花も高く伸び、花を付けるのを終えている。

葵は草丈が1mから3mと高く伸びることが特徴で、開花時期は6月から8月の花です。そのため、作者はお盆の時期に高く成長した葵の花が散り始めていた光景を目撃したのでしょう。
お盆に関する有名俳句【中編10句】

【NO.11】大野林火
『 風の盆 遠ひぐらしの ひとつきり 』
季語:風の盆(秋)
意味:風の盆だ。遠くにひぐらしの鳴き声が一つだけ聞こえる。

「風の盆」とは今で言う「おわら風の盆」のことで、富山県富山市八尾町で毎年9月1日から3日にかけて行なわれます。越中おわら節のどこか哀しい旋律を、ひぐらしの鳴き声が一つしか聞こえない寂しさで表現した句です。
【NO.12】山口青邨
『 雲海の 上に月あり 盆の月 』
季語:盆の月(秋)
意味:雲海の上に月がある。今日はお盆の月の日だ。

雲海は春と秋の早朝に発生しやすい気象現象です。幻想的な雲海の上に、お盆という霊的な何かを感じさせる月が感情に訴えかけてきます。
【NO.13】中村草田男
『 盆踊も 雨や里人 風呂へ行く 』
季語:盆踊(秋)
意味:にぎやかな盆踊りの最中に雨が降ってきた。濡れてしまった村人たちはみんな風呂へ行く。

【NO.14】飯田蛇笏
『 にぎやかに 盆花濡るる 嶽(たけ)のもと 』
季語:盆花(秋)
意味:にぎやかに備えられた色とりどりのお盆の花が、朝露で濡れている山の麓よ。

「盆花」とはお盆でお供えされる花を意味する季語です。色とりどりのにぎやかな花が、山の麓で朝露に濡れている様子を写実的に詠んでいます。
【NO.15】右城暮石
『 療苑の 盆踊赤 ふんだんに 』
季語:盆踊(秋)
意味:療養所の盆踊りでは、赤い浴衣がふんだんに使われている。

赤色には古来より魔除けの効果があるとされています。また、療養所ではあまり見られない明るい赤い色の浴衣がより映えたのでしょう。積極的に鮮やかな色を使っている印象深さが「ふんだんに」という省略から感じられます。
【NO.16】高橋淡路女
『 くさぐさの 果(くだもの)ちひさき 盆供かな 』
季語:盆(秋)
意味:いろいろな種類の小さい果物が、お盆のお供えとして置いてあるなぁ。

お盆には果物の詰め合わせをお供えします。現在ではカゴに果物が盛られたお供えセットを見たことがある人もいるでしょう。作者はお供えされた果物がみんな小さく可愛らしいサイズであったことが、倒置法を用いて表現するほど印象に残ったようです。
【NO.17】水原秋桜子
『 四万(しま)の湯の 宵の大雨や 盆の入 』
季語:盆(秋)
意味:四万温泉の夜中の大雨だなぁ。お盆期間の初めの日だ。

四万温泉は群馬県中之条町にある名湯です。夜に露天風呂に入っていたら大雨が降ってきた体験を素直に詠んでいます。お盆期間中のため、客も多かったのだろうかと想像が膨らむ句です。
【NO.18】原石鼎
『 城かべに 松の暗さや 盆の月 』
季語:盆の月(秋)
意味:月光に照らされて白く輝く城の壁に、松の影が一際暗く映えているなぁ。お盆の月だ。

月光に照らされた城壁と黒い松の影という水墨画のような風景を詠んでいます。想像しやすい写実的な句で、目の前に風景が浮かんでくるようです。
【NO.19】久保田万太郎
『 新盆や ひそかに草の やどす露 』
季語:新盆(秋)
意味:新盆だなぁ。草がひそかに露を宿している。

「新盆」とは亡くなって初めて迎えるお盆のことです。亡くなって一年未満のため、ひそかに流した涙と草の露をかけています。
【NO.20】長谷川かな女
『 うす雲の ただなかにして 盆の月 』
季語:盆の月(秋)
意味:あの薄雲のただなかに輝くお盆の月よ。

秋は晴れやすい季節ですが、旧暦の季節のため現在のカレンダーでは8月中旬になります。そのため、くもってぼんやりとした月になってしまうことが多いのが現在のお盆の月です。そんな中でもあの場所に月があるなとわかるほどの輝きであることが伺えます。
お盆に関する有名俳句【後編10句】

【NO.21】河合曾良
『 くるしさも 茶にはかつへぬ 盆の旅 』
季語:盆(秋)
意味:お盆の旅の苦しさも、お茶で喉を癒したものだ。

作者の生きた江戸時代の旅は徒歩移動が基本でした。お盆とはいえまだ暑い中での旅で、茶屋で出されたお茶が喉の渇きを癒してくれるというほっと一息ついているときの一句です。
【NO.22】高野素十
『 門を出て 道を曲れば 盆の月 』
季語:盆の月(秋)
意味:家の門を出て、道を曲がればそこにはお盆の月が輝いている。

家の門から出たときには見えなかった月が、道を曲がると目の前に表れたという一句です。不意に表れたお盆の月に見惚れている様子が伺えます。
【NO.23】与謝蕪村
『 地蔵会や 近道を行く 祭り客 』
季語:地蔵会/地蔵盆(秋)
意味:地蔵会が行われているなぁ。近道を歩いて行く祭りの客たちだ。

「地蔵会」とは地蔵菩薩の縁日のことで、現在では8月の下旬に行われています。慣れた近道を歩いていくお祭りの客たちの様子を詠んだ句です。
【NO.24】高橋淡路女
『 盆の月 侘び寝の蚊帳に さしわたり 』
季語:盆の月(秋)
意味:お盆の月の光が、1人に寂しく寝ている蚊帳にさしわたっている。

蚊帳とは布団や寝台のまわりを囲う薄い蚊除けの布です。そんな布が月の光に照らされているのを見て、1人で眠る寂しさを感じています。
【NO.25】高浜虚子
『 盂蘭盆会 遠きゆかりと ふし拝む 』
季語:盂蘭盆会(秋)
意味:盂蘭盆会が行われている。遠いとはいえ縁があるものとして伏して拝んでおこう。

「遠きゆかり」と詠んでいるため、地元や自分の祖先ではない場所で盂蘭盆会の行事に遭遇したのでしょう。自身の直接の祖先ではないが拝んでおこうという敬虔な志を感じる一句です。
【NO.26】森澄雄
『 をみならに いまの時過ぐ 盆踊 』
季語:盆踊(秋)
意味:女性たちにも今現在も刻刻と時間が過ぎていく盆踊りだ。

「をみなら」とは「おんなら」の古い言い方です。盆踊りは毎年行われる地域が多いですが、その度に時間が経過していくことを女性たちの姿に託して詠んでいます。
【NO.27】大野林火
『 日ぐれ待つ 青き山河よ 風の盆 』
季語:風の盆(秋)
意味:日暮れを待つ青い山々や河よ。今日は風の盆だ。

【NO.28】及川貞
『 盆支度 して古町の ひそとあり 』
季語:盆支度(秋)
意味:お盆の支度をしている古い町は、ひっそりとしている。

お盆では精霊棚などの準備があり、「盆支度」という季語にもなっています。支度に追われている割にはひっそりとしている町の様子を詠んだ句です。
【NO.29】富安風生
『 女童ら お盆うれしき 帯を垂れ 』
季語:盆(秋)
意味:女の子たちが着飾って帯を垂らしている。お盆の行事がうれしいのだろう。

お盆は祖先供養のために行われる行事ですが、子供たちからすれば特別なお祭りのように感じているのでしょう。帯を垂らしてうれしそうにはしゃいでいる様子が見えるようです。
【NO.30】飯田蛇笏
『 盆の月 子は戦場の つゆときゆ 』
季語:盆の月(秋)
意味:お盆の月が出ている。子供は戦場の露と消えてしまった。

作者は戦争で子供を亡くしています。お盆ということで供養のために月を眺めていたのでしょうが、戦地で亡くなった子供を思って悲しんでいる様子が伺える句です。
以上、お盆について詠んだ有名俳句でした!
さいごに

今回は、お盆に関する有名俳句を30句紹介してきました。
太陰暦での江戸時代までの俳句と、太陽暦になってからの俳句では少し時期が変わってきますが、先祖を敬う行事であることには変わりません。
最近はお盆の行事をする家庭も減ってきましたが、お寺などでお盆のイベントを行っている場所もあります。
お盆を迎えたときは、故人を思って一句詠んでみてはいかがでしょうか。

最後まで読んでいただきありがとうございました。