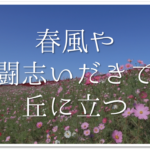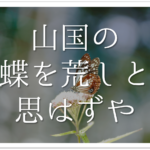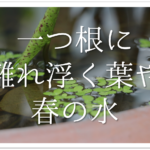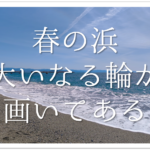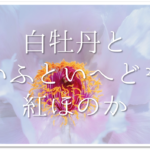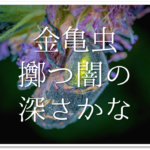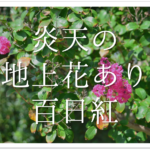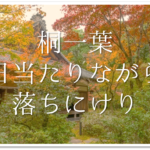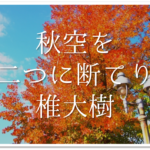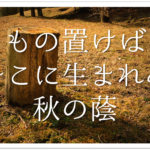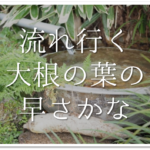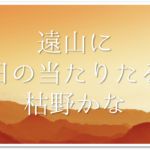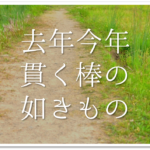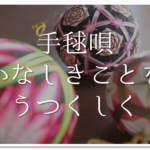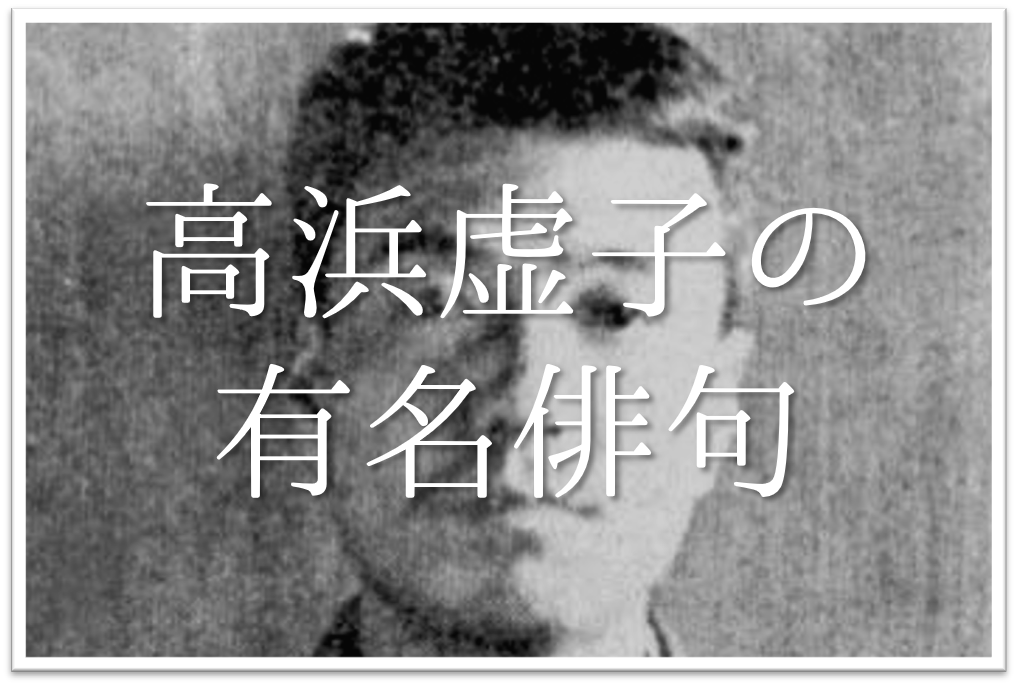
俳句は多くの人に愛好される文芸です。
今回は、近代俳句の礎を築いたとされる正岡子規の高弟にして、明治から昭和まで長く活躍した「高浜虚子」の代表作をご紹介します。
高浜虚子(1874-1959)俳人
「一面に月の江口の舞台かな」
「去年今年貫く棒の如きもの」#作家の似顔絵 pic.twitter.com/HyUf24NpZe— イクタケマコト〈テンプレ集出版〉 (@m_ikutake2) September 14, 2014
高浜虚子の特徴や人物像

(高浜虚子 出典:Wikipedia)
高浜虚子(たかはま きょし)は、本名は「清(きよし)」、明治中期から、大正、昭和30年代まで活躍した俳人です。
江戸期までの俳諧を改革した正岡子規の高弟で、正岡子規とともに、俳句雑誌『ホトトギス』の創刊に関わりました。師亡き後、高浜虚子は句作をやめ、しばらくは小説を書くことに没頭しました。
しかし、同じく正岡子規の弟子であった河東碧梧桐が定型や季題にとらわれない新傾向俳句を提唱し始めたことに反発、大正2年(1913年)、俳壇に復帰します。
新傾向を唱える碧梧桐に対して、虚子はあくまでも守旧派を貫き、正岡子規の俳句の精神を引き継いで『ホトトギス』の編集にも携わり、長く日本の俳壇に君臨した人物です。
花や鳥といった自然の美しさを詩歌に詠みこむ「花鳥諷詠」、客観的に情景を写生するように表現しつつ、その奥に言葉で表しきれない光景や感情を潜ませる「客観写生」といった考え方に基づいて俳句を詠みました。

次に、高浜虚子の代表的な俳句を季節(春夏秋冬)別に紹介していきます。
高浜虚子の有名俳句・代表作【36選】

(虚子の句碑 出典:Wikipedia)
春の俳句【7選】

【NO.1】
『 春風や 闘志いだきて 丘に立つ 』
季語:春風(春)
現代語訳:春風が吹いていることだ。私は、心に闘志をもち、丘の上で春風に吹かれながらじっと立っている。

【NO.2】
『 闘志尚 存して春の 風を見る 』
季語:春の風(春)
現代語訳:若き日に、春風に吹かれながらに抱いた闘志はいまだ私の心の中にあり、今もこうして春の風をみていることだ。

【NO.3】
『 山国の 蝶を荒しと 思はずや 』
季語:蝶(春)
現代語訳:山国に飛ぶ蝶たちは荒々しい飛び方をしていると思わないか。

【NO.4】
『 一つ根に 離れ浮く葉や 春の水 』
季語:春の水(春)
現代語訳:春の水辺に二つの離れて浮いている葉が見えるなぁ。よく見ると根が一つに繋がっている。

【NO.5】
『 春の浜 大いなる輪が 画いてある 』
季語:春(春)
現代語訳:春の浜辺に大きな輪が描かれている。

【NO.6】
『 鎌倉を 驚かしたる 余寒あり 』
季語:余寒(春)
現代語訳:鎌倉という地を驚かせていたほどの春の寒さでしたよ。

【NO.7】
『 道のべに 阿波の遍路の 墓あはれ 』
季語:遍路(春)
現代語訳:道端に阿波へのお遍路たちのお墓が立っているのがなんとも哀れである。

夏の俳句【9選】

【NO.1】
『 白牡丹と いふといへども 紅ほのか 』
季語:牡丹(夏)
現代語訳:白牡丹という名の花ではあるが、よく見ると、紅色もほんのりと帯びていることだ。

【NO.2】
『 金亀虫 擲つ闇の 深さかな 』
季語:金亀虫(夏)
現代語訳:夏の夜、部屋に入り込んでくるコガネムシを捕まえて庭に投げつけたが、それが飲み込まれていった闇の深いことよ。

【NO.3】
『 虹立ちて 雨逃げて行く 広野かな 』
季語:虹(夏)
現代語訳:広い野原に降りこめていた雨も、虹が立つと逃げるようにやんでいくことだ。

【NO.4】
『 蛍火の 今宵の闇の 美しき 』
季語:蛍火(夏)
現代語訳:蛍が光りながら飛び違う、今日の宵の闇がなんと美しいことか。

【NO.5】
『 炎天の 地上花あり 百日紅 』
季語:百日紅(夏)
現代語訳:炎天下の地上にも鮮やかな赤い百日紅の花があるのだ。

【NO.6】
『 生きてゐる しるしに新茶 おくるとか 』
季語:新茶(夏)
現代語訳:生きているという一報のためだけに新茶を贈ってくれたのか。

【NO.7】
『 牛も馬も 人も橋下に 野の夕立 』
季語:夕立(夏)
現代語訳:牛も馬も人間も橋の下に避難する野原の夕立だ。

【NO.8】
『 夏至今日と 思ひつつ書を 閉ぢにけり 』
季語:夏至(夏)
現代語訳:そういえば今日は夏至だったなぁと思いながら本を閉じた。

【NO.9】
『 力無き あくび連発 日の盛り 』
季語:日の盛り(夏)
現代語訳:力無いあくびを連発する暑い夏の日の盛りだ。

秋の俳句【9選】

【NO.1】
『 立秋の 雲の動きの なつかしき 』
季語:立秋(秋)
現代語訳:立秋を迎え、秋の訪れを実感させる雲の動きが慕わしく思われることだ。

【NO.2】
『 桐一葉 日当たりながら 落ちにけり 』
季語:桐一葉(秋)
現代語訳:桐の木の葉が一枚、太陽に照らされつつゆっくりと舞い落ちていったことだ。

【NO.3】
『 秋空を 二つに断てり 椎大樹(しいたいじゅ) 』
季語:秋空(秋)
現代語訳:秋の空を、二つに分断して割っているようだ、椎の大きな木が。

【NO.4】
『 秋風や 眼中のもの 皆俳句 』
季語:秋風(秋)
現代語訳:心地よい秋風が吹き抜けていくことよ。私の目に映るものすべてが、俳句とよべるような美しいものに思われる季節であることだ。

【NO.5】
『 もの置けば そこに生まれぬ 秋の蔭 』
季語:秋(秋)
現代語訳:物を置くとそこに生まれる影に、秋の気配を感じる。

【NO.6】
『 一夜明けて 忽ち(たちまち)秋の 扇かな 』
季語:秋の扇(秋)
現代語訳:一夜明けると途端に涼しくなり、たちまち秋の扇のように仰ぐものが必要ない気候になった。

【NO.7】
『 新米の 其一粒の 光かな 』
季語:新米(秋)
現代語訳:新米のその1粒に宿った輝かしい光だなぁ。

【NO.8】
『 われの星 燃えてをるなり 星月夜 』
季語:星月夜(秋)
現代語訳:私の星が燃えている月のない星が明るい夜だ。

【NO.9】
『 暫くは 雑木紅葉の 中を行く 』
季語:雑木紅葉(秋)
現代語訳:しばらくは雑木林の紅葉の中を歩いていく。

冬の俳句【11選】

【NO.1】
『 寒菊や 年々同じ 庭の隅 』
季語:寒菊(冬)
現代語訳:寒菊が今年も咲いたことだよ。毎年、庭の隅の同じ場所に忘れることなく咲くことだ。

【NO.2】
『 流れ行く 大根の葉の 早さかな 』
季語:大根(冬)
現代語訳:冬、小川に浮かぶ大根の葉が流されていったが、その早いこと。

【NO.3】
『 遠山に 日の当たりたる 枯野かな 』
季語:枯野(冬)
現代語訳:冬、日が陰ってきて、遠くの山にだけ陽ざしが当たって明るくなっているが、眼前には寒々しい枯れた野原が広がっていることだ。

【NO.4】
『 去年今年 貫く棒の 如きもの 』
季語:去年今年(新年)
現代語訳:年の瀬を境に、去年と今年は入れ替わっていくのだが、その中をつらぬくぼうのようなものがある。

【NO.5】
『 又例の 寄せ鍋にても いたすべし 』
季語:寄せ鍋(冬)
現代語訳:またいつもの寄せ鍋にでもしましょうか。

【NO.6】
『 大寒の 埃(ほこり)の如く 人死ぬる 』
季語:大寒(冬)
現代語訳:大寒の日の寒さでホコリのように人が死んでいく。

【NO.7】
『 うつくしき 羽子板市や 買はで過ぐ 』
季語:羽子板市(冬)
現代語訳:美しい羽子板が並んでいる市があるが、買わないで通り過ぎていく。

【NO.8】
『 手毬唄 かなしきことを うつくしく 』
季語:手毬唄(新年)
現代語訳:子どもたちが遊びながら無邪気に歌う手毬唄は、よく聞くと悲しい内容のことを美しく歌っていることだなあ。

【NO.9】
『 何もなき 床に置きけり 福寿草 』
季語:福寿草(新年)
現代語訳:正月らしいしつらえは何もない床の間に、福寿草の花を置いたことだ。

【NO.10】
『 浪音の 由比ケ浜より 初電車 』
季語:初電車(新年)
現代語訳:波音の響く由比ヶ浜から今年初の電車に乗った。

【NO.11】
『 映画出て 火事のポスター 見て立てり 』
季語:火事(冬)
現代語訳:映画が終わって、館内に貼られていた火事のポスターを見て立ち上がった。

さいごに

今回は、俳句界の巨頭・高浜虚子の有名句をご紹介しました。
明治、大正、昭和と三世代にまたがって活躍した高浜虚子には、優れた句が多くあります。
客観的に、自然の美しい風物を詠みこむことを旨として、俳句の芸術性を追求しつづけた俳人でした。
今日もありがとうございます🍀
せっかく紅葉が見られたのに
葉を落とし始めました🍂「桐一葉 日当りながら 落ちにけり」
大好きな 高浜虚子(松山出身)の句❗️仕事中にて休憩時に🙇🏻
— マカロン (@teishi_chugu) December 5, 2016

最後まで読んでいただきありがとうございました。