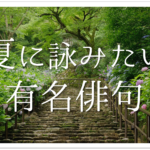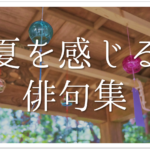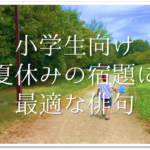猛暑日が続く「8月」…。
唸るような暑さであるからこそ記憶に残りやすい月でもあります。
過去の人々に習ってゆっくりと俳句を詠んでみたくなりますね。また、趣味で書くという方以外にも、学校の宿題で俳句を書かなくてはならない人もいるかもしれません。
(※ちなみに、8月19日は「俳句の日」です)
8月19日
俳句の日。
今日は俳句など詠んでみるのもいいかも😊🎶
なんて🌠 pic.twitter.com/HUOl6aIpJt— memu (@memuzzz) August 19, 2017
そこで今回は、そんな方の参考になるような「8月」の季語を含んだ有名俳句(+一般の方が詠んだ俳句)を紹介していきます。

ぜひ参考にしてください。
俳句に8月らしさを出す!8月の季語を知ろう

まず、俳句を書くにあたって「季語を使うこと」「5・7・5の17音にすること」の2つのルールがあることを覚えておきましょう。
5・7・5という短い文の中でさまざまな情景や心情を映し出す俳句にするには、作者が見たことをわかりやすく説明する必要があります。
その時に用いられるのが「季語」と呼ばれるものなのです。
季語とは日本にある春夏秋冬、いわゆる四季とよばれるもの。これらにはそれぞれ特徴があり、その特徴を表した言葉たちのことを言います。

8月の季語【一覧】
花火 / 盆踊り / 浴衣 / 向日葵 / 八月 / 初秋 / 立秋 / 残暑 / 秋めく / 処暑 / 八月尽 /盆の月 / 秋の初風 / 初嵐 / 秋の雷 / 秋扇 / 終戦記念日 / 竿燈 / 墓参 / 送り盆 / 送り火 / 大文字 / 燈籠流 / 精霊舟 / 踊 / 風の盆 / 盆竈 / 盆綱引 / 盆休 / 盆節季 / 中元 / 三島祭 / 鰹の烏帽子 / 秋の蛍 / 蜩 / つくつく法師 / 蜉蝣 / 鈴虫 / 松虫 / 刺虫 /木槿 / 芙蓉 / 山茱萸の実 / 桃の実 / 棗の実 / 桐一葉 / 秋の芽 / 桐の実 / 臭木の花 / 山椒の実 / 秋桑 / 楤の花 / 蘡薁 / 山葡萄 / 野葡萄 / カンナ / ジンジャーの花 / 朝顔 / 夜顔 / 仙翁花 / 模様莧 / 鬱金の花 / 落葵 / 鳳仙花 / 秋海棠/ 女郎花 / 男郞花 / 水引の花 / 苔桃 / 釣船草 / 矢の根草 / 大文字草 / ぬめり草 / 鼠の尾 / 点突草 / 星草 / 草牡丹 / 松虫草 / 露草 / 弟切草 / 蓼の花 / 赤のまんま / 溝蕎麦 / 茜草
これらの言葉を聞くと8月又は夏を思い浮かべませんか?
このような言葉を俳句の中に入れると、作者の見たもしくは周りにある状況などをわかりやすく伝えることができます。

8月の季語を使った有名俳句集【15選】

それでは早速、8月の季語を使った有名な俳句を15句紹介していきます。
【NO.1】正岡子規
『 涼しさの 腹にとほりて 秋ちかし 』
季語:秋近し(夏)
意味:涼しさをお腹に感じて秋が近いなぁと感じた。

【NO.2】山口青邨
『 咲きつづく 朝顔市の 朝顔よ 』
季語:朝顔(秋)
意味:ずっと前から咲き続く朝顔市の朝顔だ

【NO.3】久保田万太郎
『 へなへなに こしのぬけたる 団扇(うちわ)かな 』
季語:団扇(夏)
意味:あまりの暑さに使いこなされたへなへななうちわがある

【NO.4】日野草城
『 白玉の 雫を切って 盛りにけり 』
季語:白玉(夏)
意味:白玉を洗った水を切ってお皿に盛り付ける。

【NO.5】原 石鼎
『 うつし世に 妻はきよけし 夏の月 』
季語:夏の月(夏)
意味:この世に妻を明るく照らす夏の月がある。

【NO.6】永田耕衣
『 墓を去る 時に笑ふや 墓参り 』
季語:墓参り(秋)
意味:墓参りをした後墓を去る時に墓に向かって笑う。

【NO.7】富安風生
『 八月の 桜落葉を 掃けるかな 』
季語:八月(秋)
意味:八月に桜の葉の落ち葉を掃いている。

【NO.8】山口誓子
『 紅くして 黒き晩夏の 日が沈む 』
季語:晩夏(夏)
意味:暗くなるのが早くなった晩夏の頃、暗い空を赤くしながら日が沈んでいる。

【NO.9】加藤暁台
『 美しや 月の中なる 盆の人 』
季語:盆(秋)
意味:美しいな。月が出た盆の夜にお供えや精霊船を流す人々は。

【NO.10】阿波野青畝
『 てのひらを かへさばすすむ 踊かな 』
季語:踊(秋)
意味:手のひらを重ねながら進む盆踊りかな。

【NO.11】松尾芭蕉
『 暑き日を 海にいれたり 最上川 』
季語:暑き(夏)
意味:暑い日の太陽を海に入れるように日が沈んでいった最上川だ。

【NO.12】与謝蕪村
『 四五人に 月落ちかかる をどりかな 』
季語:をどり/踊(秋)
意味:4、5人ほどの人に、月の光が落ちかかっている盆踊りだなぁ。

【NO.13】与謝蕪村
『 夕立や 草葉をつかむ むら雀 』
季語:夕立(夏)
意味:夕立が降ってきたなぁ。雨宿りなのか、草葉の裏をしっかりとつかんでいるスズメたちの群れだ。

【NO.14】加賀千代女
『 朝顔に 釣瓶とられて もらひ水 』
季語:朝顔(秋)
意味:朝顔の弦に釣瓶をとられてしまった。弦を切るのもしのびないので隣家から水をもらおう。

【NO.15】黛まどか
『 旅終へて よりB面の 夏休 』
季語:夏休(夏)
意味:メインだった旅が終わって、これからはB面のサブ曲のような夏休みの残りが始まる。

こんな俳句もある!一般オリジナル俳句集【15選】

上にあげた有名な俳句以外にも、様々な人が書いたオリジナルの俳句も存在します。
ここでは、参考のために一般の方が作ったオリジナル俳句も15句紹介していきます。
【No.1】
『 落ちる火を 惜しむ線香 花火かな 』
季語:線香花火(夏)
意味:線香花火の火の玉が落ちることを惜しんでいる。

【No.2】
『 妻は絹 我れは木綿や 冷奴 』
季語:冷奴(夏)
意味:妻は絹豆腐で自分は木綿豆腐で冷奴をつくる。

【No.3】
『 ふる里の 小さくなりし 踊の輪 』
季語:踊(秋)
意味:ふるさとの盆踊りの輪は年々小さくなっている。

【No.4】
『 なほ残る 暑さ日暮の アスファルト 』
季語:暑さ(夏)
意味:日暮れのアスファルトに暑さがなお残っている。

【No.5】
『 庭花火 匂い残して 闇戻る 』
季語:花火(秋)
意味:夏の夜、庭で花火をした後に匂いだけを起こしてまわりは真っ暗闇へもどった。

【No.6】
『 律儀にも 炎暑の中に ポスト立つ 』
季語:炎暑(夏)
意味:炎暑の中、律儀にポストが立っている。

【No.7】
『 人の世は 花火のやうな 夢ばかり 』
季語:花火(秋)
意味:この世にいる人たちが望む夢は花火のように明るく鮮やかに散りやすいものだ。

【No.8】
『 風鈴を 吊るや飛びつく 風のあり 』
季語:風鈴(夏)
意味:風鈴を吊るとすぐに風鈴へと風が吹いてまるでありのようだ。

【No.9】
『 八月尽 閉店告げる 百貨店 』
季語:八月尽(秋)
意味:8月の終わり、閉店を告げる百貨店がある。

【No.10】
『 悩むより 今日を生きよと 蝉鳴けり 』
季語:蝉(夏)
意味:未来のことを悩むよりも一週間しか命のない蝉が今日を一生懸命に生きろと鳴いている。

【No.11】
『 この人と また手を繋ぎ 初浴衣 』
季語:初浴衣(夏)
意味 この人とまた手を繋いで出かけたいな。今年初めての浴衣だ。

【No.12】
『 打ち揚げの 花火に映ゆる 夜の雲 』
季語:花火(秋)
意味:打ち上げ花火が上がる度に夜の雲が映えて見える。

【No.13】
『 秋立つや 高層階に そよぐ風 』
季語:秋立つ(秋)
意味:立秋の日が来たなぁ。高層階にそよぐ風が心地よい。

【No.14】
『 ふるさとは 遠きにありて 盆の月 』
季語:盆の月(秋)
意味:故郷は遠くにあると感じるお盆の日の月だ。

【No.15】
『 西瓜割り 右か左か あれ後ろ 』
季語:西瓜割り(夏)
意味:スイカ割りをしよう。右か左か、あれ、後ろにある。

以上、8月の有名俳句(+オリジナル俳句)30選でした!
さいごに

今回は、8月の季語を使った有名俳句をたくさん紹介してきました。
8月は夏祭りやお盆があったり、何かと忙しい月である反面、猛暑日が続いたりすると何もしたくなくなる季節でもあります。
そんな時にはひんやりした床に寝転がりながら、もしくは風通しが良いベランダで、ぜひ俳句を一句詠んでみてはいかがでしょうか?
向日葵が てんでに夏を 追い疲れ #haiku pic.twitter.com/UZ8KebJYbr
— 竹田康一郎 (@tahtaunwa) August 28, 2015

普段生活をしている風景の中に新たな発見が出来たり、日常生活に物語を添えてくれますのでとてもおすすめです。