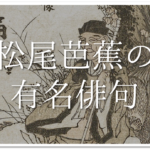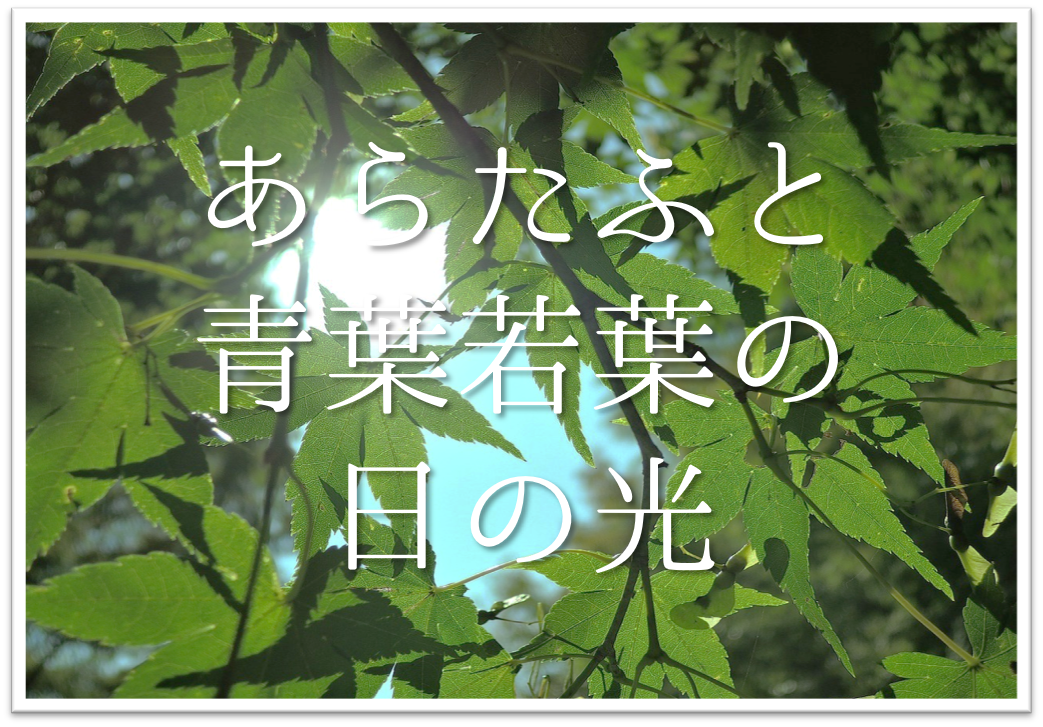
江戸時代、俳諧や発句の芸術性を高めたといわれるのがあの有名な「松尾芭蕉」です。
旅をしながら句を詠み、旅行記と詠句をまとめた俳諧紀行文を多く執筆しました。
その中でも有名なものは「おくのほそ道」です。江戸から奥州を目指し、北陸をまわって岐阜の大垣にいたるまでの道中を俳諧紀行文でまとめ上げたものです。
今回はこの「おくのほそ道」に集録されている「あらたふと青葉若葉の日の光」という句を紹介していきます。
こんにちは❀(*´▽`*)❀
みなさん優しい午後を…
あらたふと青葉わか葉の
日のひかり 『松尾芭蕉』 pic.twitter.com/5aU8LSjU6e
— Chimu (チム)🐶 (@Jimin1Best) May 22, 2019
本記事では、「あらたふと青葉若葉の日の光」の季語や意味・表現技法・作者など徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「あらたふと青葉若葉の日の光」の作者や季語・意味

あらたふと 青葉若葉の 日の光
(読み方:あらとうと あおばわかばの ひのひかり)
こちらの句の作者は「松尾芭蕉(まつおばしょう)」です。
この句は芭蕉が日光東照宮を訪れて詠んだ句になります。
日光の地は古くから山岳信仰の場として人々の尊崇を集めてきましたが、江戸幕府初代将軍・徳川家康の眠る霊廟もあり、聖地とされていました。
季語
この句の季語は「若葉」、季節は「夏(初夏のころ合い)」です。
若葉は、青々と生い茂った木の葉のことです。 特に初夏の若葉の時期を過ぎて 青々と茂った木の葉. を意味する言葉になります。
「青葉」「若葉」「青葉若葉」のどれも夏の季語ですが、「青葉」がはっきりと季語として認識されたのは大正時代以降とされています。

現在の歳時記では「青葉若葉」も季語に含まれていますが、芭蕉の時代では「若葉」のみが季語と認識されていたため、ここでは「若葉」を季語としています。
意味
この句を現代語訳すると・・・
「なんとまあ、尊くありがいことか。ここ日光の霊山の木々の青葉や若葉に降り注ぐ日の光は。」
という意味になります。
「あらたふと」の「あら」は感嘆を表す言葉で、「ああ」や「なんと」と訳します。
「たふと」は「尊い」という意味で、「たふとし」の形容詞の語幹」部分です。語幹で止めることにより、一層感動が深かったことを表します。

「日の光」という言葉には、太陽の光と言う意味と日光という地名という二つの意味がかけられています。
「あらたふと青葉若葉の日の光」の句が詠まれた背景

(日光東照宮 出典:Wikipedia)
この句は奥州への旅の途上、松尾芭蕉が門人・河合曾良(かわいそら)と日光東照宮を訪れた時に詠んだ句になります。
日光の地には、「自らの死後も神となって江戸を守る、死後は江戸の北にある日光の地に葬るように」と遺言して亡くなった初代将軍・徳川家康が日光東照宮権現としてまつられています。
江戸時代の人々にとって、将軍家はおかすべからざる存在であり、神君家康公は文字通り神でした。
芭蕉はここ日光で以下のように述べています。
「卯月朔日(うづきついたち)、御山に詣拝す。往昔(そのかみ)、此御山を「二荒山(ふたらさん)」と書しを、空海大師開基の時、「日光」と改給ふ。千歳未来をさとり給ふにや、今此御光一天にかゝやきて、恩沢八荒(おんたくはっこう)にあふれ、四民安堵(しみんあんど)の栖穏(すみかおだやか)なり。」
(意味:4月1日、日光山に参詣した。昔はこの山を「二荒山(ふたらさん)」と書いたものだが、弘法大師空海がここに寺を開いたとき、「二荒」を音読みの「にこう」にし、これに「日光」の字を宛てて表記を改めたのである。「日光」の字を宛てたのは、遠い未来のことまでも見通していたものであろうか、現在、神君家康公が権現となってその威光を天下に輝かせ、その恩恵は世の隅々にいきわたり、士農工商のすべての身分のものが平和に暮らすことができている。)
日光はもともと修験道の霊場として古代から神聖視されていた土地です。
ここに寺を開いたのは、芭蕉が言及している弘法大師空海ではなく、勝道上人ですが、そのあたりは思い違いもあったものでしょうか。
とにかく、戦乱の世をおさめ、太平の世をもたらした家康に対する江戸時代の人々の畏敬の念は、深く大きいものでした。
芭蕉は、最大限の賛辞をこの句に盛り込んでいます。
「あらたふと青葉若葉の日の光」の表現技法

この句で使われている表現技法は・・・
- 「あらたふと」の初句切れ
- 「日の光」の体言止め
になります。
「あらたふと」の初句切れ
「かな」「や」「けり」などの切れ字のあるところ、もしくは意味上での切れ目(※普通の文でいえば句点「。」で切れるところ)を、句切れと呼びます。
この句は初句の「あらたふと(なんとまあ尊いことか)。」で一旦意味が切れます。
つまり「初句切れ」の句となります。
「日の光」の体言止め
体言止めとは、下五の終わりを体言・名詞で終わる技法のことで、余韻を残したり、印象を強めたりする働きがあります。
この句の場合は、下五が「日の光」で終わります。

青々とした木々に降り注ぐ太陽の光の美しさ、そしてそこに重ねて東照宮権現、ひいては徳川将軍家の威光を強調していることがわかります。
「あらたふと青葉若葉の日の光」の鑑賞文

【あらたふと青葉若葉の日の光】は、初夏の日光の山の木々の美しさとともに徳川の威光を言祝いだ句です。
芭蕉に随行していた河合曾良の記録によると、この句の初案は
「あなたふと木の下闇(このしたやみ)も日の光」
(意味:なんとまあ尊いことか、木の下の暗がりにまで日の光が届いている)
であったと言われています。
隅々まで日光東照宮の威光が届いていることをこのように表現したのでしょう。
推敲を重ね、「青葉わか葉の日の光」となったわけですが、目にも鮮やかな緑に光が当たる、明るくきらびやかな印象の句になりました。
徳川家を必要以上に称賛しているのではないかと非難されることもある句ですが、松尾芭蕉も武家に仕えたことのある身、門人でもあり支援者でもあった人々には武家もいたはずです。

日光を賛美する姿勢を現代人の感覚だけで判断はできないでしょう。
「あらたふと青葉若葉の日の光」の補足情報

松尾芭蕉の時代と日光東照宮
松尾芭蕉は1644年に生まれています。既に戦乱の世は遠くなり、徳川家康が日光の地に葬られたのは1617年のことです。
その後、三代将軍家光により「寛永の大造替」が1636年に行われていて、現在の豪奢な社殿が出来上がりました。
芭蕉が生まれた翌年には朝廷から「宮」を名乗ることが許され、「日光東照宮」になっていったのです。
芭蕉が『おくのほそ道』でこの地を訪れたのは1689年のことで、50年ほど経っていました。

50年経っても変わらぬ威光を目にして、「あらたふと」という感嘆を詠まずにはいられなかったのでしょう。
「曾良書留」との違い
この句の初稿が「木の下闇」と詠まれていたことは上述の通りですが、この初稿は「曾良書留」という書状に載っています。
この書留によると、「あなたふと」の句は日光ではなく実際は1つ前の「室の八島」から日光へ向かう道中で詠まれたものであるとされ、いくつかの句とともに書かれていました。
『おくのほそ道』では室の八島という歌枕の説明だけを行い、芭蕉も曾良も俳句を載せていません。
しかし、「曾良書留」によると芭蕉は二つの句を作っています。
「糸遊に 結びつきたる 煙哉」
季語:糸遊(春)
意味:煙で名高いこの室の八島では、陽炎にも煙が結びついて見えることだ。
「入りかかる 日も糸遊の 名残かな」
季語:糸遊(春)
意味:山の端に消えようとしている太陽、か細くなった陽炎、この太陽と陽炎の結びつきの名残のように晩春の夕暮れが近づいてくるなぁ。
この2つの句は、室の八島で詠まれたにも関わらず、『おくのほそ道』には載っていません。
ここで室の八島の地を出発し、日光に行く道中に詠まれたのが『あなたふと 木の下闇も 日の光』でした。

元々この句は道中吟だったのです。
暮春の夕暮を表す2句
さらに「曾良書留」には「あらたふと」と同じ時期に詠まれた2つの俳句が載せられています。
「鐘撞かぬ 里は何をか 春の暮」
季語:春の暮れ
意味:春も終わりの夕暮れ、鐘を撞かないこの里では何を頼りにしているのだろうか。
「入逢の 鐘もきこえず 春の暮」
季語:春の暮
意味:春も末の夕暮れ、このあたりでは日没を知らせる鐘も聞こえてこない。
このふたつの句はよく似ているため、推敲していたものと考えられます。

しかし、この二句も掲載されておらず、「日光」の項での俳句のインパクトを重視したのでしょう。
「木の下闇」から「青葉若葉」へ
「木の下闇」と詠んでいるときは、室の八島から日光への道中ですが、「青葉若葉」ははっきりと日光という土地に対しての俳句になっています。

「木の下闇の日の光」と「日光」を掛け合わせるために推敲し、『おくのほそ道』での場所に配置したのでしょう。
作者「松尾芭蕉」の生涯を簡単にご紹介!

(松尾芭像 出典:Wikipedia)
松尾芭蕉は、寛永21年(1644年)生まれの、江戸時代前期に活躍した人物です。
本名を松尾宗房(まつお むねふさ)といいました。「芭蕉」は俳号です。
本名を音読みにした「宗房(むねふさ)」「桃青(とうせい)」などの俳号も使いましたが、「芭蕉」の俳号が最もよく知られ、彼の作風は「蕉門」と呼ばれています。
伊賀国、現在の三重県伊賀市の身分の高くない家の出身でしたが、若い頃に仕えた主君「藤堂良忠」とともに京都の国学者北村季吟に師事、俳諧をまなびました。
主君の死後、江戸に出て転居をくりかえしつつ、深川の地に庵を結びます。
この住まいの庭にバナナの仲間である「芭蕉」という植物を植えて、「芭蕉庵」と称して住んでいたといいます。
「おくのほそ道」はその芭蕉庵を出発して、東北や北陸を回る旅をした時の俳諧紀行文で、芸術性の高い文学作品として今に名を残します。
芭蕉の没年は元禄7年(1694年)。享年50歳でした。
松尾芭蕉のそのほかの俳句
(「奥の細道」結びの地 出典:Wikipedia)