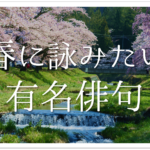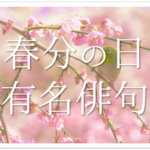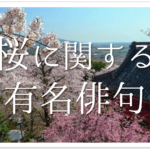「立春」は二十四節気のひとつで、現在のカレンダーでは2月3日-4日頃を指します。
立春を表す季語としては「立春」「春立つ」「春来る」「立春大吉」などがあります。
■二十四節気■立春2/4-17 ここ数日、暖かい日々が続きましたが「立春」を迎える明日からまた厳しい寒さが戻るようです。「春寒(はるさむ)」という季語がぴったりのこの時期に、百花に先駆けて咲く梅の花。「春告草」という異名を持ちます。 pic.twitter.com/ZHZb86OUB5
— 京都府立けいはんな記念公園 (@kouenkeihanna) February 3, 2014
今回は、「立春」に関するおすすめ有名俳句を30句紹介していきます。

「立春」に関するおすすめ有名俳句【前編10句】

【NO.1】松尾芭蕉
『 春立つや 新年ふるき 米五升 』
季語:春立つ(春)
意味:立春が来たなぁ。新年を古米五升という余裕を持って越せる嬉しさよ。

この句は現代の感覚からすると季重なりの上に季節まで違うと思われてしまう句になっています。旧暦の立春は旧暦の元旦前後に来ますが、この句が詠まれた年は元旦をむかえる前に立春がくる「年内立春」でした。そのため、この句で言う「新年」とはこれからむかえる元旦のことであり、立春ではあるものの年の暮れの一コマを詠んだ句になります。
【NO.2】松尾芭蕉
『 春立ちて まだ九日の 野山かな 』
季語:春立ちて(春)
意味:立春をむかえてまだ9日しか経っていないけれど、どこか春めいてきた気がする野山であることよ。

この句が詠まれた年の立春は旧暦1月4日だったため、1月13日頃の風景を詠んでいます。故郷の伊賀に帰った際に詠まれた句なので、久しぶりの郷土の野山に懐かしさを感じてもいるようです。
【NO.3】与謝蕪村
『 寝ごころや いづちともなく 春は来ぬ 』
季語:春は来ぬ(春)
意味:気持ちよく寝ていたなぁ。どこからともなく春が来る立春であることだ。

「いづちともなく」とはどこからともなくという意味になります。寒さがやわらいでうたた寝をしていたら、どこからともなく春の陽気を感じ取ったというのどかな一句です。
【NO.4】小林一茶
『 春立や 愚の上に又 愚にかへる 』
季語:春立(春)
意味:また立春が来たなぁ。愚かに生きてきたが、また愚かな一年を過ごすのだろう。

小林一茶の人生への皮肉めいた一面がよく表れている俳句です。また一年という年を重ねることに対し、「愚」という言葉を重ねることで繰り返しを表しています。
【NO.5】小林一茶
『 門々の 下駄の泥より 春立ぬ 』
季語:春立ぬ(春)
意味:それぞれの家の門を、下駄の泥が汚している。春が来たようだ。

雪解けや雨で土がぬかるんでくると、春が来たという実感がわきます。通りすがる家の門がみな下駄についた泥で汚れていることで、立春の日であることに気がついたかのような句です。

【NO.6】正岡子規
『 春立つや 昼の灯くらき 山社(やまやしろ) 』
季語:春立つ(春)
意味:立春の日が来たなぁ。それでもまだ昼の明かりでも暗い、山の中の神社である。

冬は日照時間が短く、太陽も高く登りません。立春をむかえたとはいえまだまだ春は遠いため、明かりをつけた昼でも山の中の神社はほの暗く、寒さを感じています。
【NO.7】高浜虚子
『 雨の中に 立春大吉の 光あり 』
季語:立春大吉(春)
意味:雨の中でも立春大吉の札が貼ってあると、そこだけ光が差し込んでいるように感じる。

【NO.8】高浜虚子
『 春来れば 路傍(ろぼう)の石も 光あり 』
季語:春来れば(春)
意味:立春が来て春が来ると、路傍に落ちている石も光っているように感じる。

暦の上とはいえ春をむかえて、落ちている石も春を喜ぶように光っているような気がする、と春の訪れを喜んでいます。春の日の光に照らされて、小石もまた光っているように感じたのでしょう。
【NO.9】井上士朗
『 何事も なくて春たつ あしたかな 』
季語:春たつ(春)
意味:何事もなく立春をむかえる朝であることよ。

「あした」は「明日」ではなく「朝」のことです。この1年何事もなく平穏に、また立春の朝をむかえることができた喜びを詠んでいます。
【NO.10】日野草城
『 朝の茶の かんばしく春 立ちにけり 』
季語:春立ちにけり(春)
意味:朝に飲むお茶が芳しい香りを立てている。今日は立春の日だ。

立春とはいえまだ寒い朝に、あたたかいお茶で一服している風景を詠んでいます。春であると思うと、いつものお茶もいっそう香り高く感じるものです。
「立春」に関するおすすめ有名俳句【中編10句】

【NO.11】山口草堂
『 立春の 土手は日向の はしり来る 』
季語:立春(春)
意味:立春の日の土手は、まるでひなたが走ってきているようにあたたかい光で照らされている。

寒さがやわらぎはじめた土手は、寒い冬の日差しではなくどこかあたたかい日の光に照らされています。冬によくくもっている地域では、晴れているだけで春の気配を感じられるかもしれません。
【NO.12】高浜年尾
『 川下へ 光る川面や 春立ちぬ 』
季語:春立ちぬ(春)
意味:川下へ向かって流れる川の水面に日の光が照らしている。立春をむかえたようだ。

川の水面にちらちらとうつる日光が、ひと足早い春の陽気を感じさせる句です。河原を散策できるほど寒さがやわらいでいることも読み取れます。
【NO.13】飯田蛇笏
『 春立つや 山びこなごむ 峡つづき 』
季語:春立つ(春)
意味:立春だなぁ。山に向かって叫んで返ってくるやまびこもどこか和むような山々だ。

【NO.14】室生犀星
『 春立や 蜂のはひゐる 土の割れ 』
季語:春立(春)
意味:立春がきたなぁ。蜂が土の割れ目から這い出てきた。

蜂にはいろいろな種類がいますが、土の中で越冬するものとして代表的なのはスズメバチの中の女王蜂です。冬の終わりを感じ取って冬眠から目覚めた現場を目撃した句になっています。
【NO.15】阿波野青畝
『 立春の 鳶(とび)しばし在り 殿づくり 』
季語:立春(春)
意味:立春になって、鳶がしばらくこの近辺に来ている。巣作りをしているのだろうか。

鳶は2月から3月頃にかけて山などの木の上に素を作ります。作者は巣作りをする鳶を見かけているので、里山に近い場所に住んでいたのでしょう。

【NO.16】杉田久女
『 立春の 輝く潮に 船行けり 』
季語:立春(春)
意味:立春の日の光が輝く海面に船が進んでいく。

春が来た海を船が渡っていく光景を詠んでいます。きらきらと日の光を受けて輝く海面が、どことなく春の気配を感じさせて心が踊るような感覚です。
【NO.17】久保田万太郎
『 春立てり あかつき闇の ほぐれつつ 』
季語:春立てり(春)
意味:立春が来た。夜明けの闇の暗さもどこか春の陽気でほぐれていくようだ。

春の夜明けの特徴といえば、日の出前の空が霞んで淡い色彩になることでしょう。夜の闇からはっきりとしたグラデーションになる冬の夜明けから、淡い色彩へと変化していく様子を「ほぐれつつ」と表現しています。
【NO.18】前田普羅
『 オリヲンの 真下春立つ 雪の宿 』
季語:春立つ(春)
意味:オリオン座の真下に立春をむかえた雪が積もった宿がある。

「オリヲン」「春立つ」「雪」と3つの季語が重なっています。この句の主題は冬の様子そのものではなく、立春をむかえてもなおオリオン座が見えて雪が積もっているという様子なので、「立春」が季語の俳句です。
【NO.19】原石鼎
『 かかる夜の 雨に春立つ 谷明り 』
季語:春立つ(春)
意味:こんな夜の雨でも、立春をむかえて谷はほんのりと明るいものだ。

「かかる」とは「このような」という意味です。本当に明るかったかどうかはわかりませんが、春という季節をむかえて雨が降る夜でも喜ばしいという感情が伝わってくる句になっています。
【NO.20】角川春樹
『 春立つや 雪ふる夜の 隅田川 』
季語:春立つ(春)
意味:立春だなぁ。春の初めといっても、雪が降っている夜の隅田川だ。

立春は春の初めとはいえ、東京でも雪が降ることもある時期です。立春という暦の上での季節の変わり目と、実際には雪が降っているという気象の上ではまだ冬であるという対比を面白がっています。
「立春」に関するおすすめ有名俳句【後編10句】

【NO.21】黒柳召波
『 音なしに 春こそ来たれ 梅一つ 』
季語:春こそ来たれ/立春(春)
意味:音もなく立春が来たのだ。梅の花が一つ咲いている。

「春こそ来たれ」は「こそ」が係り結びの助詞になっていて、立春を示す「春来たる」を強調しています。梅の花を見つけて、音はなかったけど立春の日は確かに来たのだと喜んでいる一句です。
【NO.22】尾崎放哉
『 焼印や 金剛杖に 立てる春 』
季語:立てる春(春)
意味:焼印が入っているなぁ。金剛杖に寄り添って立つように立春が来る。

「金剛杖(こんごうづえ)」は登山やお遍路の巡礼で持っている杖です。登山や巡礼の記念に焼印が押されている金剛杖を見て、またお遍路をする春が来たなぁと実感している句です。
【NO.23】日野草城
『 ぽんかんの あまあまと春 立ちにけり 』
季語:春立ちにけり(春)
意味:ぽんかんの味がとても甘い。立春が来た。

「ぽんかん」は冬の季語ですが、立春の日に食べています。とても甘いものに当たったようで、「あまあま」という表現から美味しそうな様子が伝わってきます。
【NO.24】夏目漱石
『 鳩鳴いて 烟(けむり)の如き 春に入る 』
季語:春に入る(春)
意味:鳩が鳴いて、けむりのような春になった。

作者の家に鳩が巣を作った時の一句です。寒い冬を越え、どこか煙のように霞がたゆたう春になったと詠んでいます。
【NO.25】渡辺水巴
『 さざ波は 立春の譜を ひろげたり 』
季語:立春(春)
意味:さざ波は立春の楽譜を広げている。

さざ波が冬の旋律ではなく、立春を祝う旋律を奏でているようだと感じている一句です。さざ波の音までもが冬とは違って聞こえる面白さを詠んでいます。

【NO.26】川端茅舎
『 立春の 雪白無垢の 藁家かな 』
季語:立春(春)
意味:立春の日の雪が白無垢のように見える藁の家だなぁ。

雪に覆われた家を白無垢に例えている面白い句です。まだ寒いとはいえ立春というおめでたさを感じる季節に、白無垢を着てお嫁に行く様子を想像したのでしょうか。
【NO.27】星野立子
『 小諸より 見る浅間これ 春立ちぬ 』
季語:春立ちぬ(春)
意味:小諸から見る浅間はこれだ。立春の日が来た。

【NO.28】後藤夜半
『 春立つと 古き言葉の 韻(ひびき)よし 』
季語:春立つ(春)
意味:「春立つ」という古い言葉の響きがとても良い。

立春のことを古い言葉で「春立つ」と表現します。そんな季語に対して、響きや韻の踏み方がとても良いと感じている句です。
【NO.29】金子兜太
『 河に青葉が 一つ落ちたよ 春来たる 』
季語:春来たる(春)
意味:河に青葉が一つ落ちたよ。春が来たようだ。

立春の日であることの例えとして、枯葉ではなく青葉が河に流れてきた様子を詠んでいます。青々とした若葉がこれから増えていく予感を覚える句になっています。
【NO.30】久保田万太郎
『 春立つや たぎる湯の音 猫の耳 』
季語:春立つや(春)
意味:立春の日が来たなぁ。煮えたぎる湯の音に、猫の耳が動いている。

立春の日とお湯の「音」、猫の耳という「視覚」という、日常によくあるものの取り合わせを詠んでいます。「湯の音」「猫の耳」と繋げることで調子の良いテンポを生み出している句です。
以上、立春に関するおすすめ有名俳句でした!


今回は「立春」に関する有名俳句を30句紹介しました。
立春は冬が終わり春が始まる季節…梅の開花や節分など寒さが和らぎはじめる時期です。
ふとした拍子に感じる春の気配を一句詠んでみてはいかがでしょうか?