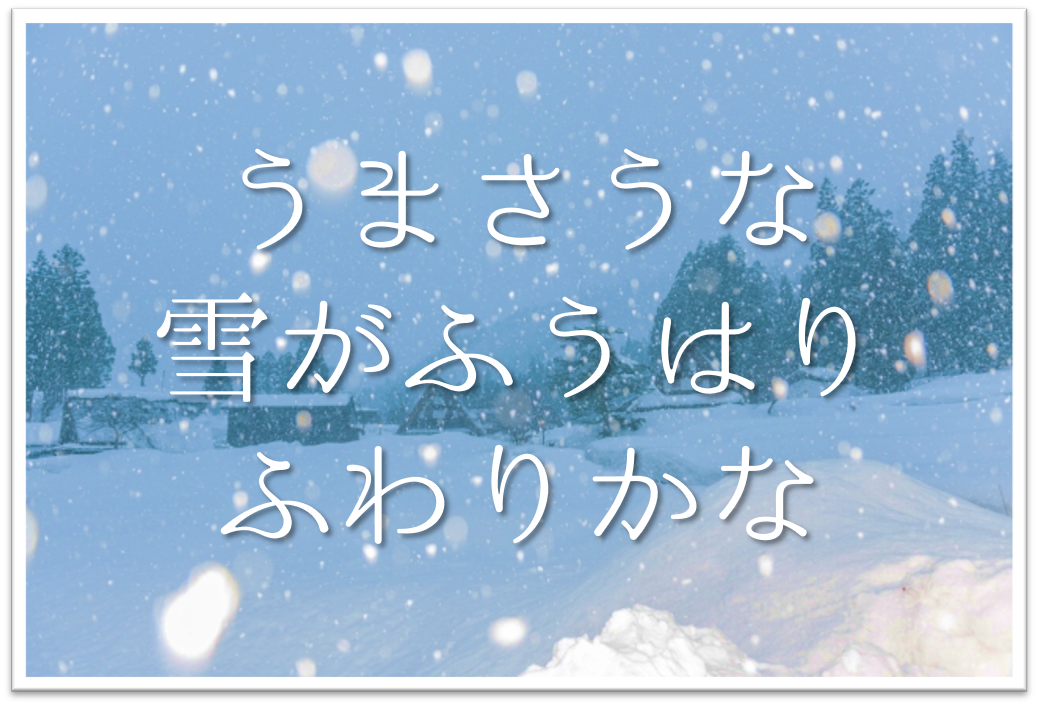
この世に存在する最も短い詩「俳句」。
わずか17音で物語つづる俳句は日本を飛び出し、今や世界中の人々から愛される芸術の一つです。
今回は数多くある名句の中でも「うまさうな雪がふうはりふわりかな」という小林一茶の句を紹介していきます。
うまさうな
雪がふうはり
ふわりかな#小林一茶 pic.twitter.com/dSSxLep8wN— tommy ☆ 夢雀 (@tommy777_tommy) December 21, 2017
本記事では、「うまさうな雪がふうはりふわりかな」の季語や意味・表現技法・鑑賞などについて徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「うまさうな雪がふうはりふわりかな」の作者や季語・意味

うまさうな 雪がふうはり ふわりかな
(読み方:うまさうな ゆきがふうはり ふわりかな)
この句の作者は「小林一茶(こばやしいっさ)」です。
小林一茶は「江戸時代の三大俳人」の1人と言われている人物です。江戸三代俳人とは小林一茶、松雄芭蕉、与謝野蕪村の3人を指します。

一茶の作品が芭蕉や蕪村と大きく違うところは、俳句になじみのない江戸時代の庶民でも理解できる簡潔な表現を使用していることです。この表現方法は「一茶句調」と呼ばれており、俳句が庶民の間に普及するきっかけになったと言われています。
季語
こちらの句の季語は「雪」、季節は「冬」です。
暦でいうと1月の季語になります。
古くから、日本では「雪」を単なる自然現象としてとらえるのではなく、何か特別な感情をもって眺められてきました。
意味
こちら句を現代語訳すると・・・
「空を見上げると、美味しそうな牡丹雪が、ふうわりふわりと降ってくることだ。」
という意味になります。

空から降る雪の様子を「ふうはりふわり」と詠むところが小林一茶らしく、柔らかい冬の情景が描かれている一句といえます。
「うまさうな雪がふうはりふわりかな」の表現技法

この句で使われている表現技法は・・・
- 比喩(暗喩)
- 切れ字「かな」
- 「ふうはりふわり」という表現
- 句切れなし
になります。
比喩(暗喩)
「暗喩」とは、たとえの表現の一種で、「~のような」とか「~のごとし」といったように、比喩であることがはっきりと分かる書き方をしていないものをいいます。
たとえるものを直接的に言い切ってしまい、聞き手に想像を委ねるように表現しています。
この句では、雪を「うまさうな雪」と言い切ってしまうことで、甘い砂糖菓子にたとえています。
切れ字「かな」
「切れ字」とは、感動の中心を表す言葉で、代表的なものに「かな」「や」「けり」などがあります。意味としては、「…だなぁ」といった感じに訳すことが多いです。
この句の切れ字は「ふわりかな」の「かな」です。
空から雪が舞い落ちてくる様子が感動的であることを、「かな」を用いて強調しています。
「ふうはりふわり」という表現
空から雪が舞い落ちてくる様子を「ふうはりふわり」という擬態語を使うことで、聞き手の想像力を刺激します。
甘くておいしい綿菓子のような雪を想像しませんか?
外は雪が降るほど寒いのに、何だかとても温かく、微笑ましい雰囲気を感じます。
このように、目に映る何気ない日常の光景が、どこか楽しいものになってしまう…小林一茶にはそんな才能があります。
句切れなし
意味や内容、調子の切れ目を「区切れ」といいます。
「区切れ」は、俳句にリズム感を持たせる効果がありますが、こちらの句では、句の意味が最後まで切れることがありません。
すなわち、「句切れなし」ということになります。
「うまさうな雪がふうはりふわりかな」の鑑賞文

【うまさうな雪がふうはりふわりかな】は、空から雪が降ってくる日常の何気ない光景を「うまそうな」という言葉と「ふうはりふわり」という言葉を使って巧みに表現しています。
雪を甘い砂糖菓子にたとえ、それを俳句に詠んでしまうところが、何ともユーモラスで、愛嬌があります。
そして、雪が舞い落ちてくる様子を「ふうはりふわり」と表現することで、綿毛のような温かさを感じます。

「その気持、よく分かる!」と思わずうなずきたくなるような表現が読んでいて楽しい一句です。
「うまさうな雪がふうはりふわりかな」が詠まれた背景

この句は文化10年(1813年)の冬に小林一茶によって詠まれたものです。
江戸後期の句日記『七番日記(しちばんにっき)』に収録されています。
文化10年(1813年)は江戸時代後半、第11代将軍徳川家斉が統治していた時期で、江戸文化が十分に発達した時代でもあったといわれています。
江戸時代はそれ以前の時代とは比べ物にならないほど文化が発達し、一般の人々にも受け入れられた時代だといわれています。江戸時代の文芸作品は大衆的なものが多く、その中の一つに俳諧(後の「俳句」)がありました。
もともと「俳諧」という言葉は「滑稽」とか「面白味」といった意味を持ち、優雅な美の世界を目指す本来の連歌からそれ、滑稽な言葉遊びとなったものを「俳諧」と呼ぶようになりました。
そして俳諧の上の句(五七五)が独立して鑑賞されるようになったものが、「俳諧の句」、すなわち「俳句」のもととなるものが誕生しました。

つまり、この句が詠まれた時代は、これまで貴族階級の間でしか浸透していなかった文化や芸術が庶民の間にも広がり、すそ野の広い発展を遂げた時代であったといえます。
「うまさうな雪がふうはりふわりかな」の補足情報

広瀬惟然の影響
この句には、広瀬惟然の影響がいくつか見られます。
広瀬惟然とは、江戸時代初期に活躍した俳人で、松尾芭蕉の門下でした。
惟然は美濃国関の俳人で、芭蕉が『笈の小文』の旅を終えて美濃国に滞留した際に門下となっています。
また、『おくのほそ道』の旅の終わりである大垣で芭蕉の元に駆けつけた門下の一人でもあり、その後伊勢神宮の式年遷宮を見物した芭蕉の世話をしています。
そんな惟然は、固い言葉使いの俳句ではなく、擬音混じりの句や口語調の俳句が見られるのが特徴です。
特に「うまそうな」の句によく似ているものがあります。
「水さっと 鳥よふはふは ふうはふは」
(訳:水がさっとかかり、鳥よふわふわ、ふうわふわと飛んでいく)
この惟然の句の「ふうはふは」という表現は、「うまそうな 雪がふうはり ふわりかな」とよく似ています。
また、惟然は雪の重みについて着目している句も詠んでいます。
「おもたさの 雪はらへども はらへども」
(訳:重たい雪は払っても払っても落としきれない)

この句では、雪の色や振り方ではなく、重さに着目している点が「うまそうな」の句と共通しているのです。
この句への批判
しかし、「うまそうな」の句は最初から評判がよい句ではありませんでした。
一茶の友人である夏目成美には、下記のように酷評されています。
「惟然坊が洒落におち入らん事おそるゝ也」
(訳:極端な口語調に走った芭蕉の最後の十哲・惟然のように駄洒落くさい俳風に陥るな)
それでも、雪の軽さを「ふうわりふわり」と現代でも通じる表現で詠んだことや、雪を「うまそうな」綿菓子のようなものとして詠んだことは、現代では評価されています。

繰り返しの技法でリズムが取れること、菓子への例えなど、口語調の俳句が主になっていく近代俳句への先駆けとも言える俳句でしょう。
雪を食べ物に見立てる俳句
「うまそうな」の句と同時期に、一茶は同じように雪を食べ物に見立てている俳句を詠んでいます。
「雪礫 馬が喰んと したりけり」
(訳:雪礫を馬が食べようとしている)
この句では主体が馬であり、口寂しさか喉を潤すためか、雪を食べようとしていると詠んでいます。
一茶の感想である「うまそうな 雪がふうはり ふわりかな」と比べると、かなり印象が変わってくる一句です。

「雪を食べるという発想」と「惟然の口語調」の俳句に触発されてこの句ができたのでしょう。
作者「小林一茶」の生涯を簡単にご紹介!

(小林一茶の肖像 出典:Wikipedia)
小林一茶(1763年~1828年)は本名を小林弥太郎といい、信濃国(現在の長野県)に生まれました。
松尾芭蕉、与謝蕪村と並ぶ江戸時代を代表する俳人の一人です。
一茶はわずか3歳の時に生母を亡くし、父の再婚相手の継母とは折り合いが悪く、次第に居場所をなくします。
唯一の味方であった祖母を亡くしたことを機に、一茶は15歳の時に江戸へ奉公に出されます。
その後も13年間に渡って争われた遺産相続問題や相次ぐ子どもと妻の死など、一茶は波乱万丈ともいえる厳しい人生を強いられます。
こうした人生における数々の苦労からか、一茶の句は日常の些細な出来事や身近な風景が描かれることが多く、温かく、親しみを覚える内容が特徴となっています。
小林一茶のそのほかの俳句

(一茶家の土蔵 出典:Wikipedia)















