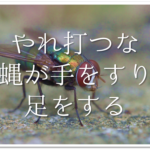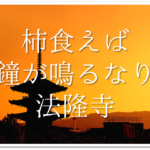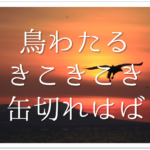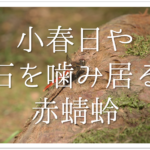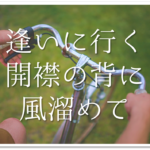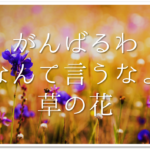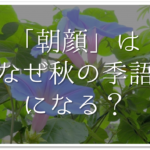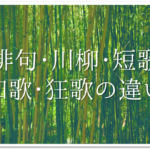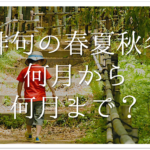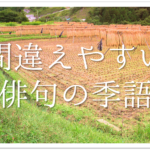俳句の表現方法の一つである「倒置法」。
倒置法は国語の文法で使われる用語ですが、小説や短歌などにも使われているので親しみやすい方法といえます。
先日、5歳児が書いた心の俳句。
たべますよ そうめんいっぱい ◯◯(子の名前)が
倒置法ときた。 pic.twitter.com/WAtPVK337w— 黄嶋カブ夫 (@walkaholics) May 31, 2014
今回は、俳句の倒置法の意味や効果・実際に俳句にどのように使われるのかなどについて、簡単にわかりやすく解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
俳句の倒置法とは?簡単にわかりやすく解説!

倒置法とは、言葉や文の使い方を本来の順番とは逆にする方法です。
文章を読むとき、私たちは最後の単語に意識を向けています。
倒置法によって、語句の配置を逆にすることで、最後に来る言葉に読み手の印象を与えることができるのです。
例えば、「今晩の月は、きれいだな。」を倒置法にすると、「きれいだな、今晩の月は。」となります。

倒置法にすることで、最後の言葉「今晩の月は」を読み手に印象強く与えることができます。
【CHECK!!】体言止めとの違い
倒置法と似た表現として、体言止めがあります。体言止めとは、文の終わりを名詞や代名詞で止める方法です。
倒置法と体言止めがどう違うのか、よくわからないという方も多いですね。
実際に例文をあげてみましょう。
「私は遊園地に行きました。」
→体言止め「私が行ったのは、遊園地。」
→倒置法「私は行ったのです、遊園地に。」
体言止めでは、名詞や代名詞で終わるのに対して、倒置法では、名詞や代名詞では終わりません。
よく似ている表現方法ですが、区別するようにしてください。
俳句における倒置法の効果

倒置法の効果としては・・・
1.語句の強調
2.感情をうまく伝えられる
3.言葉のリズムを整えることができる
の3つがあげられます。

ここからは、それぞれの効果を詳しく解説していきます。
1.語句の強調
倒置法の効果として、最も親しみやすいのが「強調」です。
倒置された言葉を強めることにより、読み手にそれをより印象深くすることができます。

実際に例文をあげてみましょう。
「夕日が燃えているよ。」この文を倒置法にすると、「燃えているよ、夕日が。」となります。
この文にすると、読み手は「何が燃えているのか。」が気になり、最後に「夕日が」とくることで、「なるほど、夕日が燃えているのか。」と夕日により強い印象を持つことができます。

「夕日が燃えているよ。」と普通に伝えるよりも、夕日の印象をより強調できるのです。
2.感情をうまく伝えられる
倒置法の効果として、感情をより読み手に伝えられることがあげられます。
「私は、嫌だ!と大声をあげた。」の文を倒置法にすると、「私は大声をあげた。嫌だ!と。」となります。

あえて最後に、「嫌だ!」と感情を伝える言葉を持ってくることで、より読み手の感情に迫ることができるのです。
3.言葉のリズムを整えることができる
「子どもがかわいいのは当然よ。」を倒置法にすると、「当然よ。子どもがかわいいのは。」となり、会話のリズムをよくすることができます。
もちろん、一つの効果だけではなく、色々な効果が合わさってできたものもあります。

倒置法によって、色々な味わいが出てくるのです。
倒置法の使い方やコツ・注意点

倒置法は、語順を入れ替えるだけで、印象を強くすることができます。

では、その使い方のコツや注意点について考えてみましょう。
1.語順を入れ替えてみる
日本語は、「主語、目的語、述語」の構成が一般的です。
倒置法では、「主語、述語、目的語」の順番となります。
例えば、以下の文章。
「わたしは(主語)、海へ(目的語)泳ぎに行った(述語)」
これに倒置法を用いると・・・
「私は(主語)泳ぎに行った(述語)海へと(目的語)」
となります。
倒置法は、語順を入れ替えるだけなので簡単に使えます。

ただ、不自然すぎる文になることもあるので、実際に声に出して読んでみることが大切です。
2.倒置法には、向かないものがある
倒置法は、俳句はもちろん、感情を伝えることができる小説や和歌、歌詞などに向いている技法です。
読み手の感情を揺さぶることができるので、倒置法により表現の幅をぐっと広げることができます。
ただ、事実を述べる必要があるもの、論文、新聞、ビジネスの場などでは向きません。

このような文章では、感情ではなく事実を書く必要があるため、倒置法を使うとわかりにくいものとなってしまいます。
3.何度も使わない
倒置法は、言葉やリズムに変化をつけるのに最適な方法ですが、使いすぎると印象度が落ちてしまいます。

特に感情に訴えたいというときにのみ、使うことが大切です。
倒置法を使った有名俳句集【10選】

【NO.1】小林一茶
『 やれ打つな 蝿が手をする 足をする 』
季語:蝿(夏)
意味:やれ、叩くな。蝿が手足をすり合わせて命乞いをしているではないか。

【NO.2】正岡子規
『 毎年よ 彼岸の入りに 寒いのは 』
季語:彼岸(春)
意味:彼岸の入りが冷えるのは毎年のことよ。

【NO.3】中村草田男
『 葡萄食ふ 一語一語の 如くにて 』
季語:葡萄(秋)
意味:葡萄の実を一粒一粒とちぎって食べる、言葉を一語一語味わうように。

【NO.4】阿波野青畝
『 赤い羽根 つけらるる待つ 息とめて 』
季語:赤い羽根(秋)
意味:募金をした証である赤い羽根を付けられるのを待っている、息を止めて。

【NO.5】松尾芭蕉
『 いざ行かむ 雪見にころぶ 所まで 』
季語:雪見(冬)
意味:さあ、雪見の宴に行きましょう。雪に足をとられて転んでも楽しいではありませんか。さあ、一緒に雪で転ぶところまで行きましょう。

【NO.6】正岡子規
『 柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺 』
季語:柿(秋)
意味:柿を食べていると鐘が鳴ったよ、この法隆寺で。

【NO.7】秋元不死男
『 鳥わたる こきこきこきと 缶切れば 』
季語:鳥わたる(秋)
意味:鳥が渡っていく。こきこきこきと缶詰を切っていると。

【NO.8】村上鬼城
『 小春日や 石を噛み居る 赤蜻蛉 』
季語:小春日(冬)
意味:小春日だなぁ。石を噛むようにそこに居る赤トンボよ。

【NO.9】草間時彦
『 逢いに行く 開襟の背に 風溜めて 』
季語:開襟(夏)
意味:逢いに行こう。開襟シャツの背に風を溜めて。

【NO.10】坪内稔典
『 がんばるわ なんて言うなよ 草の花 』
季語:草の花(秋)
意味:がんばるわなんて言うなよ、草の花よ。

以上、俳句における倒置法についてでした!
倒置法は、古来より伝わる表現技法です。
語句を並び替えることにより、より効果的に読み手に情景を浮かび上がらせることができます。