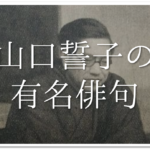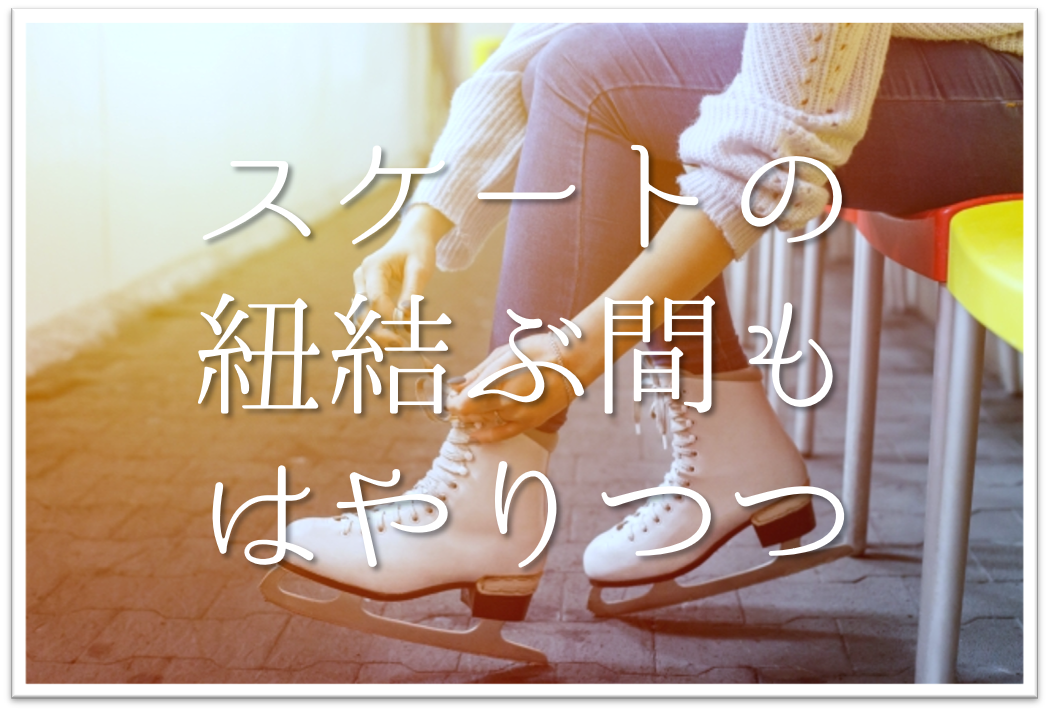
「俳句」は、日本の伝統的な文芸でありつつも、常に革新と進化を続けています。
令和の現代でも俳句をたしなむ人、鑑賞する人は増える一方です。
時代ごとの世相に合わせて俳句も変わり続けていますが、名句と呼ばれる句はすぐれた文学としての普遍性を持ち、多くの人々に衝撃を与えたり、共感を得たりしています。
今回は数ある名句の中から「スケートの紐結ぶ間もはやりつつ」という句を紹介していきます。
小3国語の教科書の俳句
「スケートの紐むすぶ間も逸りつつ」
山口誓子
スケート靴のひもをむすんでいる間にも、早くすべりたくて、むねがわくわくしてくる本読みの宿題で反応した( *´艸`) pic.twitter.com/nhxHzySyOY
— かば (@kyababa266) July 14, 2015
本記事では、「スケートの紐結ぶ間もはやりつつ」の季語や意味・表現技法・作者について徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「スケートの紐結ぶ間もはやりつつ」の季語や意味・解釈

スケートの 紐結ぶ間も はやりつつ
(読み方:スケートの ひもむすぶまも はやりつつ)
こちらの句の作者は「山口誓子(やまぐち せいし)」です。
女性と勘違いされがちですが山口誓子は京都府出身の男性俳人です。明治に生まれ、大正・昭和・平成のはじめまでを活躍した俳人です。
初期の誓子は叙情的な俳句を好んでいましたが、後に近代的、都会的なものを題材に俳句を詠むようになります。
また、「や」「かな」といった切れ字を用いるのではなく、動詞の終止形・連体形による止めや口語の使用を定着させました。
季語
こちらの句の季語は「スケート」で、季節は「冬」を表します。
じつはスケートが日本に導入されたのは、明治時代初期のことです。当時は富裕層のみしか楽しめないスポーツでした。
庶民が本格的に楽しめるようになったのは大正時代になってからですが、スケート靴が高額であったため下駄スケートを楽しんでいました。
意味
こちらの句を現代語訳すると・・・
「楽しみにしていたスケート、スケート靴に履き替え靴紐を結んでいる間も心は早く氷の上に立ちたいとはやっていることだ。」
となります。
作者がスケート場で靴紐を結んでいる情景を俳句として表現しています。

スケートを少しでも早くしたい、スケート靴を結んでいる時間さえももったいないという心情が伝わって来ます。
解釈
こちらの句のポイントは、「スケートの紐結ぶ間も」です。
この表現は、スケート靴の紐を結んでいるわずかな時間を表現しています。
さらに「はやりつつ」ははやる気持ちを表しており、「もどかしさ」「気持ちが急く」「気持ちがうずいている」という状態です。
「作者が早くスケートを滑りたくて仕方がなく、スケート靴の紐を結んでいる時間ももどかしい」と解釈できます。

どんなに誓子が、スケートを楽しみにしているのかが分かりますし、「ドキドキワクワク」と興奮している気持ちも伝わって来る作品です。
「スケートの紐結ぶ間もはやりつつ」の表現技法

句切れなし
一句の中で、意味・リズムの上で大きく切れるところを句切れと呼びます。普通の文でいえば句点「。」がつくところで切れます。
しかし、この句には途中で切れるところがありませんので「句切れなし」の句となります。
スケートを少しでも早くしたい、スケート靴を結んでいる時間さえももったいないという心情が途切れることなく一息で詠まれています。
「スケートの紐結ぶ間もはやりつつ」の鑑賞文

現在のように娯楽がそんなになかったであろう時代だけに、スケートに行くこと自体が大きなイベントであったのだろうと推察できます。
誓子は「ワクワクドキドキ」と胸を弾ませながらスケートリンクに足を運んだのです。
スケート靴の紐を結ぶ手が寒さでかじかんでしまい、うまく結べなかったかのかもしれません。
「早く滑りたいのに、思うようにスケート靴の紐が結べない」という様子が伝わって来ます。
「すでにスケートを楽しんでいる人たちのように、スイスイとスケートを滑れたら爽快だろうなあ。一刻でも早く滑って自分もあんな風に上手になりたい」といった思いも感じられます。
スケートに限らず、誰もが一度はこのように「早く行いたいのに、まどろっこしい」という状態に出会したことがあるはずです。

それだけに、誓子のもどかしい気持ち・高揚感、そして緊張がとても感じられます。
「スケートの紐結ぶ間もはやりつつ」の補足情報

日本でのスケートの歴史
日本で最初にスケートをして見せたのは、江戸時代に根室に来航したロシア帝国のアダム・ラクスマンらだと言われています。
1792年から翌年にかけて同地で越冬しているうちに、氷結した海面を、鉄刃をつけた靴を履いて滑る様子が絵と文で記録されていて、現在のフィギュアスケートのように両脚だけでなく片脚だけで滑っていても氷上を速く移動したり回ったりできることも書かれています。
その後、東京でスケートが実演されたのは、1872年2月のことです。増上寺裏手の弁天池で外国人技師たちがスケートを楽しみ、多くの人の興味を誘いました。

正式に遊戯や競技としてのスケートを伝えたのは、明治時代の初めに札幌農学校へ着任したアメリカ人教師ブルックスとされています。
日本初スケートリンクは大正時代に作られた
戦前の日本では、スケートリンクは一般的には冬季に湖水・池水の自然氷を利用して天然のリンクとして使用されていました。
しかし、天候、氷の厚さ、氷の良し悪しに左右されることが多く、いつでも滑れるわけではありません。
大正時代末期になると、大阪に日本初の人工のスケートリンク「北極館」ができましたがが、全国的には数が少なかったとされています。

戦後になり、高度経済成長期になると資金のかかるスケートリンクが多く作られるようになり、趣味や競技などさまざまな用途で用いられるようになっていきます。
スケート靴の種類
スケート靴は海外では古くから使われていて、骨や木、竹などで作られていました。
幕末の日本では、下駄に竹や鉄を取り付けたソリ状の滑り下駄がありましたが、後に海外から新たにもたらされたスケートに影響を受け、下駄に金属製のブレードを組み合わせた下駄スケートが作られます。
これは1906年に長野県で作られたもので、外国製のスケート靴を模して下駄の底に鉄製の刃をつけた「カネヤマ式下駄スケート」と呼ばれるものです。
この下駄スケートの流行により、スケートが日本国内に急速に広まりました。
現在のような革製のスケート靴に完全に取って代わられる昭和30年代中頃までは、一般的に使われていました。
作者は「紐を結ぶ」と表現しているので、この下駄スケートではなく、現在と同じような革製のスケート靴を使って滑ったことがわかります。

スケートリンクやスケート靴の歴史を知っていると、当たり前のようにスケートで遊べる時代になって作者がワクワクしているのがよくわかりますね。
作者「山口誓子」の生涯を簡単にご紹介!
(山口誓子 出典:Wikipedia)
山口誓子は、1901年(明治34年)に現在の京都府左京区で生まれました。本名は新比古(ちかひこ)で、誓子(せいし)は俳号です。水原秋桜子・高野素十・阿波野青畝とともに「ホトトギスの四S」と評価されていました。
誓子氏は、わずか10歳にして実母を自殺で亡くしています。
その後、現在の京都大学総合人間関係学部及び岡山大学の前身であった第三高等学校に進学し、19歳の時に京大三高俳句会に出席。その際に出会った日野草城の句に感銘したことがきっかけとなり、俳句の世界へ導かれます。
草城、鈴鹿野風呂に師事し、『ホトトギス』に投稿を続け初入選しています。
21歳の時に現在の東京大学法学部に入学し、東大俳句会を再興。東大卒業後はサラリーマンとなり句作をしていたとのこと。
その後、『ホトトギス』課題専任に就任。浅井梅子と結婚。1932年には第一句集『凍港』刊行するものの、病に倒れ『ホトトギス』を辞して、水原秋桜子とともに「馬酔木」に移行し、新興俳句運動の指導者として活躍しました。
戦後は「天狼」を主宰し、その後勲三等瑞宝賞、日本芸術院賞、朝日賞、文化功労賞を受賞します。
1994年に享年92歳で逝去します。神戸大学キャンパス内に山口誓子記念館があり、不定期に公開されています。
山口誓子のそのほかの俳句

( 摂津峡にある句碑 出典:Wikipedia)