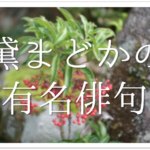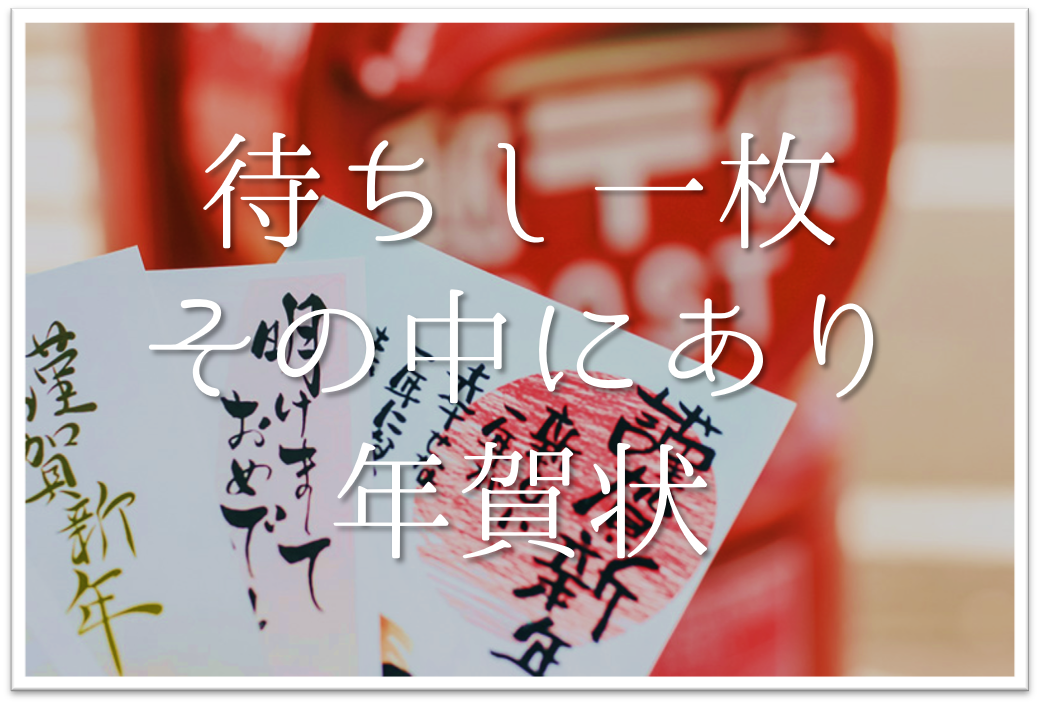
日本には現代の俳人によって詠まれた作品がたくさんあります。
その中には、季節特有の行事の中で感じた心情をテーマにした作品も多く存在します。
今回は、数ある名句の中から「待ちし一枚その中にあり年賀状」という句を紹介していきます。
待ちし一枚その中にあり年賀状か!!!!!
— エリオット (@ali_o_alio) October 11, 2012
本記事では、「待ちし一枚その中にあり年賀状」の季語や意味・表現技法・鑑賞・作者について徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「待ちし一枚その中にあり年賀状」の季語や意味・詠まれた背景

待ちし一枚 その中にあり 年賀状
(読み方 : まちしいちまい そのなかにあり ねんがじょう)
こちらの作品は、現代の俳人「黛まどか(まゆずみ まどか)」によって詠まれた作品です。
お正月に連絡を待っていた大切な人からの1枚を年賀状の束の中から見つけた時に詠まれた句です。

それでは、早速こちらの俳句について詳しくご紹介していきます。
季語
こちらの句の季語は「年賀状」で、季節は「冬」を表しています。
意味&解釈
こちらの句をわかりやすく訳すと・・・
「たくさんの年賀状がきた。その中に 待っていた1枚があった。」
となります。
待っていた一枚が、想いを寄せている恋人の年賀状であるのか、または親友からの1枚であるかは作者にしか分かりません。
こちらの作品では、ただ1枚だけ待っていた大切な年賀状をたくさんの年賀状の中から見つけた時の心情を詠んでいます。
何十枚、何百枚という年賀状の中から大切な1枚を見つけた時の、作者の弾けるような嬉しさが伝わってくる作品です。

読者のみなさんの中にも同じような経験をしたことが、1度はあるはずです。それだけに読み手の共感を得やすく、親しみやすい作品です。
「待ちし一枚その中にあり年賀状」の表現技法

こちらの作品で使われている表現技法は・・・
- 体言止め「年賀状」
- 字余り「待ちし一枚」
になります。
体言止め「年賀状」
こちらの作品では末尾の「年賀状」が体言止めです。
体言止めとは、俳句の結びを名詞で止める表現技法で、そのシーンをイメージしやすくなります。また、同時にインパクトのある作品に仕上がり、読者の記憶に残りやすい俳句となります。
こちらの句では、年賀状の中から待っていた差出人の名前を見つけた時の様子が、ヒシヒシと伝わってきます。
字余り「待ちし一枚」
字余りとは「5・7・5」の俳句の定型に対し、音が多いことを表します。字余りとすることで、独自のリズムに仕上がりインパクトのある作品になります。
こちらの作品では、「待ちし一枚」の部分が字余りです。
「まちしいちまい」は、上句でありながら7音と2音オーバーしており、字余りとなっています。

こちらでは「字余り」を用いることによって、独特のリズムで口ずさみやすいですし、作者の置かれている情景が分かりやすくなっています。
「待ちし一枚その中にあり年賀状」の鑑賞文

【待ちし一枚その中にあり年賀状】からは、とても大切な人の年賀状をたくさんの枚数の中から見つけた時の、作者の嬉しそうな笑顔とほっとした気持ちが伝わってきます。
その大切な年賀状を見つけて、「元気に過ごしていてよかった」「私のことを忘れないでいてくれて嬉しい」という気持ちがダイレクトに感じられる作品です。
どんなに作者が、たった1枚の年賀状を大切に想い、待ちわびていたであろうかが分かります。
また、同時に年賀状離れが進む現代だからこそ、1枚の便りがもたらす大切な絆がいかに貴重であるかを感じ、改めて年賀状の良さに気付かされました。
「待ちし一枚その中にあり年賀状」の補足情報

1000年にも及ぶ年賀状の歴史
新年の挨拶として日本の文化に深く根付いている年賀状ですが、その起源は古く1000年以上前の平安時代にまで遡ります。
記録に残る最も古い年始の挨拶状は、平安時代の学者、藤原明衡がまとめた手紙の文例集『雲州消息(うんしゅうしょうそく)』にあるもので、現在の年賀状と変わらない新年の喜びを伝える文例が記されており、当時すでに貴族階級の間で年始の挨拶を文書で交わす文化があったことがうかがえます。
鎌倉・室町時代を経て武家社会にも年始の挨拶状は広まりましたが、庶民にまで普及したのは江戸時代です。
この頃には、年始回りで不在だった場合に備え、玄関に場所を設けて挨拶状を投函してもらうという、現代の年賀状に近い習慣も見られました。
年賀状が現在のような形になったのは、明治時代に近代的な郵便制度が確立されてからで、1873年(明治6年)に郵便はがきが発行されると手軽さから年賀状を出す人が急増し、現在の年賀状の形に収まっています。

作者が、年賀状が届いたとワクワクしながら詠んでいる背景には、1000年にも及ぶ年始の挨拶の歴史があったというのが面白いですね。
年賀状に関する有名俳句
ここでは、年賀状を扱った他の俳句をいくつか紹介していきます。
【NO.1】日野草城
「枕辺へ 賀状東西 南北より」
季語:賀状(新年)
意味:枕元に年賀状が東西南北の知り合いから届いている。

「東西南北より」と表現することで、全国に散らばる友人知人から年賀状が届いていることがよくわかります。また、「枕辺」とあることから、作者が眠っている間に届いた年賀状を仕分けしてもらっている様子が目に浮かんでくる一句です。
【NO.2】高浜虚子
「一行の 心を籠めし 年始状」
季語:年賀状(新年)
意味:一行だけの文章に心をこめる年賀状だ。

年賀状には一行だけ手書きで年始の挨拶や今年の抱負を書く人も多いでしょう。たった一行だけの文章に、相手への友情や信頼を込めて書く年賀状をよく表した句です。
【NO.3】稲畑汀子
「年賀状 だけのえにしも いつか切れ」
季語:年賀状(新年)
意味:年賀状だけで繋がっていた縁もいつしか切れてしまった。

賀状だけで繋がっていた縁が、いつしか年賀状を出さなくなることで連絡先も分からなくなり、縁が切れてしまう様子を詠んでいます。現在のネット社会では年賀状を出さなくなることも多いので、心当たりのある人もいるのではないでしょうか。
作者「黛まどか」の生涯を簡単にご紹介!

(湯河原町の中心部 出典:Wikipedia)
黛まどかさんは、1962年7月31日に神奈川県足柄郡湯河原町で生まれ、1983年にフェリス女子学院短期大学を卒業しています。
大学卒業後は富士銀行に勤務し、杉田久女と出会い俳句の世界に惹かれて行きました。
俳句結社「河」にて吉田 鴻司の指導を受け、その後は角川俳句激励賞や山本健吉文学賞を受賞。
現代俳句の先駆者として活躍し、現在は著名人達の会員制句会「百夜句会」の主宰者でもあります。
俳人の黛まどかさんがエッセー集「ふくしま讃歌」。震災後の福島を歩き、その宝を紹介。花のあふれる桃源郷「花見山」を造った阿部一郎さん「戦争で傷ついた人の心を癒すため花を植えた。震災もこの苦しみを生かさなければ」を出発点に。絶景広がる「只見線」。雪の「大内宿」・・。しんぶん赤旗日曜版 pic.twitter.com/0Cen1oYUk3
— 中田晋介 (@sinsuke_nakata) December 3, 2016
黛まどかのそのほかの俳句

- 別な人 見てゐる彼の サングラス
- 旅終へて よりB面の 夏休
- 観覧車 より東京の 竹の春
- 虫の夜の 寄り添ふものに 手暗がり
- かまいたち 鉄棒に巻く 落とし物
- バレンタイン デーカクテルは 傘さして
- 可惜夜の わけても月の 都鳥