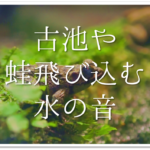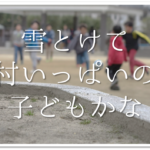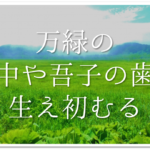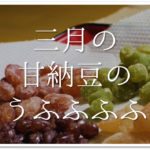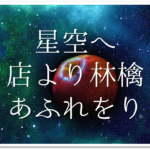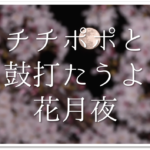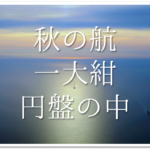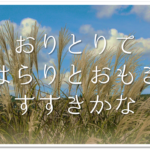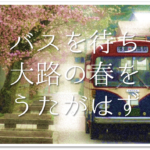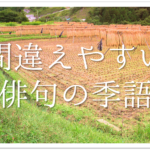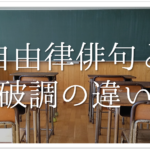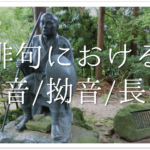バラエティ番組「プレバト!!」でお馴染みの俳句。
以前はご年配の方々の趣味といったイメージがありましたが、最近はこの番組効果もあってか随分若い方にも受け入れられているという印象があります。
しかし、俳句の世界はとても奥深いため、適当に五・七・五の文字数で作ったところでうまい俳句とは言えません。
俳句作れないなぁ。ぜんぜんうまくできないよ。
— 齋藤路恵 (@saitom11) August 13, 2015
俳句はうまく作れないけど読むのは大好きだ。
— あきのな(本物)@Skeb (@akinona) October 1, 2010
そこで今回の記事では、良い俳句はどのように作れば良いのかという点を、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

目次
良い俳句とは?うまい俳句の定義や基準・特徴

五・七・五のリズム感がある
俳句は【五・七・五】の文字のつらなりが生み出す歯切れの良いリズム感が命です。
柿くへば(5) 鐘が鳴るなり(7)法隆寺(5) by 正岡子規
このリズムによって力強さが生まれ、句の情景がありありと目に浮かんできます。
俳句を作ったら、まずは声に出してリズム感があるかどうかを確認してみましょう。
季語のチョイス
季語とは、多くの人がいかにもその季節らしいと感じるような言葉のことを言います。
例えば、春なら桜やひな祭り、夏なら海水浴やかき氷といった季語があります。
俳句には原則的には季語を1つ入れる必要がありますが、その言葉のチョイスは大切です。
良い俳句にするためには、「季語はこれで良いのか」「別の物に置き換えた方が良いのか」という点を今一度確認しましょう。
季語はあまり聞き馴染みの無い言葉まで含めると膨大な数があります。
そのため、1度「歳時記(さいじき)」という書籍を使って、季語はどのようなものがあるのかというのを勉強することをおすすめします。

オリジナリティがある
ご自身が作成した俳句が、過去に発表された俳句に似ていたり、ありきたりな表現を使っていたりする場合には良い俳句とは言えません。
例えば、季語1つとっても春の季語で「桜」を使うのはちょっとオリジナリティに欠けるかもしれません。
ありきたりな俳句の例 (季語 運動会)
運動会 全力応援 声からす
オリジナリティのある俳句の例 (季語 爽やか)
爽やかに 早まる鼓動 待つバトン

失敗しないためにも押さえておきたい!悪い俳句の特徴

無駄な説明が多い俳句は悪い俳句の特徴です。
無駄な説明が多い俳句の例
コスモスが 風に揺れるよ こころもち(風に揺れるは不要な説明)
俳句は五・七・五の17音しかないため、1文字も無駄にしてはいけません。そのため、まずは「で、ば、が、に、は」といった助詞は使わないようにしましょう。
また、個人的感情や感想の表現も不要です。この句に対してどう思うかは読み手の解釈に任せましょう。
無駄な説明がない俳句の例
コスモスや 医者に行きたい こころもち
また、意味が重複するような言葉もギリギリまで削るのがおすすめです。読み手の想像力で補うことが可能な語は排除しましょう。
そして基本的なことですが、初心者の方は季語は1つ、動詞は1つ、句切れは1つで俳句を作ってみましょう。

良い俳句の作り方・コツ・注意点

字面で全てを表現しすぎない
俳句は作者の思いなどを何でも直接的に述べてしまうと、標語のような出来上がりとなってしまいます。
そもそも五・七・五の17音で全てを説明することは不可能なため、読み手がいろいろと想像を膨らませることが出来る作品が良い俳句と言えます。
中間切れを用いてみる
中間切れとは、五・七・五の七音の途中で句切れさせる手法のことを言います。
万緑の 中や/吾子の歯 生え初むる(吾子の歯の前で一旦切れている)
上記の句のように途中で句切れさせることによって、読み手にその単語を鮮烈に印象付けることが出来ます。
主語は必ずしも必要ではない
俳句を作る際、主語は必ずしも入れる必要はありません。
俳句というのは、読み手の解釈に任せて自由に楽しんでもらうという部分も大切です。

知っておきたい!!おすすめ有名俳句集【5選】

【NO.1】松尾芭蕉
『 古池や 蛙飛び込む 水の音 』
季語:蛙(春)
意味:淀んだ水である古池は静まりかえっているけれど、一瞬ポチャンと蛙が飛び込む音がして、その後は再び静寂である。

【NO.2】小林一茶
『 雪とけて 村いっぱいの 子どもかな 』
季語:雪とけて(春)
意味:雪が解けて、村にたくさんの子供たちが遊びに出てきているなぁ。

【NO.3】中村草田男
『 万緑の中や 吾子の歯 生え初むる 』
季語:万緑(夏)
意味:夏の見渡す限り青々とした草原の中でも、我が子の生え始めた真っ白な乳歯の鮮やかさが際立っている。

【NO.4】堀内稔典
『 三月の 甘納豆の うふふふふ 』
季語:三月(春)
意味:甘納豆を頬張って思わず「うふふふふ」という笑みがこぼれている。

【NO.5】小林一茶
『 ふるさとや 寄るもさはるも ばらの花 』
季語:ばら(夏)
意味:故郷へ遥々やってきてみると、家族だけではなく、村人までもが、薔薇の花の棘のように私の心を痛めつける。

【NO.6】橋本多佳子
『 星空へ 店より林檎 あふれをり 』
季語:林檎(秋)
意味:星空に向かって店に積まれたリンゴがあふれている。

【NO.7】松本たかし
『 チチポポと 鼓打たうよ 花月夜 』
季語:花月夜(春)
意味:チチポポと鼓を打とうよ、この美しい花の咲く月夜に。

【NO.8】中村草田男
『 秋の航 一大紺 円盤の中 』
季語:秋(秋)
意味:秋の航海は、一面紺色の円盤の中にいるようだ。

【NO.9】飯田蛇笏
『 おりとりて はらりとおもき すすきかな 』
季語:すすき(秋)
意味:折りとると、はらりと重いススキだなぁ。

【NO.10】石田波郷
『 バスを待ち 大路の春を うたがはず 』
季語:春(春)
意味:バスを待っていると、この大きな道に来た春を疑うことは無いだろう。

以上、上手い俳句の作り方でした!
今回は、うまい俳句を作るためにはどんなところに気を付ければ良いのかという点についてご紹介しました。
俳句はたくさん読んでたくさん作れば、どんどん上達していくのでとても面白いです。