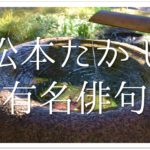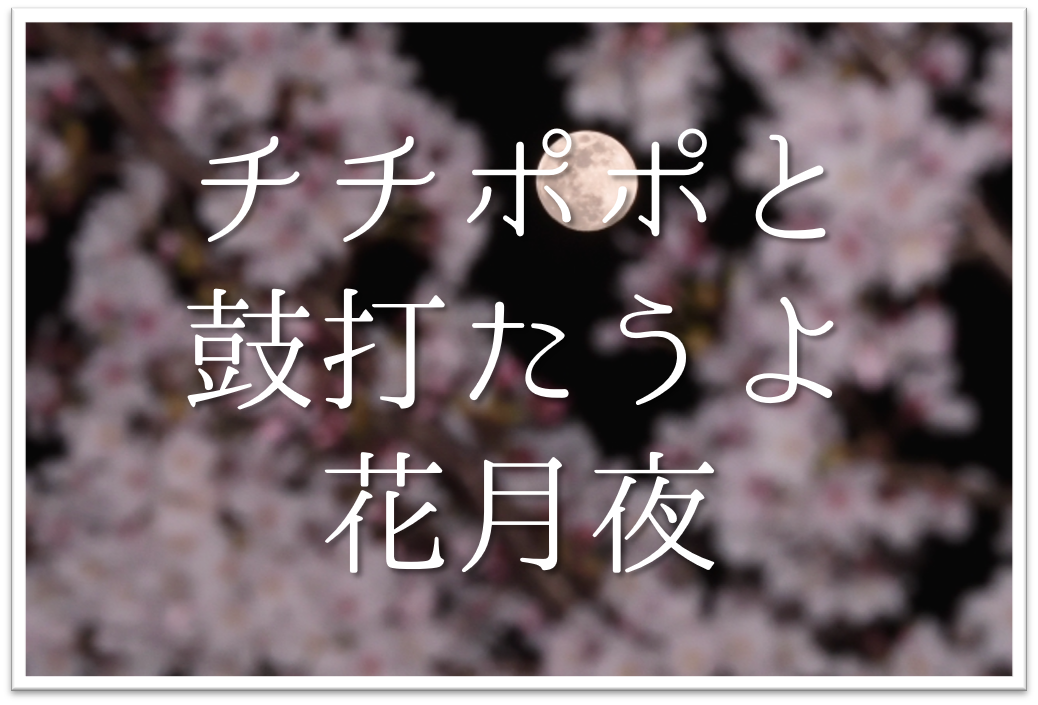
俳句は十七音を活かすために、様々な工夫を凝らします。
言葉の選定や独特な表現を使うことで、読み手が想像を巡らせます。
なかでも「チチポポと鼓打たうよ花月夜」という句は伝統的な美しさが表現されている句として知られています。
チチポポと鼓打たうよ花月夜
俳句カルタ・・チチポポと言えなかった花音が可愛い(笑) pic.twitter.com/wD5JwsQ2OU— かおり(マ) (@o_rora777) September 2, 2015
作者はどのような背景でこの句を詠み、風景の美しさを表現したのでしょうか?
本記事では、「チチポポと鼓打たうよ花月夜」の季語や意味・表現技法・作者などについて徹底解説していきます。

目次
「チチポポと鼓打たうよ花月夜」の季語や意味・詠まれた背景

チチポポと 鼓打たうよ 花月夜
(読み方:ちちぽぽと つづみうとうよ はなづきよ)
この句の作者は「松本たかし」です。
松本氏は、大正から昭和にかけて活躍した写生を得意とする俳人です。
(※写生…実物・実景を見てありのままに写し取ること)
季語
この句の季語は「花月夜(はなづきよ)」で、季節は「春」を表します。
花月夜とは、桜の季節に見られる満月の夜のことです。
風景としては、少し霞かかった空に満月が浮かんでおり、月の明かりで桜の様子が見える柔らかいイメージです。

意味
この句を現代語訳すると・・・
「美しい花月夜の夜に、鼓(つづみ)をチチポポと打って楽しく過ごそうよ。」
という意味になります。
鼓(つづみ)は、日本特有の伝統的な楽器のひとつで、もっとも狭義には「小鼓」を指します。
この句が詠まれた背景
この句は松本たかしが1938年に詠んだ句で、句集「鷹」に収録されています。
能役者の家に生まれた彼は幼少期から修行していましたが、病により能役者を断念しました。当時、彼は既に俳人として生活をしており、能を仕事で舞うことはありませんでした。
しかし、きっかけがあれば舞うことが生涯身についていました。
その一つが桜の時期で、この時期になると自宅の庭で鼓を打ち、舞って遊んでいたと言われています。

「チチポポと鼓打たうよ花月夜」の表現技法

擬音語「チチポポ」
擬音語とは、物の音や声などをそれらしく言い表した言葉のことです。音を言葉にすることで、その時の様子が分かりやすくなる効果があります。
(※例えば「くすくす笑う」「どかんとはぜる」の「くすくす」や「どかんと」など)
今回の句は鼓の音である「チチポポ」が擬音語にあたります。
鼓の音は一般的に「ポンポン」と表現されますが、そうでないのは松本たかしが能役者であったことに関係しています。
鼓には音階があり「チ」「プ」「タ」「ポ」の4種類があります。
その音にリズムをつけることで音楽を奏でており、能役者はそれを知っています。

体言止め
「体言止め」とは、文末を名詞で結ぶ表現技法です。
体言止めを使用することにより、文章全体のインパクトが強まり、作者が何を伝えたいのかをイメージしやすくなります。
今回の句では「花月夜」という名詞で終わっています。
美しい月と桜が見られる夜であったことが強調され、読み手が風景を考えるようになります。
「チチポポと鼓打たうよ花月夜」の鑑賞文

【チチポポと鼓打たうよ花月夜】は、春の夜を気品ある表現で描いた作品です。
松本たかしは能役者を病により断念する悲しい過去を持っています。しかし、花月夜には皆に舞って見せたり、鼓を打ったりするなど風流さが生活の中に残っていました。
彼の舞や鼓を知っている人たちは「芝居の舞台を見ているようだ」と表現するほどきれいであったと語っています。
花月夜だけでも美しいですが、彼の舞や鼓の音が加わることで美しさが完璧に近づきます。それほど、彼が見た月と桜は見ごたえがあるものであったことが分かります。
さらに、独特の表現である「チチポポ」が格調を高め、気品ある作品に仕立てています。

作者「松本たかし」の生涯を簡単にご紹介!
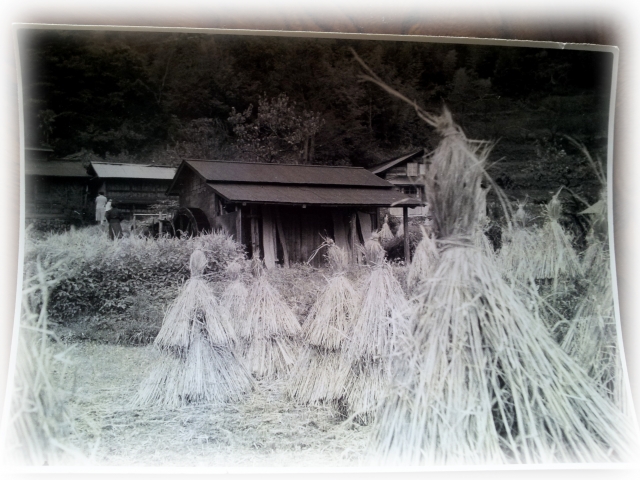
松本たかし(1906年~1956年)本名は松本孝。東京都出身の俳人です。
父は能楽師の松本長、弟の松本惠雄も宝生流の能楽師となりのちに人間国宝となっています。作家の泉鏡花は親戚でした。
たかし氏は江戸幕府に仕えていた宝生流能役者の家に生まれ、5歳から能の修行を始めました。しかし14歳の時に病を患い、20歳で能の道を断念します。
療養中、病床を見舞った父が残していった「ホトトギス」を読んで俳句に興味を持ち、1922年に父の能仲間の句会「七宝会」に参加するようになりました。
この病の間に俳句に興味を持ち、俳誌「ホトトギス」へ投句を始め、高浜虚子に師事します。
それ以降は俳人として生計を立てながら、終戦後も句集や小説を発表していました。
6月に療養中の句が「ホトトギス」に4句入選し、これを機に能役者になることをほぼ諦め俳句に専心するようになります。1929年、「ホトトギス」巻頭を取ったことを始めとして、川端茅舎や高野素十などの俳人と知り合い親交を結びました。
1948年にはかつての能の師であった宝生九郎をモデルにした伝記小説『初神鳴』を「苦楽」に発表していて、この小説はのちに映画化されています。
1956年2月、軽い脳溢血を起こし言語喪失状態となり句作が途絶します。「避けがたき寒さに坐りつづけをり」が最後の句となりました。
同年5月11日、心臓麻痺により久我山の自宅で亡くなっています。
作風は写生を重視しながら、能で培った優美さを兼ね備えた格調高い句が多いです。
チゝポゝと鼓打たうよ花月夜 (松本たかし)
たかしは、宝生流能役者の家に生まれ、幼少より能を志しましたが、20歳のころ病で断念。俳句は高浜虚子に師事しました。「チチポポ」とは鼓(つづみ)の音を表しています。季節は春爛漫の桜どき。しかも月がまんまるにのぼっている夜という背景です。
— 俳句αあるふぁ (@mainichi_haiku) April 3, 2015
「チチポポと鼓打たうよ花月夜」の補足情報

能楽の流派の一つ「宝生流」について
宝生流(ほうしょう-りゅう)は、能楽の流派の一つです。
現在、シテ方とワキ方(下掛宝生流)とがありそれぞれ別の流儀ですが、単に「宝生流」というときはシテ方の宝生流になります。
観世流に次ぐ第二の規模を誇り、重厚な芸風で謡を重視し、その独特の謡の魅力から「謡宝生(うたいほうしょう)」とも呼ばれています。
かつて宝生座は多武峰や春日大社、興福寺に参勤し、代々の宝生太夫は室町幕府に仕えていました。

「チチポポ」という音
この時、作者は鼓を打っています。
鼓というとただ肩に乗せて叩いているだけだと思われますが、実は鼓の周りの紐(調緒)を使うことで、幾つもの音色を出せるのです。

松本たかしのそのほかの俳句

- 玉の如き小春日和を授かりし
- 金粉をこぼして火蛾やすさまじき
- 春月の病めるが如く黄なるかな
- 海中に都ありとぞ鯖火燃ゆ
- 夢に舞ふ能美しや冬籠
- 水仙や古鏡のごとく花をかゝぐ
- 雪だるま星のおしやべりぺちやくちやと