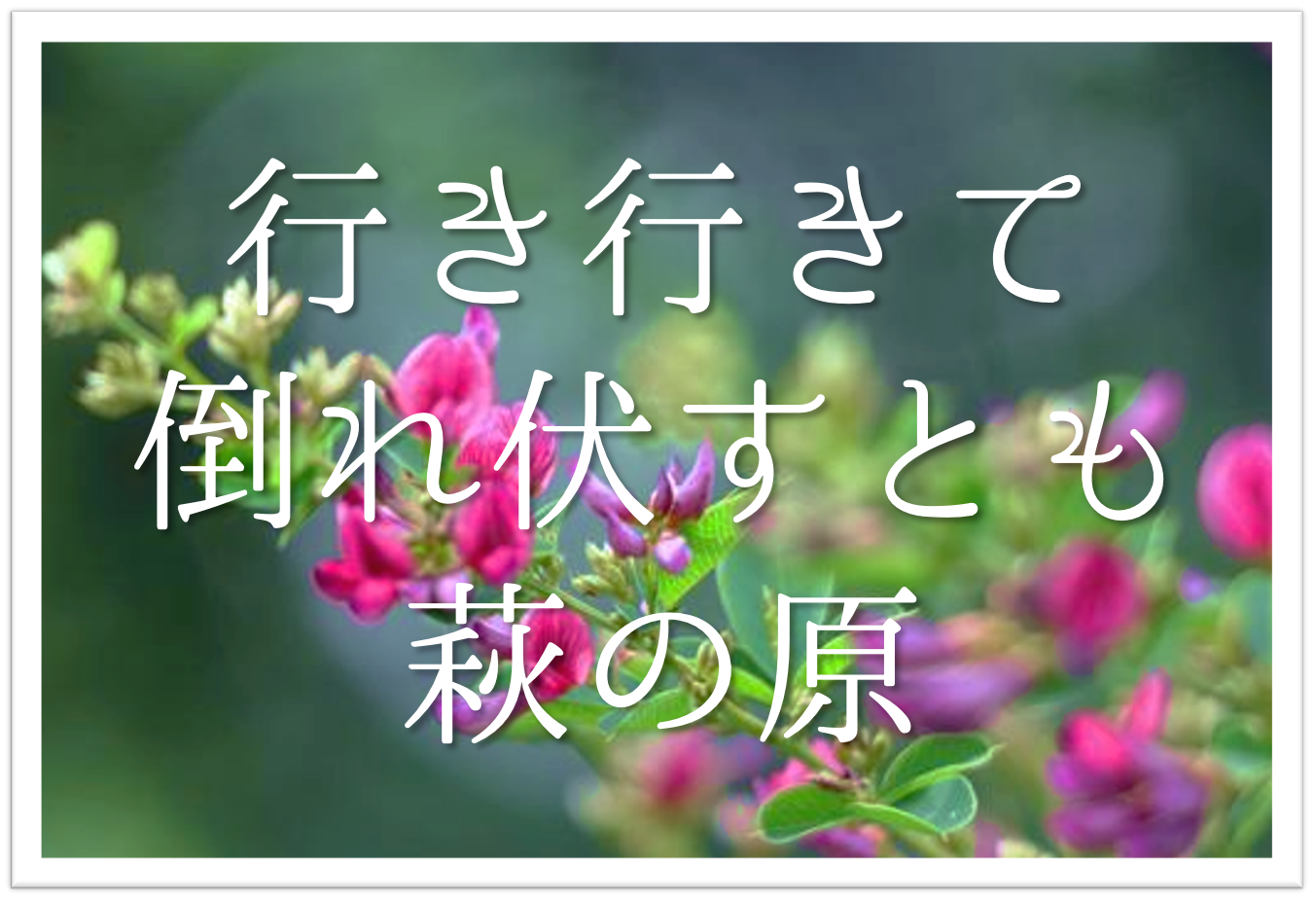
五・七・五のわずか十七音に心情や風景を詠みこむ「俳句」。
夏休みや冬休みの宿題で、取り組んでいる方も多いのではないでしょうか。
今回は、有名俳句のひとつ「行き行きて倒れ伏すとも萩の原」という句を紹介していきます。
行き行きて倒れ伏すとも萩の原 曽良 私の大好きな句です。 pic.twitter.com/pB3YZg1JZJ
— 今村方法 (@imahoho) June 15, 2018
本記事では、「行き行きて倒れ伏すとも萩の原」の季語や意味・表現技法・作者などについて徹底解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。
目次
「行き行きて倒れ伏すとも萩の原」の俳句の季語や意味・詠まれた背景

行き行きて 倒れ伏すとも 萩の原
(読み方:いきいきて たおれふすとも はぎのはら)
この句の作者は、「河合曾良(かわいそら)」です。
この句は松尾芭蕉の書いた紀行文「おくのほそ道」に収められています。河合曾良は、松尾芭蕉の弟子の1人です。
「おくのほそ道」の旅に同行し、芭蕉の身の回りの世話などをしていました。そのため、「おくのほそ道」には、河合曾良の詠んだ句も収められています。
季語
この句の季語は「萩」、季節は「秋」です。
萩は、紅紫色や白色の小さい蝶に似た形の花が、しだれた枝にたくさん咲く落葉低小木です。
「この花が咲くと秋が来る」と言われています。秋の七草のひとつであり、季語としても多くの俳句で詠まれています。

「萩の原」という場所は地名ではなく、萩の咲いている野原という意味です。
意味
こちらの句を現代語訳すると…
「行けるところまで行き、たとえ力尽きて途中で倒れてしまっても、その場所が萩の咲く野原であれば良い。」
という意味です。
曽良のこの句を詠んだ時の心情を踏まえて、「萩の花の咲く野原であれば思い残すことはない、本望だ。」という現代語訳をされていることが多いです。

また、「倒れ伏す」というところを「途中で倒れて、垂れ死にをしてしまう」と訳している場合もあります。
この句が詠まれた背景
松尾芭蕉は、弟子の河合曾良とともに東北から北陸を経て美濃国の大垣までを巡った旅を記しました。これが紀行文「おくのほそ道」です。
この句は、元禄2年8月5日、6日に詠まれました。「曾良との別れ」と題して、芭蕉はこのときのことを書いています。
弟子の河合曾良は、現在の石川県加賀市の山中温泉で、長旅の疲れからか、お腹を壊してしまい、体調を悪化させてしまいます。
伊勢長島(現在の三重県)の寺に親戚がいるというので、曾良は芭蕉と別れて療養のためにそちらへ行くことにしました。

体調が悪化しながら、もしどこかで力尽きて野垂れ死にをしてしまうかもしれない。しかし、行きついた先が萩の花が咲く野原であれば思い残すことはない、という河合曾良の覚悟が表れた句です。
「行き行きて倒れ伏すとも萩の原」の表現技法

「萩の原」の体言止め
体言止めは、句の終わりを名詞や代名詞などの体言で止める技法です。
体言止めを用いることで、美しさや感動を強調する、読んだ人を引き付ける効果があります。
「萩の原」の名詞で体言止めすることによって、「萩の原であれば本望だ」という曾良の思いがより強調されているようにも感じます。
句切れなし
この句には、切れ字や区切れはありませんので、「句切れなし」です。
「行き行きて倒れ伏すとも萩の原」の鑑賞文

昔は現在のように、交通機関やインフラが整備されておらず、旅は命がけのものでした。
そうした中で、曾良は献身的に松尾芭蕉の身の回りの世話をし、旅をサポートしてきました。
最後まで松尾芭蕉とともに旅をしていたかった、そうした曾良の無念な思い、悔しく思う気持ちも読み取れるかもしれません。
曾良は、芭蕉と別れて伊勢へ向かう間も、芭蕉の寄るところへ先回りし、お金を置いたりして芭蕉に尽くしていたと言われています。
4か月にも及ぶ、芭蕉と曾良の2人での旅は終わりを迎えましたが、曾良はずっと芭蕉を心配していたようです。
曾良は「おくのほそ道」でもたくさんの句を詠んでいますが、そのなかでもこの句は、曾良の気持ちがよく表れていると言われています。
もう2度と会うことのない俳句の師である芭蕉へ、別れとそして自分が途中で死んでしまうかもしれないけれども、心配しないでほしい、そういった思いも込めているのではないでしょうか。
芭蕉も曾良のことを心配し、師弟の絆も感じられます。
実は曾良は、「いづくにか倒れ伏すとも萩の原」という句を詠んでいました。
(※いづくにか・・・どこに)
松尾芭蕉が、「奥の細道」を執筆するにあたり、添削して「行き行きて」と表現を変えたとされています。

また、曾良がつけていた旅の記録には、曾良の体調不良については記載がないとされています。そのため、芭蕉のエピソードではないかという見方もあるようです。
「行き行きて倒れ伏すとも萩の原」の補足情報

『猿蓑』での描写
『おくのほそ道』に収録されている俳句は、『猿蓑(さるみの)』など先に刊行されている歌集に推敲前のものが載っていたり、前詞が書いてあったりします。
曾良の「行き行きて」の俳句の推敲前が「いづくにか たふれ臥とも 萩の原」であることは前述の通りですが、この句にも前詞が付いていました。
「元禄二年翁に供せられて、みちのく より三越路にかかり行脚しけるに、 かがの國にていたはり侍りて、いせ まで先達けるとて」
(訳:元禄二年に芭蕉に連れられて、陸奥から越前、越中、越後を通る三越路にかかって行脚している時に、加賀の国にて休養して、伊勢まで先に行くことになって)
この「いたはり」を「苦労する」と取るか「休養する」と取るかに寄りますが、芭蕉一行は山中温泉で休養を取っているため、「休養」という意味に取りました。
この前詞でも『曾良旅日記』のように病気のことは出てきません。

また、芭蕉の病気だったのではないかという説についても、『曾良旅日記』にも2人が別れるこの句の前詞にも書かれていないため、何か事情があったのではないかと考えられます。
「いづくにか」と「行き行きて」
推敲前の「いづくにか」の句は、とある和歌の本歌取りであると考えられています。
「いづくにか ねぶりねぶりて 倒れ伏さむと 思ふ悲しき 道芝の露」西行法師
(訳:仏の教えに目覚めないままいたずらに夜々の眠りを重ね、果てはどの路傍に倒れ伏すのだろうか。そう思うと悲しい、道芝の露の様に儚い此の身であることだ)
この和歌には「いづくにか」という共通したフレーズのほかに、「倒れ伏さむ」という言葉もあります。

また、推敲後の「行き行きて」の繰り返しと「ねぶりねぶりて」の繰り返しも共通しているため、曾良や添削したと思われる芭蕉がこの西行法師の歌を念頭に置いていたのは間違いないでしょう。
曾良はどのような道を通ったか?
曾良は加賀国から伊勢へと向かいましたが、この時代に岐阜の山々をショートカットできる道はありません。
芭蕉と曾良が歩いてきたのは、現在の青森から日本海側を通り、新潟、親不知と呼ばれる難所、遊女との一幕を詠んだ市振、金沢と続き、関ヶ原へと続く「北国街道」だったでしょう。
曾良の目的地である伊勢の長島へは、関ヶ原からの分岐ルートである「美濃路」と、「美濃路」の終点である名古屋からの分岐ルートの「佐屋路」を使用するとたどり着けます。

そのため、このルートを通ったのかもしれませんね。
作者「松尾芭蕉」と弟子「河合曾良」の生涯を簡単にご紹介!

(河合 曾良 出典:Wikipedia)
河合曾良は、長野県上諏訪の出身・本名を岩波庄衛門正字(しょうえもんまさたか)といいます。
江戸に出て神道を学んでいましたが、1685年頃に芭蕉に入門したとされています。
芭蕉は、46歳の時に曾良を伴い江戸を発ち、東北から北陸を経て美濃国の大垣までを巡った旅を記しました。これが紀行文『おくのほそ道』です。同行した曾良も「曾良旅日記」という記録を残していました。
芭蕉は「おくのほそ道」の旅から戻り、大津、京都、故郷の伊賀上野などあちこちに住みました。1694年、旅の途中大阪にて体調を崩し51歳にて死去しました。
曾良は芭蕉が亡くなった当時、幕府の仕事に従事していました。1710年5月、幕府の仕事で赴いた壱岐にて61歳にて亡くなりました。
河合曾良のそのほかの俳句

- 卯の花に兼房見ゆる白毛かな
- 卯の花をかざしに関の晴着かな
- 剃り捨てて黒髪山に衣更
- 松島や鶴に身をかれほとゝぎす
- 破垣やわざと鹿子のかよひ道
- 終夜秋風きくや裏の山
- いづくにかたふれ臥とも萩の原
- 向の能き家も月見る契かな
- むつかしき拍子も見えず里神楽
- 大峯やよしのの奥の花の果
- 春の夜はたれか初瀬の堂籠
- 涼しさや此菴をさへ住捨し
- 病僧の庭はく梅のさかり哉
















